タラ子さんのレビュー一覧
投稿者:タラ子

じんかん
2020/08/12 10:22
胸に抱いた夢の実現のために命をかけた1人の男の物語
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
貧しい者は搾取され続け、弱き者は殺される。大切な人を理不尽にも亡くすことが当たり前に繰り返される世の中。そんな混沌とした時代に生まれた松永久秀。父母を殺され、同じような境遇の子どもたちと生きるも、その仲間も殺されてしまう。人の死に嫌というほど接してきた久秀は「自分は何のために生まれてきたのか」を問い続ける。
そんな久秀の人生を変えたのは、武士がのさばる世の中を変え、民が民の手で政を行う世を目指す三好元長との出会いだった。生まれた時から当たり前のように武士が支配する世を見てきた久秀にとってそれは画期的な考えだった。
それからの久秀は夢の世を実現するため尽力するも、三好家内の度重なる争いなど欲望と戦乱渦巻く時代にのみ込まれていく。
本書を読むと民主主義の現代は、松永久秀のような人間が一生をかけて尽力し、少しずつ時代を進めてきてくれたおかげなのだと気づく。1人の力は小さいが、1人の強い思いは受け継がれ、世を変える程の大きな力になるのだと感じた。
自分が生きるこの時間に誰しもが精一杯の中で、後世のことを考え、到底無理だと思われることでも、自分の信念を曲げずに死ぬ最後の最後まで走り続けた松永久秀の人生にふれ、己は何のために生まれてきたのか問われている気がした。
2019/11/18 21:00
相手を思いやる会話ができる大人はステキ
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
なかなか話が弾まない、誰とでも楽しくコミュニケーションしたい!と常々考えていたところ、この本の題名を見てハッとさせられすぐに読みました。
人の話を聞いていて、『私も』とついつい会話をのっとっていたことなど気づかされることがたくさんあり、反省するとともに、もっと相手を思いやり、自分が相手に何ができるのかを常に考え行動できるようにこれからの毎日本書で学んだことを意識していこうと思いました。
著者のような会話上手で周りの人を幸せにできるような人を目指して頑張りたいと思いました。

悲しみの秘義
2023/05/30 14:11
言葉によって心が落ち着き癒やされていく
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
苦しいとき、悲しいとき、わらをもつかむ思いで探すのが言葉だと著者が言うように、この本に、この言葉に救われたという経験が誰にでもあるだろう。
この1冊には、著者が様々な本から選んだ珠玉の言葉と、著者自身の思いがギュッとつまっている。
この先の人生、何度も手にとるだろう本に出会えたことに感謝したい。
また、この本で引用されている本についても読みたいと思うものが何冊もあり、これからの楽しみにもなった。
“どんな 微細な光をも 捉える 眼を養うための くらやみ”という岩崎航氏の詩は私の心にしっかりと刻まれた。

エンド・オブ・ライフ
2020/09/22 10:25
最期の瞬間まで自分らしく生きるとは
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
在宅医療という選択肢が当たり前になかった時から京都で在宅医療を専門にしてきた病院関係者と、死をテーマにした作品を多く手掛けてきた著者が、様々な人たちの死を通して、死について、そして死から生について考えさせる1冊。
死ぬ前に子どもの願いを聞いてやりたいと海に出かける家族。たとえ海に出かけたことで数日間この世にいる日が短くなったとしても後悔はないと決断し、またその思いを実現するために同行する医療関係者。
意識ははっきりしているのに身体が全く動かなくなった妻を7年間自宅で介護し妻が亡くなる最後まで傍にいた夫。
人は死を意識するとここまで強くなれるのか、家族の絆はここまで強いものなのかと衝撃を受けたと同時にその思いを大切にしようと寄り添う医療関係者の志に感動した。
この本で"人は生きてきたようにしか死ねない"という言葉がたびたび出てきて、生と死はつながっていると思う瞬間がたくさんあった。
たくさんの人のエピソードを読み、死にゆく人の死に様は残された人の心に何かを残すということを学び、最期の瞬間まで自分らしく生きられるように、そしてその自分らしくの理想に近づけるように日々しっかりと生きていかなければならないと強く感じた。
死について病気や何かがあった時にしか普段考えることはないが、誰にでも訪れるものだからこそ、必ず読んでおきたい1冊だ。

美容は自尊心の筋トレ
2020/01/03 17:07
自分に自信がなくなる時、自暴自棄になりそうな時におすすめの1冊
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「この世にブスは存在せず、ただ多様な美しさがあるのみ。」という1文に世界が変わった気がした。
誰にでもコンプレックスはあるけど、卑屈になったり、自信をなくすのではなく、人からの評価に関係なく、決して驕らず、でも容姿も含めて自分の嫌な部分も個性やチャームポイントとして捉えて好きになるという著者の生き方に感銘を受けた。
その境地に至るにはなかなか大変そうだけど、少なくとも自分はいつでも自分を好きでいてあげる努力をしようと思えた。

隣人の愛を知れ
2021/12/05 21:59
様々な女性の視点から描かれる愛のカタチ
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
6人の女性それぞれの物語にすぐに引き込まれた。
それぞれが本気で人を愛したからこそ苦しみ、葛藤する様子に愛の様々なカタチを見た。
たくさんいる人の中で本当に愛し合える人に出逢えるということは、奇跡のようなもので、どんな愛も自分を成長させてくれるものだと思えた。
この小説の
“好きだと思える自分になればいい。自分で好きだと思えないのに、隣にいる人には愛してもらおうなんて矛盾している。相手の愛情に不安になる前に、わたしが信じられるわたしでいること。それでも裏切られるなら、自分の愛に悔いはない。”
という言葉は、自分の中で大切な言葉になった。

半沢直樹 アルルカンと道化師
2020/11/07 21:39
読後はスッキリ爽快!明日への活力も湧いてくる!
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
半沢直樹シリーズ最新作の舞台は大阪。
経営不振に陥ったある会社に飾られたピエロとアルルカンという1枚の絵に隠された驚愕の真実とは。半沢直樹の倍返しも健在。組織の悪と戦う半沢直樹の姿には勇気をもらえるし、揺るがない信念を持って仕事をすればきっとそれは人の心を動かすと読者に教えてくれている。
読み終わってすぐに続編が待ち遠しくなった。
まだまだ半沢直樹熱は冷めなさそうだ。

i
2019/11/24 17:41
読後優しい気持ちになれる1冊
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
シリアで生まれ、裕福な家庭へ養子として引き取られたアイ。金銭的に厳しい家政婦の子ども達と接したり、貧困の子どものニュースを見るたびに自分の状況に罪悪感を感じ苦しむ。
世界で日々多くの人が亡くなり、その家族や友人などが涙している。その死者の数をノートに記し、一緒になって悲しみ、考えるアイは、夫や親友と出会い、また様々なつらい経験をしてこの世に確かに自分は存在しているし、存在していいんだという歓びを手にいれる。
近くにいる友人や同僚の表面的には見えてはいない悲しみや、また会ったことのない人々の苦しみに毎日少しでも思いをはせ、考えるだけで世界はもっと平和になるのではと感じた。大きな変化は起こせないけれど、他者の苦しみを分かろう、感じようとすることの大切さや、忙しい毎日で忘れかけていた他者への共感の心をこの小説は私に気づかせてくれた。

電車のなかで本を読む
2023/10/22 22:29
本っていいよねと心から思わせてくれる本
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
編集経験などないが、この言葉を届けたい、こんな本を読んでほしい!という気持ちから1人で出版社を立ち上げた、本を心から愛する著者の書評集。
読んでいてとても楽しかったし、この本で紹介されている本もしかり、無性に本が読みたくなった。
著者のエピソードはどれも本に対する愛に溢れていたし、本と向き合う姿勢にも共感できた。
本を買うのは、本を読むという豊かな時間を買うということだ。という言葉が刺さった。
どんなに忙しくても、心豊かに充実した時間を送るために、今日も私は本を手にするのだ。
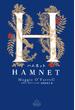
ハムネット
2023/09/26 15:34
シェイクスピアの家族の物語に涙した
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
シェイクスピアにはハムネットという幼くして亡くなった息子がいた。
あまりにも有名なシェイクスピアという人物のあまり知られてこなかった家族の物語。
シェイクスピアはなぜ亡き息子の名を戯曲にしたのか。
この問いを本の帯で読んだとき、この本を手に取らずにはいられなかった。
この物語はあくまでフィクションだが、子を失った親の思いがひしひしと伝わってきて、その問いの答えが明らかになるシーンでは胸が震えた。
また、決して癒えることのない苦しみを、シェイクスピア彼にしかできない方法ではきだし、昇華したというところに、今まで数々の傑作を世に出してきた天才というイメージしかなかったシェイクスピアという人物に、人間らしさ、また親しみを感じた瞬間だった。
改めてハムレットを読もうと思った。

1984
2023/03/12 21:47
今までに読んだどの小説よりも恐ろしくてゾッとする
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
党に24時間行動を監視され、思考もすべて管理され、党に目をつけられた人物はことごとく抹殺。最初からそんな人物はいなかったように過去の出来事すべてが塗り替えられてゆく。そんな恐ろしい世界を描いた作品。
2+2=4と当たり前に答えられる自由。そんな自由が素晴らしいなんて考えたこともなかった。当たり前が当たり前でない世界に足を踏み入れてしまった時に、私達はどうあるべきか。また、そんな世界を作り出さないためにどうすればよいのか。
自由とは、人間らしく生きるとはどういうことかなど様々なことを深く考えさせられた。
この小説を読んで、コロナ禍において、とある国の国民が、街中に無数に設置された監視カメラで政府が人々の行動を監視してルールを守らない人を罰してくれたおかげで蔓延が防げている、と笑顔で語る映像をテレビで見て衝撃を受けたことを思い出した。
近未来の設定で書かれた本作だが、着々とこの世界に近づいている国が既に存在している。
この本が読めなくなる未来にするかは今を生きる人間にかかっていると思う。
"戦争は平和なり。自由は奴隷なり。無知は力なり。"そんな未来が来ないように精一杯考え、生きていきたいと思った。

殺人犯はそこにいる 隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件
2022/07/19 11:26
とにかく1人でも多くの人に読んでほしい衝撃の1冊
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
4〜8歳の4人の少女が殺され、1人の少女が行方不明の事件。5件とも近い場所で似通った手口で起こっている。しかもうち3件について自供した犯人が捕まり、1件が起訴されているが、犯人とされた人物は無罪を訴えている。真犯人は別にいるのではないか。この本は、そんな疑問を持った著者の執念の取材、調査に基づく衝撃の実話である。
なかった物証があったことにされ、警察のシナリオに合わない目撃情報は除外され、杜撰なDNA鑑定かわ犯人特定の鍵となった。そして17年間無罪の人が刑務所に入れられ、その人が釈放されても真犯人逮捕に警察は動かない。
これは本当に日本で起こったことなのか!
17年間間違った人を刑務所に入れて捜査していなかったのに時効成立はおかしくないか。
またそれについて国会でとわれた時の当時の法務副大臣の真犯人の人権を擁護するような発言には唖然とした。
他にも杜撰なDNA鑑定と、しっかり検証すれば疑わしい目撃証言で、無罪を主張するも死刑が執行された事件についても書かれていて、私の警察や司法への信頼は崩れていった。
事件はまだ終わっていない。殺人犯は今日も普通の顔をして私達と同じ空間で生活している。
今なお悲しみの中にいらっしゃる被害者家族のため、また安全安心な社会のためにも早く真犯人を捕まえてほしいと強く思う。

悪い夏
2022/07/10 12:06
夏の暑さが見せる悪夢であってほしい!と思わず願ってしまう展開
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
生活保護を扱う部署に配属になった守。正義感溢れる同僚に、生活保護を不正受給するひとたちなど、配属されなければ関わらなかった人たちとの関わりから、とんでもない方向へ人生が転がっていく。
まさかまさかの展開から目が離せず、一気読み必至!
この物語を読んでいると本当にやるせない気持ちになることが多かった。
先の展開がわからないからこそ、その時その時で最善と思われる選択を考えてしていかないと人生取り返しのつかないことが起こってしまうかもということを思った。あのときああしておけばは通用しないのだ。
また、主人公の守のことを思うと、それまでの人生からは想像もできない悪に巻き込まれたときに、人は何ともろく悪にのみ込まれてしまうのだろうと恐ろしくなった。

人間のしがらみ 下
2022/04/11 13:45
生きることに何の意味があるのか?主人公が辿り着いた結末は。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
9歳で母親を亡くし、叔父夫婦に預けられたフィリップ。生まれつき内反足であるがゆえの苦労や、自分を抑えきれない恋などを経験しながら、生きる意味を自問して成長する彼が辿り着いた幸せとは。
著者モームの自伝的小説。
上、下巻のページ数に読了できるか不安だったが、読み始めるとフィリップの人生から目が離せずあっという間に読めた。
“やりたいようにやれ”を人生訓にいざパリの美術学校に入学したフィリップだったが、自分は絵に人生をかけるほどに才能があるのか迷い、苦しむ。
芸術家ではない私でもその苦悩、不安が手にとるように伝わってきて、胸が苦しくなった。
何のために生きるのか、生きることに何の意味があるのか、幾度となく自問してきたフィリップが、人生に意味などない。自分の人生は1つの模様で、幸せも苦しみもすべて人生という模様を凝ったものにするだけ。終わりが近づけば、それは自分だけが知る芸術作品となり、死をもって直ちに消え去るがゆえに美しい。と悟る場面がとても印象的だった。
何かを成し遂げたい、立派に生きたいと願えば願うほど理想とのギャップに苦しむ気持ちが生まれる。そんな現状にやるせなくなった時にこれも1つの模様に過ぎないと考えれば少しだけ心が落ち着くと思った。
この物語を読み、その時は人生に失望し、全て無駄だったと感じたとしても、そこで経験したことは自分が気づかないうちに豊かな心と人格を作り、いつか思いもしない場所へ連れて行ってくれるかもしれないと思えた。だから生きることを諦めてはいけない。そんな風に感じられた。
巻末で著者モームが辿った人生とフィリップの人生を比べてみるのも面白かったし、モームの他の作品も読んでみようと思った。
本著には深く考えさせられ、心を打つ言葉が沢山あり、自分のおすすめ小説ベスト5に入る本になった。

悪の芽
2021/12/21 17:33
誰もがもっている悪の芽の存在に気付かされる
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
大量殺傷事件の犯人が小学校の同級生だと分かり、かつていじめの原因となるあだ名を自分がつけてしまったことで彼の人生を狂わせてしまったのではないかと主人公は思い悩み、事件の全容を探り始める。
物語では事件現場に居合わせ動画を撮影した学生、被害者家族、犯人の職場の同僚などの目を通して見た事件が語られる。そこからは、皆が皆それぞれの正義を胸に生きており、それは本人さえも気づかないうちに悪の芽を育て、他人の攻撃につながるということが分かる。
加害者の家族、また加害者をかつて虐めていた人など、攻撃対象を見つけると当然のように罰しようとする人が物語でも現れる。しかし、それがいかに異常なことか、そしてそれが誰もが持っている悪の芽で、人間の悲しい性質だということをこの物語は教えてくれる。
この物語を通して著者は何度も読者に、その行動は想像力に欠けたものではないかと問いかけているように思えた。インターネットでの誹謗中傷など想像力の欠如による行為はあとを絶たない。1人でも多くの人が想像力を働かせ、自分の悪の芽を自覚してほしいという願いがこの物語には込められていると感じた。
自分にも悪の芽があることを自覚し、善の芽を育てるという気持ちを忘れずに生きていきたい。


