みゆの父さんのレビュー一覧
投稿者:みゆの父
紙の本
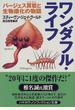
紙の本ワンダフル・ライフ バージェス頁岩と生物進化の物語
2002/07/04 09:00
タイトルが全てを語っている
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
タイトルが全てを語っている、分厚く、専門用語にみちあふれた一冊。バージェス頁岩からみつかった化石群をめぐって繰り広げられたドラマ、この本の表紙を見ればわかるトンデモな姿をしたカンブリア紀の生物たちの生態、ダーウィン進化論をめぐる生物学者たちの論争、そういった話題がてんこ盛りになっているので、読み通すには根気がいるかもしれない。
しかし、この本は単なるノンフィクションではないし、単なる専門書でもないし、単なる教養書でもないし、「断絶平衡説」という自説を宣伝するための単なる伝道書でもない。いわば、それらのどれでもなく、同時にそれら全てでもある類の本なのだ。
それではこの本のメッセージは何か。答えは単純、それは「ワンダフル・ライフ」だと僕は思う。〈ワンダフル〉は〈奇妙な〉で〈ライフ〉は〈生物〉だから、「ワンダフル・ライフ」は「奇妙な生物」と理解する(訳す)ことができる。たしかにバージェス頁岩からみつかったのは先カンブリア期の「奇妙な生物」だったから、これは正しい理解だろう。
ただし〈ワンダフル〉には〈驚異の〉という意味もあるし、〈ライフ〉には〈生命〉という意味もある。つまり「ワンダフル・ライフ」は「驚異の生命」、逆に言えば「生命の驚異」を意味している。そう、生命はそれ自体で驚異なのだ。先日惜しまれつつ亡くなった生物学者グールドさんがこの本で伝えたかったのは、そんなことだったのではないだろうか。
紙の本

紙の本かくしてバンドは鳴りやまず
2002/07/03 22:42
書くことの〈物狂ほしさ〉
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
著者の夭折によって未完に終わった企画から生まれ、優れたノンフィクション作家の遺作にして、少なくとも〈ライター〉と名の付く職業を目指している人には必読の一冊。この本を読んでいるうちに、僕は「心にうつりゆく由なし事をそこはかとなく書きつくれば、可笑しゅうこそ物狂ほしけれ」(多分)という一節を思い出した。これが『枕草紙』の出だしの一文(の一部)であることは、言うまでもないだろう。つまり、この本には著者の井田さんの〈物狂ほしさ〉が溢れているのだ。
現在の日本を代表するノンフィクション作家といえば、大抵は立花隆さんとか佐野眞一さんとか鎌田彗さんの名前が挙がるだろう。彼らの作品は驚異的な量と質の構想と読書と取材と執筆、一言で言って体を酷使する営みの産物なのだろう。佐野さんが自らの方法を語った『私の体験的ノンフィクション術』(集英社新書)を読むかぎり、ノンフィクションを書くことは一種の体力勝負なのだ。そして彼らの営みは、僕のような素人にとって、まったく尊敬に値する。
ところが、この本を読むと、井田さんの営みは、立花さんや佐野さんといった人々とは質を異にしていることがわかる。井田さんが書いた五頁分足らずの連載企画書と一三頁分のコンテ(一〇〜二七頁)に目を通した瞬間、そのことが実感できるはずだ。ノンフィクション論、取材対象の選び方、そして距離の取り方、これら全てについて、井田さんは体よりも心を酷使する立場を選んだ。そして、それに値する対象を描き、あるいは描こうとした。トルーマン・カポーティ、カール・バーンスタイン、『きけわだつみのこえ』、あるいはジョン・ル・カレ、コンテに出てくるのは、僕みたいな素人の想像をはるかに超え、しかし不思議と納得させられてしまうラインナップなのだ。
実際に書かれたのは、このうち、カポーティと、バーンスタインと、『きけわだつみのこえ』とを扱った三つの章だけれど、そこからは、自らの心と取材対象の心を同調(シンクロ)させようとする井田さんの〈物狂ほしさ〉が漂ってくる。折れそうなほど硬質な文体と姿勢で、取材対象の心に潜む死や生や、そして人間の尊厳をえぐりだそうとする井田さんの。
こんな井田さんのスタイルには、きっと賛否両論があるだろう。しかし、書くことの〈物狂ほしさ〉を感じさせる彼女の作品は、これからも読み継がれてゆくに違いない。僕はそう確信している。
紙の本

紙の本日本型サラリーマンは復活する
2002/06/30 23:09
快刀乱麻
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
サラリーマンが「構造化されたデフレ社会」(一九頁)をのりこえ、「働くものの自己実現」(一一七頁)を現実化する方途を、気鋭の経済学者が説いた書。いまやぱっとしない名称になった感のあるサラリーマンだけれど、だからといって馬鹿にしてはいけない。自分も広義のサラリーマンだから余計そう思うのかもしれないけれど。
この本を読んで僕が思い起こしたのは、かつて愛読した山田正紀の冒険小説『アグニを盗め』(角川文庫?)のなかで、ダーティビジネスの専門家に対して主人公のサラリーマンが〈サラリーマンを馬鹿にするなよ〉と一喝したシーンだった。そう、サラリーマンだって何かの専門家であり、プライドがあり、そして生活があるのだ。
そんなサラリーマンに対する風当たりは、ここのところ強くなるばかりだけれど、この本の著者の田中さんは、経済学や歴史に関する知識を動員して、サラリーマンに厳しい通説を片っ端から論破してゆく。たとえば有名な「構造改革なくして景気回復なし」というスローガンは、マクロ経済学からすると、目的と手段がずれている。雇用の流動化によって景気を回復しようという考えは、情報の経済学や現実のデータを見ると、はずれ。いわゆる三種の神器を中心とする日本型雇用システムは構造として耐用年数を超えたという意見は、歴史や労働市場論、さらにはヴェブレンの有閑階級論やハーシュマンの〈エグジット・ボイス〉論に反する。IT化は会社組織のフラット化を進めるとか、サラリーマンの自立が進んでいると主張する説は、現状を調べると俗説にすぎない、などなど。まさに快刀乱麻というか、寄らば切るぞというか。
そのうえで田中さんは、市民社会とも関連する「社会資本を、市場からの規律とエグジット・ボイスの確保によって再構築していく」(二三三頁)ことを提唱する。なるほどなあ。ちょっと「循環」から説明しすぎているところもあるけれど、構造改革賛成派も反対派も一読の価値がある本だ。
紙の本

紙の本その仕事、好きですか?
2002/06/19 23:04
好きこそものの上手なれ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
仕事って、本当に不思議な存在だ。ありすぎても困るけれど、なければないで(金銭的だけじゃなくて)精神的にも参ってしまう。仕事がなければゆとりが出来て、好きなことが出来そうなものだけれど、何かものたりなくなるのだ。
この本は、色々な職業に就いている二〇人の女性に対するインタビューをまとめたもの。職業は国会議員から歌手まで様々だけれど、みんなに共通しているのは本のタイトルにもなっている「その仕事、好きですか?」という質問に対して〈イエス〉と即答できる点だ。その意味では、幸せな二〇人だと言えるだろう。
ただし、この本は単純なサクセス・ストーリー集じゃない。朝から晩まで働くプレス、当選以来休日なしの国会議員、顧客の情報をすべて記憶しているクラブのママ、廃業しかかった経験を持つ蔵元、みな人並み以上の苦労と努力をしているのだ。でも、仕事が好きだから楽しく、楽しいから努力が苦にならず、努力するから成功し、成功するから楽しさが増える。つまり〈仕事が好き〉から好循環が始まるわけだ。
ついでに、歌手やカフェ経営者といったお洒落な職業だけじゃなくて、イルカ調教師や自然ガイドや花火師といった(はっきり言って)地味な職業も取り上げているのも鋭い。好きならば、それが自分のために存在する仕事なのだ。
ただし、ただし、疑問が三つ。まず、好きな仕事がある人は良いけれど、それがみつかっていない人はどうすればいいんだろうか。そんな人がこの本を読むと、さらに落ち込むかもしれない。「新しいものや価値観に敏感で、肩ひじ張るんじゃなくて、興味あることに積極的な女性たち」(九五頁)だけならいいのだけれど。
次に、この本には苦労話と努力話はあるけれど、失敗話はない。だから、結局はサクセス・ストーリーに落ち着いてしまう。夢見るためのカンフル剤としてはつかえるけれど、現実はもう少し厳しいんじゃないだろうか。
最後に、細かな点だけれど、「自分のためだけじゃなく、会社のため、人のため、という働き方は、自分を犠牲にするとかではなくて、会社の売上げで給料をもらうという原則がある限り、当然といえば当然なのだ」(四一頁)ってフレーズがあるけれど、僕は「当然」だとは思わない。給料は仕事の対価であり、それ以上のものではないのだ。
といった疑問は残るけれど、様々な職業に就いている、魅力的で輝いている人々を紹介してくれたわけだから、高ポイント。
紙の本

紙の本世界を不幸にしたグローバリズムの正体
2002/06/02 22:04
「優れた経済学者は悪口雑言が上手い」
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
僕が勝手に考えついた法則に〈優れた経済学者は悪口雑言が上手い〉っていうのがある。そのモデルとして僕の頭にあるのは、マルクス。マルクスっていえば、大抵は『資本論』を書いた経済学者として知られてるけど、僕にとっては、一九世紀フランスについて通称「フランス三部作」(『フランスにおける階級闘争』、『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』、『フランスにおける内乱』)って呼ばれるルポルタージュを残した、優れたルポライターなのだ。そして、この三冊のなかで、彼は、当時のフランス皇帝ナポレオン三世をはじめとする自分の敵(かたき)を、悪口雑言の限りを尽くして切りまくる。当時のフランスのことを少しでも知ってると、その毒舌ぶりに思わず笑い出してしまうはずだ。
ところが、最近、僕はこの法則に当てはまる学者をもう一人みつけた。二〇〇一年のノーベル経済学賞を受賞したスティグリッツがその人。僕は不勉強だから、彼が書いた専門書も教科書も読んでないけど、きっとすごい経済学者なんだろう。そんな偉い経済学者が、アメリカ合衆国大統領経済諮問委員会や世界銀行で過ごした日々の体験記を出版した。それを翻訳したのがこの本だ。とすると、もしかして、この本は難しい専門用語のオンパレードなんじゃないだろうか。そんなふうに予想して、この本を敬遠したとしたら、本当にもったいない、と僕は思う。
じつは、この本は、国際通貨基金(IMF)と合衆国財務省、とくにIMFに対する悪口雑言のてんこ盛りなのだ。資金援助を必要とする発展途上国に対して、IMFがどれほど偉そうに振舞い、そのくせ間違った薬を処方して事態を悪化させ、そのくせそのくせ全然反省してない様子が、自分の具体的な経験と経済学の初歩的な知識とを織り交ぜながら、皮肉たっぷりに描かれる。IMFにとっては、経済学の理論と発展途上国の現実がずれていたら、間違ってるのは理論じゃなくて現実だ、ということなんだろうか。
もちろん、世界銀行だってIMFと〈同じ穴のむじな〉でしょ、とか、色々と突っ込めるところはあるけど、それもご愛敬。世界金融界の裏話も聞けるし、日本が不況が脱出するヒントも隠されてるし、〈優れた経済学者は悪口雑言が上手い〉って法則の証明にもなるし、今こそ「人間の顔をしたグローバリゼーション」が必要であり、そのために私たちは「声をあげなければならない。手を拱いて傍観していることはできないし、そうすべきではないのだ」(三五三頁)と熱く断言するノーベル経済学賞受賞者を知ることもできたし、読みおわって満足、満足。
紙の本

紙の本同じ年に生まれて 音楽、文学が僕らをつくった
2001/10/19 17:03
永遠の少年たちの笑顔
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
それは、まさに一目惚れだった。娘(二歳)を託児に預けてかみさんと育児講座に参加するつもりが、託児に必要なCDを忘れて、最近よく見かけるようになった本屋兼CD屋に入ったときのこと。娘を肩車しながら、僕の目はこの本の表紙に吸い寄せられた。わかる人はわかると思うけど、肩車しながら腰をかがめるのって、なかなか重労働だし、そもそも危ない。おまけに僕はもうすぐ不惑だし、娘はすくすく成長してる(から重い)し、僕はぐらぐらしながらこの本を手に取った。でも、それも当然だろう。全身から幸福感を撒き散らしてるかのような、小澤征爾さんと大江健三郎さんの満面の笑顔が表紙だったのだから。そんなわけで、娘の大切なCDを忘れた僕らは、CDを買うのも危うく忘れる羽目に陥るところだった。それから二週間、もったいなくてなかなか頁を開かなかったけど、とうとうこの対談集を読むことになった。そうはいっても、『ヒロシマ・ノート』位しか読んだことのない僕は大江さんの愛読者でもないし、小澤さんの指揮を生で聞いたこともない僕は小沢ファンでもない。でも、表紙の写真と『同じ年に生まれて』ってタイトルは僕の心を確実につかんだし、多くの人々の心にも届くだろうと思う。
まず僕は、二人が一九三五年に生まれ、一〇歳で第二次世界大戦の敗戦を迎え、ひもじい竹の子生活を過ごしたはずなのにもかかわらず、当時を「苦しいが、生き生きして新生の情動にあふれていた時期」(九ページ)と回想してることに圧倒された。僕は二人よりも三〇年近くあとに生まれ、高度成長の恩恵を十分に受け、ひもじさや戦争の恐怖を身近に感じたことはないけど、それじゃあと三〇年経ったときにあんな笑顔を作れるだろうかって考えると、疑問だ。もちろん二人は人生の大成功者だから、自分と比較するのもおこがましいかもしれない。でも、憧れは人間を動かす。僕も、三十年後の自分の顔があんなふうに輝いていることを望みたい。そんなかたちで、二人に対する憧れを持ちつづけたい。
おっと、全然この対談集の内容に入ってないじゃないか。この本の元になった対談自体は「二十一世紀の日本の新しい人たちがどういう理想のもとに、どのような努力を積み重ねていけば、より豊かな日本の文化の風土が形成できるか。あるいはまたそこから第二、第三の大江さん、小澤さんが輩出できるのか、そのための教育、社会通念、社会システムなどについて、お二人の豊富な海外体験をまじえて存分に語っていただきたい。その上で何か御提言願えれば幸いだと思っております」(一三ページ)っていう某新聞社の動機から生まれた、わかったようなわからないような企画の産物だけど、実際は、二人の言葉はそんな企画者の意図を飛び越え、とても直接的なメッセージを読者に伝えてくる。
そして二人のメッセージは、僕にいわせれば、とてもシンプルで、それだけに普遍的なものだ(そりゃそうだろう。シンプルかつ普遍的でなきゃ世界で活躍はできない)。つまり「個として立っていることが……人間が生きていることの原則」(六七ページ)だってことだ。でも、これはエゴイズムを勧めてるわけじゃない。個人として立つことは、自己を表現し、他者に開かれ、対話し、比較し、やがては普遍的な勇気や夢に至るための第一歩なのだ。制度は個人のためにあり、「中心と周辺」ではなく「普遍的なものに向かう周縁」だけがあるって考えるための第一歩なのだ。個人が自立し、同じく自立した個人との間で平等なコミュニケーションを結び合うことは、じつは戦争直後の日本人の多くに共有された夢だった。まさに二人は「あの時代に少年として生き、いまにいたるまで根本においていき方と熱望を変えることなしで来た」(一〇ページ)稀有な例なのだ。表紙の笑顔からは、その喜びが溢れ出してくる。そして、それが僕らを幸せにしてくれる。
紙の本

紙の本小田実の世直し大学
2001/10/18 11:03
地に足が着いた理想主義
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
うちの娘(二歳)が通う無認可の保育所には、少額だけどまちから補助金が出る。年に一回、補助金をもらってる保育所の代表は、まちの保育課と懇談会を持つ。僕はちょっと興味があったので「父兄として懇談会に参加したい」って頼み、保育所側は認めてくれたんだけど、まちの側に断られた。保育行政のあり方を考えるために保育所の代表とまちの当局者が一堂に会する重要な場に、保育所に子供を通わせてる父兄がどうして参加できないんだろうか。父兄の立場から見た保育行政の問題点を知ることって、まちにとっては役立たないんだろうか。悔しいので、どうすれば口をはさめるか、次の手を考案中だ。
そんな僕にとって、小田実さんは伝説的な人物だ。つまり、凄いってことは知ってるけど、リアルタイムでは知らない存在。『何でも見てやろう』も「ベ平連」も名前しか知らないし、本を読んだこともない。でも、あのふてぶてしい面構えは一度見たら忘れられないし、阪神淡路大震災の被災者の生活を支援する法律を制定するために走り回ったって話を聞いて「まだ現役なんだなあ」って感心した。それが、偶然、最近出版された小田さんの対談集を手にとることになった。対談相手は二人の大学人だから、話題は大学の問題が中心だけど、その行間から小田さんの思想が滲み出てくる。いや、「滲み出てくる」なんて生易しいものじゃなくて「炸裂してる」っていうほうが正確だろう。自分で考え、自分で行動してきた、日本では(嫌われるから)珍しいタイプの人間が、そこにいる。
ここで小田さんが語ってることを、三点にまとめておこう。第一、大学論。大学は、教員と学生が出会い、交わり、お互いが変わる場だ。知識が対話のなかで学問になり、学問が人生とスパークして思想に生まれかわる場だ。だから、大学の目標は「知的に豊かな市民を作ること」(三九ページ)でなきゃいけない。第二、市民社会論。現実の社会には様々な矛盾があるから、まず自分で考え、集まって議論し、立ち上がる人が出てくる。そのとき「市民」が生まれる。市民は動き、感動を共有し、市民社会を作る。この社会の基本的な原理は対等で平等で自由な共生だ。第三、現代論。現代は既存の価値ががたがたになり、問題が噴出してる。でも、僕らにとって、これはものごとを考えたり行動したりするにはいい機会だ。たとえば、「良心的軍事拒否国家」ってコンセプトを作り、賛同する人々を世界中から集めれば、多元的な社会ができたり産業が活性化したりするかもしれない。
日本みたいに横並びで上に従う体質の社会で、ほんのささやかなことであっても、庶民が人と違うことを言ったり実行したりするのは大変なことだ。そのとき「それは市民になるための、ほんの第一歩だ」っていって、ぽんと背中を押してくれるような人や言葉があったら、すっと気が楽になる。この本に出てくる小田さんの言葉は重いし、彼のキャリアは「凄い」の一言だけど、でも、この本のところどころには僕らにも使える言葉がころがってる。ハウツー本として読まれるのは小田さんの本意じゃないかもしれないけど。
ただし、この本に不満がないわけじゃない。一つだけ挙げておこう。後半に収録された講演で、小田さんは職人を否定的に評価する。司馬遼太郎さんに倣って「文句を言わないで黙々と働く、ただ与えられた職務を忠実に遂行する人」(一八〇ページ)って定義し、「職人というのは市民とは違うでしょう」(一八一ページ)って批判する。でも、職人と市民は本当に対立する概念なんだろうか。ある日職人が道具を投げ捨ててデモに参加し、市民になる、これって歴史上何度もあったことだ。むしろ日々の暮らしをよく知ってる職人のほうが市民になりやすいかもしれない。そんなことも想像しておかないと、小田さんが嫌いなエリート主義に陥る危険があるって僕は思うのだ。
紙の本

紙の本スローなビジネスに帰れ eに踊らされた日本企業への処方箋
2001/10/11 11:29
「常識」の復権を説くマニフェスト
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この前、先祖の何十何回忌だったかで、久しぶりに従兄弟に会った。彼は箱を作る中小企業に勤めてるんだけど、今度社内ベンチャーで「B2C(個人客相手)バーチャル・ラッピング・ショップ」とやらを始めたんだそうだ。そこで僕が「でも今はIT不況でしょう」ってつっこんだら、彼の答は「最終消費者のニーズを調べるのが目的だからいいんだ」。つまり儲けるつもりはないらしい。それじゃ僕自身はっていうと、IT弱者のひがみかもしれないけど、インターネットでものを買うのは好きじゃない。セキュリティや接続代金の問題もあるけど、何より面倒くさい。某インターネット書店を利用したことがあるけど、同じ本を二冊同時に買えないとか、検索結果の画面から二種類の本を買えないとか、注文に手間がかかる。「直したらどうか」ってメールを出したら「検討します」って返事が来たけど、数ヶ月たった今も変化なし。これなら近くの本屋で注文したほうが早いし、店員さんと話せるから楽しい。とはいっても、いま二歳の娘が成人するころにはIT不況は終わり、IT弱者はまた「弱者」に戻るかもしれない。やっぱり娘をパソコン幼児教室に通わせるか、なんて親は悩むわけだ。そんなことを考えながら、この本を読んでみた。
著者の阪本さんは、インターネットビジネスを重視するアメリカ型の経営術は失敗したって断言する。それは「いかに、アイディアを売るか」ばっかり考え、思いつきに頼り、手段に過ぎないインターネットを目的と勘違いしてしまったのだから。それなのに、日本の企業や経営コンサルタントたちは、アメリカを追えっとばかりに、間違った方向に走ってる。今こそたちどまり、流行のスピード経営じゃなくて「スローなビジネス」に帰ろうって阪本さんは主張する。彼はその具体的な内容を八項目にまとめてるけど、僕なりにさらにまとめると、顧客の生活の質を上げるって立場に立ちながら自分で考えること、人がモノを長く作るって原点を忘れないこと、この二点になる。阪本さんの発言は経験に裏打ちされてて面白いし、色々な実例が挙げられてて説得力がある。「農業型」(一四八ページ)のスタンスも、僕にとってはポイントが高い。何しろ僕は、自分は土に触るのが嫌いなくせに、最後に大切なのは食料だから、息子が生まれたら自給自足型の農民になってほしいって考えてたほどの「農業型」人間なのだ。
でも、不満が二つ。第一、ヒットを狙うスピード経営とロングセラーを狙う「スローなビジネス」の違いを、阪本さんは生物の子孫の残し方の二つのタイプ、つまり多産多死戦略と少産少死戦略の違いに例える(七四ページ)。でも、この二つの戦略ってどちらも有効だ(だから、前者を利用する魚も、後者を利用する人間も、存在してるわけだ)。そうすると、二つの経営術も「どっちもあり」ってことになる。つまり「スローなビジネス」のメリットそのものはわかるけど、スピード経営と比べたときの「スローなビジネス」の長所は何なのか、この本を読んだだけじゃわからないのだ。第二、顧客の立場に立ちながら自分で考えろって阪本さんはいうけど、これって難しいし、微妙なバランス感覚が必要だ。顧客参加型の製品開発やマーケティングからは「破壊型技術が出てこない」(一二四ページ)っていうのは言い過ぎだと思うし、阪本さんが望ましいと考える顧客とのコミュニケーションの創出や維持の方法について、もう少し説明してほしかった。この本はハウツー本じゃなくて阪本さんのマニフェストだから、これは「ないものねだり」かもしれないけど。
それにしても、第二章にある「日本企業への処方箋」は、どれも一昔前だったら「常識」だ。これはつまり、今の日本の実業界では、常識が常識じゃなくなってるってことなんだろうか。それって、かなりあぶない。
紙の本

紙の本文明の対話
2001/09/21 11:01
「無視」から「衝突」へ、そして「対話」へ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
前に本屋で見かけて何気なく手にとり、ちょっと前に読みはじめたんだけど、そのあと例の連続航空機テロが発生して、あれよあれよという間に(幸か不幸か、不幸に決まってるけど)タイムリーな読書になってしまった。それにしても、一時「文明の衝突」って言葉が流行ったけど、これってまさに「文明の衝突」の実例なんだろうか。
などと書いておきながら、じつは僕はそう思ってない。日本の、それも地方のまちに暮らしてる僕は、別の文明と出会ったって実感を持つ機会が少ない。この本の著者のハタミさんが大統領をしてるイランを例にすると、僕が自分の体験にもとづいて持ってるイランやイラン人のイメージって、せいぜい昔懐かしい「バンダル・ホメイニ石油プロジェクト」(叔父が参加してた)と「ペルシャ絨毯」(見たことがある)と「偽造テレカ」(上京したときに販売現場を見た)くらいだ。これじゃ「文明の衝突」どころか、それ以前の「文明の無知」だろう。格好良い話じゃないけど、僕はイスラム教に対して、何も知らないからこそ、偏見や先入見を持ってる。無知ほど怖いものはない。難しい問題を引き起こすのは、「衝突」よりもむしろ「無知」なのだ。そして、今回の展開は、まさに「文明の無知」を地でいってるような印象を僕は持ってる。
実際、衝突するには出会うことが必要だけど、出会ってみると「悪くないぞ」って思う人が出てくるものだ。僕は昔フランスで暮らしたことがあるけど、当時のフランスは北アフリカ出身のイスラム教徒移民との「文明の衝突」の真っ只中。それこそ、イスラム教原理主義者によるテロと、軍隊や警察による弾圧が、小さな悪循環を続けてた。空港や駅では、軽機関銃を携えた軍人が闊歩してた。移民は出てけと叫ぶ政党の支持率が一割をこえてた。でも、忘れちゃいけないのは、「文明の共存」を主張し、移民と共存するために地道に活動する人たちもいたことだ。そして、「衝突」派と「共存」派と移民の間には、冷静かどうかは別にして、一種の対話が実現してた。
さてさて、本題に入ろう。ハタミさんは、まさに「文明の衝突」論に対抗して「文明の対話」を唱えるために、この本を書いた。文明の対話とは何か、対話が可能であり必要である理由は何か、対話を可能にする条件は何か、イスラム文明にとって西側文明と対話する必然性はあるか、ハタミさんはこういった問題を深く、でもわかりやすく論じる。対話によって合意を作り上げられれば最高だけど、そこまでいかなくても、お互いの違いを最小化したり自分の思想を深めたりできる。対話しなければ、批判も協力も生まれないし、自分の魅力も増さない。対話にとって一番大切なのは、相手の言葉を「聞く」こと、「相手の目で」自分を見直すこと、そして協力する義務を含んだ積極的な寛容なのだ。
僕には二歳になる娘がいるけど、将来彼女がイスラム教徒を婚約者として連れてきたら、イスラム教に偏見や先入見がある僕はどう対応できるだろうか。そんなことを考えると、ハタミさんの言葉は結構使えることがわかる。とにもかくにも話をすればいいのだ。相手が日本語を話せるかもしれないし、娘が通訳してくれるかもしれないけど、とにかく話す。口喧嘩になってもいいから、とにかく話す。あとは彼の個人的な性格と、僕との相性の問題だ。考えてみると、「イスラム教徒」とか「文明」とか一括りにするって、傲慢だし怠慢な態度だ(僕は韓国人に良い印象を持ってるけど、それは友人の韓国人がいいやつだからだった)。一番大切なのは、個人としての関係なのだ。そして、最後はもちろん娘の気持の問題だ。でも、せっかくハタミさんも勧めてることだし、親としては対話するつもりだ。議論して、あとは酒でも飲もう。おっとイスラム教は禁酒だったっけ。
紙の本

紙の本日本型コーポレートガバナンス 従業員主権企業の論理と改革
2001/09/18 02:10
「経済生活と社会生活を豊かにするために存在する」企業の時代は来るか
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
僕は最近、経済関係のニュースを聞いてると、なぜか違和感を感じて仕方がない。よく記者が「マーケットは従業員の削減を求めてます」とか「市場(しじょう)の声によると、一層のリストラが必要なようです」とかリポートしてるけど、金融市場を支配する株主は従業員の削減を求めることができるほど偉いんだろうか。どこか違うって気がしながら、僕は何も考えてこなかった。でも、いずれは働くようになる(今はまだ二歳の)娘から「マーケットにいわれて解雇されちゃった」なんて訴えられたら、きっと「株主と従業員の関係について、あのとき勉強しておけばよかった」って後悔するに違いない。何といっても僕は親馬鹿なのだ。しかも、ここのところ日本の経済や企業の行方は不透明で、はっきりしてるのはグローバル化が必要だってことだけらしい。でも、日本企業は戦後一貫して海外に進出してきたはずだから、今になって企業のあり方を変えなきゃいけない理由がわからない。こんな問題にも悩んでたので、この本の副題(従業員主権企業の論理と改革)に惹かれて読んでみた。
この本の著者の伊丹さんは、以前から、日本企業は株主じゃなくて従業員が(政策決定と付加価値の分配と経営者の任免を司る)主権者である「人本主義」だって主張してきた。企業は従業員のものなのだ。さて経済学者のクルーグマンさんによれば、経済で大切なのは失業と分配と生産性の三点だから(『経済入門』、メディアワークス、一九九九年)、これら毎に、株主の利益を重視する最近流行の経営スタイルと比べながら、人本主義企業を評価してみよう。人本主義企業は、安定的で長期的な人間関係を重視するから、なるべく解雇を避ける。情報や財や権力を分散させようとするから、出来る限り多くの利害関係者が納得する分配を試みる。情報の蓄積とか学習の動機付けに優れてるから、経済効率が高い。株主主権と資源一元化と自由市場で特徴付けられる英米型の資本主義企業と比べると、経済合理性という点では、人本主義企業のほうが優れてる。よく人本主義企業は経済効率が低いって批判されるけど、それは誤解なのだ。
もちろん人本主義企業にも問題がある。まず、閉鎖性が強いため、悪平等やしがらみや働きすぎがおこりやすいこと。伊丹さんは利益原理を導入して従業員の個性を活かしたり、市場原理を導入して経営者をチェックしたりすることを提案するけど、これじゃ十分な解決策にはならない。本当に働きやすい職場を実現するためにはどうすればよいか、具体的に考える必要があるだろう。次に、利益至上主義、経営者の独走、資本効率の低下、変革の忌避、グローバル化への対応ミスなどが発生する場合があること。伊丹さんは、従業員の発言機会を制度化すること、従業員主権を明確にすること、経営者をチェックする体制を整備することについて、具体的で詳細な処方箋を示す。主権者が経営者をチェックすることを企業統治(コーポレートガバナンス)と呼ぶとすれば、人本主義企業にとっては、従業員が経営者をチェックできるか否かが企業統治の鍵を握ることになる。
従業員が主権を持つ企業がありうること。それは英米型の企業よりも経済合理的なこと。問題点もあるけど、具体的な処方箋もあること。伊丹さんは「時代に逆行した議論に聞こえそう」(まえがき)だっていうけど、人本主義企業には、経済効率を上げることと従業員を重視することが両立する可能性がある。企業は営利を追求するものだけど、娘が働く時代の企業は、せめて「企業に関係するさまざまな人々の経済生活と社会生活を豊かにするために存在する」(三一七ページ)ものであってほしい。一人の(親馬鹿な)親としては、そのことを、まだ娘が二歳なのに、心から期待してるのだ。
紙の本

紙の本人口ピラミッドがひっくり返るとき 高齢化社会の経済新ルール
2001/09/14 02:14
幻想なき未来予測
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
日本は論争の時代に入った。経済構造改革は是か非か、中流幻想は崩壊したか否か、新学習指導要領で学力は低下するか否か、議論の種には事欠かない。でも、経済には自動回復装置が備わってて、構造改革をしてもしなくてもやがて上向く。失われた十年で中流幻想はダメージを受けたけど、実態を見ればそもそも日本に中流階層があるか否かは疑わしい。これから子供の平均的な学力は確実に低下するけど、私立校に通ってる子供には他人事だ。そう考えると、どの問題も一部の人にしかあてはまらない。でも、唯一、全ての日本人に影響を及ぼす事態がある。それが少子高齢化だ。合計特殊出生率は国民が再生産するのに必要な二・〇五をとっくに切った。日本人は減少の一途を辿り、同時に高齢化が進む。そして、好むと好まざるとにかかわらず、全ての日本人の生活に影響が及ぶ。ちなみにうちも娘が一人なので、少子化と日本人の滅亡に貢献してる。
少子高齢化については、評価や原因や経済的影響や対策といった様々な点をめぐって、議論が続いてる。でも、少子高齢化を道標化するかが重視されてるためか、わりに大きいというか大雑把な話が多く、僕らの日常生活がどうなるかについての明確なイメージを結びにくい。まあ、僕やかみさんは、もう人生の折り返し点近くまで来たから、このまま惰性で行けるだろうって予想してるし、期待もしてる。ただし、問題は二歳になる娘だ。彼女が成人式を迎える二〇一九年は、そろそろ日本が高齢化のピークを迎える年だ。そんな高齢化社会で娘が普通の日常生活を営むには、どんなことに気を付けなきゃいけないんだろうか。そんなことを考えながら、二〇年後の娘のためにこの本を読んだ。ここまで来ると、我ながら本当に親馬鹿としか言いようがない。
著者のウォーレスさんは、少子高齢化を人口革命って命名したうえで、投資、住宅、ビジネス、労働、年金という五つの具体的な分野について、人口革命が何をもたらすかを具体的に予測し、可能であればそれに対して実践的に対応することを勧める。
第一、予測。投資については、リスクのある株式投資ができるのは中年世代だから、人口革命が進めば投資は減り、株価が下がる。住宅については、高齢者の貧富格差が拡大することに伴って、特定の地域の地価だけが上昇する。ビジネスについては、青少年ではなく高齢者が主な市場になるから、成人教育や健康・医療や資産運用やレジャーに対する需要が増え、青少年向けのブランドの需要は減る。労働については、高齢者の退職勧奨やアウトソーシングが進む。年金については、人口革命の結果、賦課式の年金は不可能になり、積立化と民営化が進む。全体として、労働可能人口が減るから生活水準は下がる。
第二、対策。リスクのある株式投資よりは、債権投資を選択しよう。企業に依存するよりは、生涯学習を続けて自分の価値を高め、独立も考えよう。労働可能人口が減れば、外国から移民を呼ぶか、技術革新を進めるか、退職年齢を引き上げざるをえないだろう。経済が成熟するから、株主資本主義化やサービス経済化や消費者経済化を進めよう。
もちろんウォーレスさんの説明には問題もある。たとえば、株主が優待されなきゃいけない理由がわからない。移民が来てくれる保証がない。一方で企業は高齢者を必要としないっていいながら、他方で退職年齢の引き上げを主張するなど、議論がぶれる。でも、彼の提示する予測と対策には一種の臨場感がある。日本が高齢化するとき娘はまだ若いから、希少価値として大切にされるかもしれない。でも、社会全体のあり方は、僕らには想像もつかないものになってることだろう。娘がこの状況を自力で打開できるようにすることが、親の努めなのかもしれない。
紙の本

紙の本げんきなマドレーヌ
2001/09/12 06:51
お菓子じゃないマドレーヌもよろしく
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
子供も二歳くらいになると、読み聞かせる絵本のストーリーが少しずつわかるようになるし、片言だけど言葉も喋るようになるから、次のセリフを予測して喋れるようになる。娘は今ちょうどそんな段階で、読み聞かせをしてて楽しい。途中で一瞬黙って待ってると、セリフの一部を自分から口にしてくれて、一種のコミュニケーションみたいになるのだ。生まれてからの長い日々を思い出し、ようやくここまで来たかと感無量な毎日である。というのは大袈裟だけど、やり取りをしながら絵本を読むのって楽しい。そんな娘の最近の愛読書の一つが、一昔前のパリを舞台にした、この「マドレーヌ」シリーズだ。
娘は一歳になる前にフランスで暮らしたことがあるから、当時のことを思い出して懐かしがりながらこの本を読んでる、というのはもちろん嘘だ。こんなに小さい子供が日々の生活を鮮明に覚えてるはずはないし、生活したのはパリじゃないし、生活そのものも大変だった。なにしろ言葉が通じない。僕もかみさんも多少の日常生活会話の心得はあったし、食べなきゃ生きられないって考えれば買い物はどうにかなった。要は必要に迫られるかどうかなのだ(日本に住んでる日本人が外国語を喋れないのは必要に迫られないからだ。英語教育を強化しようって意見があるけど、無意味だし、英米の片田舎に放り込めばすぐに喋れるはずだ)。ところが、問題は病気だった。フランス到着後一週間目に、当時九ヶ月の娘は高熱と発疹でふらふらになった。週末の深夜だったので内科の医者の往診を頼んだけど、とにかく医学用語がわからない。辞書と首っ引きで、医者が言ってることのうち必要最小限のことだけは、どうとか理解した。これも必要に迫られたわけだけど、こういう必要にはあまり迫られたくない。結局、最終的には小児科に行き、突発性発疹だったことがわかってめでたしめでたし。のはずが、今度はその数種間後にベビーチェアから落っこちた。フランスでは台所はタイル張りで、僕らは台所に食卓を置いてたので、娘は頭からタイルに突っ込んだわけだ。これまた心配したけど、幸い大丈夫だった。でも頭(というか額)のこぶと青あざは、しばらく消えなかった。
話がどんどんずれてしまったけど、この本を読むと、そんなフランス生活で苦労した思い出が一気に蘇ってくる。とくにこの本は、主人公のマドレーヌが盲腸炎になって病院に担ぎこまれるっていうのが主なストーリーだ。僕は、フランスの救急車のマークは青い十字架だとか、大抵の都市には二四時間往診システムが整備されてるとか、本筋と関係ないことばかりに頷きながら読んでしまった。
そんなことは抜きにしても、この本は面白い。リズムが良い文章というか訳文。下手なようにみえるけど、きちんと計算されてる絵。「パリの、つたのからんだあるふるいやしきに、一二にんのおんなのこが、くらしていました」から始まるストーリーのリズム感。そして「ねずみなんかこわくないし……どうぶつえんのとらにも、へいっちゃら」ないたずらっ子のマドレーヌと、「なにどこにもおどろかない」先生のミス・クラベルの名コンビ。子供たちの生き生きした日常生活が目にみえるようだ。
もう一つ感心するのは、この「マドレーヌ」シリーズには他に何冊かの絵本があるけど、レベルが下がってないことだ。たとえば「お化けのバーバパパ」シリーズは、第一作は本当に繊細な絵だけど、その後はほとんどアニメ調の荒い絵になってしまう。こんなふうにレベルが下がってくシリーズがあるなかで、「マドレーヌ」シリーズは、この第一作以後の本も丁寧に作られてる。ちなみに、うちにはこのシリーズがほとんど揃ってるし、マドレーヌの人形だってある。娘を寝かしつけるのに役立つし、ちゃんと活躍してるのだ。
紙の本

紙の本アンジュール ある犬の物語
2001/08/30 09:57
ミニマリズムの勝利
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
もうすぐ二歳になる娘の愛読書になった。この本を読んでるとたまに寝てくれるので、大変助かってる。ありがたい本だ。セリフが一切ないので読み聞かせる親が適当に言葉を補わなきゃいけないんだけど、そこがまた面白い。ちなみにうちではこんな感じが定番だ。
「ある日、ワンワンはブーブー(車)の窓からぽいっとなげだされました。びっくりしたワンワンは一所懸命ブーブーを追いかけて走りました。走って走って走りました。でもブーブーはみえなくなってしまいました。がっかりしたワンワンはしょんぼりして歩き出しましたが、あれっ、何か音がしました。それは別のブーブーの音でした。ワンワンは、また皆に会えるかなぁと思って近づき、ぴょんとブーブーの前に飛び出しました。危なぁいっ。ブーブーはワンワンを避けようとして、ガッシャーン、反対から来たブーブーと衝突してしまいました。ワンワンはびっくり、ブーブーはコロリンとひっくり返ってしまいました。ワンワンが遠くでみていると、ブーブーはドッカーンと火を吹き、人々が集まってきました。ワンワンはまたしょんぼりと歩き出しました。歩いて歩いて歩きました。途中で一休みし、ワオーンと空にむかって鳴き、また歩いているうちに夜になりました。町に着きました。道路で、おじさんに、あっちに行けって怒られました。しょんぼりと座っていると、むこうからみゆちゃん(娘の名前)がやってきました(ここで娘の歓声)…」
突然捨てられてしまった犬の寂しくもハッピーエンドの一日を鉛筆のデッサンだけで描いたこの本は、上で書いたようにセリフが一切なく、鉛筆の白黒の画面がシンプルなこともあって、読み手の想像力を刺激してくる。また、読み手の読み聞かせ力に挑戦してくる。最小限の情報しか盛り込まないミニマリズムの勝利。絵本だからって馬鹿にしてはいけない。
ただし問題が一つ。この本の原題はフランス語で『Un jour, un chien』、日本語に直すと直訳で『ある日、一匹の犬が』、意訳しても『ある犬の一日』ってところだろう。それを『アンジュール』っていわれても、どういう意味なのかわからない。もしかしてフランス語がわからない人が日本語のタイトルをつけたんだろうか。
紙の本

紙の本ユビキタス・コンピュータ革命 次世代社会の世界標準
2002/06/19 09:54
実験一本勝負
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
号砲一発飛び出して、あっという間に大幅リード、でも最後に疲れて、追走してきた集団に飲み込まれかけてデッドヒート。そんな感じを与える本だ。著者の坂村さんはOS〈トロン〉の開発者。最近出た科学者や技術者のインタビュー集(畑村洋太郎他『成功にはわけがある』、朝日新聞社、二〇〇二年)のなかで圧倒的な存在感を発揮しているので、何を考えているのかを知りたくて、読んでみた。
この本の白眉は、何といっても、近未来のコンピュータのあり方を論じる部分だろう。そこで坂村さんが惜しげもなく披露するアイディアの数々は、独創的で論理的で、しかもそれだけではなくて、実現可能かつ製品化を視野に入れている点で、僕のようなコンピュータ科学の素人でさえも唸らせるものだ。僕はパソコンを使って仕事をしているけれど、基本的には素人だから、突然画面が真っ暗になるなど、何か起こったときには本当に困っている。それに対して坂村さんは「どこでもコンピュータ」(九頁)を提唱するけれど、これはパソコンと正反対の発想をもとにしている。つまりコンピュータは「誰でも使え」(八二頁)て「人間を助ける」(二一六頁)ような「環境」(六三頁)でなければならないのだ。そして、その背景には、コンピュータ技術はオープンでパブリックでなければならないという「基本的な理念や哲学」(一一三頁)がある。
ただし、しゃべるだけならサルでもできる(無理か)。坂村さんのすごさは、単なる提唱にとどまることなく、それを〈トロン・プロジェクト〉として実践してきたことにある。そのうえで、いまは「電子実体」(一三一頁)という、情報に実体を持たせる試みを続けているらしい。情報に実体を持たせようという発想そのものに、僕は圧倒される。
ただし、こういった「どこでもコンピュータ」が作り出す近未来の社会「電脳都市」(二四五頁)のイメージは、どこでもコンピュータが使え、二四時間化され、機能が分散された空間という、わりとよく聞くようなものに留まってしまう。もちろん、理念にもとづいて思考実験と実際の実験(実践)とを積み重ねるのは大変な営みだし、近未来社会をイメージする仕事を科学者だけに押し付けるのは間違いだということは、わかってはいるけれど。
紙の本

紙の本成功にはわけがある 「創造力」の正体
2002/06/13 16:57
失敗は成功の母である
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
世界的な発見や画期的な発明をした八人の研究者や技術者のインタビュー集。ひとつ間違えると、ただの自慢話に終わってしまったり、〈日本も捨てたもんじゃないなあ、うん〉型の美談になりそうなテーマだが、そうならないのは、やはり〈失敗学〉の権威、畑村さんがこの本に一枚かんでいるからだろう。この本を読むと、どんな偉大な発見や発明の裏にも、偶然、不運、失敗、試行錯誤、思いつき、出会い、といった要素が存在していることがわかる。〈失敗と成功は紙一重〉であり、〈失敗は成功の母〉なのだ。
たとえば、カーボンナノチューブを発見した飯島さんは「物を見ることと物を発見することのあいだには、大きな差があります」(二一〇頁)と言う。この言葉が重いのは、発見者がノーベル賞を受賞した炭素分子フラーレンを、世界ではじめて電子顕微鏡で〈見て〉はいたが、〈発見〉は逃したという失敗の経験を持っているからだ。
光触媒を発見した藤崎さんは、光をエネルギー源として利用しようとしたものの、変換効率が悪くて行き詰まっていたときに、何人かの研究者や技術者と出会い、環境問題に応用するという新しい視点を見つけることができた。
そして、畑村さんは、こういった〈成功と失敗は紙一重〉型の人々のしごとには失敗や試行錯誤が付きものであり、それらを許容するような社会でなければ創造的なしごとは生まれないと主張する(「おわりに」)。これは、まったくそのとおりだと思う。
ちなみに、ただ一人、コンピューターのOS〈トロン〉の開発で知られる坂村さんの言葉だけは異彩を放っている。リアルタイムの情報処理、電化製品への組み込み、「組み込み、遍在、分散、オープン」(一三〇頁)、「超漢字」(一三三頁)、そして実体のない電子的なデータに実体を与える「電子的実体」(一三五頁)。「時代がトロンに追いついた」(一一五頁)という謳い文句は、どうも嘘ではなさそうだ。それほど、坂村さんの言葉からは、偶然も不運も失敗も試行錯誤も思いつきも出会いも蹴散らすような、強い信念が伝わってくる。
この本を読んで「想像力」の正体がわかるとは思えない。でも、科学者や技術者の世界の面白さというか、奥深さというか、そういったものが伝わってきて、僕らをわくわくさせてくれる本だ。
