ドン・キホーテさんのレビュー一覧
投稿者:ドン・キホーテ
紙の本

紙の本制服捜査
2021/12/02 09:36
交番巡査部長の勤務日誌
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
佐々木譲の警察小説である。北海道警のシリーズである。何年か前に道警本部ぐるみで裏金をプールして問題になり、退職した警察官も返却したというスキャンダルがあった。それは同じ職場に長年勤務していた弊害が原因という結論に達した。勿論、それだけが原因とはとても思えない。
しかし、そのお陰で現場の警察官たちの勤務は乱れてしまった。今まで長年培ってきた分野における専門性を全く無視した人事異動が行われるようになったからである。所轄署の刑事課に勤務してある程度の仕事のコツをマスターしていた主人公も、地域課の交番勤務になってしまった。帯広近くの警察署の交番である。
地理、住民の特性、それまでのいきさつなど、ろくに教えられずに配置となった。札幌の署に勤務しており、せめて電話番として家族連れの赴任をしたかったが、子供の学校等があり、単身赴任となってしまった。
その主人公の交番勤務ぶりが面白い。赴任直後に地場の防犯協会長などのボス連中が押しかけてきて、この土地の事件処理方法を押し付けてくる。防犯協会長は元議会の議長経験者であった。この会長が刑事捜査を専門に勤務してきた主人公にとっては地元癒着となれ合いの元凶であった。
様々な事例で、読者の留飲を下げてくれる。痛快な警察小説であったが、地元での多種多様な嫌がらせや、悪しき習慣を一掃することはできなくても、正義を通そうとする交番巡査部長の信条がよく理解できる。さすがに読ませる佐々木譲であった。
紙の本

紙の本民王 1
2021/12/01 10:28
残念な政治小説
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
池井戸潤の政治小説というので期待して読んでみた。しかし、よくある設定で人間同士の中身が入れ替わるという仕掛けである。これが前提なのであまり真面目に読む気にはならなかった。
内容は政界の日常が垣間見えるというところだが、この入れ替わりが複数組登場するとなっては大人の漫画も同然である。読書意欲を喪失してしまった。こんな入れ替えなどの姑息な手段を使うまでもなかろう。そのまま書き進めばよかったのだ。
それでも池井戸が書く政治小説というだけでも面白そうだが、話が進むにつれてどのようにストーリーを盛り上げるかが問題であろう。それで禁断の手段に手を染めてしまったのかも知れない。がっかりである。入れ替わりなしのバージョンを書き直してもらいたいくらいだ。
政界に経験がない池井戸だから、それらしいストーリーを創造することができなかったのか。残念である。
紙の本

紙の本人質カノン
2021/11/23 17:39
宮部の短編小説集
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
宮部みゆきの短編集である。1993~95年のオール讀物と小説新潮に発表された短編7編を収めたものである。
短編7編に相互に関連したテーマはない。気に入ったものを以下に書き出してみる。「十年計画」は恋愛に敗れて、相手に復讐をしようとする女性タクシードライバーの話、「過去のない手帳」は大学生が電車の車内で網棚にあった雑誌と手帳を拾得したが、その手帳の持ち主が行方不明になっており、返却ができずにいるうちに持ち主に関心を持つようになった話。
「過ぎたこと」はある事務所に属する調査人がいじめ調査の依頼を中学生から受けたが、十年を経て街中でその中学生を見かける。後をつけると意外な人生を送っていることが分かる話、「生者の特権」は恋愛に敗れて、自殺志願で深夜に死に場所を探しているさ中、悩んでいる様子の小学生を見かけ、相手になっていると新たな生きるエネルギーを得る話。
いずれもテーマの関連はないのだが、30年近く前に発表された作品なので、社会のありようが共通しているという感覚を持つ。大人の失恋は年代の世相を反映していることはないと思うが、学校でのいじめの悩みは、このときから30年もの間、延々と続いている。否、学校が存在するようになってから続いているのかもしれない。
宮部は短編集も数多く発表しているが、どれも質が高く、奇想天外な点に興味を惹かれるのである。
紙の本

紙の本辞令
2021/11/23 17:32
日本的な経営慣行の改革を読者に訴えている
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
企業小説で名を馳せた高杉良の作品である。舞台は国際的な家電メーカーという設定である。同族企業のようでCEOにワンマン会長が座り、息子が社内におり、副部長を務めている。しかし、母親が人事に口を出して、息子を役員にしろと担当役員にねじ込む。会長もそれを制することができない。
典型的な同族企業であるが、国際的な家電メーカーといえばソニーしかないであろう。ソニーは決して同族企業という企業構成ではないが、それ以外は当たりであろう。主人公は宣伝部副部長の広岡である。
ある日突然に宣伝部副部長から人事部付という辞令を受ける。何も心当たりがないので、広岡は大いに悩む。左遷ではないかと心配する理由が明快であればこうはならない。何が失敗の原因なのかは知りたいところである。
これを巡って上司の部長、担当役員などが複数人登場し、広岡は探りを入れる。元はと言えば広告代理店の甘い誘いに乗り、海外旅行を受けるなどの疑惑の行動をしてしまう自業自得の判断の結果が出ただけだと広岡は推測する。
本書は30年も前に書かれた作品であるが、今から見ればこれでは経済成長で中国、韓国、台湾の後塵を拝するのは誰でも当然だと思うであろう。しかし、それでは現在ではどうかと問われてみれば、旧態依然の職場であるところが上場企業でも多いと思われる。広岡の人事に複数の役付き常務が登場すること自体、時代遅れに見える。
日本的な職場での非生産的な慣行、非効率的な決裁システム、社員の人事考課などをダイナミックに改革する必然性がここにある。読後感をいえば、上記のように思うのである。小説では単に表面的なことしか書けないかも知れないが、本書で書かれていることを改めて眺めてみると、日本企業の悪い点のみがクローズアップされているようにみえて仕方がない。モデルはソニーかと考えたが、少なくとも昔ソニーは風通しの良い会社であったように思う。モデルがソニーと言われるのはソニーにとっては迷惑なことかもしれない。
紙の本

紙の本流転の中将
2021/11/16 09:07
幕末の混乱ぶりを象徴する大名を描く
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
奥山の時代小説なのだが、本書は珍しく幕末モノである。主人公は幕末の桑名藩主であった松平定敬である。といっても幕末通以外にはあまり名の知れていない大名かもしれない。実兄が松平容保で、こちらの方が名が通っている。どちらも王政復古の折に幕府側として抵抗する。
最後の将軍徳川慶喜を頂点とする幕府は戊辰戦争などでほぼ崩壊していたが、慶喜自身も幕府の総括者としての自覚を失いかけていたようで、幕府側の指揮命令系統は行方が定まらない。主人公の定敬も慶喜について江戸に出てみたり、新潟・柏崎の領地に転じてみたりで腰が定まらない。最後は函館から上海に逃亡するというように逃げ回っていたようにも見える。
特に定敬自身に問題があったとも思われないのだが、尊王攘夷の運動に翻弄されたのであろう。徳川慶喜ではなく、定敬を主人公に持ってきたところが面白い。この逃亡の過程で様々な史上の有名人とも邂逅する。勝海州、幕府艦隊の榎本武揚などもその例であるが、武揚には相手にされない。
武士の政権にしては、幕府側に潔さが感じられないが、世間の動きには抵抗できないし、時代の波に呑まれた名門大名だったことが納得させられた。大河ドラマなどで幕末モノがよく取り上げられているが、明治の草創期が為政者達に如何なる混乱をもたらしたかを教えてくれる歴史小説であった。
紙の本

紙の本草の陰刻
2021/11/11 23:48
一昔前の四国地方の検察庁支部での事件捜査
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は松本清張が書いたお得意のミステリー小説である。ミステリー小説というと警察官が登場しそうであるが、本書では検察官が主人公である。愛媛県のある町にある松山地方検察庁の支部に勤務する検察官である。今でこそ検察官が主人公であるストーリーは珍しくはないが、おそらくこの当時は今ほど検察の存在が注目を浴びていなかった時代なので、これ自体が珍しかったものと思う。
主人公が勤務する支部には検事は主人公しかいない。そこで夜間の当直勤務者2名が食事をとりに街へ出かけたところ、留守中に書類を保管してある倉庫で火事が発生した。しかも、2名のうち1名は火事で死亡してしまった。
これが事件の始まりであったが、主人公はこの事件が単なる火事だとは思えず、心当たりを調べていく。調べれば調べるほど、不審な点が出てきた。大筋はこのような内容だが、如何にも清張の小説を読んでいるという書きっぷりが読者の印象に残る。
推理小説の質は、如何に早く小説の内容に引き込むかにかかっているといってもよい。成長の小説はそこが抜群に良い。本書もそうである。また、随分冗長であるように見えて、それがきちんと伏線になっているのも清張の特徴である。
文庫本でもかなり分厚い一編であるが、あっという間に読了してしまった。このような本との出会いはミステリーファンにはたまらない。そして、清張は多作家だったので、未読の書は山ほどある。有難いものである。
紙の本

紙の本かばん屋の相続
2021/11/10 11:24
金融機関にかかわる人物描写が見事である
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
元銀行員であった池井戸潤の銀行に関する小説である。6編の短編からなる短編小説集である。本書を構成するこの6編の短編小説は、いずれも主人公が銀行勤めの若手の銀行員という設定である。
しかし、銀行員と言っても随分多様である。その銀行員として様々な業務を担当する若手の活躍と悩みを表現した小説である。といえば、池井戸も元銀行員である。おそらく自分の銀行員時代を振り返って、読者が興味を持ちそうなエピソードを小説化したものと想像できる。
今や銀行は構造不況業種に成り下がっているが、元銀行員の作家は結構大勢いることに気が付く。池井戸潤、江上剛、江波戸哲夫など上げればキリがない。しかし、池井戸の作品は他の作家とは一線を画している。
本書では銀行、金融機関に関するストーリーのいわばアンソロジーであるが、どれも相当な水準に達している。決してアンソロジー、オムニバスだからといって手を抜いているとは思えない。その一因を考えてみると、ここに書かれている短編はほぼ池井戸本人が銀行員時代に経験した話であろうと想像できる。
したがって、実にリアルなのである。加えて、登場人物の描写が巧みであるし、ストーリー全体に銀行員、融資先などの立場の異なる人々の生活の描き方が見事である。半沢直樹でもそうであったが、単に上記のように金融機関特有の事件の表面を描くのではなく、金の使い方や預金者などの個々の事情を表現している。
本書の短編の材料は短編にしてはもったいないくらいで、それぞれが大きなドラマの一部になっていると考えた方が読後の感想全体に納得がいく。
紙の本

紙の本笑え、シャイロック
2021/11/04 17:24
銀行の貸付金回収にまつわるストーリー
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
中山七里の描く銀行小説である。短編を5編集めているが、いずれも主人公は同じ人物で大手銀行の渉外部に勤務する若手の銀行員結城の物語である。
主人公結城が勤務するのは帝都第一銀行である。その渉外部というのはあまり耳にしない部署であるが、本書では融資の回収がその主たる業務という設定である。支店レベルでは融資の回収は融資課が担当するのが普通であるが、本書では渉外部ということになっている。
主人公が渉外部に異動になり、やや腐っているが、有能な先輩行員山賀の教えを受けて徐々に成長していく姿を描いている。短編は各々融資相手を変えて、読者に飽きさせない工夫をしている。例えば、出版社を早期退職した人物、新興宗教団体への貸付金の回収、貸付金の担保として確保している美術品の鑑定評価、担保物件の土地の鑑定など、貸付金の回収に関する実例を小説風に表現している。
有能な山賀は早々に殺害されて、結城は単独で勘を働かせてこの回収業務を続行していく。担保物件の鑑定、評価までその概要が登場する。なかなか読ませる内容である。その辺りは一般の銀行利用者にはなかなか見えない面が多いので、興味深かった。
紙の本
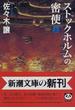
紙の本ストックホルムの密使 上巻
2021/10/24 11:18
スパイ小説風に戦史のプロローグを描く
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
佐々木の所謂三部作の最後の一作である。これまでの『ベルリン飛行指令』、『エトロフ発緊急電』そして、真珠湾攻撃に際しての駐米大使館での物語である『ワシントン封印工作』はそれぞれ関連した一連の作品群である。
大部の文庫本上下2冊でたっぷりとした内容で、冗長のように見えてもかなり中身の濃い作品である。戦時中、ストックホルム海軍駐在武官であった大和田大佐は、連合国、そして同盟国のドイツの動きの詳細を本国に伝えていた。しかし、本部はその貴重な情報を黙殺してきた。戦争末期に同盟国のドイツは無条件降伏し、日ソ不可侵条約を結んでいたソ連の動きが怪しくなってきた。
そのソ連がポツダム宣言の受諾と連動して、条約を破棄して満州に攻め込んでくるという情報、連合国側が原爆の開発が完成した情報を大和田大佐は入手した。日本に送ったにも関わらず、政府は依然として動かない。業を煮やした大和田大佐は複数のルートでそれらの重要な情報を送ろうとする。
その担い手が風来坊で在仏の日本人である森四郎であった。ポーランド人スパイと一緒にモスクワ経由で日本にたどり着いた森は、海軍書記官に情報を手渡す。しかし、時すでに原爆は広島、長崎に投下されたが、終戦を回避しようと陸軍はクーデターを仕掛けて政府を襲撃する。この一連の動きは映画にもなった半藤氏作の『日本の一番長い日』と同じ状況を描いている。
実に興味深い記述であるし、読者を興奮させるシーンでもある。大勢の犠牲者を出した太平洋戦争も終わりを迎え、登場人物たちもそれぞれの終戦を迎えたわけである。三部作の最終作品にふさわしい盛り上がりを感じさせた。少し以前のスパイ作品を彷彿とさせる作品であるとともに、欧州のスウェーデン、スイスからユーラシア大陸を横断する逃避行は圧巻であった。
すでに80年近い年月を経過した大戦であるが、時とともに人々の記憶からは風化していく。本書が細部にわたって史実であるか否かは別として、大戦の終結の仕方や文民統制ができなかった当時の軍政の在り方など、現代人には是非知っておいてもらいたいと思った。
紙の本
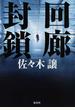
紙の本回廊封鎖
2021/09/22 22:24
迫力があるモデル小説
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
佐々木譲の警察小説である。警察小説として読み始めたが、やや通常とは異なるようである。勿論、警察官は登場する。警視庁捜査一課の刑事2名が主人公のように見えた。殺人事件が続けて発生した。被害者の身元を探っていると、皆元大手消費者金融の社員であった。しかも、各支店の幹部であった。
実はその大手消費者金融は表向きは過払い金が支払えなくて、破綻していた。それだけではなく、同社の創業者の息子が香港に住居を移していたので、国税当局を相手にすでに支払っていた税金の還付訴訟を起こしていた。この結果、裁判所はその訴えを認めて二千億円の還付を決定したのであった。
会社は破産してしまい、当然過払い金の返還を目論んでいた消費者金融の利用者は会社に対しては恨み骨髄であった。その調査は佐々木譲のいつものように丁寧に情報を収集していくが、殺人事件の犯人の動きをある程度掴むことに成功した。
ただし、たしかな証拠が収集できていない。その中で犯人たちは香港から息子が帰国するというニュースを掴む。実際におきた出来事を下敷きにしているので、臨場感がある。結局この消費者金融は市場から消滅した。
モデル小説とは言っても、最後は読者サービスかも知れない大立ち回りがある。そして佐々木譲の十八番である刑事たちの丁寧な捜査が見ものである。
紙の本
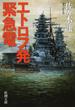
紙の本エトロフ発緊急電 改版
2021/09/22 17:58
戦中の情報戦を描く
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
これは佐々木の初期の作品群のうちの1冊である。初期の作品群には戦時中のストーリーが数多い。『ベルリン飛行指令』、『ワシントン封印工作』、『昭南島に蘭ありや』、『ストックホルムの密使』などである。いずれも名作で名高い。いずれも外国の地が舞台となっているが、本書は中でも現在、戦争以来ロシアに不法占拠されている千島列島の択捉島が舞台となっている。また、登場人物が別の巻に顔を出すことも多い。
択捉島、国後島、歯舞島、色丹島の北方四島は根室の先にある寒冷の地である。漁場としても有意な島々である。現在はロシア人約三千名が居住している。もう少し詳しく言えば、舞台となっているのは択捉島の単冠湾(ひとかっぷわん)である。単冠湾と聞いてすぐに反応する人は、おそらく年輩者であろう。
米国情報部は日系人スパイを送り込み、本当にこの北の果ての単冠湾に連合艦隊の主力部隊が集結し、ハワイの真珠湾攻撃を敢行してくるのか否かを確かめたかった。この日系人スパイが主人公の斎藤賢一郎である。
当初は択捉島がなかなか登場せず、タイトルは択捉島ではなかったのかと疑問も持ったのだが、択捉島が最終目的地と言えよう。真珠湾攻撃に絡むストーリーなのであるが、わざわざ日系人を登場させるところに無理があったという印象を持ったが、ストーリーとしては必要であったのかも知れない。
寒冷の地の択捉島までの追跡劇はなかなか迫力もあるし、荒涼とした気候がその雰囲気を盛り上げていく。本書もドラマ化されたようだが、上記の佐々木譲の関連の各小説は、戦中秘話として興味深い。
紙の本

紙の本源氏将軍断絶 なぜ頼朝の血は三代で途絶えたか
2021/09/22 17:38
頼朝は源氏の将軍家を続ける気があったのか?
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書はPHP新書の一冊である。やはり来年のNHK大河ドラマ『鎌倉殿と13人』を盛り上げる新書であろう。著者の坂井教授はその大河ドラマの時代考証を担当するとのことである。大河ドラマもこれだけ続くと、歴史上の有名な人物を単に描くだけでは材料が足りなくなってきたようだ。同じ時代、同じ人物を描くにしても細部にわたって人気の出そうな部分を切り取るようになってくる。しかし、それは両刃の剣であって、皆が同じポイントに興味を持つか否かは不明である。したがって、視聴率も長期低落傾向が顕著である。
本書もまさに頼朝が天下を取り、武家政権が誕生するところから始まる。鎌倉時代の武家政権では数々の伝説や逸話が遺されている。坂井教授はそれを『吾妻鏡』、『愚管抄』などの古文書を紐解いて、伝説や逸話の定説を覆す。
鎌倉将軍の歴史は三代までが源家で、それ以降は天皇家または摂関家から将軍を招いている。なぜ、源氏は三代までで終わってしまったかを明らかにすることが本書の最大のポイントである。
頼朝はいわば創業者であるが、源氏の系図を見てみれば源氏に連なる武士は大勢いる。頼朝の代まで下れば分家や親族は全国に散っており、相当な力を持つ分家もある。それらを制圧して頼朝が武家の棟梁の地位に上ったことは、頼朝の力量と言えよう。
問題は2代以降である。とりわけ、これまでの通説では頼家の評判は芳しくない。その源は『吾妻鏡』にあるという。北条家によって著された同書には、2代、3代の頼家と実朝は蹴鞠、和歌などの京風の趣味に溺れてろくに公務をこなしていないと書かれている。ところが、史料の少ないこの時代でも、ないわけではない。愚管抄がそれである。2人とも極めて真面目に公務に取り組んだと書かれているようだ。
こう見てくると、北条家がまとめた『吾妻鏡』は虚実ないまぜに書かれており、北条家に不利な記載は隠され、有利な記載は誇大に表現されているという当然の結果である。北条家の代々の執権には、義時、泰時、時頼、時宗など傑出した実績を遺した傑物もいたようだが、概して信憑性が薄いと言わざるを得ない。
これまで我々が知ることのできた史上の事実は、ほぼ『吾妻鏡』が出典となっているようだ。しかし、本書を読むとこの鎌倉時代の様相はだいぶ異なっている。気の毒なのは頼家や実朝であろうか。とはいえ、新たな古文書の発見によって人間同士の憎悪、対立、親近性などの感情的なところまでは到達するのは困難であろう。
本書も何故源氏将軍家が3代で終わってしまったかの結論を出すまでには至っていない。13人に代表される頼朝の御家人たちは皆隙あらば将軍を狙っており、それに勝ち残ったのが北条氏であることは間違いないようだ。
紙の本

紙の本あしたの官僚
2021/09/18 09:00
『官僚たちの夏』の現代版か?
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
国家公務員として霞が関の本省に勤務する官僚の物語である。これまで様々な作家が官僚を取り上げて小説化している。城山三郎の日本銀行や官僚たちの夏がとくに名を知られている。この物語の舞台は厚生労働省である。時代によって注目される官庁も変わっていくということか。
本編では、厚生労働省公共政策局に勤務する係長クラスの官僚が主人公である。この官僚、松瀬がよく口にするのは、城山三郎が著した官僚小説、『官僚たちの夏』であり、その主人公である風越通産事務次官である。この小説は随分前に週刊誌に連載されたものである。しかし、これは所謂モデル小説である。実在した誰それが描かれている官僚であることが分かるものであった。本編は作家の作り上げたフィクションである。そこが大きな違いである。
したがって、ここで登場する社会的な問題は実際にはなかったものである。そしてもう一つの大きな違いは、本編は国会と官僚の関わり合いがかなり濃密に描かれている点であろうか。議員からの質問を受けて、官僚がその答弁書を作成する。この過程がかなり細密に描かれている。おそらく城山が描く当時の通産省では国会での議論よりは国家全体の通商政策や産業政策のあり方に議論が集中していたのであろう。
国会での議題や質問内容も現在とは異なる点が多いようだ。城山は国の産業政策の行方に注目していたようだが、周木は厚生労働省をはじめとする中央官庁での官僚の働きぶりを、より具体的に描いていきたいと考えたのであろう。どちらがよいとも言えないが、この描写を見ると、官僚志願者が減ってしまうのも分かるような気がする。
ストーリーはハッピーエンドに近いが、主人公の働きによって職場の雰囲気が改善されて、新たに働く意欲が出てきたというものだ。この辺りは企業ものでも全く同じで、官庁という舞台を借りたものだと思えばよい。しかし、舞台である厚労省の実態の一端がよく理解できる小説であった。
紙の本

紙の本身もこがれつつ 小倉山の百人一首
2021/08/25 11:26
藤原定家と歌人そして武家と公家の争い
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は周防の描く平安時代の歌人の世界である。具体的に言えば藤原定家の一生をその周囲にうごめく人々の姿とともに描いている。定家といえば歌人の頂点に立っていた貴族であるから、本書にも和歌がふんだんに登場する。和歌といってもわれわれに最もなじみの深い和歌である。すなわち、百人一首がその中心となる。
周防は以前の作品の中にやはり歌人であった紀貫之を主人公にしたものがあった(『逢坂の六人』)。これは貫之が古今和歌集の編纂を命じられた話を取り上げたものであった。名前だけは聞いたことのある平安時代の歌人が、大変身近に感じられる描き方で、個性豊かな歌人たちが面白かった。
本編もその続編と考えてよいが、やや時代が後になり、歴史的な事変なども加えられており、歴史を語る小説としても面白い。その最たるものが鎌倉将軍の登場である。それは源実朝である。実朝は金槐和歌集という歌集を編纂している歌人である。あえなく身内に暗殺されてしまうが、和歌における定家の弟子でもあった。時代が下り、もう一人の主人公である後鳥羽上皇も本書のスターである。
しかし、この後鳥羽院も彼我の軍事力を見誤り、承久の変をおこして流人となる。この時代としてはかなりの激変で、いよいよ武家が内裏を支配する時代の到来を実感させたわけである。そういえばNHKの大河ドラマ『鎌倉殿と十三人』スタートまで間もなくとなった。そちこちで話題を耳にするので、プロモーションも盛んなのであろう。本書はその全体を知るには最適かもしれない。
ストーリーの軸としては定家、後鳥羽院、定家の親友である藤原家隆の三角関係の変遷がつづられている。さらに歴史的な変事が絡まり、和歌中心のストーリーのはずであるが、和歌以外でも十分楽しめるものとなっている。周防は現代ものも書いているが、本書や時代ものの作品が抜群に面白い。シリーズ化して欲しいと思う。
紙の本

紙の本憂いなき街
2021/05/06 08:15
道警シリーズの面白さが出ている
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
北海道警本部の刑事が主人公の物語である。これも北海道警シリーズに含まれているようだ。主人公は道警札幌の大通署刑事佐伯である。本編ではその佐伯と以前仲間であり、現在は機動捜査隊に属する津久井が活躍する。
札幌で開催されるジャズ・フェスティバルの主役であるサックス奏者がバンドを組んで久しぶりのセッションを行うことになっていた。そのピアノ奏者の女性が津久井と親しくなり、一夜を共にした。ところが、このサックス奏者は女性関係が複雑で、女性ファンも多かった。
セッションが近づくさなか、女性ファンらしき人物が殺害される。ストーリーはその犯人を追及する津久井と佐伯の刑事同士のつながりを描いている。テレビ等で描かれる機動捜査隊は初動のみに関わるだけで、所轄あるいは本庁の刑事に引き継いで任務完了となる場合が多い。このケースは珍しく津久井の出番が多い。
ところが、佐伯は個人的にセッションで演奏側のピアニストとねんごろになってしまうが、そのピアニストにも殺人の容疑がかけられてしまう。その殺人のあった前夜佐伯はそのピアニストと一緒にいた。
表面化はしなかったものの刑事自身にも容疑がかけられてしまう恐れがある。捜査側が容疑者になりかねない状況である。それが現実か否かは分からないが、警察官の人間らしい、否プロらしからぬ姿も本編では描き出している。
いつもそうなのだが、急転直下犯人が判明し、事件は解決する。本編ではジャズのサックス奏者は意外に女性にもてるのはよいが、後の不始末の様子がピックアップされている。これが現実なのか否かは分からないが、リスクに対して無防備な音楽家と警察官という印象が読者に植え付けられたのかもしれない。
