コーチャンさんのレビュー一覧
投稿者:コーチャン
紙の本

紙の本虞美人草 改版
2012/11/14 00:56
漱石文学初期の主人公
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
甲野欽吾は、亡くなった父の遺産を、継母が実の娘の藤尾にやりたがっていることを知っている。彼は、遺産をみな藤尾にやり、自分は一人で暮らしたいと言うが、世間体を気にする継母は、甲野の家督にこだわり、これを認めようとしない。
一方、明るく豪胆な甲野の親友、宗近は、藤尾に好意をいだき、甲野も妹が彼といっしょになることを望む。しかし、気位が高くわがままな藤尾は、宗近よりもむしろ自分の自由になり、社会的地位も教養もある男、小野清三に近寄る。小野も彼女の財産に目がくらみ、許婚となっていた恩師の娘、小夜子を捨てようとする。小野があやういところで、良心をとりもどして、小夜子のもとへ戻るのに対し、最後まで我を通した藤尾には悲劇的な結末が待っている...
漱石が本格的な作家となって初めて書いたという『虞美人草』は、同じく初期の『坊っちゃん』、『二百十日』などと同様、正義感にあふれた小説である。これらの作品では、人間の心理や社会にひそむ悪があばかれ、それへの断罪がおこなわれる。『虞美人草』における悪役は甲野の継母であり藤尾である。それに対比した正義と純粋の人もいる。この作品では宗近とその妹の糸子、あるいは小夜子がそれに属する。
しかし、この単純明快な勧善懲悪の物語においても、のちの漱石文学における典型ともいえる分裂的な人格は姿を見せている。この作品では、主人公の甲野がその人物である。世の中のあらゆる偽善に我慢できない彼は、継母を軽蔑し憎んでいるようである。しかし、世間体を第一に置く彼女の生き方は純粋とは言えないものの、きわめて常識的であり、彼女のさもしい魂胆を理由に家も財産も投げ出そうとする甲野の方が、わがままという気がする。
この時点における漱石作品の主人公たちは、純粋に善を求めながら、自己のうちに何の矛盾も破綻も抱えていないようである。ところが、後期作品の主人公においては、完全無欠だった精神状態も次第に支障をきたすようになる。『行人』や『彼岸過迄』においては、自己の潔癖性と他者への猜疑心から分裂する人格が、また『こころ』では、かつて他者に向かって放たれた非難と憎悪の矢が、自分自身へともどり、ついには自ら死を選ばざるをえない悲劇的人格が描かれるようになる。
漱石にとって最大の問題は、「私」であったとは、よく言われることである。他者が、社会が、国家が悪いと論じ、それを非難することは、一種の心地よさをあたえる。しかし最も苦しいのは、自分で自分がいやになること、みずからが自分の敵になることである。「則天去私」にいたるまでに漱石自身が大いに悩んだ「私」とは、そのような苦しみを知った自己であり、甲野のように自己の倫理感に充足している人格ではないという気がする。
物語の最後、甲野はロンドンに旅立った宗近に宛てた手紙で、次のように述べる。
「道義に重きを置かざる万人は、道義を犠牲にしてあらゆる喜劇を演じて得意である...この快楽は生に向って進むに従って分化発展するが故に―この快楽は道義を犠牲にして始めて享受するが故に―喜劇の進歩は停止する所を知らずして、道義の観念は日を追ふて下る」
これに対して宗近は『此処(ロンドン)では喜劇ばかり流行る」と返事をした。これが甲野への同調か、反論かはここからはわからない。しかし、後期の漱石作品の主人公たちを追い詰めたのが、他ならぬ道義の問題であったことを考えると、彼らにむしろ必要だったのは、喜劇だったのかも知れないとも思われる。
紙の本

紙の本不連続殺人事件 改版
2012/05/17 23:57
論理と心理分析によって構成されたプロット
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
純文学の作家、坂口安吾が書いた不朽のミステリ小説『不連続殺人事件』。さぞかし、文学臭漂う、冗長な文体と思いきや、まったくテンポよく無駄のない、それでいてウィットに富んだ気持ちのよい文章である。作者みずから本作において皮肉っているヴァン=ダインやクイーン流の衒学趣味を排除しつつ、文学、芸術についてのオリジナルな見解も自然に織り交ぜるあたりはさすがである。登場人物のほとんどが文学者であることもそれを成功させる要因だろう。
安吾は、だれにも犯人がわからない探偵小説を書くと豪語してこの作品を書き始め、犯人とプロットについての推理を公募したという。いわば、読者への公開挑戦状であるが、作品の中盤、探偵の巨勢が、「消去法」による一般的推理の盲点を突いた犯人の意図を漏らす時点で、重大なヒントがあたえられ、犯人の予想は容易であるという気もする。実際、結末までを正確に言い当てた読者は4人いたというし、作者の意図は完全に成功したとはいえないだろう。それでもトリックに頼らず、論理と心理分析だけで構成されたプロットは、実に緻密かつユニークで新鮮だ。
勝手な意見ながら、日本の古典的探偵作家の多くは、謎解きとは別の要素に力点を置いている気がする。たとえば江戸川乱歩の場合、怪奇性が、また松本清張の場合、社会性が追及されていて、それぞれ探偵作家としての確固たる名声にもかかわらず、トリックなどで読者をあっと言わせ、なるほどと唸らせる作品は案外少ない。その点、この『不連続殺人事件』は、イギリス、アメリカの本格ミステリと肩をならべるだけのプロットをもった、日本が世界に誇るべき良質の作品ではなかろうか。
紙の本

紙の本禁煙セラピー 読むだけで絶対やめられる
2010/11/29 00:58
不思議な本である。
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
タバコを吸ったことのない自分には、そもそもタバコを嗜好し、ましてやその中毒になる人の心情が理解できない。健康へのリスク、経済的負担にもかかわらず、多くの人がタバコを吸い続けることは、私にとっていまだに謎であり続けている。
そんな私にとってやはり不可解なのが、この『禁煙セラピー』という本の効用である。親戚の一人がこの本を読んでタバコをやめたというのを聞いたとき、正直驚いた。ヘビースモーカーだった彼は、この本を、タバコを吸いながら読み続け、終わりに近づいた頃、「ああ、これが人生最後の一本になるのだな」と思い、ついに読み終えた瞬間、タバコの火をもみ消し、それ以来吸っていないし、吸いたいとも思わないと語ったのである。しょせん言葉による説得に過ぎないものが、いかにしてそれまで依存してきた物への執着を読者から取り払い、その後も再びそれに依存させないようにできるのか。そんな興味が、タバコを吸わない私が本書を手にしたきっかけだった。
読んでみてさらに驚いたのは、そこに書かれてあるのはきわめて当たり前のことばかりである点である。タバコがなくては生きていけないという考えが幻想にすぎないこと。禁煙をすれば、食事もおいしく味わえるということ。タバコを吸うことはカッコイイどころか、むしろみっともないということ。ストレスを感じたり、集中力が出ないのはタバコを吸っているからだということ...
喫煙に関するこれらの否定的記述は、どれも世間一般で言われている類いのものである。おそらくはこの本を手にとったタバコ中毒者も同様なことはさんざん言われてきただろうから、ああまたかと、失望しつつ本を放り投げそうなものだが、実際にはこれを読んだ90パーセントの人が禁煙に成功しているという。
本書にも「この本に書いてあることはすべて紛れもない事実です。それもスモーカーならいつも、耳にタコができるほど聞かされていることばかりですね」とある。問題はその説得の仕方にあるのだろう。著者は、タバコの魅力として喫煙者がしばしば挙げるものが単なる思い込みや偏見にすぎないことを、ひとつひとつ例をあげながら、説いている。そのどれもが、タバコの魅力でも長所でもないということを明らかにしながら、喫煙という行為がいかに無益で有害なものであるかを読者に印象づけているようだ。
そうは言うものの、これらの議論の中で、なるほどとうなずけるものはそう多くはなかったというのが、私の率直な感想である。そもそもタバコを吸ったことのない人間が、タバコの無意味さを知ったところで、目からウロコの感動が味わえるわけもあるまい。さほど論理的とはいえない議論もひょっとしたら、ある種の暗示を依存症の読者にあたえるためのものかもしれない。いずれにせよ、私には永遠にわからない世界のようだ。
だが、本書は明らかに多くの人の禁煙を成功させている。上にあげた私の親類も、友人たちにこれを勧め、その全員がそれを読み、喫煙をやめたと言っていた。私も何人かに本書を紹介したが、その結果やめなかったのは、読まなかった人たちだけである。唯一これを読んだ人は、すぐにタバコとサヨナラをした。つまり私の知りうる限り、これを読んだ人の100パーセントが禁煙を成功させているのである。
この10月からタバコも値上がりし、現在多くの人が禁煙しようと奮闘している。彼らにとって、150ページほどの読書で長い間やめられなかったタバコから抜け出せるのとしたら、試してみないという法はあるまい!
紙の本

紙の本二大政党制批判論 もうひとつのデモクラシーへ
2010/08/27 23:02
はたして理想の政治体制か?
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
いつの頃からか日本人のあいだには、自民党の一党支配ではいけない、アメリカやイギリスのような二大政党制を確立しなければ真の民主国家たりえない、という風潮がうまれた。そして、そのような風潮が肥大して結果的に民主党への支持を強め、民主党政権の誕生の大きな要因となった。民主主義の先進国で発達した制度だからきっといいのだろうという漠然とした気分から、自民党と民主党の二大政党制を、日本における民主主義の進歩ととらえている人は、この本を読むとよい。二大政党制がいかに多くの問題をはらんでいるかを、殊に日本という政治的土壌のもとでは、むしろそれがマイナスに働きうるということを、これは教えてくれるから。
二大政党制の基礎にあるのはいうまでもなく政党政治であるが、政党とは本来、国内の特定の利益集団を代表するものである。歴史的に見て、西欧では社会の進展とともに、地方と中央、国家と教会、資本家と労働者という具合に、さまざまな階層の分裂と衝突が常に生じていた。そして、対立する集団同士の政治的主張の必要から議会制民主主義と政党制が発達してきた。
ところが日本の場合、近代化以降も社会の中に深刻な対立が存在しなかった。本書の著者は、このことがそもそもこの国に政党政治を定着させることを困難にしたと指摘する。これは、平等主義という、ある意味ですぐれた日本の社会構造に由来するものであるが、このため日本の政党政治は、常に上から民衆に与えられるだけのものとなり、民衆自身が参加するものとはなりえなくなった。
政党政治が上からのものである以上、それは政党執行部本位のものとならざるをえない。汚職事件が続き、政治改革が本格的に起動した1990年代、「政治改革イコール選挙制度改革」という通念が生まれ、中選挙区制から小選挙区比例代表制へと選挙制度が変わったのも、結局はそれが自民党を始めとする巨大政党の利益に合致したからにすぎないことを本書は明らかにする。そして、自民・民主による二大政党制も、もとはといえば小沢一郎というきわめて権力欲の強い党のリーダーが自己の権力拡張のために仕組んだシナリオにすぎないということは、本書の指摘を待つまでもなく明らかであろう。
本書ではまた、二大政党制によって、特定の集団がますます多数社会から除外される危険性を指摘している。これは、多数あった政党が淘汰されることによって二大政党の支持者の声しか政治に反映されなくなるというだけでなく、二つの政党それぞれが、有権者が離れるのを怖れ、互いに相違点のない似通った政策を実行するようになるからである。
つまり、二大政党制とは民主主義の理想像ではなく、民衆参加という民主主義の理念に反する政治形態なのである。これはアメリカやイギリスといった二大政党制の典型といわれる国においてさえ見られる傾向である。特に日本ではその弊害ははなはだしいというべきだろう。
二大政党制の弊害を明らかにして、この政治体制に対する妄信を戒めてくれる点で、本書は現代の日本人にとって大いに啓蒙的な書である。これは民主党政権誕生の直後に出版された本であるが、同政権への期待が大きく裏切られ、安易に自民党の対立勢力を求めていたことに対する反省の念が多くの国民の中にめばえている今こそ、手にとる価値のある一書かもしれない。
紙の本
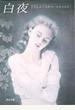
紙の本白夜
2009/04/30 02:10
ドストエフスキー作品の典型的キャラクター
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ペテルブルグの町なかを夜な夜な練り歩く若者が、本書の主人公である。友達もいない孤独な男だが、町で出会う人々や建物には愛情を感じている。彼はまた、人々が夏の休暇で町からいなくなるだけで憂うつな気分になるほどの寂しがりやでもあった。
そんな夏の夜、主人公はある運河のほとりでナースチェンカという若い女性と出会う。彼女は再会の約束をした許婚を待っているのだが、許婚は現れていなかった。主人公は、その後毎晩彼女に会って恋の手助けをしつつ、次第に彼女のことを好きになっていく。彼女も彼への感謝と尊敬の念を強める。四日後、いまだ現れない許婚に愛想をつかした女に、男は突如求婚をし、女もそれを受け入れる。幸せな気分で白夜の町を歩き回る彼ら。しかし、その直後女の許婚がそこに姿を現わす。走り去ってゆく女。一瞬にして遠ざかった幸せを苦々しく見つめる男・・・
四夜のできごとすべてが物語のタイトルである「白夜」に見た夢さながらに感じられる幻想的で美しい短篇作品である。ドストエフスキー作品ではおなじみのペテルブルクという都市の魅力も存分に描かれており、多くの読者が、このロシアの古都への憧れを強くすることだろう。
女の心変わりに涙を流しつつも、その幸せを願い、彼女との束の間の愛を大事に思い出にとどめようとするお人よしの主人公は、ドストエフスキーの典型的キャラクターの一つであろう。それは、『罪と罰』のソーニャ、あるいは『白痴』のムイシュキン公爵のように神的な愛の権化ではなく、俗的な欠点やもろさを有した普通の人間である。だが彼らは、不器用ながらも純粋でやさしい心をもっている点で魅力的である。『悪霊』のシャートフ、『白痴』のパーヴロヴィッチ、あるいは『罪と罰』のラズミーヒン、そしてこれらの原型ともいえる『貧しき人々』の主人公マカール・ジェーヴシキンが、このような人物の例といえよう。
紙の本

紙の本落穂拾い・犬の生活
2013/04/26 23:51
お前も生きていけ
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『ビブリア古書堂の事件手帖』で紹介された『落穂拾い』を含む小山清の短編集の復刻版が、ちくま書房から発売された。私自身ドラマを見るまでこの作家の名は知らなかったのだが、小山は太宰の弟子であったらしい。そのせいか作風には似たところも多く見受けられるが、太宰のように奇をてらったところは少なく、その真摯な作風には素直に好感がもてた。
たいていの作品の題材は、師の太宰同様、自身の生活や少年時代の思い出からとられている。これは私小説というジャンル一般に言えることかもしれないが、このタイプの小説は読んでいると、内輪話という印象が強く、文学的感動は薄れる。これらの短編もそのほとんどは、正直なところ退屈であった。
そんな中タイトル作品の『落穂拾い』は、自身の経験にもとづきながらも、オリジナリティのある作品でおもしろかった。語り手である作者は、北海道での思い出や、現在の生活の中から慰めになるような人々との出会いやふれあいを描く。夕張での炭鉱生活をともにしたF君、名も知らぬ純朴そうな隣家の青年、芋屋の優しいお婆さん、そして古書店の健気なうら若き女店主...どれも、中年作家の孤独な心に明るい光をともす者たちである。人間だけではない、自然からも彼は声をかけられ、励まされている。
―僕はいま武蔵野市の片隅に住んでいる。僕の一日なんておよそ所在ないものである。本を読んだり散歩をしたりしているうちに、日が暮れてしまう。それでも散歩の途中で、野菊の咲いているのを見かけたりすると、ほっとして重荷の下りたような気持になる。その可憐な風情が僕に、「お前も生きていけ。」と囁いてくれるのである。―
「お前も生きていけ。」こんなふうに、自然であれ人間であれ、毎日の生活の中から、慰めを感じられたらいい。辛いことがあっても、それでも人生はうつくしく輝いている、そう思えるようになりたい。こんなふうに私は感じた。
他の多くの作品についても同様である。もの言わぬ犬の心の声を交えながら、拾ってきた牝犬のお産までの奮闘をコミカルに描く『犬の生活』。若く無名のアンデルセンを理解し、励ました心やさしい文学者のサークルについて、アンデルセンから母親への書簡という形で綴った『聖アンデルセン』等々...どれも、人間とあらゆる被造物に対するやさしき愛にあふれた秀作である。
紙の本

紙の本怪獣ウルトラ図鑑 カラー版 復刻版
2013/01/29 00:40
デジャブの感動
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
表紙にはイカルス星人と戦うウルトラセブン、裏表紙には髪をとかしているアンヌ隊員とその背後から忍び寄るペガッサ星人...書店でこれを見たとき、少年時代の思い出が一瞬にして蘇った。それは、ウルトラシリーズの熱狂的ファンだった私が40年以上も前に愛読していた『怪獣ウルトラ図鑑』の復刻版だったから。(「鑑」という字もこの本で覚えたっけ...)
3990円という高値には躊躇したが、かつてもっていた同じ本が今はどこかへ行ってしまったので、懐かしさに負けて、購入してしまった。
本を開いてみると、ページをめくるごとに記憶はさらに鮮やかに呼び起こされた。豊富なイラストや写真とともに、今読むとおかしくて噴きだしてしまう各怪獣・宇宙人の解剖図(内臓の機能なども詳述)つきの解説なども、当時はまじめに読み耽ったもの。最後のページには、カネゴン、ケムール人、ぺスターといった怪獣のキグルミの作り方が紹介されているが、当時真剣にこれらを作ろうとして、できなかったことも懐かしい思い出である。
本書が網羅しているのは、ウルトラマン、ウルトラセブン、そしてウルトラQに出てくる怪獣たちである。ウルトラシリーズの図鑑ならば、もっと充実したいいものがいくらでも出ているだろう。だが、これら初期ウルトラシリーズをリアルタイムで観ていた世代にとっては、当時発売されていたこの種の図鑑こそが、少年時代の感動をそっくりそのまま呼び覚ましてくれるという点で最もありがたいという気がする。
なお、当時は目にも入らなかったが、作者の大伴昌司氏について調べてみると、彼はウルトラシリーズの製作スタッフの一人で、怪獣のプロフィールも主に彼が考えたようである。本書に掲載されているような怪獣の図解を少年雑誌などに載せ、怪獣ブームを盛り上げるのに一役買ったが、この図説をめぐって円谷一と対立し、二人は絶縁状態となったという。1973年36歳の若さで亡くなった、われわれの世代の夢を作ってくれた人に改めて感謝を捧げたい。
紙の本

紙の本ルネサンスの女たち
2012/10/31 23:53
塩野文学の出発点
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1969年に出版された塩野七生の文壇デビュー作。後に『ローマ人の物語』全15巻を書き上げ、その後も西ヨーロッパ中世史に関する数々の著作を執筆中である彼女の出発点となった作品が文庫本になったのは、意外なことに今回が初めてという。それを記念してか、今回の文庫版では、執筆当時の思い出を振り返った序文がつづられている。
それによれば、本作を書いた動機には、1960年代の高度経済成長のさなか、日本社会に充満していた微温的な雰囲気への反抗があったという。「みんなで仲良く、なんて嘘っぱちだと思っていたし、それで社会が進んでいると思って疑わない当時の日本のエリートたちが大嫌いだった。...イイ子でいたんでは生きていけないんですよ、昔のヨーロッパにはこういうたくましい人間が生きていたんです、と日本人に突きつけたい思いでいっぱいだった」。
本作におけるそのたくましい人々は、人類史上稀に見るほどに権謀術数の発達したルネサンス期のイタリアに生きた4人の女たちである。4人はそれぞれ、地位も、性格も、またそのたどった運命もさまざまであるが、どの女もさまざまな艱難を経験しながらも、運命を甘んじて受けるだけでなく、彼女らなりに我を通しながら生きている。塩野にとって、戦乱を生きぬいた女たちを描くことは、ぬるま湯のような環境に生きる60年代当時の日本人への反撥であり、また当時(今でもか)一般的だった「女=男の被害者」という視点へのアンチテーゼだったという。
それゆえ本書は、自主独立を尊び保守正道を歩むというその後の塩野文学の出発点となった作品といえよう。彼女はまた、ルネサンス時代を扱った本作の執筆を通じて、フィレンツェ、ヴェネツィア、さらに古代ローマといったその後彼女自身が取り込むことになるテーマが次々と見えてきたという。この意味においても、『ルネサンスの女たち』は文学者としての彼女の出発点となったわけである。
紙の本

紙の本地図で訪ねる歴史の舞台 日本 6版
2012/09/30 01:03
「世界」版と一体化してほしい
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
歴史とは地球上で繰り広げられるものだから、歴史を学ぶ上で地理的な知識は必須である。いわゆる世界史や日本史の図説には、各時代の各地域の地図が載っており、それぞれの時代の地理が把握できるようになっているが、それらはあくまでも現代とのつながりのない遠い時代の地図であって、それらを見てもどこか過去と現在とは遠いままである。
帝国書院から出ているこの『地図で訪ねる歴史の舞台』は、一見普通の地図帳だが、現代の地図に昔の都市名や重大事件の場所が別の色の文字で表示されているという、実に便利で興味深いものである。ページをめくっているだけで、歴史の現場が現代の空間によみがえってくるような印象をあたえられる。
この本、かつては日本と世界両方の地図が一冊に収められていたが、今は日本と世界別々の地図帳として販売されている。だがこれにはあまり感心しない。なぜならば新しい版には、地図以外に歴史上の人物の伝記や、関が原のような有名な戦さについての解説が掲載されているからである。
それらの文章そのものが悪いと言っているわけではない。堺屋太一のような著名人も筆をとっているようだ。しかし、あくまで本書は地図帳であって、歴史書、参考書の類ではないのだから、ただ地理的情報のみを提供すべきだと思う。1冊にまとめられていた旧版を日本の地図と世界の地図の2冊に分け、それぞれに余計な情報を盛り込み、わざわざ使いづらくした狙いは何だったのか。単に収益のためだとしたら、実にがっかりである。ぜひコンパクトなバージョンを復活させてほしいというのが、このシリーズの愛好者としての真摯な要望である。
紙の本

紙の本文明の衝突と21世紀の日本
2012/06/28 20:05
孤高の日本文明
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
冷戦が終わり、イデオロギー対立の消えた21世紀の世界を、ハンチントンは文明の衝突する時代と位置づける。文明は大きく7つ―すなわち中華文明、ヒンドゥー文明、イスラム文明、東方正教会文明、西欧文明、ラテンアメリカ文明、そして日本文明に―分かれる。 これらの文明には、それぞれ中核となる国家とそれに付随する国家が存在する。たとえば、中華文明の場合、中核国家は中国であり、それに台湾、朝鮮、そして東南アジアの華僑などが、それに属する国家や勢力として存在する。西欧文明におけるそれはアメリカ、ドイツ、フランス、イギリスという具合に複数存在する。イスラム文明のように、中核国家をもたない文明もある。同じ文明に属する民族や国家はたがいに仲間意識をもち、ときに同胞のために共に戦うこともある。イスラム文明と西欧文明の対立はその典型である。
ハンチントンの文明論において注目すべきは、日本を一国で一つの文明を形成するユニークな存在ととらえている点であろう。みずからが中核国家であるとともに、他にそれに属する国家も勢力ももたない単一国家、単一民族による唯一の文明、それが日本文明なのである。
日本は、東アジアの国でありながら中華文明ともちがう、またアジアで最初に西欧化に成功した国でありながら西欧文明ともちがう独自の文明を保持している。また日本人は、外国に移住をすると、アメリカの日系人社会のように完全にその国の文化・習俗に溶け込み、日本文明から脱却してしまう。このため、日本以外の地域でこの文明が勢力を伸ばすことはない。
このような特異性、孤立性は、日本がなんらかの危機に見舞われた場合、同じ文明に属するものとして手をさしのべてくれる勢力はないということを意味する。この不安定さゆえに、近代に入ってからの日本は、日英同盟、日独伊防衛協定、戦後の日米安保条約など強国との同盟を模索し続けたが、これらは対等な立場での同盟ではなく、相手に追随する日本にとっては危険な同盟であった。支配的な国は攻撃的になるかもしれないので、対等な立場での同盟の方がより安全である。今後アメリカが衰えれば、中国への追随的な同名を模索するであろうとハンチントンは予想する。
ハンチントンの分析は、日本人にとって示唆に富んでいる。まず日本が独自の長い歴史をもち、単一民族で一つの文明を築き上げたということに、われわれは誇りを持ってよいだろう。同時にこの事実は、世界における日本の根源的孤立状況を示すものであるから、おのずとわが国と他の文明との共存に大きな不安をいだかざるをえない。しかしだからこそわれわれは、まず不断の外交、防衛の努力を通じて、自国の安全保障体制を確立することが求められている。中国、半島国家、ロシアとの緊張はまさに中華文明、東方正教会文明と日本文明との文明衝突と位置づけられよう。
われわれはまた、国防だけでなく献身的な国際貢献を通じて、わが国の重要性を国際社会にアピールする必要にせまられているといえよう。それを怠り、ただ自民族の繁栄と安全のみを追求するならば、歴史上ユダヤ人がたどったのと同じ道、さらには現在もなおイスラエルがおかれているのと同じ軍事的緊張関係にみずからを追いやることにもなりかねない。孤高の日本文明がたどる運命は、われわれ日本人自身の手にゆだねられているのだから。
紙の本

紙の本現代社会主義を考える ロシア革命から21世紀へ
2011/09/30 09:20
「社会主義没落は歴史の必然」というところまでは...
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
個人的な話であるが、著者の渓内譲先生とはずっと昔に知遇を得、食事もご一緒させていただいたことがある。その立派な業績や名声にもかかわらず、当時学生だった私に対しても実に腰が低く、人懐っこく温かみのある態度で接してくださった。短いおつきあいながら、先生は私の中で、最も尊敬できる人物の一人として記憶されている。
そんな心の恩師の著書としてずいぶん前に購入したこの『現代社会主義を考える』を、最近になってはじめて読んでみた。反共という私の基本的な立場からすると、社会主義礼讃のような本を読むことには、やや複雑な思いもあったが、それでもさすがはロシア革命史、ソ連史研究の第一人者、多くの刺激と啓発を受けることができた。
本書は、1987年、ロシアがまだソ連だったころに書かれた本で、その主題は「社会主義は本当に人民を解放するものか?」という問題であるといえよう。とりわけ、当時ソ連が陥っていた危機的状況は、ロシア革命そのものに由来するものか、それとも単にスターリンという一独裁者のせいなのかという点をポイントに、議論がおこわなれている。
本書によれば、ロシア革命とは内政的には、都市部の労働者(ボルシェビキ)と農村部の農民との戦いでもあった。ボルシェビキが農民に譲歩したのが、ネップ(新経済政策)であったのに対し、その後の歴史はボルシェビキが農民の自由を抑圧する過程であった。それはレーニンも容認し、スターリンからはそれが国策となった。彼の死後も、その基本路線は変わらなかったという。つまり一党独裁国家は、革命そのものの当然の流れであり、すべてをスターリン個人の悪行のせいにするわけにはいかないというのが、本書の主旨である。また、世界革命から一国社会主義という流れも、ソ連が生き残るためにはやむをえない部分があった。
さまざまな史料を用いながら、一切の感情論を排した冷静な議論を展開している点は、さすがに碩学の技を感じた。また、社会主義における「社会」を、「個人」と「国家」の中間に位置づけるコールの概念なども示唆に富んでいた。しかし、ここまで社会主義のシステムを批判的に分析する一方で、なおも著者が社会主義の理想に大きな期待を寄せているのは、不思議な気がした。どうして、社会主義の没落は歴史の必然であるという結論まで行かなかったのだろう?おそらくは、当時まだペレストロイカという改革運動がソ連国内では進行中であり、なおも人間を真に解放する社会主義という理想をもち続ける余地はあったのかもしれない。その後ソ連が崩壊し、世界の社会主義国の腐敗が白日のもとにさらされても、先生はこの考えを捨てなかったのかどうか、気になるところではある。
紙の本

紙の本ガリヴァ旅行記 改版
2009/01/30 20:36
人間愛に満ちた風刺文学
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
小人国、巨人国、空飛ぶ王国、そして馬王国と、不思議な国を次々に旅をする船乗りガリヴァの荒唐無稽な冒険奇譚。空想力豊かな児童文学と思いきや、さにあらず、実は古今東西を通じて最も鋭い社会批判・人間風刺を行った文学の一つである。
小人国のリリパットは、ミニチュア化されたイギリスそのものである。巨人となったガリヴァが火事を消すために宮殿に向かって放尿するくだりは、王政への痛烈な当てこすりともとれる。巨人国のブロブディンナグでは、逆に虫けら同然の大きさになった彼が、巨大な人間の肉体を間近で眺め、そのあまりの醜さに嫌悪感を覚えるが、われわれ人間もみな同様な姿であることを悟る。空飛ぶ王国ラピュタでは、不死というわれわれが無条件にあこがれる状態が至福どころか絶望であることが語られる。無意味な研究や議論を続ける衒学家たちの様子も、戯画風におもしろおかしく描かれる。
そして、高度な理性と教養をもつ馬族、フウイヌムの章で展開される文明論こそ、本書中における社会風刺の白眉であろう。そこでは、飽くことを知らぬイギリスの海外への侵略や社会の中のさまざまな矛盾が批判されている。個人的には、弁護士を法と正義を蹂躙する存在と定義しているくだりが特におもしろかったが、やはり最も強烈な個性を放つのは、その国における人間種、すなわちヤフーと呼ばれる野蛮かつ醜悪な生物だろう。(ガリヴァは、これの祖先をイギリス人だと分析している。)
ガリヴァ物語はこのように、当時のイギリス社会、あるいはもっと進んで人間性一般を徹底的に風刺した書物である。これは、同時期に出版され、同じく不朽の名作となったデフォーのロビンソン物語が、イギリス人気質を肯定的にとらえているのとまったく対照的であるし、架空の社会を題材に社会批判をしている点では、トマス・モア以来イギリスの伝統であるユートピア文学の代表作ともいえよう。
かくも人間を醜く描くことに長けた書ではあるが、美しい人間性も描かれる。巨人国で献身的にガリヴァの世話を続けた少女グラムダルクリッチや、巨人国とフウイヌム国それぞれの国を脱出した際にガリヴァを救出してくれた船の船長たちは、特に印象深い心やさしい人々である。だが彼らだけでなく、本書に登場する者たちには悪人はおらず、どれも憎めないユーモラスなキャラクターばかりである。ラピュタ、ヤフーという現代人に馴染みの深い名前がこの本から生み出されたものであること自体、これらの空想的産物が人々に愛されていることを示しているといえよう。辛らつな風刺物語は、案外人間批判とともに人間愛に満ちた文学なのかもしれない。
紙の本

紙の本たそがれ清兵衛
2006/07/05 16:22
かっこわるい男たちのダンディズム
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
うらなり顔の醜男、だれかれかまわず愛想振りまくおべっか使い、異臭を放つやもめ男...人から冷笑される、かっこわるい下級藩士たちを主人公にした短編集。彼らはみな人の風評など気にも留めず、というか留める余裕もないほど、せっせとわが道を歩んでいる。しかし、同時に彼らに共通するのは、人をいたわるやさしい心と、その風貌に似つかない凄腕の剣である。いざ彼らが秘蔵の技を見せるとき、それまでのうだつのあがらない姿が一転して、弱者を助け、悪者どもを倒すかっこいいヒーローとなる。
個人的には、『かが泣き半兵』という作品を気に入っている。仕事場、家庭でさまざまなことを針小棒大に愚痴る(かが泣く)くせをもつ半兵は、ふとしたことから美人の後家と知り合う。普段だれにも相手にされない自分の愚痴を聞き、苦労をねぎらってくれる彼女と、甘い禁断の関係に入っていく彼を待っていたものは...。命がけの仕事のあと、何の報酬もないばかりか、はかなく消えた恋を苦々しく眺める、ラストシーンでの半兵のなさけない表情は、直前に展開された気魄にみちた立ち回りと小気味よい対照をなし、実にユーモラスな可愛いげのある人物像を浮き上がらせている。
ダサい、かっこわるい男に焦点を当てて活躍をさせる手法は、月並みとはいえ、藤沢周平の手にかかるとこれほどまでにすがすがしく、痛快な時代小説になるのかとあらためて感心させられる。ただ、この作者の小説一般にいえると思うのだが、藩の権力抗争にまきこまれる主人公たちのかたき役がどれもきまって、悪人であるというのはいささか都合のよすぎる設定ではないか?ことの成行きで、ある派閥の刺客になり暗殺を敢行することには、たいがい道義的・感情的な問題がからむものだ。しかしこれらの作品群では、相手を悪人に仕立てることにより、その辺の矛盾や葛藤というものを、感じずに済むようになっている。そんなところに正直、軽さを感じてしまう。そもそもそのようなタイプの文学ではないのだと言ってしまえば、それまでだが。
紙の本

紙の本四色問題
2018/05/31 23:59
脳が用いる道具としてのコンピュータ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1852年10月23日、「ド=モルガンの法則」等で有名な数学者のド=モルガンは、教え子から地図の国を分ける色は四色で足りるということの証明を求められる。これが、いわゆる「四色問題」の始まりだった。この地図製作者ならば経験上だれでも知っていたといわれる命題を、いざ数学的に証明するとなると、究極の難問であることは、その証明がなされたのが、約120年後の1976年であったことからも明らかであろう。しかも、その証明方法が、コンピュータを使って行われたものであるということが大きな物議をかもしだし、これをきっかけに数学的証明の意義が問われるようになった点でも、四色問題は画期的であった。
本書では、四色問題の証明にいたる歴史が主に時系列で述べられている。数学の素人にも理解できるような簡潔な説明である。原書の“Four Colors Suffice”では、四色以上の原色を用いた図例が掲載されていて、非常にわかりやすい。(ただし、本書では単色刷りなのは残念...)しかし、いかんせん扱っている内容は高度に専門的なものであるから、私も途中からは、歴史的な流れを追うので精一杯だった。この問題に関わり、最終的に証明へと寄与した人びとの証明手順を、自分なりに解釈してみるならばこういうことになるだろうか。
まず地図上の国々の配置をパターン化する。特に一定の領域を囲む鎖という観点を用いると、その鎖の色を交互に塗り替えることで、その中にある領域も含めて四色の塗り分けが可能となる。あらゆる配置パターンをこのように整理しながら、共通の類へと還元する。こうして得られた可能な配置すべてについて、四色の塗り分けが可能かどうかを吟味する。しかし、それらのパターンだけでも膨大な数であり、それを人間の力だけで行うのは不可能である。そこで、コンピュータを使って、その作業をおこない、人力でミスをチェックするという方法でそれを解決しようとしたのが、ケネス・アッペルとヴォルフガング・ハーケンであった。コンピュータを使った作業でさえも数年かかったが、このようにして証明は完了したのである。
数学の証明は明晰判明でなければならない、すなわちそれは人間が最初から最後まで自分の脳で考えて結論を出すものでなければいけない。このような観点からすると、人間の脳とは別ものであるコンピュータを用いた証明など、真の証明とはいえない。アッペルらの証明は、当初からこのような批判にさらされた。
これも私見であるが、コンピュータが人間の知性により発明されたものであるかぎり、それが人間の能力を超えた働きをしたとしても、やはりそれが出した答えはやはり人間の知性の範囲内にあると思う。電子計算機を用いて複雑な演算を行うとき、人間の脳は答えの真実性を体感はしていない。しかし、電子計算機の計算の確実性は疑うべくもないから私たちはそれを明晰判明な結論として信じることができる。本書のなかでスワートという数学者が述べているように、コンピュータによる証明は紙と鉛筆を使った証明の延長にすぎない。紙も鉛筆もコンピュータも、数学という神聖な真理を探究する人間の脳が用いる道具にすぎないのだから...
紙の本

紙の本ギリシア人の物語 2 民主政の成熟と崩壊
2018/02/28 23:40
二人の偉大な哲学者を生んだ精神的緊張の時代
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『ギリシア人の物語』第2巻の前半は、ペリクレスの時代におけるアテネのデモクラシー全盛期が、後半は、ペリクレスの死後、衆愚政治に陥るアテネとペロポネソス戦争の悲劇が描かれる。
ペリクレス時代-アテネ民主政の理想とされるこの時代は、実際にはペリクレスというただ一人の政治家が支配した時代であった。
塩野は、彼の政治家としての手腕を次のように要約する。「これこれの理由でこの政策が最も適切であると、彼自身の考えをはっきりと示す。こうして...現状を明確に見せたうえで、ただしこの政策への可否を決めるのは、あくまで君たちだと明言する...」さらに「ペリクレスの演説を聴く人は、最後は常に将来への希望を抱いて聴きおわる...なるほどこういう見方もあるのかと感心しながら政策の説明を聴き...積極的で明るい気分になって家路につける」これこそが、33年もの間ただ一人の支配者としてアテネを率いたペリクレスの人心掌握術であったという。
国家防衛を用意周到に行う一方、諸外国特にスパルタとの友好関係の構築には気を配り、その王とも親友関係にあったという。また外国からは芸術家や劇作家など能力のある者が移り住み、アテネは絢爛たる文化の熟成が見られたのだった。
ペリクレスの死後、アテネは急速に分裂への道を進む。武将としては、アルキビアデスなど有能な人材も出たが、政治の実権がデマゴギーグに牛耳られたアテネに、もはや自浄能力はなかった。ペリクレスの晩年に発生したペロポネソス戦争はその流れを決定づけ、多くの悲劇をアテネにもたらす。とりわけ、シラクサ攻撃の失敗による、多くのアテネ兵の運命はあまりに悲惨である。
紀元前461年から紀元前404年までのわずか57年という短い期間に、まさにアテネの光と影2つの時代が、見事な対比をもって語られている本書は、現代にも通ずる民主政治の光と影を描いた書でもある。さらに、ペリクレス時代の理想と衆愚政治の暗黒という大きな矛盾に満ちた50年は、ソクラテス、プラトンという偉大な哲学者を立て続けに生むことになる精神的緊張の時代でもあった。だが、本書にはそのような角度からの描写はなかったことが残念といえば、残念ではある。著者の塩野七生が学習院の哲学科出身であるだけに...
