拾得さんのレビュー一覧
投稿者:拾得
紙の本

紙の本錯視芸術 遠近法と視覚の科学
2011/12/25 18:44
魅力ある読書体験をあなたに
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は、「アルケミスト双書」と題されて刊行されている翻訳シリーズの1冊である。
「錯視」というと、北岡明佳氏らの大活躍のおかげもあって(本書でも紹介されています)、日本でも、とても身近になったのではないだろうか。最近は「立体錯視」なんていうのも注目されているそうだ。数多くの関連書が豊富なカラー図版で刊行されている。
そうした書籍に対し、黒を基調にしたカバーに違わず、本書の中身は「白黒」である。しかし、地味さは感じさせない。むしろ、本を手にする満足感を感じさせてくれる。
エッシャーをはじめとする古典的な錯視や、古い図版を多く掲載するばかりではなく、新規の図版もトーンをそろえて作成されている。なんといったらよいのだろうか。秘密の財宝のありかがわかるのではないか、という期待感をもちつつ古書をひも解くような、そんな感じの読書体験を与えてくれる。
ここでは財宝=各種の錯視図形だけではなく、遠近法などの「仕組み」についての解説もかなり入っており、「読める」錯視本となっている。それぞれ見開き2ページで完結しており、解説としては不十分かもしれないが、この小さな本に詳細さを求めるのは無理と言うものだろう。とりあえず知る、という意味では十分であろう。
高精度のカラーの本も手軽に入手でき、電子書籍2年らしい。そうした技術に頼らずとも、魅力のある本はできるというお手本のようなシリーズと感じられた。
紙の本

紙の本安全・安心の心理学 リスク社会を生き抜く心の技法48
2011/12/17 19:06
後知恵バイアスの魅力をこえるために
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
今年は、大震災・津波や原発事故がらみで、関連書籍が多く刊行されたようだ。レポートみたいなものもあれば、「**の安全性・危険性を問う」といった類いの勇ましい本も少なくなかったであろう。言っていることに間違いはないのだろうし、必要なことなのだろうが、違和感は残る。その違和感の元というのは、本書で紹介されていることばでいえば、「後知恵バイアス」というのだろう。
刊行されてから少し時間が経っているが、心理学の側面から安全安心にかかわる課題をまとめた一書である。安全対策は、通例はハードや制度によるものが多い。ただし、何か問題が起こった場合、さまざまな対策を列挙したうえで、「関係者の意識の向上を」というのが決まり文句のようにもなっている。「その意識って何?」と、いつも思うのだけれど、本書はまさしく「その意識」を扱ったものといえるだろう。
人間心理の「落とし穴」みたいなものの指摘ばかりではなく、それを防ぐ考え方にはどのようなものがあるか、という点にも軸を置いてコンパクトに解説してくれている。同じ著者による「ヒューマンエラー」の姉妹編といえよう。何より読みやすく、とりつきやすいのが有り難い。鉄道でふだんから行なわれている「指差呼称」などいうのも紹介されている。プラットフォームで駅員さんがしている「あれ」ですね。こうした身近な場で応用できるものから、組織風土での問題克服まで、48のキーワードが取り上げられている。
ところで、今回の大震災でも、繰り返し「パニックにならないように」という告知が専門家やTVなどからなされたように思う。しかし本書では、「パニックよりも怖いもの」という指摘がある。「緊急事態の認知の遅れ」である。ある地下鉄構内の事故では、煙が充満しているのにかかわらず、平然と歩いている人が多かったという。集団でいると、同調バイアスにより、かえってこうした傾向が出現しやすいともいう。
安全・安心にかぎらず、これからを考える1冊として。
紙の本

紙の本作家の猫 2
2011/12/11 23:09
猫は友だち、犬は身内、というけれど。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ほぼ、ひとつのジャンルとなった感のある「猫本」。猫を飼えない者の代理体験なのか、単に猫好きが多いのか、とにかくネタが尽きない。本書も、趣向そのままの「その2」なのだけれど、見飽きはしない。
加藤楸邨から立松和平まで、26人の作家の愛した猫たちの写真とまつわるエピソードが綴られる。それぞれの家族もしくはそれに代わる者による一文がつく。たとえば久世光彦であれば、妻の久世朋子が、といった具合である。これも一つの現代日本文学史の参考書である。
写真は、猫たちの表情がよく決まっていたり、猫を抱いた作家の幸せそうな笑顔は、他の猫本と同様の定番である。プライベート写真ならではの「幸せな家庭」の写真もよく出てくる。裏表紙にも使われているモダーン部屋にいる夫婦と娘の3人と猫の写真は、これは武満徹の家族。そのままCMにも出てきそうである。一方、ご飯を食べているのか、猫とじゃれているのかわからないようなのが、米原万里。これが日常だったのだろう。
人の猫と家族の写真を喜んで見るのも、なんだか変だが、日常の幸せを少し分けてもらえた気になるからかもしれない。そうそう、もちろん「作家の犬」もあります。
紙の本

紙の本家族という神話 アメリカン・ファミリーの夢と現実
2011/11/13 22:16
神話の役割と強さ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「両親が女性」という家族のアメリカ映画を見た。大きくなった子どもは、精子提供者である生物学上の「父」に関心をもち、探し出して・・・、とそのてんやわんやが描かれる。子どもをもった同性婚カップルの「その後」という、先端的な設定で話題をつくろうとしたのだろうが、その描かれ方はとても「ふつう」であった。言い換えれば、「両親共に女性だろうがなんだろうが、家族は家族だ」というメッセージ満載だった。むしろ、このふつうさのほうに驚いてしまった。
本書は、そのアメリカにおける「家族は家族だ」を歴史的に問い返す試みである。著者のことばを借りれば、「伝統的」とおもわれる家族は、アメリカの歴史の中で一度も存在しなかった、ということである。もしくは、1950年代のごく一部の白人中流家庭によって実現されていたに過ぎないイメージが、普遍的な価値を持つものとして理想化されたにすぎない、ということである。「近代家族」の議論になじんだ人ならば、さして新味はないだろう。しかし、ここでとりあげられる、さまざまなエピソードや事実、そしてテレビドラマなどメディア上のイメージなどの丹念な収集からは、日本の家族論議においても、多くの刺激を得ることができるだろう。
目を惹くのは、アメリカンファミリーと対になる価値観としてあった「自立の精神」についての議論である。アメリカにおける自立の精神の原像は、家族単位で行なわれた西部開拓民にある。そう、あの「大草原の小さな家」である。家族こそが自立のための基本単位なのである。本書では、そうしたイメージはあくまで虚像でしかなく、国家による支えなくしては成り立たないものであったことを詳細に明らかにしていく。アメリカ社会における格差の大きさは、こうした自立の精神によって肯定されてきたといってよい。いいかえれば「私がこれだけの報酬が得られるのは、私が自立した精神でがんばってきたからである」と。著者の議論は、そこに「自分の得た報酬は。実は自分の能力や努力によるものではないかもしれない」という考えを入れるきっかけとなるはずだ。
本書の原書が刊行されてからだいぶ日が経っているようだが、本書は明らかに80年代の「家族回帰」へのアンチテーゼとして出されていることがわかる。この時間差は、本書の受け止め方にも差をもたらしているのであろう。日本でも、近代家族論議も一時期のようにははやらないようだ。「無縁社会」など「現実」からの別のインプットが大きな影響を与えていかにみえる。もしからしたら、家族は神話でしかないことに皆が気がついてしまっているからかもしれない。しかし、「児童虐待」の問題など、(本書でも繰り返し取り上げられ)本来であれば当時の論客が踏み込むべき課題はまだまだあるように感じるが、いかがか。家族に代わる絆は何なのか、議論すべきものは山ほどあるのではないだろうか。
ところで、本書で著者はアメリカの伝統的家族のもつ虚像性を繰り返し指摘している訳で、それは説得力もある。しかし、これだけ根拠がうすかったにもかかわらず、なにゆえそのイメージが強力に広がったのかが、かえって気になってしまう。
紙の本
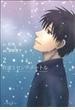
紙の本秒速5センチメートル 2 (アフタヌーンKC)
2011/10/27 00:01
時には秒速5センチで、時には時速千キロという速度で。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
なんとなく見ていてたテレビで、映像の美しさに、つい見入ってしまったアニメ映画があった。本書は、そのコミカライズである。物理的距離に隔てられてしまった「思い」を扱ったセンチメンタルなストーリーも、山崎まさよしの音楽と合わさって、観る者を放さないものがあったのではないか。
ある男女というより、男の子と女の子の出会いからはじまり、優に10年をこえる時間を扱った物語でもある。こう書くと大河ロマンかと感じられるかもしれないが、映画版では、おもに3つの断片から構成されている。2人の出会いと別れを扱った「桜花抄」、種子島での高校生活を描く「コスモナウト」、社会人になった男の子のその後を描く「秒速5センチメートル」(コミックでは「エンドテーマ」と題されている)である。コミックでは、この3つをメインとしつつも、その間を埋めるように全2巻11話で再構成されている。
映画版では、映像に関心が向いてしまって、冷静にストーリーを考えると、割り切れないものも実は残る。主人公の元男の子には、「え、キミ、それでいいのかい?」と、突っ込みを入れたくもなる。センチメンタルも行き過ぎれば、ただ過去を引きずっているだけ、になりかねない。
コミック版では、ストーリーそのものは変えずに、エピソードを要所に加え、その「すき間」を埋めようとしている。断片的だった物語を、「彼を見届ける」ことができるようなストーリーにしたといってよいだろう。より説明的になり余白がなくなったことには、「蛇足でしかない」という原作ファンもいるかもしれないが、この辺りは個人の趣味次第だろう。ただ、原作者がこうしたコミック版刊行を受け入れたのも、原作映画の「宙ぶらりんさ」を自覚していたからではないだろうかと思う。
個人的には、まっすぐな気持ちをもち続けていた花苗ちゃんの、大きくなった姿を見ることができ、うれしかったような、安心したような。
紙の本

紙の本パラダイムでたどる科学の歴史
2011/10/12 23:37
科学とは何か、と考えるということとは?
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
人文社会系の学問と自然科学の学問とを区別するひとつの手がかりが、「学説史」の位置づけではないだろうか。基本的に決定的な証拠がないともいえる人文社会系の学問において、学説史はその学問分野のアイデンティティをさぐる試みともいえ、重要な位置におかざるをえない。自然科学系でも、「*学史」という分野は確かにある。しかし、科学史と総称されるものに一括することが可能であろう。ところで、人文社会系の各学説史はこのように一括できるだろうか。 「この両者の違いは何なのだろうか?」とふと思ったことがあるが、そうした疑問に明快に応えてくれるのが本書である。
本書は、日本の科学史研究の碩学である著者の「語り下ろし」である。著者が語り、編集部がまとめたものに、さらに赤字を入れていったそうだ。「です・ます」調でなめらかに話が進められており、「語り下ろし」という表現がふさわしい。また、「あとがき」で述べてあるように、「物理帝国主義」というような、「学界俗語」もあえて使ったとしている。そうしたわかりやすさも、語り下ろしの魅力だろう。
先の私の疑問に応えるのであれば、自然科学で学説史がないのは、「パラダイムが変わったから」となる。いいかえれば、アイデンティティの求める先が変わった、ともなる。現在ではパラダイムという表現は一般化しているので、「たいていの学問でもパラダイムは変わったのではないか?」と言われそうだ。しかし、パラダイムという考え方そのものは、科学史研究から生まれ、それは当初は近代科学が生まれる時に使われた一回限り「科学革命」におけるパラダイムの交代という事象をさすものであったのである。
むしろ、人文社会科学研究は、そうした自然科学を模倣して、自然科学的な手法を(部分的に)取り入れて近代化をはかったといってよいだろう。しかし、模倣であったがゆえに、過去の蓄積を否定しきった訳でもないのである。
狭義の「科学史」のみならず、学問のあり方全体を考えるような、そんな刺激を受けながらの読書となった。本書では、人文社会研究に言及している訳ではないが、そうした刺激を得られるような全方位性がある。
通例の概説書では、自らの狭義の専門に近いところの記述が大半となることが多い。本書の著者で言えば、それは天文学史にあたる。しかし、科学史である以上、記述は包括的であり、17世紀以降の科学の歴史を大まかに押さえることができる。何より、天文学や物理から始まった科学革命から、化学、生物・生命科学へとどのように影響を与えていったのかを一書の中で俯瞰できる。さらに、現在進行形のコンピュータを軸とする情報デジタル革命にもふれ、科学や科学史の社会的位置にまで筆を進めていく。本書を「科学史」ではなく、「科学の歴史」としたのは、科学史自身の役割変化を、著者自身も自覚しているからかもしれない。
ふだんの新聞でも、意外に科学の話題は多い。今年の日本は特に多くなることだろう。かといって、科学の知識が増えていったからと言って、適当に考えられるようになるわけではない。科学における「考え方」をたどることが、ふだんの科学報道などを見直す補助線にもなるわけだ。
紙の本

紙の本昭和天皇 「理性の君主」の孤独
2011/09/26 23:42
エンペラーズホリデー
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
映画「英国王のスピーチ」は面白かった。よく考えてみれば、旧敵国の宣戦布告スピーチがクライマックスな訳で、そこを日本人が興味深くみれてしまうのも妙な話だが、そうした大状況の中での、一個人の孤独な戦いをよく映像化できていた。そのジョージ6世の娘を描いた「クイーン」も面白かった。日本でも同じような映画ができないものだろうかと思ったら、ちょうとよい格好の「青年」がいた。
20歳前後の青年が海外旅行をするのは、今となっては珍しくもないが、彼の父も祖父も海外に出たことはなかった。自分が初めてである。おつきの者に囲まれるのは国内にいるときと変わらないにしても、その程度は全然異なり、解放感を大いに感じることができた。何より、日本で会うことのできない、多くの海外の人にも会うことができた。皆、きちんと遇してくれた。「外に出る」ということについては、さんざん心配されたが、「習うより慣れろ」ということなのだろう、大方無難にこなせたし、この半年で自分の成長を感じることができた。これから担う「仕事」では、自分の理想が少しずつでも活かせるようになるのではないか。
その青年は帰路の船上で、こんな感じで大いに希望に胸をふくらませていたのではないだろうか。本書では、そんな一青年の教育環境からはじまり、記者会見、周囲の者の回顧録や政治状況といったものから、その一生を描いていく。没後20年をこえたが、おもいのほか、さまざまな資料が出まわるようになり、興味深い逸話や発言も多く収録されている。それだけでも興味深いが、それ以上に著者のストーリーテリングもうまい。
私の頃の昭和天皇イメージとは、なにより「感情を表に出さない人物」だった。長年仕えた侍従が亡くなったときの受け答えも「あ、そう」だったという報道がされたこともある。「天皇」とはそういう存在なのだと思った。しかし、それは「長い戦後」を生きてきたがゆえの言動とも解釈できる。近代戦における「敗戦国」の元首が無傷で残ったのは、おそらく「彼」だけだろう。もちろん、それだけに背負うものが多くなったのでもある。
本書によると、昭和天皇は、かなり頻繁にさまざまな積極的な発言・言動をしている。初期からの侍従が引退するときには「泣いた」とも言う。戦後の発言も意外に多く積極的だ。ただ、報道されなかっただけである。弟の発言に不満をもって、それを解消する意図もあって、回顧録の続編「拝聴禄」を入江侍従長と作成していたのは、とても人間臭く、かえって微笑ましい。
「『理性の君主』の孤独」というサブタイトルがうかがええるように、筆者の基本線は、大正デモクラシーという時代の子として昭和天皇という位置づけといってよいだろう。洋行帰り以後の宮中改革からはじまり、文字通りの立憲君主制の理想への気概も小さくなかったはずだ。ところが、周囲にいたはずの政党政治の選良たちもいつしか亡くなり、時代とともにその「同志」は減っていったわけである。また本書から改めて気づかされるのが、大衆社会化の影響である。昭和天皇の報道のされ方によるイメージ形成から、天皇自身がごく若いころから「新聞をよく読む」という習慣を身につけるている点など、興味深い。
かの英国王がスピーチをしなくてはならなかったのと、事情と似ているところもあれば、異なる部分もある。ただし、両者ともかなり生真面目に自らの役割をまっとうしようとしている。英国王はそれゆえに死期が早まったともされる。日本の彼は、「その後」の長い人生を生きることになった。そんな彼を支える思い出の一つが、一青年としての海外旅行だったという。
もしその青年の映画をつくるのであれば、「エンペラーズホリデー」と名づけてみたい。
紙の本

紙の本海炭市叙景
2011/09/17 00:13
街を想像して,創造する。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書を原作にした映画が作成・公開され、それに合わせて原作も文庫化された。映画への評価もそれなりに高く、実際,芸達者な俳優を集めた見応えのあるものであった。そこであらためて原作を読んでみたのだが、忠実に、いやそれ以上に丁寧な映像化といってよいだろう。多少の設定の変更はあるにしても、原作では書かれなかったような行間までも丁寧に埋めようとしている。それにもかかわらず、映画と原作との印象の違いを感じてしまうのである。
原作は、函館をモデルとした海炭市を舞台とした18の連作短編から構成されている。映画では、このうちの5つほどを再構成したものという。映画でも原作でも冒頭の「まだ若い廃墟」の印象が強いせいだろうか、映画の受け止め方は「現代日本における地方都市の閉塞の現状を描いた」といったものが少なくなかった気がする。実際に見ても、その閉塞感には息苦しくなる。地方経済の不況、造船所(原作では炭鉱)での大量解雇、若年者の生活困窮、・・・。原作は現代の「無縁社会」や「ロストジェネレーション」を予期していたのだ、という解釈も成り立とう。
ところが原作をひととおり読むと、その印象はもっとさまざまだ。少なくとも原作者には、「社会問題」を取り上げようという意識はなかったろう(そうであれば、ノンフィクションを書けばよいわけだ)。連作の中には、「まだ若い廃墟」とは全く異なる印象をもつものも少なくない。別の部分を取り上げれば、趣の異なった映画もつくれただろう。街にはさびれていく部分もあれば、新しく作られていく部分もある。老いていく者もいれば、成長していく者もいる。絶望する者もいれば、希望のみを抱く者もいる。変化もあれば、変わらない部分もある。原作は、そんな街の姿すべてをかかえこもうとした、というしかないだろう。
ところで、文庫版にも付けられた「単行本解説」によると、18のショートストーリーのタイトルは、詩人である解説者の詩集からとられたという。あくまでも海炭市は著者の想像の産物という主張なのであろうか。また、18のストーリーは2つの章に分けられているが、「第1章 物語のはじまった崖」と「第2章 物語は何も語らず」と付されている。第1章のタイトルは、冒頭の「まだ若い廃墟」が物語の中核になるとしている一方で、それを否定するような第2章のネーミングである。「謎掛け」のような感じさえする。本作品は未完のまま、著者の自死により中断したという。残りの2章で何をどう描こうとしたのか。それを完成させるのは読者の想像力だよ、とでも試されているかのようである。
紙の本

紙の本片思いレシピ
2011/09/11 00:42
「ふわミス」誕生!
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ハードボイルド作家のはずの著者にしては、やけにガーリーで華やかな装幀と感じたものの、今回の語り手が「柚木草平シリーズ」の草平の一人娘・加奈子と知って納得。この作家は、青年にさしかかろうかという少年を主人公にしたミステリーは、処女作以来、数多く出しているが、少女を中心にしたのは初めてではないだろうか。同じような設定がくり返される著者の作品群の中で新機軸を試みたのだろうが、それは確実に成功したといってよいだろう。
加奈子の通う塾の講師・松永先生が、何者かに殺されるという事件が起きる。講師控室で殺されたものの、誰も逃走者を目撃していない。当初は衝動的な殺人とも考えられたが、なかなか容疑者が浮かばず・・・。
物語の語り手である加奈子は、元刑事そして私立探偵を父にもつものの、積極的に事件の謎解きにかかわるわけではない。事件捜査に(勝手に)乗り出すのは、加奈子の友人「柚子ちゃん」とその家族なのである。とりわけ祖父は、地主としての金と人脈を使って積極的に動き出す。この家族のペースに加奈子も巻き込まれて物語が動いていく。ちなみに父・草平氏は、今回は電話ごしでの登場のみである。
ところで、この「加奈子ちゃん一家」がなんとも個性的で魅力的である。父親は海外赴任、母親は若くして亡くなり、父母の影はとてもうすい。どうやら60年安保にかかわっているらしい祖父と、彼とは学生運動で知り合ったという祖母、そして動物に関心の強い中学生の兄・翔児、そして飼い猫・恋之介が全メンバーである。その中でも最も個性的、いや実は本書の主人公ともいえるのは「フランス人形が電池で動いているような」柚子ちゃんである。
祖母の作ったお姫様のような「ふわふわな服」を小学校6年生になっても着続け、学校ではからかわれることもあるそうだが、本人は気にしない。体が弱いらしく、学校も塾も休むことが多いらしいが、どうもそれだけではないらしい。しゃべり方もゆっくりしているらしく、「**しますう」というしゃべり方になる。何かが足りないわけではなく、世間の目を気にしていないだけのようだ。好きなことはお料理。勉強ができてもできなくても気にしない。実は大物かもしれない。ゆっくりしているからといって、鈍感なわけでもなさそうで、観察力も記憶力もよい。物語全体にふしぎな味を出してしまっている。「舞田ひとみ」シリーズが「ゆるミス」なら、こちらは「ふわミス」とでもよべようか。
紙の本

紙の本幻の終戦 もしミッドウェー海戦で戦争をやめていたら
2011/08/28 18:18
日本の8月は有意義だ
7人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1945年8月15日にポツダム宣言受諾を発表して以来、8月の日本には「戦争もの」があふれる。書籍、ドキュメンタリー、マンガ、証言集、もろもろ。このことに疑問を呈する向きもあるようだが、「考えるべきこと」が沢山あるだけではなく、多くのことを教えられる。そんな貴重な機会を、後代に生きるわれわれが活かさないわけにはいかない。
歴史を考える禁じ手のひとつに、「もし、あのとき・・・」というものがあるそうだ。しかし、それを考えたくなるのも人間の性であろう。「太平洋戦争」において、その「もし」の対象となってきたのは「ミッドウェー海戦」ではないだろうか。昭和史を中心にノンフィクションを次々と著している著者も本書でそれに挑んでいる。
「もし、ミッドウェー海戦で勝っていれば、その後の戦闘も有利になり、アメリカとの講和条約に持ち込めたのではないか」と考える人は、今でも少なくないだろう。そうした人々と著者が異なるのは、「ミッドウェー敗戦」を前提としたうえで、早期の講和が成立することはできなかっただろうか、という問いを立てていることである。日本自身の政治のあり方と政治家にどこまでの可能性があったのか、というものを問うことである。ある種の思考訓練か。「ミッドウェーに勝っていたら」と想像することは自由だが、それを前提に「もし」を考えることは、結局は「他人(他国)任せ」の夢想でしかなくなることを暗に指摘している。ミッドウェー以前からかかえていた日本内部の問題をかえって考えさせなくさせてしまうからである。
さて著者は、「もし」と言いつつも、前半第1部はミッドウェーそのものの検証に費やし、作戦そのものが「張り子の虎」でしかなく、どだい「勝てる」ものなどではなかったことを明らかする。これだけでも十分に読み応えがある。暗号が傍受され、それに気がついてさえいなかった、という1点を指摘するだけでも十分に理解されよう。
「もし」が描かれる第2部では、その中心になる人物は吉田茂と近衛文麿である。正直いって、最初はあまりに「ふつう」に感じてしまった。戦前、戦後と分かれるとはいえ、総理大臣経験者である。そのうち一人は、「政権投げ出し」の印象の強い総理大臣でさえある。フィクションであれば、ここに第3のヒーロー登場を期待したくなる。しかし、組閣経験のある2人が、そのもてる人脈を前提として手を組んでいれば、というのは「なるほど」と思わせるのに十分である。国難において、意外性のヒーローなどは現れない。それぞれが知力を尽くすしかない、ということでもあろう。
著者自身も日米の早期講和が成立したことだけで、諸々の問題がすべて解決するとは思ってはいない。それでもなお、このことを考えるのは、その後の戦争で失われた人命があまりに多いこと、そして、戦争を引き延ばすなかで「知的退廃」ともいえる精神状況がもたらされたことへの憤りから、といってよいだろう。
戦争と戦後をめぐっては、史観の問題とか何とかいろいろと議論がされているが、その前に考え抜くべきことは余りにも多いのだ。
紙の本

紙の本日本の歴史 23 帝国の昭和
2011/08/18 22:09
同時代の時空間を再現する試み
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
毎夏、繰り返し問われる「昭和史」の主題とは、「あの戦争は避けられなかったのか」である。正解はないであろうし、論者の現在の立ち位置によっても歴史への見方は大きく異なり、これからも延々と問われ続けることだろう。しかし、それが無駄だとは決して思わない。
戦争までの20年くらいを近代日本の「逸脱」とする一方で、戦争を明治以来の「結果」と見るものとに大きく分けられるといってよいだろう。どちらもそれぞれに説得力をもっており、素人にはなんとも言えない。ただ、政治史などの史実をこまめに追うだけでは、この時期の歴史はあまりに困惑してしまう。それゆえに、こうしたなんらかの史観をつい欲してしまうのであろう。本書は、この戦争へと至る「昭和史の決定的瞬間」の時期を扱っていながら,この両者の史観に偏することない記述をこころがけているようだ。
そのひとつの象徴といえるのが、最後の元老とされる西園寺公望の扱い方である。彼の言動は同時代の政治史の一級史料とされ、その見方やバランス感覚からは、「彼がもう少し長生きしていたら昭和政治史は変わっていたかもしれない」と思わせるものがある。しかし著者はそれに異を唱える。一言で言えば、結果としてそう見えるだけである、と。誰かの言動を中心に歴史を組み立ててしまうと、「その人は正しかった」ということになるのは、論理的に考えれば当然の帰結である。残された史料から歴史を描く際の基本的かつ誠実な姿勢であろう。
では著者は、歴史をどう描こうとすのか。そうしたさまざまな主体の「言動」そのものをあえて追う道をとっている。「実は、こんな事実があった」式の路線はとらない。今となっては、一顧だにされないような当時の言動、たとえば、戦争末期の近衛上奏文や蝋山正道ら知識人による東亜協同体論など。当時の彼らの立場と、その言葉の発せられた対象などを丹念にたどりながら、その位置を考えていく。決してわかりやすい記述ではないが、同時代の政治家、知識人の陥っていた自縄自縛の言論空間の再構築の試みといってよいだろうか。そうすると、それは現在われわれが安住している空間とさほど隔たってはいないような感じがしてくるのである。
紙の本

紙の本関東大震災 新装版
2011/08/07 23:42
災害下の人心を冷静に見透す記録文学
14人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
3月11日の東日本大震災以後、同じ著者の「三陸海岸大津波」とともに、改めて広く読まれているのが本書である。たいていの書店には並んで置いてあるようだ。震災以後4ヵ月、関連書籍は数多く積まれている。単に「著名人が何かをちょっと書いた」程度の、首をかしげたくなるような本もあるが、吉村氏の2作は今なおこの国に必須の書といってよいだろう。
同じ著者が同じ「震災」を扱った本とはいえ、両著は重きの置き方が実はだいぶ異なっている。「三陸」のほうが「証言」と「対処」によって構成されているとするならば、本書の重心は「証言」と「人心」におかれている。災害などを扱っている書を読んでいるとき,懸命かつ適切な対処がなされている記述を読むと、ほっとするものがある。本書でも、バケツリレーで町の類焼を免れた話などがあり、読んでいる方が励まされる。しかし本書で紙幅が費やされているのは、見出しとしても掲げられている「人心の錯乱」である。「あとがき」にあるように、両親の体験談になじんだ著者が「人心の混乱に戦慄した。そうした災害時の人間に対する恐怖感が、私に筆をとらせた最大の動機である」という出発点ゆえでもあろう。
ここで「人心の錯乱」として、具体的に取り上げられているのは、各種の流言、大杉事件、避難民の生活、犯罪などである。おそらくそれらの中でも、最も大きくかつ複合的なものとして取り上げられているのが、朝鮮人蜂起の流言とこれを信じた自警団などによる朝鮮人虐殺である。すでに歴史上の知識として広く知られてもおり、背景としてどのような心理的要因があったかもしばしば議論されている。また、この混乱の中、日本人自身が殺されたケースもあることも知られている。
本書ではどのようなルートでこの流言が出まわり、具体事例としてどのようなことがあったのか、また、流言の根拠にもなった日本人自身による略奪行為など、丹念に事実を重ねていく。さらに、流言に踊らされた警察などが電信などで、「事実」として発信したことが、よりこの問題を根深いものにしたこと、そして、事実無根に気がついた警察自身が、これをなんとか消そうとしたものの自身も攻撃の対象にもなったことも書き込まれている。そのように強力にこの流言と虐殺とは広がった。なお、警察発表では被害者は200余名だが、在日団体の地道な調査を参考にした吉野作造らによる計算では1府1市6県で2600名をこえているという。
さてこう書くと、「パニック時の群集心理は怖い」というように、本書の話が落ち着くかに見える。しかし、本書ではそれ以上の群集心理の分析がなされているわけではない。著者の筆はごく冷静に事実を重ねていく。怒りや嘆きをにじませてもよさそうなのだが、それもない。それがこの著者のふだんからの特徴とも言えるが、どうも本書はちょっと違う。丹念に読むと、「騒擾を好む一部の者」というフレーズが何度か使われていることに気がつく。読み流してしまいそうな決まり文句にも見えるが、パニックに陥っているはずの群衆の中にいる確信犯的な存在を読者に知らしめる。その者たちをこそ、筆者は冷静かつ執拗に追いつめようとしていたのではないか。そんな著者の気魄を感じた。
紙の本

紙の本昔も今も
2011/07/31 21:40
『君主論』以前のマキャベリズム
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書の紹介文を見てびっくり。あのモームが、『君主論』のマキャベリを主人公にした小説を書いている。しかも扱っているのが、あのチェーザレ・ボルジアとの出会いの場面という。どのように描いているのか、気になって仕方がない。まさしく『君主論』誕生の瞬間を描いたものと容易に想像がつくし、実際にそうである。しかし、そこはモーム、素直にそんな場面を描くであろうか?
フィレンツェの外交官であるニッコロ・マキャベリは、共和国使節としてローマ法王軍司令官であるチェーザレ・ボルジアのもとに赴く。何かの取り決めをするというより、何か取り決めることを引き延ばすことによって、状況を見極める時間を稼ぐというのがマキャベリに課せられた課題であった。それは、ボルジアも承知のうえである。
本書の核は、そこで行なわれる両者の虚々実々の緊張感あふれるやりとりである。そこから君主論のエッセンスが・・・、と紹介したくなるが、そう簡単にはいかない。本書は、陽気でおしゃべりがうまく、女好きのマキャベリを丁寧に描くことからはじまる。そんな彼が派遣先の街で、仕事だけをしているわけにはいかない。地元で世話になっている商人の若き妻に、なんとか手を出そうと策略を繰り出す。そう、彼の「マキャベリズム」は、実はここで発揮されているのである。他愛もない話と言えばそれまでだが、後者こそ読ませる部分になっている。『君主論』などというと、なんだか敬遠したくなるようなテーマであるが、それを軽快さとユーモアとで、最後まで面白く読ませてくれるのである。
大学の学部学生くらいであれば、まずは『君主論』を読んで議論をしたくなるだろう。かくいう私も。何の学問的ヒントを与えてくれそうにない本書など、見向きもしなかったろう。しかし、『君主論』について議論したところで、そう大したものは生まれてこない。大した人間が読むのでもない限りは。むしろ人生のユーモアの中にこそ、さまざまなヒントがある、とでも言いたげな作家の声が聞こえてきそうだ。大作家モーム、72歳の歴史小説、あなどれません。
紙の本

紙の本舞田ひとみ14歳、放課後ときどき探偵
2011/07/22 23:27
名探偵登場、の巻
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「舞田ひとみ11歳、ダンスときどき探偵」につづく第二弾。きっちり三年後に14歳編が出るとは、と少々の驚きをもって手にとる。
カバー袖の著者の自称では「ゆるミス」ということになっているものの、扱っている素材は決して、「ゆるい」ものではない。今回のメインの登場人物は舞田ひとみとその小学校時代の級友・高梨愛美瑠、さらにその中学校の友人2人の計4人。高梨と2人は大学までエスカレーターで進める私立中学校に進学している。一方、ひとみは公立中学校に通っている。
「ゆるミス」で中学生が主人公などというと、学園ミステリー×「日常の謎」ものを想像してしまう。ところが、そんな中途半端な想像をする読者を置いてけぼりにするかのように、そして学園の枠も関係なく事件が起こっていく。同じくカバー袖に書き込まれているように、いずれも「人生の苦さや社会の不条理さ」を感じさせるものになっているのである。連作ものなので事件が多いのは致し方ないが、窃盗だけではなく、殺人も誘拐も自殺もある。公立中と私立中との間の微妙な格差もさりげなく描かれている。「ゆるミス」といっても、ゆるやかなのは、中学生4人の他愛もないおしゃべりくらいなものかもしれない。
さて、前作のひとみは、刑事でもある叔父・舞田歳三に、何気なくヒントを与えるような役回りだったが、今回は積極的に事件にかかわり、謎解きにも積極的に挑む。いつのまに成長してしまったのか、名探偵誕生である。その行動力も推理も、お手並み鮮やかである。しかし、どこかもやもやが残る。
まずひとつは、この「人生の苦さや社会の不条理さ」にある。いかにひとみが鮮やかな推理で「事件」の解決を導いたとしても、メインとなる事件や問題とは別の苦さや不条理さがそこには依然としてある。事件解決がそうした不条理さを解消するわけではないのであり、彼女たちもそれを自覚せざるを得ない。
もうひとつは、今回の語り手は高梨愛美瑠であること。前作の語り手は叔父の歳三と、実は、舞田ひとみ自身の心中は描かれていない。彼女は何を感じ、思っているのか、読者にはそれもわからないままなのである。
「ゆるミス」といっても、実は「ゆるさ」を見出すのもむずかしい、そんな社会派なシリーズになってしまっている気がする。せめて、彼女たちの放課後のおしゃべりくらいはゆるやかであれ、などと願ってしまう。
紙の本

紙の本不確実性の時代
2011/07/18 21:36
ハイルブローナー VS ガルブレイス
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
最近、とある(よく売れているという)新書でガルブレイスの『不確実性の時代』を揶揄するような注記があった。そうなると、俄然読みたくなってしまった。日本国内でも流行語となるほどに売れた書籍は、いったいどのようなものなのか。折よく、近年再文庫化されている。
本書をひとことでいえば、一般向け経済史と経済学史の本である。最近はやりのリスク論を先取りしたものではない。19世紀の経済と経済学に見られた確実性に対照させて、変動激しい20世紀を「不確実性の時代」と表現したわけだが、このネーミングのよさは卓抜である。本書の内容をこえて、一人歩きしたとしても不思議はない。ちなみに、本書は連続テレビ番組で放送されたものの台本をもとに書かれており、とにかく読みやすい。日本語訳でも「です・ます」で書かれ、文庫版500ページという厚さもほとんど気にならない。
一般向けのわかりやすい経済学史といえばもうひとつ、ハイルブローナーの『世俗の思想家たち』というのがある。これもネーミングが絶妙に興味深い。もちろん内容もわかりやすい。とりあげる経済学者の、経済学説のみならず本人のエピソードも紹介しており、記述に緩急をつけるなど、読者にうまく親しみをもたせている。彼らの経済学の「考え方」もしっかりかつわかりやすく解説している。米国内では何度も版を重ねてきたというが、それもなっとくの読みやすさである。
現在の経済学は数理モデル中心で、素人にとってはまったくもって訳がわからない。マスコミにでるエコノミストや経済評論家は、声高だが、なんだか雑だ。そんなこんなで経済学はなんだか疎遠なものになりがちだが、本来、経済学は、人間が考え出したものである。そうした本来の人間くささというか間口の広がりを知るにも、こうした先達による導きはたいへんありがたい。しかも、いずれも名人芸の説明の明晰さ。読まない手はない。
私のもう少し見識があれば、両者の得失を論じるところだが、そこは素人には手が余る。ただ、そんなことを考えずとも、この二冊は素直に楽しめばよいと思う。ひとついえるのは、ガルブレイスのほうが、インド大使もつとめたことに象徴されるように、現実社会との接点をもつことに勤めた経歴がある。そのぶん本書の後半は、一人の経済学者としての社会へのコミットの歴史を語ることになる。時代の証言としても興味深い。
