拾得さんのレビュー一覧
投稿者:拾得
紙の本

紙の本勝負の分かれ目 メディアの生き残りに賭けた男たちの物語
2011/07/08 00:26
大河ノンフィクションの面目
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
人から薦められていて、半ば忘れかけていた本を改めて手にとる。それがとんでもなく面白かった場合、それは「得をした」というべきか、「損をした」と感じるべきか。そんな本書は1999年刊行。すでに文庫化もされており、いまさらながら紹介するのは気が引けるのだけれども、何度紹介されてもそれに見合う内実を本書はもっている。
大まかにいって、イギリスの通信社「ロイター」と日本の通信社「時事通信」の二社の90年代までに至る戦後史を通して、「報道」という業務がどのように変質していったのか、ということを描いた、大河ノンフィクションである。本文二段組み500ページをこえる物量に圧倒されてしまうが、量をもってしか書けないものもある、ということがよくわかろう。
ポイントをいくつかあげると、こうなるだろうか。第二次大戦後の通信社というものが、一般ニュースではなく、経済報道に軸足を置くことで成長と生き残りを図ってきたこと。そうした経済報道は、コンピュータやインターネットという技術革新によって、より金銭的な重みを持つ秒を争う「情報」になったこと。金銭的な重みをもつ経済報道は、「報道」という概念そのものを変質させるものであったこと。などなどである。
本書の軸足は通信社にあるものの、新聞を含んだジャーナリズムの問題、金融界のあり方、「日本的な会社」の種々の問題、情報化社会における労働の変質などなど、いろいろなことを考えさせる。日本の国策会社QUICKの例など、「失われた十年」などというものは、すでにその前から根深く爆弾のように抱えこまれていたにすぎないことが示唆されて興味深い。というより正直言って、80年代の関係者のあまりの「おめでたさ」に呆気にとられてしまうくらいだった。
バブルが一段落した90年代はじめは、これからは落ち着いた時代になるのではないかという予感があった。90年代が終わったときのベストセラーに「不平等社会日本」があったが、この間の社会の変わりようにうちのめされる思いがしたことがある。本書は、単に不況がどうこう以上に、70〜80年代に用意されたものによって、90年代の社会がどのように変わっていったのか、の一断面を知るよい教科書である(ただし、21世紀以降は別の本をあたられたい)。
本書で著者は、ジャーナリズムについてなんらかの価値判断を示しているわけではない。著者自身も出版社勤めであり、その留学経験からも、「調査報道」にこだわりをもっていることはよくわかる(本書そのものがそのあらわれだ)。しかし、「これからは日本のジャーナリズムも調査報道の時代です」などと陳腐な言い方はしない。むしろ一般ニュース重視の日本のジャーナリズムがいかに経済報道を軽視して、その経営をあやうくしてしまったかや、経済状況そのものを変えかねない経済報道の危険性を見逃してしまっていたかを冷静に書き綴っていく。とりわけ、アメリカのブルームバーグが日本の記者クラブに挑戦する際の、両者の思惑とやりとりを描いた部分は、日本のジャーナリズムの自己矛盾や鈍感さを余すことなく描いてしまっている。
著者自身も本意ではなかったのかもしれないが、本書は、調査報道に象徴されるようなジャーナリズムが変質していくさまを描き出し、図らずもその哀切な挽歌になっていいるかのようだ。
紙の本

紙の本忠臣蔵とは何だろうか 武士の政治学を読む
2011/06/28 22:34
物語と事実の断片の双方から真実を照射する試み
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書が刊行されたのは、大河ドラマ「元禄撩乱」が放送されていた頃だろうか。だいぶ時間が経っているが、改めて読んでみると素直に「面白い」。大河ドラマ便乗本などとあなどってはいけない。忠臣蔵のもつ「わかりにくさ」と「面白さ」とを上手に解説してくれている。
忠臣蔵が何度もドラマ化・物語化されるのは、起承転結がはっきりし、またドラマ性の高い「見せ場」がいくつもあるからだろう。一方、浅野内匠頭、吉良上野介、大石内蔵助といった主要人物が、「回顧録」を残しているわけでもないので、それぞれどのような「思い」をもっていたのかは、最終的にはわからない。ここに通俗的なストーリーを量産する力と、さまざまな解釈に挑む余地が生ずるのだろう。杉浦日向子「吉良供養」のように、見方を変えれば全く異なるイメージも出てくる。揺泉院黒幕説のドラマもできた(本書でも、彼女の資金=公金を大石が使っていることが指摘されている)。本書はそんな忠臣蔵に、「史実」としての忠臣蔵と、「物語」としての仮名手本忠臣蔵双方共に対象としつつ、サブタイトルにある「武士の政治学」を解き明かそうとする。
仮名手本忠臣蔵が、様々な架空のエピソードによって成り立っていることはよく知られていることだが、そこに「武士」という存在について、庶民に解説するという意図を著者は指摘する。一方、史実については、「仮名手本」などの物語によって、善玉/悪玉といった色分けがされてしまった人々を改めて洗い直す。それを考えるときの一つの補助線が、制度としての「仇討ち」である。武士の世における仇討ちとは、単なる「復讐」ではない。主君から認められた権利みたいなものであり、晴れて仇討ちが成功すれば、改めてほぼ同じ家格で召し抱えられる。認めるべき主君が既にいない忠臣蔵はここから外れてしまう。それなのに、なぜ、「討ち入り」に至ったのか?
もうひとつの補助線が、さまざまな忠臣蔵ものでも取り上げられる「敵討ちか、御家再興か」という二者択一問題である。忠義であることを示すのは、何も討ち入りだけではない。むしろ、御家再興のほうが上位にくる。さらに著者は、大石家は単なる家臣ではなく、浅野家の縁戚に近い家格にあったことも指摘する。もう少し縁戚関係が進んでいれば、大石家自身が御家再興を担ってもおかしくなかったのである。
こうした補助線をもとに、さまざまなエピソードを改めて読み解く。「藩札」の正銀引替の件は、赤穂藩の「正直さ」を示すエピソードとして紹介されることが多いが、ここでは赤穂藩の会計処理の優秀さ、また、御家再興に備えたものでもあることを想定する。なるほど、こうした見方もあったのか、と感心した。また、著者は大石の動機を読み解くにあたって、「忠臣と見られたい」という欲望の存在を仮定する。大石自身が、自覚的に「忠臣蔵」を演じていたということか。
忠臣蔵とはこんなに興味の尽きない考えさせる素材をもっていたのか、とあらためて勉強になった。まだまだ、さまざまな論点の著作が出てくるのだろう。それもまた、楽しみである。
紙の本

紙の本神保町「書肆アクセス」半畳日記
2011/06/15 00:00
今はなき書店の日記を読む、ということ。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
書誌アクセス。この書店名を知っているのは、そこそこの神保町通か、地方出版社関係者であろう。書籍取次である地方小出版流通センターの書店として、神保町にその存在感を示したものの、2007年に惜しまれつつ閉店した。本書店を偲んだ本まで出ている。本書は、閉店になる前の1998年から2002年までの日記である。前半は黒沢さんという20代末(当時)のスタッフが、後半は店長の畠中さんが書き記している。
閉店になってしまったお店の、日々進行していく日記を読むというのも、なんだか妙な気分だったが、読みはじめていると素朴に面白い。とりわけ前半部分は、まだ若めの黒沢さんのライフイベント(引越、結婚、引越、出産)とも重なり、テンポよく読める。慣れない業務にあたふたし、神保町そのものを盛り上げるべく「路地裏マップ」を町の関係者で打ち合わせて作成する。週末には映画のはしご、レイトショーにも時折いく。よく働き、よく食べ・飲み、よく話して、よく観る。サラリーマンも見習わないと、と思う。
後半の店長日記になると、前半部にもちらほら出てくるが、売上げ減の話がやや増えだす。「半畳」とは店内の事務スペースのことだが、「繁昌」への思いも込めていたに違いないだけに、残念であろう。中小取次のあった「神田村」の再開発の時期とも重なり、神保町そのものの変化期とも重なる。その意味でも実は貴重な記録なのではないか。
本書を読んでいて気づくのは、お二方がよく人と話していることである。一見、プライベートな飲み会に見えつつも、関係者の社交になっている。また、話す相手は、アクセスを頼りとする地方小出版関係者だけではない。個性的なお客さんもよく来て、よく語る。少々かっこよくいえば、このお店がサロンや社交場のような役割を果たしていることがよくわかる。本や読書というのは一見、孤独な行為に見えるけれども、こうした場によっても支えられているものであることがよくわかろう。
私自身はさほど地方出版の本を買うほうではない。むしろ、地方小出版にかかわる人々自身の方が個性的で「面白さ」を感じてしてしまう。そんな面々がこの場には集っていた訳である。ちなみに、本書の版元は秋田の出版社であり、その社長・あんばいこう氏もこの日記の常連登場人物である。
さて、アクセスと言う場が失われたことを、「偲ぶ」こととは別に、出版流通と言う視点からも別途検討が必要ではないだろうか。地方の出版物の売れ行き不振だったのか、出版界全体の地盤沈下なのか。ただし、地方小出版流通センターそのものがつぶれたわけではない。むしろここ数年、書店の大型化にともない、地方出版社のコーナーをよく見かける。アクセスの売上げ減には、「アクセスまでいかなくとも地方書が手に入る」という状況も進行していたのではないだろうか。であれば、ひとつの役割を果たしたうえでの終焉、ということになるわけだ。そうした分析がもっとあってよいように感じる。
一方で、本書で見られるような、「社交場」としての役割が失われることについては、やはり残念な思いが残る。オンライン書店の拡大が、かえって孤独な読者・読書を増やしているだけなのかもしれない、とふと考え込んでしまう。いや、これからの読者の力量次第であろう。
紙の本

紙の本武士の家計簿 「加賀藩御算用者」の幕末維新
2011/06/07 23:33
ある武士の家族の「生きざま」を現代に再現する。
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
昨年2010年の日本映画界は、「時代劇映画」豊作の年だったという。その中でも本書の映画化は異彩を放っていた。「家計簿の本が、どうやったら映画になるのか」という声もあったものの、ある家族のドキュメンタリーを見るようで興味深かった。本書は、サブタイトルにあるように「加賀藩御算用者」である猪山家三代の家族史を、その家計簿=入り払い帳をもとに再現している。家計簿だけに、文字通り「身辺」の再現になっているのである。
時代劇映画とはほぼサムライ映画のことであり、その基本はチャンバラとなる。ところが、本書の主人公である侍は刀を抜かない。御算用者=経理みたいなものだから、当然ではある。実は「最後の忠臣蔵」も、斬り合う場面がほとんどないことで話題となったが、「生きる」ことの姿勢をめぐっては、本書と対照的であった。しかし、時代は幕末から維新へ。その激動の時代を、刀ではなく算盤の腕でもって生き抜いてきたのである。サムライは刀のみによって生きるにあらず、とでもいえようか。
幕末維新というと「志士」ばかりが注目されるけれど、この家族は大所高所から議論をすることもなく、自らの家業=算用にひたすら邁進する。一見、融通が効かなそうな、時代の変化に乗り遅れそうな、保守的な姿勢に見えるかもしれない。ところが、これこそがこの家族を盛り立てていくことになる。加賀藩の陪臣から直参に、そして主君のそばに、さらには維新政府で兵站事務を担い、海軍省に勤めるまでになる。
ところで、本書でも映画でも大きな見せ場は、年来の借金を返済するために、弁当箱に至るまで家財道具のほとんどを売り払う場面である。家としての「覚悟」を見せる場面である。その一方で本書では、武士というものが構造的にどのような「借金体質」におかれているのか、どのような相互扶助の中にいるのか、といったことも綿密にあきらかにしており、読み応え十分である。「武士の借金」というと、家禄などが固定されて収入が増えない一方で消費支出が増えていったから、という教科書的に説明がされることが多い。間違いではないもの、本書ではさらに踏み込んで、儀礼や交際などの支出にあたる「身分費用」というものの存在を明らかにしていく。武士の「階級」としての姿を、より立体的に見せてくれるのである。
本書を通して「武士道」などというものは見えてこないけれど、それよりももっと大きくて大事な、「生きる」とはどのようなことなのか、ということがよりよく見えてくる。「武士の家計簿」と言う側面に注目した著者の慧眼である。著者の経歴をみると、速水融からつらなる歴史人口学者の系譜のようで、その姿勢に納得した。猪山家の綿密な家計簿は、著者に読まれるのを待っていたとしか思えない。
さて猪山家では、さらにお金に窮した時に、「刀」も売り払っている。「たそがれ清兵衛」も同じである。「武士の魂」を売ることについては、マイナスイメージをもたれがちだが、「売って当座をしのげる財産」としての側面にもっと注目されて良いように思う。
紙の本

紙の本もっとも美しい数学ゲーム理論
2011/06/01 23:52
「心理歴史学」の見果てぬ夢をさぐる。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
現代で、経済学や統計学のみならず、社会科学一般を学ぶ人・学んだ人にとって、「ゲーム理論」ということばを、どこかで耳にしたことがあるだろう。一般向けの概説書も数多く見られるようになった。本書も、ゲーム理論をやさしく解説したものの一つと思って手にとったが、だいぶ趣きが違う。おそらく本書を読んだからといって、ゲーム理論を使いこなせるようになるわけではない。本書のねらいは、ゲーム理論はどのような「流れ」の中にあるのか、を解き明かそうとすることである。ゲーム理論の系譜学ともいいかえられよう。
この系譜を解き明かす一つの鍵が、アシモフの『ファウンデーション』で展開されるという「心理歴史学」である。SF小説の中で掲げられたこの架空の学問は、政治・経済・社会の流れ、すなわち政府の興亡や戦争勃発にるまでを予測できるという。一見、SF小説中の絵空事に見えるかもしれない。しかし実は、「予測」というのは、社会科学系学問の「見果てぬ夢」といってよい。
社会科学もしくは人間社会を対象とする学問においては、考慮すべき変数が多すぎて「予測」など難しいということが「定説」のようになっている。その一方で、経済予測を根拠なしに平然と語るエコノミスト、政局の予想する政治学者、などなどあぶなっかしい「予測」が大手をふっている。その一方で、「ゲーム理論」は、シンプルで明快な設定をおくことで、人間行動を予測してみせている。本書はそんなゲーム理論を、「やさしく」ではなく、その生まれた素地から行く末までを描こうとしている。
まずは、経済学の祖とみなされるアダム・スミスからはじまる。そして、ナッシュ均衡、進化生物学、神経経済学まではじまった神経科学、社会物理学、ネットワーク理論と、ゲーム理論の接してきた世界を一通り紹介してくれる。ゲーム理論というものに関心がさほどなくとも、さまざまな学問の世界でどのような動きがあるのかを一通り知るというのにも便利な1冊になっている。
ただし、本書のテーマは、予測の可能性や妥当性ではないし、その批判でもない。人間にかかわる森羅万象を解き明かしたい、という人間の欲望そのものを対象としているといってよいだろう。この欲望はなかなか貪欲で、精緻なシミュレーションをつくるときもあれば、感情など今までなかった要素を取り込むこともある。その知的好奇心の遍歴を追うことはとても興味が尽きない。
紙の本

紙の本旅する力 深夜特急ノート
2011/05/24 22:14
旅する理由/旅をしない言い訳
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
初めての海外旅行の前、『深夜特急』を読んで大いに気分が盛り上がってしまった一人として、本書を読むべきかどうかずっと迷っていた。「旅をしなくなった自分」いや「旅をしない言い訳がうまくなった自分」に向き合うようで、いたたまれなくなるのではないかと感じたからだ。実は、「ドラマ」になったときは少々感じた。
沢木氏は、この『深夜特急』のみならず、その軽やかな人生—入社初日で退社して、そのままルポライターになってしまったという逸話などから、ある種の若者の偶像であったといってもよいのではないか。しかも、文化人や評論家などのように軽々しくテレビには出ない。かといって隠棲しているわけでもなく、きちんとした文章を読ませてくれる。魅力の尽きない書き手である。
さて、そんな沢木氏の本書を一言で言えば、「旅した言い訳」大全集である。『深夜特急』の周辺や裏話については、数々のエッセイから断片的にも得られるが、それらを1冊にまとめてしまったわけである。それは直接的な話に限らない。小田実の本を読んだ経験や子供のときの小冒険、駆け出しのルポライター時代の話まで書き込まれていて、ほぼ沢木氏の半自叙伝といってよい。『深夜特急』で彼の旅を感じた読者は、本書で、彼の人生という旅路の一端を垣間見ることができる。
さらに、読者の感想やサイン会などでのエピソードも披露されており、なかなか贅沢である。個人的には、書き手としての修行時代の話が興味深かった。一見、軽やかに見える文体や姿勢も、人との出会いや修行を通して培われたことがよくわかる。とりわけ、『深夜特急』の旅以後の数年で大量の仕事をしていることは、単に「旅の熱に浮かされた」わけではないことを教えてくれる。
ところで、『深夜特急』は、90年代半ばに大沢たかお主演でドラマ化されており、その当時の逸話も盛り込まれている。思わぬライバル出現へのコメントやゴールでの粋な演出など、これまた興味がつきない。ちょっとした感動ものだった。さらに2人の対談がついているというのも、なんだかとても贅沢である。
残念ながら、今の私には「旅する力」が少々足りないようだ。けれども、そんな旅をしなくなった者にとっても、どこか優しい時間を与えてくれる。
紙の本

紙の本おたから蜜姫
2011/05/11 00:10
ユーモア時代小説と見せかけて、実は古代史ミステリーという、鮮やかなお手並み。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
退屈姫君シリーズで、江戸時代を舞台に独自のユーモア時代小説の分野を切り開いた著者の米村氏。本書も「気分転換に耽読を」と気軽な気持ちで、600ページをこえるこの文庫を手にしたのが運のつき。蜜姫を中心とするユーモア活劇と見せかけて、今回の中心は「竹取物語」の隠された真実をめぐる古代史ミステリー。この最初からの「どんでん返し」に驚きつつも惹き込まれてしまった。「気軽な」どころか、古代史と古典について、わが頭に残存する知識を総動員しての、意外に大変な読書となった。
最新の発掘成果や新発見事物に基づきつつ構成する、古代史ノンフィクション仕様とは異なり、あくまでも現時点で(この場合は江戸時代)入手可能な文献にもとづき『竹取物語』に迫っていく。こうした、文献ミステリーともいえるアプローチは、『邪馬台国はどこですか』『六の宮の姫君』『邪馬台国の秘密』などと趣向を同じくするといえよう。
そういうことで、今回の実質的な主人公は、蜜姫の母・甲府御前である。読書家の彼女と、それをとりまく人々とによる、文献の解読と推測がストーリーを進める。もちろん、蜜姫を中心とした「活劇」組も、ちゃんと東へ西へと渡り歩く。そのうえで、「竹取物語」の解読と現代(というか江戸時代)とをむすびつくものも次第に明らかになっていく。前回より出演の吉宗も出てくれば、そこには家康も一枚かんでくる力技の1冊。なにより興味深いのは、謎解きが日本古代史像の再構成を試みることにもなるところにある。
ミステリーとすれば、詳細をここで明らかにすることは、ネタばれになるので避けておきたい。『竹取物語』は、なるほど確かに「不思議な作品」であることがよくわかることは指摘しておきたい。この不思議さは「なぜ、かぐや姫は求婚者に無理難題ともいえる宝探しの課題を出したのか」という1点に集約される。得体の知れない「子安貝」を筆頭に、それぞれの宝にはどのような意味があるのだろうか? しかも、求婚者のうち何人かは実在の人物や氏族に比定できるそうだ。帝も出てくる。今で言えばモデル小説か。では、なぜ・・・?
なるほど、よく知られた物語にこんな読み方があったのかとうならされる1冊。学生時代に「古典」の授業で「竹取物語」を習ったけれど、こんな方向には話をもっていってくれなかったぞ!と昔の先生に文句のひとつもいいたくなる1冊でもある。
紙の本

紙の本ビューティフル・ネーム
2011/05/05 00:19
同時代の作家の最後の作品を読む
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
私が書評らしきものを書きはじめた頃から、著者の作品を紹介してきた。一番最初には、才能ある同時代の作家と伴走できる同時代の読者の喜び、みたいに書き出した記憶がある。その時には、彼女の「最後の作品」について書く時がこようとは思いもしなかった。「残念」とも「無念」とも言いがたい、複雑な心境である。できれば「読みたくなかった」。
本書は、作家のPCから発見された未完の作品を含む、4編から構成されている。そのうち著者の生前に発表されたのは「眼鏡越しの空」「故郷の春」の2つである。「ビューティフルネーム」という表題作があるわけではなく、この2つに未完の「ぴょんきち/チュン子」をくわえた一連の作品につけられる予定だった作品集名である。いずれも、在日朝鮮人の「本名」や「通名」をめぐる物語である。
在日朝鮮人における「通名」の問題などというと、「差別の問題が・・・」と想像されてしまうかもしれない。しかし、著者はそうした展開になるのは慎重に避けているように見受けられる。現在の日本において、在日朝鮮人に対する差別がないとはいわないし、かといって、日々「即物的な差別」だけにかこまれて生活しているわけでもない。それぞれの年代で、たいていの日本人もかかえるであろう、それぞれの問題にも出会うはずだ。
「眼鏡越しの空」では、小学校で「本名」で通学していたのが、名前をからかわれたばかりに親にあたり、かといって「通名」で私立の中学高校に通うようになれば、どこか違和感を感じ過ごさざるをえない。小学生などのときに名前でからかわれるなどということは、在日か日本人かにかかわらず「よくあること」ですらある。そんなこんなで一喜一憂してしまう年頃の在日の物語である。「在日問題」という括りから言えば、それぞれは些細なことかもしれない。しかし、作者は、そうしたものをこそなんとかすくいとろうとしている。おそらく、この感覚は「在日」だけに限るものではないだろう。読者それぞれのテーマにひきつけることで、共感をもって読めるのではないだろうか。
作者は、自らが在日の血を受け継ぐクォーターであることを知ってから、『君はこの国を好きか』など、在日を主人公にする作品を多く扱うようになった。それまで、『帰れぬ人々』『少年たちの終わらない夜』などからはじまって『スタイリッシュキッズ』など、「今どきの若者」をとらえたものが中心だっただけに、その変わりように違和感をおぼえた読者も少なくなかったのではないか。ましてや彼女自身は、本名/通名をもっているわけでも、在日としてなんらかの差別を受けてきたわけでもない。
ただ、改めて本作品集を通してみると、作者自身もこうした読者からの違和感に対し自覚的であったように見受けられる。この作品集の4つめ「春の居場所」を読んでいて、ふと合点がいった。自分の高校時代を投影したとおぼしき未完の作品で、他の三作とはまとまりを異にする。本作では「頭のよろしい子」のいる中学校から「まあまあ」の高校へ、偶然にも進学してしまった高校生の回想が中心だ。彼女の今までの随筆を読んでいれば、ある程度彼女の人生との符合もつく設定である(もちろん「そのまま」ではない)。
高校生時代に好感をもっていた同級生への回想を軸としつつも、作品全体に流れているのは、「今いる場所」と同時に、「さっきまでいた場所」にも向けられる違和感である。この違和感はかたちを多少変えつつ、彼女の作品に繰り返し現れてくる。高校時代から思い感じてきたのであろう、彼女が作品を初めて世に問うたのも高校の卒業間際だった。ただし、彼女がしよとしたのは、その違和感を克服したり、抗議をしようとするものではなかった。「書く」ということで、丁寧にすくいとろうとしてきたのみだった。実は、その姿勢は、初期の作品群でも在日にかかわる作品群でも変わらなかった。
誰がいったか、作家は「処女作に向かって成長する」というが、その通りを示す作品集である。作家は、「すくいとること」の先に何を見たのだろう。もはやその答えはわからないのだけれど。
紙の本

紙の本科学コミュニケーション 理科の〈考え方〉をひらく
2011/04/19 22:04
正念場を迎える科学コミュニケーション
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書の刊行日は2011年2月15日。著者も出版社も、刊行後すぐに科学コミュニケーションの「正念場」を迎えることになろうとは、想像すらしなかったであろう。著者の元々の専門は「素粒子物理学」「原子物理学」という。おそらく原発にかかわったことなどないであろう。しかし、3月11日を境にして、多くの一般人にとっては、著者は「向こう側」の人になってしまっているのである。
この東日本大震災においては、地震や津波予知や防災そして原子力発電と、現代の科学技術をめぐる論争も巻き起こしつつある。「やっぱり、原子力は危ないのだ」と「今、ここ」で批判をすることは、実は容易なことであろう。ましてや、原子力による電力の恩恵を少なからず得てきたことを自覚しているのであれば、なおのことである。「今、ここ」で考えるべきことは、もっと他にあるのではないか、と足踏みをせざるを得ない。かといって批判の対象を、東京電力や政府の対応に絞ることも、それが必須のことであったとしても、問題を矮小化してしまってはいないかと感じてしまう。
実は本書の趣旨も、同じようなところにあるのではないだろうか。
本書が展開するのは、単に「理科離れをふせぎましょう」「科学をもっと身近なものに」といったレベルの話ではないし、ましてや科学コミュニケーションの正しいあり方、を示すものでもない。まずは、コミュニケーションとはどのようなものか、といったところから思索を深めている。従来の類書が、科学史や科学社会学などの蓄積に立って、「科学とは何か」といった視点から論じようとしていたことに対し、本書は心理学や脳科学などの知見にも視野を広げた上で、共感と共有を重視する論旨を展開する。著者自身の出自は物理学なだけに、精密科学からほど遠いと思われる心理学までの目配りを行なうのは、やや意外な展開と言ってよいかもしれない。いわば物理学者から歩み寄ろうとしているのである。たとえば、「物理学が難しい理由」というタイトルで1章を設けているところにもそれがよく現れている。
コミュニケーションとは、相手があってはじめて成立するものである以上、著者の論旨はごくまっとうな道と言えよう。この「震災」や「原発」が大いに問題化している現在、どのような科学コミュニケーションが行なわれるべきなのか、志ある人はきっと賢明に考え、行動しているものと信じたい。実際に、この状況下でも成功事例をいくつか見出すことができる。津波時の避難指導を学童に行ない、そのほぼすべてが生き残ったという防災教育の話は、文字通りのコミュニケーションの成果であろう。そして、福島第1原発で冷却活動を行った東京消防庁。危険な地に乗り込んだという行為以上に、マスコミを前にした明快な説明と率直な感想は、成果以上の説得力をもった。そして、対策の現場というものへの想像力や共感というものを、多くの国民に教えてくれたのではないだろうか。
紙の本

紙の本日本の歴史 20 維新の構想と展開
2011/04/08 21:42
明治最初期の制度変化をダイナミックに再現
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「幕末」「維新」、今なお、人々の関心を呼んでやまない時代である。さまざまな個性の人が出現し、さまざまな事がめまぐるしく起こった。その一方で、戦国時代に次ぐくらいに、混乱の時代でもあった。いや、「混乱」というのは婉曲的にすぎるかもしれない。内戦・内乱、略奪、暗殺、襲撃、殺人、・・・と、ダークサイドの面も見せた。幕末〜維新とは、短い間に、とてもさまざまなことが押し込められた時代であった。負の側面を含めて、物語に紡いだのはなんといっても山田風太郎だろう。
本書は、五箇条の御誓文が示された慶應4年(明治元年)から、明治憲法が発布された明治22年までの時期を扱っている。ごく短い期間だが「教科書で覚えるべき」ようなさまざまな事が起こった時期でもあり、それらを追う(おぼえる?)だけでも大変だ。しかし、本書は出来事や有名人物中心の記述をとらない。おおざっぱに言えば、幕藩体制から明治政府とへ体制が変わる中で、どのような制度の変化が、どのようになされていったのか、に記述を絞っている。「新政府ができた」からといって、一朝一夕で制度が変わったわけではない。また、制度を変えたからといって、人々にスムーズかつ十分に受け入れられる訳でもない。考えてみれば当たり前の事だが、こうした制度の変化を、体制の側と受け入れる側の双方の視点から、愚直なまでに描くことを試みている。
この変化を描くにあたって、「五箇条の御誓文」と「明治憲法」が、重要な区切りとなっている。明治憲法以前の「制度模索」の時期であったことを示す象徴的な目印なのである。たとえば現代から見ると、御誓文の「万機公論に決すべし」と「帝国議会」の間には、つながる「線」を見てしまう。自由民権運動も「万機公論」に依拠していた。しかし一方で、この2つの間には、制度的にも公議所や集議院、左院など、今では見えづらい「線」もあったわけである。「教科書で見た気はするが中身はよくわからない」これらの制度について、実際に参加した藩士の一人の日記も参照するなど、具体的にどのようなことが行なわれたのかを丁寧に記述し、どのような限界があったのかを解説していく。納得しきりである。
こうした丁寧かつ手堅い記述で、社会体制の変革=版籍奉還から廃藩置県まで、身分制度=士族における秩禄処分、地方自治の仕組み=戸長の役割から府県会の体制まで、また企業勃興の経済メカニズムなどまで、政治経済社会にまたがる制度変化を丁寧に解説してくれる。英雄史観を期待する人には物足りないだろうが、今まで気になっていた教科書の「すきま」を知るには得難い1冊である。
紙の本

紙の本ダメになる会社 企業はなぜ転落するのか?
2011/03/31 21:17
サラリーマンの倫理と資本主義の精神を考える
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
組織における人間、日本ではそれはサラリーマンと総称するが、この問題は近代資本主義諸国において共有された「悩み」ではないだろうか。「困難」というほど、深刻なものではないだろうが。専門職業人として一匹狼で生きて行けるほど強いわけではなく、かといって日雇い労働者のような不安定な身分と収入に踊らされているわけではない。そして、このふらつきのすき間をねらって、実にさまざまなビジネス書が投げ込まれる。
本書もそんなビジネス書の1冊といっていいだろう。多くの著作を上梓している経営学者による一般向けの書である。「会社制度」について、法制度やさまざまな事例をもとに解説するのが主旨である。いろいろなところで書かれたものを集めたらしく、雑然とした感じもしなくはない。また、何か即効性(資格試験など)が目指されている訳でもない。しかし、本書はサラリーマンの「すき間」に確かに入ってくる。
本書、またこの著者がさまざまな書籍で一貫して主張していることは、実にシンプルである。私なりに整理させてもらえれば、資本主義とは「金儲け」が目的なのではなく、「天職」を追求できる社会だ、ということである。「なんだウェーバーそのままじゃん」となるわけだし、実際、本書の最終章はそのまんまである。しかし、著者は大上段にふりかぶって、からまわりしそうな主張を、親しみやすい語り口やエピソードをもとに、日常レベルでの「腑に落ちる」感覚にもっていく。
たとえば「株」というものの役割については、映画「タッカー」の紹介からはじめる。私も一度だけあった地上波放送を、とても面白く見ていたのよくわかる。著者が注目したシーンとは、「新車発表会」でタッカーが売ろうとしたのは、新車ではなく「新車をつくる会社の株」であったことである。株とは「投資」なのである。あるモノを実現するために夢を共有することなのである。また、「会社は誰のものか」という大所高所の議論に対し、ペット愛護の事例をもってきて、「所有権」の問題を考えさせる。「所有」しているから、といって何でもできるわけではない。所有には責任がともなうのである。
天職を追求できるといっても、それを続けられるのはごく限られているはずだ。しかし、それを描く余地のある社会を維持し、一方で、自らの仕事になんらかの手応えが得られるようなものとする。彼が言っているのは、実はそんなごくごく平凡なことにすぎない。
国難ともいえる状況の中で、日々の仕事に追われざるを得ないサラリーマンの我が身を顧みて、疑問に思うことも少なくない。そこには大いなるすき間がある。そのすき間を考え続けるきっかけとなる一書になろう。
紙の本
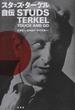
紙の本スタッズ・ターケル自伝
2011/03/15 22:14
彼もまた、大恐慌の子どもだった。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『仕事!』をはじめ、米国におけるオーラルヒストリーの第一人者として知られる著者自身のヒストリーである。1912年に生まれ、2008年に96歳で亡くなっている。本書の原書が2007年刊行というから、ぎりぎりで間に合った待望の自伝である。
個人史の試みにはさまざまな流れがあるが、『仕事!』のもつインパクトは独特のものがあった。日本国内でもさまざまな類似出版を生んだことからもよくわかるように、その独自性は、さまざまなふつうの人のオーラルヒストリーを、ひとつのまとまったものとして提示してみせた企画力にある。阪神大震災に遭った人々を「仕事」から括った本を手にしたときは、ターケルの本のもつ力強さをあらためて感じた。
彼の本で訳されているものは少なくないが、彼自身の話は意外によく知らなかった。60歳前後に様々な人にインタビューをして本にまとめる、という作業をはじめる前は、それはそれは自身がさまざまな職を転々としている。法律の職につきかければ、労働運動に肩入れしたり、演劇を試みたり、テレビにかかわったり、ラジオのパーソナリティもやってみる。そんなこんなの延長で、インタビューをはじめたのだそうだ。
「そんなこんなが歴史家ターケルを作り上げたのだ」とまとめたくもなるが、本書はそんなにまとまりがいいものではない。著者の思索のあゆみを知りたいと思った真面目な読者はむしろ面食らうだろう。本書の多くを占めるのは、どんな時に、どんな人と出会って、どんなことがあったのか、というばらばらなエピソードが雑然と積み重ねられているからである。
90歳をこえて、こうした昔のエピソードの細かな部分を覚えているのは驚異的であるが(それに対して細かな注を付した訳者も大変だったろう)、好奇心おう盛な著者の人となりがよくわかろう。日本の自伝(もしくは最近のテレビ番組の多いエピソード)によくみられるような、「内面の歴史」や「苦労談」を期待する読者を軽々と裏切ってくれる。これらのエピソードをいくらまとめても、「ターケルの思想」などというものは描けないだろう。いや、そんなふうにまとめられない軽やかさこそが、彼の仕事を可能にしたともいえる。過去の自分の内面を現在になって語る、ということは、どうしても脚色を避けられないだろう。そうしたものこそ、ターケルが一番嫌っていたことではないか。「今、ここ」の語りを丁寧に聞き取ることに価値を見出していたのではないだろうか。
そんな本書の中で、唯一、「人生観を変えた」と明確に語る出来事は「大恐慌」だという。しかしそれは、彼のキャリアや生活に大きな影響を与えたから、というわけではなく、「大発見」があったからだ、というのである。「人は特殊な状況に置かれたときどうふるまったかが問題で、どんなレッテルを貼られたかは問題ではない」(242ページ)ということが、よくわかったというのである。厳しい条件下で、人はどのように行動をするのか。おそらくそれは、「肩書き」やその人の「発言」などとはまったく無関係であったのだろう。それを彼は冷笑的にではなく、興味津々に見ていた訳である。十代の少年はとても困難な時代において、その好奇心を大いに開花させていたのである。
紙の本
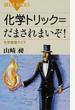
紙の本化学トリック=だまされまいぞ! 化学推理クイズ
2011/03/01 22:22
目指せ! 探偵ガリレオ
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「化学推理クイズ」と副題された本書は、なんとも不思議な味わいのある1冊である。
特許収入で暮らす悠々自適のエヌ氏を主人公=謎の解き手として、彼をとりまく人々にかかわるエピソードで構成されている。ショートショートのミステリーの体裁である。 「クイズ」というだけに、30それぞれが「トリック」と「解決編」にわけられているのだけれど、それなりの化学の知識がないと「推理」がまったくできない。そんな「解けないミステリー」を読んで楽しいのか?と思われる方もいるだろうが、それが意外にも楽しいのである。
何より、化学トリックといっても、大がかりなしかけがあるわけではない。灰皿の中の紙がタバコによって急に燃え上がったり、重要な手紙が白紙だったり、トンネルの照明の不思議などなど、そのほとんどはたいていの人にも身近か入手可能なもので構成されている。ミステリーでいえば「日常の謎」派といえるかもしれない。うまく使えば理科での実験や、手品にも使えるかもしれない、とさえ感じさせる。
ただし、化学だけに毒物をめぐるものも少なくない。お菓子を食べて苦しむ愛犬、古い邸に住んだらなぜだか体調が悪くなる、などなど、実は「ちょっとあぶない」ものも含まれている。ただし、これらの危なさも特別なものではなく、本来であれば、「日常生活で知っておいた方がよい」範囲といえるだろう。それもまた「日常の謎」の中である。くわえて、「エヌ氏」といえば、星新一のショートショートでよく出てくる名優ではないか!
ショートショートでもあり、化学入門でもあり、実験・手品のコツ入門でもある、そんな不思議な味わいの1冊である。「探偵ガリレオ」は確かに面白かったけれど、一般人にはちょっと真似ができない(いや、してはいけない)ものばかりだった。探偵ガリレオ気分を味わうための、「はじめの一歩」としてお薦めしたい。ちなみに、探偵ガリレオは物理学者だったが、本書の著者は化学者である。
紙の本

紙の本日本の歴史 19 文明としての江戸システム
2011/02/22 00:26
江戸時代への自負と偏見
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
予備校生たちの学習相談というアルバイトを長らくしていたことがある。その時にふと気がついたのが、江戸時代のもつ重要性だった。世間的な歴史というのは政治史が中心であり、それは英雄史観ともいいかえられよう。「歴女」がみる日本史もそうは変わらない。しかし、大学受験の世界でさえ、それでは通用しない。特に江戸時代あたりになると、「経済的なものの見方」が求められてくる。経済のありようについての知識と理解はいつの時代も重要とはいえ、荘園などは制度として理解すればある程度は済んでいた。ところが、江戸時代あたりになると、制度そのものがわかりにくいうえに、情報量が格段に増えてくる。「三大改革」が政治史的に重要に見えても、経済的な視点からみれば、評価はまったく異なってくるのである。八代将軍吉宗は単なる倹約家ではない。「市場社会」をなんとかコントロールしようと、文字通り「計算」していたのでもある。
経済の重要性などは、学界では当たり前なのだろうし、大学受験指導でも受験生にとっても広く気がつかれていることかと思う。しかし、そのことをコンパクトにまとめてくれている一般向けの良書はなかなか思いつかなかった。小説というかたちではあれ、貨幣制度からその経済をうまく解説した佐藤雅美の『大君の通貨』くらいではないか。市場経済の展開を踏まえたうえで、江戸時代の全体像を描こうとしたのは本書がほぼ初めての試みかもしれない。
著者は歴史人口学を専門とする経済史研究者である。その持ち味が存分に発揮された1冊といえよう。本書を一言でまとめれば、社会科学の視点から江戸時代を再構築する試みとなる。エピソードや政治史中心の編年体ではなく、経済、生活、人口、環境といった社会を支える個々のテーマで構成されている。「政治史以外全部」といっていいだろう。とりわけ、村などの個別社会単位で、家族の消長と社会階層を見事に説明しているあたり、歴史人口学者の面目躍如である。「階層分化」などとはよくいわれることだが、下層家族が絶家しやすく、その後を埋めるように上層からの分家が入っていたことなど、人口の動態が明快に解説される。
江戸時代を描くにあたっての本書の立ち位置は、「文明としての江戸システム」という書名そのものに十二分に込められている。「江戸ブーム」という用語があるが、その中には現代西欧型社会とはまた異なる社会システムが存在したことへの主張(そして自負)があった。本書はその系譜につらなりつつも、より詳細な実証性を備えている。明治維新以降の経済成長を準備したのは江戸時代にあった、とはよく見られる主張だが、勤勉さなどその精神性を重視する評論家が多かった。それらに対し、本書では「プロト工業化」など経済史学上の研究成果を豊富に紹介してくれている。その一方で、経済的な視点をつきつめていくと、江戸システムがそのままでは現代になれなかった点、すなわち資源などにおける閉鎖性をも明らかになってくる。本書では、この限界についても自覚的でバランスがとれている。
従来の「江戸ブーム」とは、どこか「失われた善きもの」に対する憧憬の念が先に来ていた気がする。文芸の面でそれが顕著だったが、エコロジーの面でも先進的だったとするような議論も実は大同小異であろう。本書をもって初めて、「江戸時代というものが社会科学的な検証の対象となる」というスタート地点に来れた気がする。
紙の本

紙の本偶然とは何か その積極的意味
2011/02/09 22:59
統計学を一歩下がって「考える」入門書
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ここ数年、統計について、特にビジネスマン向けに、「わかりやすい解説」を謳った本がよく目につく。統計についての知識と考え方が、これからの社会に必須であるという認識が広まっているからでもあろう。その一方で、リーマンショック以降、金融工学の果たした役割への懐疑も広まっている。どちらにしても、統計について道具的な関心しかもたない点では共通している。本書はそうした流行とは一線を画する、統計の基礎にある確率についての「考え方」へ考察を加えた1冊である。道具的関心に行く「ちょっと前」もしくは「ちょっと後」にでも手にとられるとちょうどよいのではないだろうか。
統計学は数学の一分野としてされていることが多いようだが、なんだかちょっと違う気がする。専門書を開けば難解そうな式のオンパレードで、たしかに数学っぽい。しかし、その成り立ちや発展の契機を見ると、なんだかとても人間臭い。そもそも賭けの分析からはじまったこと、また、ポアソン分布などは「馬に蹴られた軍人」を数えて見出されたこと、はよく知られていることである。確率論は、「この世」の不確実性を減らすように発展してきたと考えられている。その典型が金融工学である。著者は、実はそうではないのではないか、という立場から考察をくわえていく。
本書の前半は、統計的方法の前提にある確率についての基礎知識をまとめている。時には、例の「予言ダコ」パウル君を例にとって、確率論の考え方を教えてくれる。それは予言が成功したのではなく、あくまでも「不思議な偶然」でしかないのである。
後半になると、統計学そのものの時代性というか、文明論の世界へと思索が進んでいく。議論の分かれるところからもしれないが、これからの学問や研究・活動への問いかけもしくはヒントとして積極的に受け止めて行くべきではないだろうか。たとえば、戦後の産業界を支えた「統計的品質管理」についても、それは大量生産を前提としたものであり、品質管理そのものが統計的でありうる余地はなくなった、とも指摘する。
筆者は、前東大経済学部教授で、数理統計学者・経済統計学者として、功なり遂げた人物といってよいだろう。そんな彼をしてなお、このような本書を書かしめたのは、人生という、個々人にとっては一回きりしかない経験の存在があったからははないかと思われる。偶然によって不条理な仕打ちを受けた人に対して、「その不運の確率は・・・」と正確に説いたとしても何の意味もないからである。では、統計学はそれにどう答えたらよいのか? どんなに統計学や確率論の思索が進んだとしても、防げない不運は多い。けれども、と筆者は言う、「不運はわかちあえる」と。「最小不幸社会」というものの考え方はこういう部分にあったと思うのだけれど、提唱者も批判者もあまりよくわかっていないような気がする。
