アルテミスさんのレビュー一覧
投稿者:アルテミス

シエナ 夢見るゴシック都市
2003/09/07 01:36
イタリア麗しの迷宮都市、立体版
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
なぜ立体版かというと、イタリアの麗しの迷宮都市の筆頭はもちろんヴェネツィアで、ただしあちらは地勢上、平面の迷宮だからである。
ヴェネツィアを別格にすればシエナは私の最も好きなイタリアの町で、なのにシエナに関する日本語の著作は少ないので(ヴェネツィアは本棚ひとつ埋められそうなぐらい出版されている)私にとって貴重な一冊だ。
シエナに関する著作といえば石鍋真澄氏の名著「聖母の都市シエナ」(吉川弘文館)がある。が、そちらは内容が城壁内にほぼ限定されている上に美術の解説にかなりページが割かれていて(著者が美術史家なのだから当然だ)、周辺の農村地帯や鉱業資源についての記述は乏しい。ひるがえってこちらは、周辺地帯が都市の発展に果たした役割や、市民の気風がどのように形成されていったかなど、より全体的な内容になっている。「聖母の」が、これからシエナを旅行しようという人にとって旅をより興味深いものにするために役立つなら、こちらは、中世イタリアの都市国家というものに対する歴史的興味を日本にいながらに満足させるために役立つと言えよう。
とはいえ本書は旅行者への配慮も忘れていない。最終章ではシエナで味わうべき味覚の記述があるし、巻末には観光情報の一覧もある。この一覧は、下手なガイドブックより役に立つものだ。
ただ、本書の初版を購入する際には注意が必要だ。表紙を開いて最初のページが町全体のパノラマ写真なのだが、当初これが裏焼きだったのである。刊行後すぐに編集部に指摘したところ、まもなく(本当にいくらも待たずに)正しく印刷された本が出版社より送られてきた。対応のすばやさに版元の良心をみて感心した。ただし、書店の店頭にはまだ作り直す前のものが残っているので(これは流通上仕方のないこと)、もし白い大聖堂が中心より右側になっていたら、頭の中で左右裏返してご覧になることをお勧めする。

第六大陸 2
2003/09/06 00:53
わくわくして、あこがれて。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
月面に、居住地を作る。
すれたSFファンなら古すぎるテーマだ、と失笑するかもしれない。白状してしまえば、たいしたSF読みでない私も、そう思った。
しかし、読み始めたら、止まらなくなってしまった。読み終えたら、思い出してしまった。
人類が初めて月に立ったのは30年以上前の話で、私や私と同世代の人たちは子供の頃、君たちが大人になる頃には誰でも宇宙旅行ができる時代になっている、と本で読んで胸をときめかせていたものだ。
だが、21世紀になれば当然できていると思っていた月面都市はまだないし、そもそも人類が月に立つことさえなくなってしまった。その現実に対する失望が、月へ行くと言うテーマを古いものとして忘れようとさせたのかもしれない。
だから私は、本書を巨大建築プロジェクトの達成物語として読み始めたのだ。
私企業が、桁は大きいとはいえ限られた予算内で何かをしようと思えば、常にコストとの戦いになる。事故も、地球上での建築現場でだって珍しくないのだから、宇宙だの月だのでは起こらないほうが不思議だ。技術的な問題はもちろん、法的な問題もある。競争相手の横槍も、反対運動も。
そういったことごとへの、立案者でありリーダーである少女や技術者たちの苦闘を愉しんでいたのだが、読み終わったときには、「重さ、六分の一なんだなあ」という主人公のつぶやきや、靴底に比べてドレスの裾の摩擦係数が大きすぎて、歩こうとしても前へ進まないといった月ならではの描写の数々に、かつてのときめきを揺り起こされてしまっていた。たとえば。
空気のない月面では、風景はどのように見えるのだろう。
こんな疑問に、幼い頃は単純に、地平線(月平線?)が丸くて、その上に地球が浮かんでるんだろうなあ、と考えていたものだ。今なら、空気がなく遠くの景色がかすんでしまうことがないから、たとえば空気遠近法を巧みに用いて背景を書いたレオナルド・ダ・ヴィンチだったら、どうやって遠近感を出したらいいんだと悩むんだろうなあ、いや大天才のことだから別の方法を考え出すんだろうか、などとずいぶん違うほうに連想が行く。しかし、わくわくする、と言う1点においては全く変わることがない。
NASAに、スタートレックにあこがれて宇宙飛行士になった女性がいるという。宇宙からの帰還後に、スタートレックに特別ゲストとして出演したそうだ。
日本にも、失礼ながらお名前を忘れてしまったが宇宙飛行士として訓練を受けている女性で、宇宙戦艦ヤマトの沖田艦長にあこがれたのがきっかけとインタビューをうけて話している方がいた。
本書のような優れた作品がもっとたくさん出て、宇宙へ行きたいなあ、いや、宇宙へ行こうと思う人がたくさん出たらいいな、と思う。
わくわくして、あこがれて。そんな人々が。

天使の舞闘会 暁の天使たち 6
2003/11/30 05:18
第3部完結、第4部を乞うご期待!…とでもやったら良かろうに。面白ければどんなに長くたって読者はついてくるんだよ。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
著者の意向か編集部の戦略か、そのどちらなのか知らないが、いったいどこが、完結なんだ? 看板(帯)に偽りありじゃないか!
…と、言うのが、読者の大方の感想ではあるまいか。まあ、5巻までの話の広げ具合から言って、6巻で完結したりしたら相当に尻つぼみだよなあ、との予想はあったけれど、やはりというべきか、あとがきにしっかりと続きの予告が載っている。
いや、著作の大部分がひとつのシリーズなのが悪いと言っているわけではない。
SF界の3巨匠の一人、故アイザック・アシモフ御大も晩年に、全然べつの話をシリーズの一環として統合してしまおうとして、つなぎになる話を書いていた。
赤面ものなのだが私自身、いくつか書き散らしていた小説らしきものを長大なシリーズにまとめて「おお、なんという大河ロマンだ」と思っていた時期があった。(若かったな〜。戦記ものを書いているのに戦闘シーンが書けなくて作家になるのは断念したが。余談の余談だが、ペンネームの「アルテミス」は、その小説の主人公の一人の通り名だった。)
(私の文才のほどは別問題として問わないでもらえるとありがたいのだが)自ら創作したキャラクターが創作者の中で確固とした存在になってしまい、離れようにも離れられない、という状況は身をもって理解できる。
シリーズ物をもつ作家の中には、スティーヴン・キングの「ミザリー」の主人公のように、好きでもないシリーズを売れるからというだけの理由で書き続ける人もいるのかもしれないが、茅田さんの場合はそうではないだろう。今シリーズの1巻のあとがきで「ただ、書きたいと思ったから書きました」と明言しているのだから。
冒頭の、著者の意向か編集部の戦略か、そのどちらなのか知らないが、というのは取り消そう。
まず間違いなく、編集部の戦略であろう。でなければ、今シリーズの1巻目と最終巻のあとがきにこういう文章が並ぶはずがない。
しかし、だとすれば、編集部はなぜこんな戦略をとる必要があるのだろう。第2部である「スカーレット・ウィザード」では1巻で既にラー一族が登場しているのだから、第1部である「デルフィニア戦記」を読んだ人なら、話がリンクしていることは容易に想像がついた(ここまで密接につながるとは思わなかったにせよ)。
いや、第1部と第2部は舞台となっている世界が違うから、これを同一シリーズとして売り出すのは無理がある。しかし、これから続くであろう話の舞台は今シリーズに既に登場しているのだから、切り離す方に無理がないだろうか。
まだ読んでいない(書かれてもいない)物語を論評するのは無謀の極みとは思うけれど。
私は栗本薫氏のグイン・サーガという、ギネスに乗るような大長編に20年以上付き合っているような読者なので、たかだか30冊ぐらい(!)の長編にびくついたりしないから、堂々と長大シリーズを誇ればいいのに、と思うのだ。
面白ければどんなに長くたって読者はついてくるんだよ、と。
と、言いたい文句を言ってすっきりしたところで。
所々にでてくる、リィやシェラのデルフィニア時代を思い出しての台詞を読むたびに、ウォルやバルロ、イヴン、ナシアスといった面々が恋しくて仕方がない。
一番はあのおとぼけ者の王様だが、意外なぐらい恋しいのがドラ将軍だ。「スカーレット」や「暁の」には、ドラ将軍のような頑固親父の役回りのキャラクターがいない。「スカーレット」以降の話がいささかすっ飛びすぎに思えるのは、こうした地に足がついたタイプの成熟したキャラクターが主要人物として登場しないからだろう。今後の物語を構成するうえで検討して欲しいものだ。
そして、リィとからまなくても、短編でもいいから、デルフィニアの面々に再会できたら嬉しいなあ…と思うのは、やっぱりわがままなんだろう、ねえ。

女王と海賊 暁の天使たち 5
2003/08/30 15:39
ケリー・クーアに物申す。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
私はデルフィニアが大陸書房から刊行中だったころから茅田さんの作品が好きである。新刊が出るとなれば書店へ飛んでいき、会計を済ませる間も惜しくてあらかた立ち読みしてから買ったこともあるくらいだ(書店さんごめんなさい。でもちゃんと買ったからいいでしょ)。
で、どこが好きかというと、主人公たちはとんでもないキャラクターの中にそれぞれ一本芯の通った価値観を持っていて、事の是非を、細部にとらわれることなく本質において判断し、それが一見荒唐無稽に見えて、実はごくまっとうなものである事だ。
が、今回のケリーに、初めて「ちょっと待った」と言いたくなった。
今回、恵まれすぎていると非難されたケリーは、自分では自分ほど何もかも奪われた人間は滅多にいるまいと考えていた。確かにそうだ。だがやはり本人の考えるように、もうずいぶん昔の話だ。
その後の人生で得たものを、ケリーは過小評価してはいないか。
大財閥の総帥であることなどケリーには意味がないというのはわかる。
しかし、宇宙船乗りであるケリーにとって、最高の相棒であるダイアナとめぐり会ったことは、恵まれていたことではなかったのか。息子の成長を見届けられ、直接にではないにしろ孫の顔を見られたことは。七十過ぎまで病気ひとつせず健康でいられたことは。何より、生涯をかけてまで再会したいという相手に出会えた事は。
自分で言っていたではないか。「スカーレット・ウィザード」の5巻で、「大昔の話だ」と。それは、今は違うということ、あるいは、昔のことを否定しないが今は今ということではないのか。
とんでもないキャラクターが暴走するのが茅田作品の面白さで、その爽快さは、「へ?」と言ってしまいたくなるような無理のある筋書きも、「おいおい」とあきれてしまいそうなご都合主義も吹っ飛ばしてしまうほどだが、主人公に傲慢が見えては爽快さに翳りが出る。
ケリー、反省しなさい。
話は変わって、ダンですが。
母親を病弱で優しくて上品だったと信じていたダンが妻に選んだ女性が病弱で優しくて上品だったということは、ダンはいわゆるマザコンだったんでしょうねえ。
その母親が実は…。同情申し上げます。
なんとも半端な
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
旅行やイベントにはずっと一眼レフを使ってきたけれど、山歩きには軽さを優先してコンデジの防水耐衝撃タイプにしたところ、撮っていてどうにも楽しくない。
ファインダーのないシロモノなんぞカメラじゃない、ただの画像記録機だぁ~~!!
というわけで、SONYのRX100M3を買いました。
値のはるコンパクトカメラはフィルム時代のGR以来。
なので、ちゃんと使いこなそうとこの本を購入。
期待したのはこの機種の特徴や操作方法の解説で、もちろんそうした記述が本書のメインではあるのだけど、機種とは関係のない、もっと一般的な写真の基本の記述(露出とは?とか構図の取り方とか)が多い。
たとえるなら、電気炊飯器の取扱説明書に、水を多めにすると柔らかいご飯になります、少なくすると硬めですと、小学生の家庭科か?というレベルのことが書いてあるようなもので、正直に言ってしまうと邪魔くさい。
そういうのは入門書にまかせて本書では省いて欲しかったと思うのだけど、スマホカメラに押されて需要が縮小しているコンデジでは、一冊でカメラに慣れた人もそうでない人も対応できなければいけないのかなぁと思ったりもする。
中途半端な本ではあるけれど、要らないところは飛ばしてしまえばいいので、本書を読みつつ100M3をいじり倒しています。

スターリーテイルズ DIGITAL FINE ART
2003/10/05 08:09
レイアウトをした人に拍手。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
KAGAYA氏はラッセンやシム・シメールの絵が好きな人ならきっと好きになるだろう日本人画家。ジグソーパズルなどでおなじみの人もいるかもしれない。美しい色彩で、天体とギリシア神話のキャラクターとを重ね合わせて描く人である(ちなみに、本書にはアルテミスの絵も載っている)。
この画集を手に取ったとき、実はちょっと危惧があったのだ。オリジナルの絵の方を知っていたので、あのサイズが大きく描写の緻密な絵をこのサイズに印刷したのでは、細部がつぶれてしまうんではないかと。
表紙を開いてみたら、全体図の他に細部拡大図(というか細部実物大図?)がふんだんに載っていて、わたしの危惧を無用のものとしてくれた。おかげで本書はKAGAYA作品の魅力を堪能できるものとなっている。
が、全体図と細部図とに同じようにページを割くということは必然的に掲載作品数が少なくなるということである。最後のページを繰ったとき、あれ、これだけ?という感じがしたことは否めない。ページ数を増やすという手段もあるわけだが、知名度の高さがよほどのレベルに達した画家でないと、分厚い画集は売るのが困難だろう。
ともあれレイアウトをした人(画家本人か編集者か造本デザイナーか知らないが)に拍手。
最後に、評価が星三つなわけを。星が減った理由のひとつは、上記の「あれ、これだけ?」という食い足りなさ。もうひとつは画風が最初に述べた二人に近すぎるので、もう少しオリジナリティが欲しいということ。画風が私の好みと外れるということでもうひとつ減らそうかとも思ったのだが、そういう主観的な理由では申し訳ないので結局星三つ。蛇足だが、私の好みと外れるということは作品の優劣を意味しない(私はルノワールを嫌いだがすごいと思うし、すごいと思うが嫌いである)。
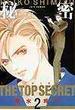
秘密 トップ・シークレット 2
2003/10/03 00:25
面白い。だけど…。
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
清水玲子さんといえばほとんどの作品がSFなのだけれど、どうもいくつかの短編を除けばSFを読んでいる気がしない。
面白くないわけじゃない、というより面白いんだけど。
このシリーズも、MRIスキャナーという新しい技術に初めて接した人間の戸惑いを描いた1巻の第1話はSFの秀作を読んだ気になったのだ。が、第2話では確立された技術に対する初心者の葛藤にとどまり、この第2巻ではもはや単なる舞台装置となってしまった感がある。
しつこく言うが、面白いとは思っているのである。ただし、その面白さがストーリーテリングのうまさによるものであって、いわゆる「SFマインド」によるものではないのだ。
舞台設定はSFだがストーリーはSFでもなんでもない作品しか書いていない漫画家には、始めからSFマインドを期待していないので素直にストーリーを楽しめる。だが、清水玲子さんの場合、時に「やるなあ」とうならせてくれるSFを書かないわけではないので、もどかしくなってしまうのである。
デビュー以来この著者の作品発表の場のほとんどが少女漫画誌(それも、読者年齢層があまり高くない)であったので、ストレートなSFが編集者に歓迎されなかったとは推察できる。
漫画家を契約で縛りこんで、本来あるべき作風を自誌向けにたわめてしまう日本の漫画出版界の問題点が清水さんにも及んでいるのだろうか。それとも、もともと主眼がストーリーテリングに向いていてSF設定はその手段でしかないのか。
かつて、ひょっとしたらこの漫画家は少女漫画家の枠を超えて、SF漫画家として大化けするかもしれない、と期待していたのだが。
できれば、初期の短編「ノアの宇宙船」や、このシリーズの第1話のような、これぞSF、という感じの短編集にチャレンジしてみて欲しい。

日本海海戦かく勝てり
2012/05/21 05:31
お二方とは逆の結論に傾いている私だが、本書を読まなければ、日露海戦への興味がこれほど深まることはなかった。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本を初めて読んだのは日露戦争に興味を持ち始めて間もない頃。定説自体が私の中ではまだ定説になっておらず、といって本書にも納得しきれず、丁字戦法の有無の判断は私には出来なかった。
しかし3年ものあいだ史料を読みあさってくれば、多少は自分なりの意見も出て来る。
現在のところそれは、丁字戦法はあった、である。
最初にそのヒントとなったのが吉田惠吾氏の『創出の航跡』であった。吉田氏は、優速を活かした並航戦が敵の嚮導艦を圧迫するのに有効であることをこの著書で証明している。
以来、丁字戦法の有無は、丁字戦法という言葉の定義を、丁字の陣形を描くことと、敵の頭を押さえることのどちらに比重を置くかによって判断することと考えるようになった。
戸高氏と半藤氏は前者を採っているので「丁字戦法はなかった」と言っているわけだが、問題は当事者達がどう考えていたかである。
それは、後者であった。
三笠艦長の伊地知彦次郎が旗艦の戦闘詳報に、「敵ノ前面ヲ圧ス」「更ニ敵ノ前面ヲ圧ス」と繰り返した後に、2時47分「敵艦隊ニ対シテ丁字形ヲ描キ」と明瞭に書いているのである。
この詳報は極秘戦史にも収録されているのだが、戸高氏と半藤氏は何ゆえこれを無視しているのだろう。
また、お二方が重視している奇襲作戦だが、これは当日の天候を見るまでもなく実質廃案であったとする論考も出た。(これを述べた木村勲氏の『日本海海戦とメディア』は、奇襲作戦のほか開戦劈頭の仁川沖海戦でも浅間を派遣するなど、厚い信頼関係があったとしか思えない秋山と八代に不和があったように書くから評価を下げたが、戦策の変化についての論考は検討に値する。)
お二方とは逆の結論に傾いている私だが、本書を読まなければ、日露海戦への興味がこれほど深まることはなかった。読んでよかったと思っている。
付記。
現在、極秘戦史は国立公文書館アジア歴史資料センターのHPで閲覧できる。
また、P97の『朝日の艦橋から見た日本海海戦』は国会図書館のHPの近代デジタルライブラリーで閲覧可能。ただし、正確な書名は『朝日艦より見たる日本海海戦』である。

ヴェネツィア私のシンデレラ物語
2003/10/10 01:38
玉の輿願望の女性にとってはうらやましい限り、しかし、自立した女性にとっては不愉快な限り。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
読了後、不愉快になった。
時代の違いもあるとは思うのだが、私は男の経済力にぶら下がって生きるタイプの女性は嫌いである。専業主婦が、というのではない。大多数の専業主婦は、家事を請負い子育てを行い家計をやりくりするという形で、家庭をともに築くことに貢献している。
が、この著者はほとんど初対面のときから、後に夫となるレンツォ氏からの高額のプレゼントを受け取り、幸運が舞い込んだと喜んでいる。その後も、いくら贈る側にとってはたいした金額ではないにしても、遠慮なくプレゼントを受け取り続け、また、ねだり続ける。
これが、著者がイタリアに行ったそもそもの目的である、ハープ演奏者としてのパトロンへの援助要請なら文句はない。芸術という金銭には換算し得ないもので返すことになるのだから。しかしこの場合は、レンツォ氏はハーピストとしての著者には関心を示していないのだから、単なる金食い虫の愛人ではないか。
男女の仲は当人たち以外には本当のところを知るすべはない。しかし、レンツォ氏の没後、数少ない血縁である甥が、氏の資産がすべて著者に行ってしまうことに憤りを感じたとしても仕方ないと思う。
甥の側からみれば、おじいちゃんが一生懸命働いて築いた財産の半分を放蕩者の叔父が使いつぶすだけでも腹だたしいのに、ほんの5年間結婚していただけの愛人あがりが残りをさらっていくなんて許しがたい、ということだろう。(あくまでも甥の側からを想像して、である。念為。)
無論、子供のないレンツォ氏が親から相続した資産を妻に遺しただけのことで、相続に関して著者に非はない。遺言状の偽造疑惑などを持ち出した甥のやり方こそ非難に値する。
しかしそれでも、不愉快さはぬぐえない。
人と人との関係は基本的にフィフティ・フィフティでなければならないと考える私にとって、交際相手がいかに破格な大金持ちであろうと、自分の生活は自分で何とかするという気概があるべきではないかと思うのだ。まして著者は、ハーピストとして立とうという努力をかなりの期間、続けていたのだから。まあ、芸術で生計を立ててゆくのは容易ではなかろうから、一時的に援助を受けるのは仕方ない場合もあろうけれど。
いっそ、商売として愛人をやっている女性の方が、それはそれで嫌いなのだが、いさぎよいような気さえしてしまうのである。
著者が、残された遺産を自分の遊興費に浪費するのでなく、世界中の音楽家たちへの援助に使っているのがまだしもの救いである。

アベラシオン
2004/03/12 07:31
著者の集大成。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
堪能した。
箱入り、2段組、本文の厚さ3cm、しかも活字が小さい。
これは手ごわそうだと思ったが、読み始めたら麻薬のごとくにやめられなくなり、とうとうまる一日かけて読破してしまった。
帯にもあるが、本書はまさしく篠田真由美氏の集大成であり、渾身の力作であろう。
篠田氏のこれまでの著作で書かれてきたありとあらゆるモチーフがこれでもかと注ぎ込まれ、その目眩を誘うような絢爛たる世界の濃密さに、まるで水を呼吸してでもいるかのような息苦しささえ覚える。
独立独歩を誇った中世都市国家時代から、他国に翻弄され蹂躙され忍従させられる近代までのイタリアの歴史。それによって生み出されたルネサンスからマニエリスムを経てバロックに至る美術と建築。
薬であり毒でもある植物を集めた、閉じた庭園。地獄への道にも似た螺旋状の路を持つ、深く暗い井戸。
貴族という華やかな響きの裏に絡みつく、血の桎梏。掛け違う愛情。
推理小説であるからには許されぬはずの、超自然の存在である天使までもが、登場人物の名前に、店の名に、館の名に繰り返し現れ、ついには作品の主題のひとつにまでなっている。
あらすじは、読んだばかりの興奮状態で書くと、うっかりネタ晴らしをしてしまいそうなので止めておく。
が、私だけ惑わされるのは癪なので、イタリア語の知識のない向きには、館の当主であり貴族である兄弟の「兄」アベーレの名が、旧約聖書で「兄」カインに殺された「弟」アベルの、イタリア語読みである、という余計な情報を披露しておこう。
篠田真由美氏の代表作としてよく挙げられるのは、建築探偵桜井京介シリーズである。篠田氏のシリーズとしてはもっとも多い12冊(2004年3月時点。含番外編)が刊行されていて、また、もっとも売れているようでもあるから、まあ、あながち誤りではない。
しかし、以前から私は、篠田氏の著作としては建築探偵は本流から外れており、これを代表作とするのは違うのではないかと思っていた(作品として劣っているという意味ではない、念為。私は建築探偵も好きである)。
篠田氏の著作を並べて、そこから建築探偵を抜いてみれば、一目瞭然である。
『琥珀の城の殺人』『ルチフェロ』『天使の血脈』『ドラキュラ公』『彼方より』ほか多数。
ジュニア向けに書かれたいくつかを除けば、推理小説の形をとるものであっても、そのほとんどはヨーロッパの歴史に題を採り、その脈々たる流れに想像力を刺激されて書かれた、欧州歴史幻想小説ばかり。
こちらこそが篠田氏の本領であろう。
はたして、本書のあとがきで、建築探偵は作家として立ち行くための苦肉の策であったことが明かされている。
建築探偵のファンは怒るかもしれない。が、苦肉の策であろうと無理やりひねり出した口を糊する手段であろうと、12冊も書いており今後も続く予定があるからには、書くに必要なだけの愛情は持っていよう。
でなくば、著者がその持てるもののすべてを注ぎ込んで書いた作品の語り手に、建築探偵の登場人物の姪を持ってきたりはしないと思う。
(売らんかなの手段であるとのみ見るのは下衆のかんぐり。そうすることによってもっと売れるようにしようという計算が全くないとは言わないが、全力を投入した作品に、商売っ気のみで愛情をもてない作品を持ち込める作家がいるとは、私は思いたくない。)
その著作の嫡流と傍流とが合流した本書は、やはり篠田真由美氏の集大成なのである。

復活の朝
2003/10/10 23:35
友人には、グインの新刊が出るたびに…
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
いやー、やっと終わりました、パロ内乱編。
まだいろいろと問題は残っているけれど、とりあえず区切りはつきました。お祝いに評価は五つ星をあげてしまおう。
それにしても、登場人物がこれだけ多い小説なのに、どうしてどの国の王家も王族の数が少ないんでしょうね。今回の内乱で王族の数が減ってしまった、困ったと言っているパロでもまだ多い方で、平和を享受してきたはずのケイロニアでも、アキレウス帝と、シルヴィア、オクタヴィア、マリニアのほかには婿二人(グインとマリウス)しかいない。ユラニア公家やサウル皇帝家は全滅してしまったし。何代も続いた王家なら、傍流ってものがいくらでもあるはずじゃないかと思うんですが。歴史の浅いモンゴールは外すとしても、ねえ。
話の区切りがついたところであらためて振り返ってみると、初めの頃に比べて、登場人物たちがどうも小粒になってしまったような。
イシュトヴァーンってこんなに内向きな性格でしたっけ? 辺境編の頃は、もっと陽気でタフだったような気がするのですが。今回出番のなかったリンダも、巫女姫としてもっとカリスマ的な働きをするものと思ってたのに。
変わらないのはグインとレムスだけ。
グインは始めっから王者の風格ある人物だったし、レムスは姉と自分を引き比べていじいじしてたし。
それとも、読んでいるこちらが変わったんでしょうか。何しろ、読み始めた頃は10代だったのに、今では40の声を聞いてるんですから。
前の巻から、新刊時の帯に100巻までのカウントダウンが載っていますが、今のペースでは、到底100巻では終わりそうにありません。願わくは、完結するまで栗本さんと私の寿命が続きますように。友人には、私が死んだら香典は要らないから、私の墓にグインの新刊が出るたびに供えてくれと頼んではありますが。

日露戦争物語 第5巻 天気晴朗ナレドモ浪高シ (ビッグコミックス)
2004/05/29 08:42
主人公が兄上のようなイイ男に成長してくれることを期待しつつ。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
北朝鮮はどうしてあ〜ゆ〜国なんだろうかという疑問から始まって韓国についての本を読み、そこから反日の韓国と比較される親日の台湾についての本を読んだが、どうでも日清日露の戦争までさかのぼらなければ根本が見えてこないということが解ってきた。
で、今までさかのぼる形で読んできたのだから、順序良く?日露戦争について読もうと思ったら、今年は日露戦争から100年ということで、日露戦争についての本が山ほど出ている。
多すぎて選べないよ〜と思っていたら、マンガで『日露戦争物語』なる本が出ているではないか。ちょっと長そうだが、マンガなら入りやすかろう。でもこの著者知らない。とりあえず始めだけ読んでみよう。
そう思ってbk1に2巻まで注文して、届いた本を開いた第一印象。
「ヘタクソな絵だな〜〜〜」
失礼。しかし、絵だけでなく、コマ割りやネームの構成も不十分。時間経過とか間合いを表現するテクニックが特に不足していて、前のシーンの続きだと思って読みすすめたらいきなり日付が変わっていたり、内心を察しあいながらの会話のはずが、どうかすると説明する台詞を書き落としただけのような、映画で言えばコマ落としのようになってしまっていたりする。
が。
面白いのである。
ストーリーは日本海海戦で作戦参謀を務める秋山真之の伝記。
2巻までの主人公はまだ子どもから少年といった年齢で、負けん気の強いガキ大将。自分より体が大きく強い相手とのケンカを、色々な戦術を用いて勝っていくあたりは後の作戦参謀の片鱗をのぞかせている。
しかしそれよりは、時代が激変してゆく中でアイデンティティというものを、大人はいかに保とうとするか、子どもはどのように構築してゆくかの群像劇として面白い。
これは当たりだ、と、すぐに次の巻を読みたくなり、夜中までやってる近所の書店へ飛んでいった。(bk1さんごめんなさい。宅配便が届くのが待てなかったんです。)
が、6巻が店頭にない。仕方なく5巻まで買って帰って、6巻以降をbk1に注文した。注文時点で24時間以内発送だったので、書店へ注文するよりずっと早い。(bk1さん有難う。)
で、5巻までを読みながら待っているのだが。
主人公より、その兄、後に海軍の弟に対し陸軍でコサック兵と戦うことになる秋山好古が実にかっこいい。
9歳(10歳?)も年上の兄と比較しては主人公が気の毒だが、成長途上で生き方がまだ定まらずふらふらしている弟に比べたら、近代をサムライの精神を保ったまま生きる兄上は筋が通っていて気持ち良い。
フランス留学は出世街道から外れてゆく道であると承知の上で、「フランスの酒も美味いのでしょうなあ」と一言、旧藩主のお供を引き受ける。
ううう。感涙ものである。
主人公も海軍へと人生を定めた。
兄上のようなイイ男に成長してくれることを期待しつつ、早く届かないかな〜〜と首を長くしている。

世界の紛争地ジョーク集
2004/03/30 06:49
笑いとばすほうを選ぶわよ!
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
有名なので、知っている人も多いだろう。第二次大戦中のドイツでのジョークである。
真夜中に空襲があった。防空壕に集まった人の中で、「こんばんは」と挨拶した人は、まだ寝ていなかった人。「おはよう」は、既に充分に眠った人。
「ハイル・ヒットラー!」は、まだ目が覚めていない人。
本書には、この種のジョークがてんこ盛りである。
どんな独裁者も戦争も、それを完全に封じることは不可能。何しろ、あの北朝鮮で聞いたという、金正日をおちょくったジョークまで収録されている。
人は、どんなに息苦しい生活をおくっていようと、笑うことをやめられない。いや、それだからこそ、笑い飛ばしてしまうことが必要となるのだろう。
スターリン時代の旧ソ連のものもいくつか載っているが、だいたいは私もリアルタイムの記憶のある時代のものである。
イラク。パレスチナ。アフガニスタン。旧ユーゴ。
ただし、イラクと言っても湾岸戦争後のフセイン政権下のもので、さすがにイラク戦争後のものはない。が、自衛隊を派遣している今、日本をネタにしたジョークがもし生まれているとしたら、ぜひ聞いてみたいものだ。怖い気もするが。
数々のジョークを読んでいると、そのジョークを発する国や民族の性格や、登場する国への見方や力関係などが垣間見える。
パレスチナでは、パレスチナ人を押さえつけようとするイスラエルのやり方の愚かさを笑い敵対意識むき出しなのに、イスラエルではユダヤ人はアラブ人を見下した形で笑う。パレスチナ人がイスラエルを敵とみなしているのに、イスラエル側は対等な敵とは見ていないということだろう。
日本が登場するものも三話ほど収録されている。それによると、やはり日本人は勤勉で勉強熱心、正確さを求めると思われているらしい。
笑い飛ばす対象として登場するのでない点が少々残念なのだが、これは著者の自主規制か、それとも、日本人である著者に、日本をネタにしたジョークを教えるのを世界中の人が遠慮したためか。
本書を読んでいて、二冊の本をしきりに思い出していた。
一冊は、日本発の困難の中の笑いとして、藤尾潔氏の『大震災名言録』(光文社・知恵の森文庫)である。阪神・淡路大震災をネタに、笑いを誘いながら人のたくましさを謳い、同時に、日本のさまざまな問題点を提起してもいる。大地震にみまわれたときのさまざまな知恵が得られるので、お勧めである。
もう一冊は、私の好きな漫画家・獣木野生氏の半自伝作品である『青また青』(新書館・ウィングス文庫)。著者はずいぶんと大変な半生を過ごされたらしいが、この本に、こういう台詞がある。
「自殺するか笑い飛ばすかない状況に追い込まれりゃ、タマナシでもない限り誰でも笑いとばすほうを選ぶわよ!」

カタコト・イタリアーノで旅しよう 食べたりしゃべったり極上イタリア
2004/03/20 04:29
付け焼刃のイタリア語をものにするヒント。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
いくつかの書評でえらそうにイタリア語の知識を披露しているが、私のイタリア語の会話能力は、実はこの本のカタコト・イタリアーノとどっこいどっこい。
つまり、基本的な挨拶はできる。買い物もレストランでのオーダーもなんとかなる。道に迷ったら人に聞くことはできるが相手の返事がよくわからないことはしょっちゅうで、そういう時はイタリア人の身振り手振りの大きさに感謝しつつ行くべき方向だけでも理解しようとこころみる。そういうレベルである。
なので、なまじ地元の人とコミュニケーションをとろうなどと考えると、もうお手上げである。たいていのイタリア人は愛想がいいので、相手が暇でありさえすれば、がんばれば簡単な会話を成立させられないでもないのだが、忙しそうな人には申し訳なくて声をかけられない。
(どう見ても暇そうなのに愛想の悪いイタリア人も、たま〜〜〜には、いる。運悪くそういう人に話しかけてしまうと、相当落ち込む羽目になる。)
しかし、言い換えれば観光だけしている分にはとりあえず何とかなるということで、それには秘訣がある。
この本の、「火事場のイタリア語」という章にのっている三つの助動詞だ。
この章を読んだとき、おお、同志よ! と心の中で一方的に著者と握手をしてしまった。
何しろイタリア語の動詞は一人称、二人称、三人称、そのそれぞれの単数形と複数形と、現在形だけでも6通りに変化する。しかも、使用頻度の高い動詞ほど変化が不規則で、まる覚え以外に方法がない。
英語のhave動詞に相当する単語はavereだが、これの一人称単数形現在形が、いったいどうしてhoなんだ? つづりにも発音にも全く共通点がないじゃないか!…と心の中で絶叫した日本人は、私だけではない(と、思う)。
それでも、はじめてのイタリア旅行のときは、その前の半年間NHKのラジオ講座を、仕事中と寝ているときとお風呂のとき以外は聞き続けて、よく使いそうな動詞はちゃんと変化形まで覚えて行った。
だが、旅行が回を重ねるに従って使わない変化形はどんどん頭からこぼれ落ちていき、助動詞一人称単数形プラス動詞の原形で用が足りることが経験的にわかってきた(私はたいてい一人旅)。それ以来、私はよく使う動詞の原形を並べた一覧のある旅行会話集の、その部分だけをコピーした紙を、地図などをとじているバインダーに一緒に閉じて持ち歩くようになり、会話集をめくることは滅多になくなった。
その点、この手があることに最初から気づいて、それに徹した著者は賢い。
イタリア語のテレビやラジオの講座や各種テキストは、なぜこんな便利なことを最初に(は無理でも、早めに)教えてくれないのだろう? 本格的にイタリア語を勉強したい人だって、実際にイタリアに行ったとなれば、まずは最低限のコミュニケーションを成立させないことには生きていけないではないか!
ただ、おしいことに、この本だけで旅行はバッチリ!とは言えない。
つづりの読み方の基本が載っていないからだ。なので、イタリア旅行の予定がせまっている人は、目に付く中で一番薄いテキストの始めの方だけ読んで、その後にこの本を読むのがいいだろう。
イタリア語の発音は、実に簡単。LとRにさえ気をつければ、カタカナ読みで立派に通用する。聞き取りも同様。少なくとも私の場合、英語は知っている単語でも聞き取れない方が多いが、イタリア語なら知っている単語はあらかた聞き取れる。
観光収入世界一のイタリアだけに、有名な観光スポットでは英語が通じるが、カタコトでもイタリア語を使うと相手の態度ががらりと変わることがある。
日本人だって、日本に来たガイジンさんがカタコトでも一生懸命日本語を話すと嬉しくなるのと同じこと。
付け焼刃でも何でもいいから、イタリアへ行くならちょっとでもイタリア語を覚えて行こう。

ヴェネツイア帝国への旅
2003/11/16 11:40
「海の都の物語」を読んだら(読んでから)、この本を読もう。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本書は、ヴェネツィアが地中海沿岸の海洋拠点を獲得、維持、喪失してゆく過程を、現代(ただし1980年)の英国人旅行者の視点で述べたものだ。
おそらく、ヴェネツィア史の知識がないと、この本は読んでもさっぱりわからないだろう。あるいは、ヴェネツィアをかつての帝国主義諸国のような、領土欲ばかり強い覇権国家と誤解するかもしれない。
フン族に追い立てられて干潟に逃げ込んだ人々には、資源といえば魚と塩しかなく、家を建てる土地さえもなかった。家を建てるには大量の杭を打ち込んで土台を作ることからはじめねばならなかったが、その杭とすべき木材も他国から買い求めねばならなかった。ヴェネツィアが交易に必死になったのはまさしく生き残るためだったのだ。
交易によって生き残ることができたヴェネツィアが更なる発展を期したとき、その手段を交易に求めるのは当然である。ヴェネツィアが地中海に欲したのは領土ではなく海洋基地で、領土はそれを維持するに必要な場合に限られた(イタリア本土は例外)。
それを頭に入れた上で、初めて本書に描かれるヴェネツィアを理解できるだろう。
しかし、当時、海外にいる自国民に対し最も人道的であった国家とされるヴェネツィアにしても、海外にいる自国民に支配される人々に対してまでは人道を尽くせなかったようだ。
共和国から地中海の島を領土として与えられた領主の中には非道な者も少なくなかったが、共和国はそれによって支配地域の秩序が乱れたり他国につけ込まれたりしない限りは放置していた。本来が都市国家に過ぎないヴェネツィアには、そこまで監督できる人材の絶対量がなかったのだろう。そもそも、当時はフランス革命前であり、基本的人権などという概念のない時代であった。
それにしても、それらの領主が、ごく一部とはいえ20世紀なかばまで領主として残っていたとは知らなかった。共和国がナポレオンに滅ぼされたあとも領主が領土を維持できたのは、いかに共和国健在の時代にしっかりした支配体制を構築しえたかの証明であろう。
塩野七生氏の「海の都の物語」は私にとって無二の書であるが、この書に不足しているヴェネツィアに支配された側の立場を補完するのに格好のものである。
ただ、本書について2点の不満がある。
図版がたくさん載っているのはよいのだが、原書にあるものを再録するだけでなく、日本版では詳細な地図を章ごとに付けて欲しかった。東地中海に無数に散らばる島々の名前をすべて把握している日本人など滅多にいないだろうし、まして現在の地名と当時のヴェネツィアでの呼び名を正確に結び付けられる者など極少数だろう。
また、邦題であるが、英語の「Empire」と日本語の「帝国」はニュアンスが違う。ヴェネツィアが独立国であったことさえ知らない日本人の方が多いのだから、「帝国」とやってしまっては、ヴェネツィアには皇帝がいたのか、と早合点されかねない。「ヴェネツィア・海洋国家を旅する」とか、あるいは原題のまま「ヴェネツィアン・エンパイア」とかにした方がよかったのではないかと思う。

![今すぐ使えるかんたんmini SONY RX100 基本&応用 撮影ガイド[RX100IV/RX100III/RX100II/RX100完全対応]](https://img.honto.jp/item/1/f8f7ef/75/110/27735522_1.jpg)
