BH惺さんのレビュー一覧
投稿者:BH惺
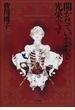
開かせていただき光栄です DILATED TO MEET YOU
2011/12/29 21:50
この作品に出会えて光栄です
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
タイトルからして人を食ってます。
最初一体どんな内容なのか想像もつかず。が、冒頭からいきなり解剖室での妊婦の死骸描写にあ然・呆然。ここでもう作者の術中にハマってしまいました。かなりグロテスクなはずなのに、ちっとも陰惨ではない。むしろカラッとしてユーモラス。なにより登場人物たちが個性的で魅力的だから。
重要なキーパーソンである解剖専門の外科医・ダニエル。そして5人の才能ある助手たち。そのやりとりが面白い。師弟の絆は強く結束していて読んでいて羨ましいくらい。
舞台設定が18世紀ロンドンなので解剖学がまだまだ認知されていない時代。そのため、技術向上のための死骸調達もままならず、危ない橋を渡ってようやく手に入れた死骸はなんと準男爵令嬢。しかも未婚でありながら妊婦だったという、いわくつきのもの。
紆余曲折あって、なんと男爵令嬢の他に2体もあるはずのない死骸が発見されてしまう……。
もうここからが本格ミステリーの始まり。探偵役は清廉潔白な法の番人サー・ジョン治安判事。彼は盲目であるけれど、その分雑多な周囲に惑わされることなく、しっかりと真実を見極めることができる。
インパクトありすぎる脇キャラ・少年ネイサンの所有する稀覯本をめぐる陰謀にまきこまれるダニエルとその助手達。彼等は解剖技術を武器にして共にサー・ジョン治安判事とタッグを組んで数奇な殺人事件を解明してゆく。
二転三転する事態。一体真犯人は誰なのか? ネイサンを主軸に置いた視点とサー・ジョン判事主軸の現在進行形視点。時系列が異なりながら進行し、ラストには見事に融合するという構成の巧みさ。裏に裏をかくトリックの鮮やかさ。そして毒々しいまでのユーモア。そしてほのかに漂う背徳と耽美。
作者はとてもご高齢とのこと。ですが、その熟練の職人技に酔わされました。特に事件が解決したあとのあの寂寥感がたまらない。そして全編通してどこか突き放して達観しているような洒脱さ。助手たちが死者を送るために歌う「解剖ソング」をラストにもってきているところがなんともブラックユーモア溢れています。それに対する、特に作中最も魅力的なキャラ、エドとナイジェルの末路がこれまた切なく哀しい。
解剖学とミステリーのコラボが白眉。元ネタ的作品「解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯」も併せて読むと、より一層作品世界を理解できること請け合いです。

解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯
2012/01/16 12:09
好きこそ物の上手なれ
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
期待せずに読み始めたのですが、意外や意外。最高に面白かったです。分厚いし、解剖医なんてまるっきり興味無い自分がのめり込むように一気に読了してしまいました。
18世紀イギリスに実在した「近代外科学の開祖」とまで言われた人物ジョン・ハンターのバイオグラフィー。と言っても、従来の単なる偉人伝に終始するのではなく、とにかく一筋縄ではいかない、まるで小説のようにドラマティックなバイオグラフィーとなっていました。
当時の宗教観から外科医師はとても低い身分とされていて、古来から伝わるなんの根拠も無い医療法がまかり通っていた18世紀。そんな時代に突如として現れた天才もしくは鬼才の外科医師・ジョン・ハンター。幼少時の彼は勉強が大嫌いでほとんど無学に近い。内科医として成功を収めている10歳上の兄・ウィリアムの援助を受け彼の医療助手を務めていくうちに、解剖医・外科医の学問に目覚め熱中し没頭。その天才的な能力を開花・発揮してゆきます。
このジョン・ハンター、はっきり言ってとんでもない人物。田舎モノで下品。上流階級とは無縁だけれど、きさくで豪放磊落。ある意味自然児だった彼が実は医師として見事な変貌を遂げてゆく様に胸がすく思い。解剖技術向上のために、人間の死体を収拾するという裏稼業もこなすところがまたなんともブラックで、医師として患者の治療をする行為と真逆でギャップとともに魅力を感じさせます。
王室とも繋がりを持つ兄やライバル達との嫉妬と確執。彼の愛すべきキャラクターと天才的技術を慕って訪れる多くの弟子たち。その人間ドラマも見事に描写されていてまるで小説のように読ませます。面白すぎてページをめくる手がとまらなかった。
現在の外科医療のベースとなるあまりにも偉大&多大な功績を残していながら、その業績は彼の死後ライバルや身内によって殆ど消失させられてしまう。けれど、そんな状況下にあっても、偉大なる師を最後まで敬愛した助手クリフトによって細々と受け継がれ今も博物館や書籍として残っているとのこと。そしてなによりジョン・ハンターが教えた多大の弟子たちが各国に散らばり、彼の理念と教義を護りながら今日の外科医療の進歩に貢献したという事実に思わず涙。
天然痘ワクチンを開発したエドワード・ジェンナーは彼の最愛の愛弟子だったということも初めて知りました。
さらに彼の患者にはアダム・スミス、バイロン卿といった歴史的人物の他、「進化論」のダーウィン父子とも浅からぬ関係があったとか。有名な「ドリトル先生」のモデルも彼であり、古典「ジーキル博士とハイド氏」の家のモデルは彼の自宅であったとのこと。さらに、あの手塚治虫氏の名作「ブラック・ジャック」も実はジョン・ハンターがモデルだったのでは? という説もあるとか。なるほど、納得できます!
外科技術だけでなく、歯科・病理学・動物学・解剖学など諸々の学問の基礎固めの他、人間の進化までを究めようとしていたという、その情熱に読んでいて胸が熱くなりました。
好きこそ物の上手なれ。
思わずこの言葉が思い浮かびましたね。
残念なのは、ジョン・ハンターの思想と学問は18世紀の世界では先端を行きすぎて当時の社会から理解を得られなかったということ。外科医療を科学の地位まで引き上げた彼の偉業がもっと評価されてもいいんじゃないかなと、この作品を読んで歯噛みする思いを禁じ得ませんでした。
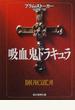
吸血鬼ドラキュラ
2011/06/02 10:38
人間の英知と勇気に勝るものはない
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ヤバイです。面白すぎます! メディアミックスされた、あらゆるドラキュラモノの元祖ともいうべき作品! あまりの面白さに驚いてしまいました。
自分的に大絶賛。極上のゴシックホラー小説だと思います。
一人のイギリス人弁理士・ジョナサンが仕事のため、辺境のトランシルヴァニアに単身乗り込んでゆく冒頭からもうなにやら怪しげな雰囲気が漂い始めます。闇の中疾走する馬車・狼の群れ・奇怪な御者……そしてついに目指すドラキュラ城で待ち受ける、彼の想像を絶する恐ろしい運命!
初っ端からグイグイと惹きこまれて一気読み。別の本を読もうと思っていたのですが、結末が知りたくて、とうとう我慢できずに読了してしまったという……。
展開はすべて書簡・日記形式という、これもまた凝った構成で唸りました。600ページ弱の厚さなのに、まったく飽きずに読み切ってしまったし。まったく関係のなかった重要人物たちが、手繰り寄せられるように繋がってゆき、ラスト吸血鬼狩りのメンバーへと収斂されてゆくストーリーにハラハラドキドキ! 巧すぎてもう、何も申しません!
最大のダークヒーロー・ドラキュラ伯爵も、吸血鬼のお手本のようなキャラクターです。ま、これがオリジナルなので当たり前ですが。ニンニクや十字架、コウモリ、狼といった重要アイテムも登場して、ドラキュラ伯のブラックでダークな魅力も充分に味わえます。
対する正義のヒーローは、ヴァン・ヘルシング教授! 老齢にもかかわらず、博識で高名、正義感強し! その彼の仲間となってドラキュラ伯爵を狩るのは4人の男性と1人の女性。この、唯一のヒロイン・ミナが今作のキーパーソンとなって、控えめながらも、ヘルシング教授と同等に活躍します。
その彼女がドラキュラ伯爵に血を吸われ、自ら吸血鬼になってしまうという恐怖を抱えながらも、仲間とともに必死にドラキュラ伯爵を追跡するシーンが緊迫感ハンパないです。
狡猾なドラキュラ伯爵VSヘルシング教授という構図は、そのまま、怪物VS人間の英知と勇気に置き換えられます。おそるべき吸血鬼・ドラキュラ伯爵に対して、人間であるヘルシング教授達は、一体どのようにして闘ってゆくのか。そのスリリングな展開にもはや目は釘付け!
幾度となく窮地に陥り、気弱になった仲間を励ます、信心深いヘルシング教授から語られる、数々の言葉がグッと胸に迫ります。ホラー小説であるけれど、人間の友情と信頼、団結と絆の大切さを謳いあげている名作かと。
不死者の物語であるのと対照的に、ラスト、新たな生命の誕生で締めくくるあたり、作者の巧さを痛感しました。思わずアツくなってしまいましたが、個人的にはものすごい名作だと思いました!

ある小さなスズメの記録 人を慰め、愛し、叱った、誇り高きクラレンスの生涯
2011/05/18 00:13
揺るぎない絆
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
まず、装丁からしてとても凝っています。なんといっても今時珍しいケース付き。しっかりとした作りのハードカバーで、表紙をめくるとトレーシングペーパーのような遊び紙がなんとも高級感醸し出しています。これだけでもう作品世界に引き込まれてしまいました。
内容はとても淡々としてます。まるで鳥類観察日記のよう。「序」にもありますが、作者の語り口は意識的に装飾をそぎ落とし、ありのままの事実のみを伝えるように心を砕いています。決して創作でもなく、誇張でもない。作者とスズメの間に起きたあらゆる出来事と揺るぎない絆が、感情を抑えた文体で書かれているのでとても読みやすかったです。
第二次大戦中のロンドン。作者は自宅前で障碍を持った瀕死のスズメの雛を拾う。それが、今作の主人公・クラレンスと名付けられるスズメなのですが。
その後は、クラレンスの成長を丁寧に追って記述が展開。右翼と左足が不自由な彼の世界の全ては飼い主である作者と、その自宅。ある意味閉ざされた2人だけの小宇宙で、クラレンスは作者の愛情を一身に受けて、のびのびと成長してゆく姿が微笑ましい。
互いに互いの存在を意識しだし、大切な存在となってゆく。作者としてみれば、完全な庇護者という感情なのだが、クラレンスにしてみたら彼女の存在って一体?
最初はきっと母親の如き存在であったはず。けれど第四章にあるとおり、彼が成長してゆくに従って、作者が母親から恋人へと意識が変化したことにちょっとビックリ。でもなんだかとっても人間らしくて途中からスズメとは思えなくなってしまいました。愛情を欲するのは人間ばかりではないのだなあと、今さらながら感慨深い。
このクラレンスは感情面でも特化していますが、才能という面でも並みのスズメ以上。作者が教えた芸を覚え、戦時下にあえぐ人々にそれを披露してその心を癒したり、音楽に対する豊かな才能で歌を歌うことを覚えたりと、その秘めたる力はとどまるところを知らず。
けれどそんな絶頂期を迎えた後は、やはり人間と同様にクラレンスにも「老い」の影が忍び寄ってきます。
この、彼が必死に「老い」と闘い、なんとか適応しようと奮闘する姿がまた健気で愛おしい。そして、それを懸命にサポートする作者の姿もまた心打ちます。かけがえのないパートナーに忍び寄る「死」による自身の心の空白に怯えながら、必死にこの作品を書きつづった作者の心情を思うと、読んでいて辛かった。
ちっぽけな存在であるはずのスズメのクラレンス。けれど、その存在感は圧巻。その彼の一生を克明に記述し1冊の本に完成させた作者の深い愛情に深く感銘。
「お涙頂戴」ではない、真摯な生命への賛歌と読みました。名作です。

神保町公式ガイド 神田古書店連盟がつくった公式本 世界一の本の街 Vol.1(2010年秋)
2010/11/07 22:21
本の街神保町はコレ1冊でOK!
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
先入観を捨てよ、書店へ入ろう! という何処かで聞いたことのあるキャッチコピーの下、公式ナビ本として充実の内容。
まず表紙からして凝りすぎです。あの有名なビートルズのアルバムジャケットを連想します。
モデルの4人は正真正銘古書店員サン達。とても素人サンとは思えません。驚きながらページをめくると、巻頭のカラーページにさらに驚かされます。
「若手古書店員三人と、古本と恋をめぐる一週間 妄想版&リアル版」というかなりインパクトある特集タイトル。
まずは「妄想版」から。
若手(イケメン?)古書店員3人が、タレント(多分)の沖樹莉亜を囲んでポーズをキメるキメまくる~!! 巧いです、ホント。ロケ地はもちろん神保町、そしてしっかり古書や個性派スポットの紹介になっていたりして。初っ端からやられた~!! もっと見たい~!! と引き込まれる!!
次に「リアル版」。
古書店員サンてとってもヒマそう(失礼!)と思っていた認識を改めます。目録を作成したり、買い取りに走ったり、市場(!)に赴いたり、くずし字の勉強会(!!)もあったりとなかなか激務と知りました。
そして次の特集は「古本屋の女房」。ご紹介されている方々はナント台湾人の方だったり、手彩色写真を手掛けている方だったりと、意外な経歴と美女ぶりに驚きます。
待望のメイン特集は店員達が自ら書いた古書店案内。
文学・古典籍・歴史・思想、宗教・外国書・社会科学・自然科学・美術、版画・趣味、芸術・サブカルチャー・古書全般の11のジャンルに分類して、古書店員サンたち渾身の紹介が圧巻! その店員サンおススメのグルメのお店も教えてくれたりして、ちょっとオトク情報も。コレ1冊あれば古書店街で迷わない? 神保町めぐりの必携の1冊?
書籍関連の記事ばかりでなく、ランチやカフェ・スイーツの店舗情報も満載! グルメの街神保町としての一面も余すところなく紹介してくれるし。
ところどころに顔を出す? マメ知識満載の「神保町かわら版NEWS」も読んでいて楽しい。
神保町を完全網羅し、とても楽しく遊びゴコロ溢れたムック本。
神田古書店連盟の方々の神保町に対する「愛」を強烈に感じる1冊でした。
BIBLIO HOLICより

あさのあつこのマンガ大好き!
2011/09/04 20:30
最強マンガ論
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
Vol.1 家族とマンガとわたし
Vol.2 少年マンガと少女マンガ、それぞれに思うこと
Vol.3 小説家から見たマンガ
Vol.4 わたしを虜にした二人のマンガ家
Vol.5 勝手にキャラクター論
Vol.6 最終回に望むこと
Vol.7 戦後のマンガブームの背景と海外における「MANGA」
あつコメ!付き マンガ紹介(36作品)
年表 ─あさのあつことマンガの歴史─
目次を見ても俄然興味そそられる内容です。なんと出版社が「東京書籍」。確か教科書とか出版している会社だよね? さすがです、あさのセンセ。
で、意外や意外、初の自伝的エッセイということで。もっと以前に出されているのかと思ってました。しかしフタを開けてみると自伝的要素は2割くらい? あとの8割はほとんどマンガのハナシです。ものすごいです。
マンガオタクを自称されているだけあって、その読了数はハンパない!マンガの創世記(ちとオーバーか)に関わる作品から現在に至る話題作まで殆ど網羅されていて頭下がります。その作品数の多さもものスゴイですが、さらにその解説も詳細で丁寧で、はっきり言って語り尽くしちゃってます!そのアツすぎる語りに、こっちものめり込むのめり込む!
特に興味惹いたのが、 Vol.4 わたしを虜にした二人のマンガ家 ですね。あさのセンセ、手塚治虫と吉田秋生を挙げてます。どちらも納得の偉大なマンガ家サン。特に吉田秋生を大絶賛されていて、「河よりも長くゆるやかに」が大のお気に入りとのこと。主要3キャラのあの、アホさ加減がなんともツボらしく、その感想もまた愉快すぎる!!
「BANANA FISH」もお気に入りのようで…コレはやっぱりなー感がアリアリでした~! 自分的にNO.6のネズミは多少なりとも絶対アッシュの影響受けてるな!! と思っていたので。自分も読了済みの作品なのでものすごく楽しく読めたし。
Vol.6 最終回に望むこと も爆笑モノ!
なぜあのキャラクターがあんな死に方をしたのか!!! と憤慨気味且つマジメで語る様もなんだか愉快。
「タイガーマスク」を例に挙げて、主人公があっけなく交通事故で死んでしまうことに不満タラタラで、「ダンプカーくらい、投げ飛ばしてほしかった」 との弁には超絶笑った!
もちろんここでも「BANANA FISH」のアッシュの死ネタについて言及されてます。お気に入りキャラだったんですね。
Vol.7 戦後のマンガブームの背景と海外における「MANGA はちょっと本格的なマンガ論というか、あさのセンセによる日本のマンガの歴史と鋭い考察が読めて貴重。
あつコメ!付き マンガ紹介 はお気に入りの36作品にひと言コメントをつけて愉快に紹介! 「あつコメ」がおちゃめで正直笑えます!!
ラストの年表も遊び心いっぱいでとてもよろし。
カバーイラストもデザインもとってもホンワカして素敵です。そしてなにより冒頭の言葉がとても印象的。
日本にはマンガがある。何も恐れることはない。そんな心境です。
まさしく名言。恐れ入りました。

小説を書く猫
2011/07/07 00:00
素の個性を垣間見ることのできる貴重なエッセイ。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
エッセイ集とはいえ、かなり読み応えありました。ほとんどがかなり昔、商業誌に発表された作品ばかりなので、あれ? なんか読んだことあるぞ? と思ったりもしましたが。最新2作も収録されていてファンとしては嬉しい限り!
「白い薔薇の淵まで」で山本周五郎賞を受賞したあたりのエッセイが中心となっているのかな? 初めてメジャーで高名な賞を受けた作者サンの喜びが素直に伝わってきて読んでいてとても嬉しくなりました。わりと淡々と書き綴りながらも、さりげにぽろっとユーモアを垣間見せるあたり巧いし、好きだなあ。
この方の作品って、作中ヒロインにかなり自分を投影しているモノが多いのですが、その理由も今作でわかりました。同性愛者で有名な作者サン。報われない自身の現実の恋愛の苦しさを作品の中で吐露し、昇華させることで精神の均衡を保っていたとのこと。なるほど。作品ほとんどにご自身を連想させるヒロインが多いので正直食傷気味になることもあったのですが、その理由がわかるとなんとも切なくなりますね。読み方・捉え方が変わります。
自らの恋愛遍歴とかつての恋人との出逢いと別れを赤裸々に描いているのも、好感度高いです。今はお独りのようですが、寂しくとも独りであることの気楽さ・身軽さを楽しんでいるとのこと。
最新エッセイの、横浜から京都に引っ越されたエピソードなどはなかなか面白い。京都という見知らぬ土地に住むための物件探しの苦労譚、とある事情で個人情報が漏れてしまったことに対する赤裸々な怒り……などなど、作家としてではない、中山可穂という個性的すぎるけれど魅力的なひとりの女性の姿を知ることが出来て、ファンには垂涎の1冊なのではないでしょうか。
遅筆で長編が書けずに苦労されているようですが、ぽろりと弱音を吐きだしてしまうのも人間味感じられていいなあと。
相当な猫好きサンらしく表紙もレトロムードでとっても良いです。猫チャンがカワユイ。
この作者サン独特の濃密な作品も良いけれど、このようなサラリとした飾り気の無いエッセイもまたオツなもの。充分堪能させていただきました。

ジェニィ 改版
2011/06/20 17:42
猫好きでもそうでなくてもたまらない1冊
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ギャリコ作品って好きだなあ。ファンタジックでありながら、鋭い諷刺・洞察を作品に投影していたりして。寓話的な作風がなんとも良い味だしているかと。
で、この作品。もう~、泣きました。感涙の嵐でした。自分的に面白い作品・そうでない作品の見分け方がつい最近わかったんですが、それは読んでいる最中に居眠りしないこと。面白い作品はうとうとしているヒマなんか無い! グイグイと作品世界に惹きこまれていってしまうッ! ということですね。
なので、この作品も居眠りどころじゃありませんでした。一気に読んじゃいました!
まず主人公のピーター少年が交通事故で意識不明の重体に。そして気がつくとその身体は純白の毛に覆われた猫に変わっていた!!
ここからが猫化したピーター少年の辛く過酷な冒険の始まり。人間からは邪険に扱われ、路頭に迷い、ボス猫からは瀕死の暴力を受ける──ある意味猫社会の洗礼をいきなり受けてしまった訳ですが……そんな彼を助けるのは、心優しい雌猫ジェニィ。
このジェニィのキャラ造形がもうもう、サイコーです!! かつて人間に捨てられたことがトラウマとなって、決して人間に心許さない。強靭な心と体力を持った素敵な彼女が、人間の心を宿したままのピーターに猫社会で生き抜く術を伝授し、そして始まる新たな冒険。
その冒険譚もものすごく読ませます。ジェニィのルーツであるグラスゴウへ行くため、船に密航する件が楽しい!
ここでもピーターはジェニィからネズミの捕獲の仕方を教わったり、人間とココロを通わせたり……そして何と言っても白眉のシーンが、海に落ちたジェニィをピーターがなりふり構わずとび込んで救出するトコロ!! その姿に感動した船員たちがたった2匹の猫のために救出ボートを差し向ける……というココロ温まるエピソードがね~、もう読んでいて泣きそうでした。
その出来事がきっかけとなって人間に対して信頼を回復し、自分を助けてくれたピーターに対して愛情を寄せてゆくジェニィ。対するピーターもジェニィという愛すべき・守るべき存在を得たことによって心身ともにめざましく成長してゆく様が読んでいてものすごく心地良い。
お互いがお互いにとって唯一無二のかけがえの無い存在となって絆を深めていくあたり、ああ~、こんな純粋な関係っていいなー! とココロの中で叫んでました。
が、あくまでもこの作品はファンタジーです。まったくの個人的見解ですが、作者がもっとも痛烈に作品に込めたメッセージはラストの章「大団円」にあるのではないかと。
それまでのファンタジー色は一気に払しょくされ、ピーターはお約束通り人間の姿へと戻ってしまいます。
彼の大切な存在であったジェニィは、そのまま普段あまり接点の無かった彼の母親への愛情と限りない思慕の情が具現化された姿だったのだと思い知らされると共に、人間に対する愛玩動物への接し方の痛烈な批判・皮肉も込められており、少年ピーターの見事な成長譚として極上のラストだと思った。唸った&泣いた&感動的結末でした。
あああ……久しぶりにアツくなってしまいました。脈絡ない箇所がありましたら謹んでお詫び申し上げます。
猫好きな作者サン・猫好きサンを狙って書かれた本書とのこと。自分は特に猫好きでも(愛玩)動物好きでもないのですが、この作品を読んで生きとし生けるものに捧げる無上の愛情の素晴らしさ、逆に彼等から享受する計り知れない癒しや慰めを羨ましく思ってしまいましたね!で、この作品、もっと子供向けバージョンがあっても良いと思う。オトナだけが楽しむのはもったいないゾ!

村田エフェンディ滞土録
2011/04/18 14:48
まるでラヴェルのボレロのよう
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
奇妙なタイトルからして興味を惹かれ、そして読了後すぐにラヴェルのボレロという曲を連想しました。 あの淡々と同じフレーズが繰り返されて、クライマックスに向けて盛り上がり劇的なラストで終わる、あの有名な曲。
まさにそんな感じのストーリーでした。初っ端から言い切りますが、名作です。
時代的には第一次世界大戦前。トルコ文化研究のために招聘された日本の学者・村田が主人公。舞台はエキゾチックなスタンブール(イスタンブール)。
その村田が下宿している屋敷の女主人はイギリス人。そして下宿人は彼の他、ドイツ人・オットー、ギリシア人・ディミィトリス。そして下働きのムハンマドと、その彼が拾ってきた鸚鵡の、国際色豊かな面々と一羽との静かで大切な心の交流。
最初はまるで実在の人物のトルコ滞在記かと見まごうばかりの、淡々とした村田の語り口で綴られていきます。スタンブールの風俗・風習、古代遺跡発掘の様子、村田と下宿人との交流……などなど、街や人々の的確で詳細な描写。情景が目に浮かぶようなリアルさに驚きも。
クライマックスには妖しげな女性霊媒師・美しい女革命家が登場し、そして今まで同じ下宿人と思っていたディミィトリスも密かに来るべきトルコ革命に一役買っていたという事実の判明。さらに、村田本人の日本への帰国……と、怒涛の急展開。戒律厳しいトルコ女性が実は急進的な革命分子であったり、世界は第一次大戦に突入していったり、そして戦後、トルコ革命の成功などなど。それまでのゆったりと流れるような日常から、真逆の事態の急変に目が離せず。
そしていよいよラスト、スタンブールでの下宿先の女主人から送られた村田宛の手紙が心打ちます。
共に生活し、青春時代の一時を分かち合った、それぞれ国籍の違うオットー・ディミィトリス・ムハンマド。その彼等は無残にも戦争の犠牲となってしまい、皆を偲ぶその手紙が涙を誘う劇的な内容。
何故作者は登場人物の国籍をこう設定したのか。ラストまで読んでやっとその理由がわかります。最初から張り巡らされた巧妙な伏線。秀逸なのは、なんといっても鸚鵡でしょう。 最後に村田に届けられたその鸚鵡こそ、村田の青春時代の証であり、亡き友たちの魂の化身でもあるのだなと。
「およそ人間に関わることで、私に無縁なことは一つもない」
特に印象的な作中のディミィトリスの言葉なんですが、これが今作のテーマでもあるのかなと。そして、村田の平坦な語り口の裏に隠された反戦への想いも併せて感じ取ったのですが。
エフェンディとは、おもに学問を修めた人物に対する一種の敬称とのこと。その村田の大切な青春時代とかけがえのない友情へのノスタルジーを描いた秀作。
読了後、静かな感動でしばし呆然としてしまいました。もちろん、涙腺が崩壊したことは言うまでもないです。
BIBLIO HOLICより

西の魔女が死んだ
2011/03/07 15:08
名作は色褪せず
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ずばりテーマは「生きる力」と「人の死」でしょうか。おもわず宮崎駿の世界を連想してしまいました。
学校生活での目に見えない確執に精神的に疲れてしまったまいの、再生の物語なんですが……。なんといっても「西の魔女」こと、まいのおばあちゃんの存在感が圧巻でした。清貧で高潔で優しくて、理想のおばあちゃん像を体現したような人物造形。素晴らしい。
そして、実の母親から「扱いにくい子」と言われるまいも、流されやすいけれど、芯のしっかりとした少女で個性的。
話の展開としては、この2人の淡々とした日常が綴られるのみなのだけれど、どうしてだか目が離せない。グイグイと作品世界に惹きこまれてしまって一気読み。
外国の田舎を思わせる「西の魔女」の日常生活。そこにはおよそ「現代」を感じさせない。
生みたて卵や手作り苺ジャム。洗濯機ではなく「たらい」で洗うシーツなど。時間から置き去りにされたような世界で繰り広げられるまいとおばあちゃんのつつましい生活こそが、まいの疲れた心を癒す最良の治療法。
「この世には、悪魔がうようよしています」
おばあちゃんのいう「悪魔」とは、誘惑であったり、イジメであったり、怠惰であったり、まいがおのずと経験してきたさまざまな負の体験。そんな彼女に、「魔女修行」と称して、現代社会を強く生きていく方法を伝授する、おばあちゃんの数々の言葉と教えがとても印象的。
精神的に傷ついた孫とそれを癒す祖父母。という設定の物語は多々あります。が、なによりこの話が印象的なのは、「生きる」ということと共に「死」も描写しているからなのではないかなと。
ラスト、「西の魔女」が死出の旅立ちの際に、「東の魔女」こと、まいに残したメッセージが強烈です。最高に泣けました。これで、まいは最愛のおばあちゃんの「死」を力強く乗り越えて行けると勝手に思い込んでしまうほど、激しく感情移入。
作品の分類としてはYA(ヤングアダルト=青少年向き)なのですが、思った以上に硬質で一般向きの感じがしました。タイトルもインパクト強くて、とても良いと思います。
発表されてから10年経ちますが、名作は色褪せず。古さをまったく感じさせません。
BIBLIO HOLICより

わたしがちいさかったときに 原爆の子 他より
2011/08/16 10:56
体験を書いてくれてありがとう。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
まるで悲しい小説を読んでいるような気になりました。
あまりにも悲惨な子供たちの原爆体験記。どうしても過去現実に起こった事実として捉えることができず、どこか絵空事であって欲しいと思うほど。
原爆体験をして6年後に書いた作文ということですが、やはり思い出したくない、書きたくないと訴えている子供たちが多いです。それでも小学4年生から高校3年生までのそれぞれの年代の子供たちが書きつづった数多の文章は悲しくて重くて果てしなく貴い。
学年が下の子は感情の描写がまだ未熟だけれど、考えつく限りの拙い言葉を並べた中で訴える肉親の死に対する悲しみが痛烈に伝わってきて余韻が残る。
一番年上の高校3年生の文章は素晴らしく本当に優れた短篇のよう。母と兄弟を失った悲しみを乗り越え心静かに偲び、書きつづる文章が読んでいて辛かった。
また同時に、当時の子供たちのなんと作文の巧いことか。同年代の現代の子供の比ではない。
いわさきちひろの哀愁に満ちた子供たちの画がより一層悲しみと、子供の中の芯の強さを巧みに描写していて白眉。
印象に残った文をいくつか引用させていただきます。
「妹は目がつぶれているために、大きい人にもばかにされるのだ。だが、ぼくは、いまに見ておれというかおをしている。
~原爆で目がつぶれた妹を思う兄の心情~ 小五男子」
「親しくしていた先生やお友だちと死別したことを、悲しいとは思いますけれど、また一方ではうらやましいと思っています。私もあの時、下敷きになったまま死んでいた方がよかったような気がします。
~原爆による傷痕でいじめに遭った少女の作文~ 高2女子」
絶望にくれながらも健気な子供たちの決意と心情の吐露に思わず涙。

君のそばで会おう
2011/03/20 11:41
懐かしいあの頃
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
テーマは「失恋や別れ」……だと思う。どちらかというと、同系列の作品「わかりやすい恋」と似たテイストかも。
少年少女達の恋の終焉、あるいはその予感を瑞々しく、爽やかに、そして残酷に詠っているのがもう素晴らしい。
幸せの絶頂にいながら、いつかは訪れる恋の終わりに怯えたり、相手の心が既に自分から離れているのを知りながら確かめることが出来なかったり、未だ好きなのに別れた相手のことを忘れられずに想い続けていたり……と、さまざまなシチュエーションにおける恋に想い悩む若者の心情描写と、ノスタルジックな写真の数々とのコラボが秀逸。
もういい年した自分でも胸キュンになる詩ばかり。
詩も切なく、瑞々しく文句無く素晴らしいですが、写真もそれ以上にステキです。見開き・航空写真を多用したスケール大きい写真の数々に思わず見とれてしまいます。
青春のあの時を今一度! 恋に想い悩んだあの気持ちを今再び!
……と、大人になってから読み返すのも、また一興。
哀愁帯びた優しい言葉の数々と素晴らしい写真で、ひととき別世界へ、懐かしい「あの頃」へと心がトリップしてしまうこと請け合いです。
BIBLIO HOLICより

一瞬と永遠と
2011/06/28 12:12
萩尾望都の意外な一面
16人中、16人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
萩尾望都の新作エッセイ。1987年から2010年までの間にさまざまなメディアで発表されたエッセイ・解説を1冊にまとめたモノ。巻末の初出一覧を見てもかなりな量です。
おおまかには4章構成。その内容は以下の通り。
1 いわゆるホントのエッセイ。
少女時代に感じたこと、懐かしの恩師のエピソード、「青」という色に関してのイメージ、興福寺の阿修羅像を巡ってのあれこれ。などなど、萩尾望都が素直に感じたこと、素顔の一面を垣間見ることができます。中でも、「私は生き物。同じ生き物」が印象的。アフリカ滞在時の解放感を、世間から逃れて、のびのびと自己の解放と絡めて描写しているところが良いなあと。
2 文学について(小説について)
萩尾望都といえばSF!! 特にブラッドベリとの出会いの感動とショックを素直に熱く語っています。
「 誰しものことだとは思うが本とのめぐり会いというものは実に不思議なものだと思う。ちょうど何かが読みたい時に心や魂を震撼させる生涯の本に出会う幸福」 p48より
という一文に激しく共感してしまいました!
他に松井今朝子・森博嗣・寺山修司・矢口敦子等の作家との交流や作品についても言及。あたりまえですが、かなりな読書家というイメージです。
3 お気に入りのマンガについて
今度は主にマンガ作品やマンガ家について述べられてます。過去に衝撃を受けたマンガ家さんとして、和田慎二(超少女明日香シリーズ)・聖悠紀(超人ロック)・石森章太郎(サイボーグ009)などの男性マンガ家を挙げてまして……うん、かなり面白かった。特に和田慎二について作品テーマがフェミニン(女性的)であると評しているところがなるほどなと。
その他多大なる影響を受けたであろう手塚治の作品を紹介。今夏アニメ映画化されるブッダについての言及はさすが。(エッセイ初出は1993年)。
4 その他もろもろ、メディア文化について
萩尾望都のアンテナに引っかかったいろいろなモノが網羅されています。
例えばゴジラ・映画「ディア・ハンター」・夢の遊眠社の舞台・ノルウェイの森・ニジンスキー(バレエダンサー)等々。映画にかなり造詣が深いらしく、エッセイを読んでいるだけでも楽しい。自分の萩尾望都に対する勝手な印象は感情派、情緒派、感覚派というイメージだったけれど、なんと実は冷静な分析派・理論派なのだということを知りちょっと意外な一面も。とある映画のワンシーンをその分析魂をもってして、なんとか説明しようとする件が面白すぎます!
自分にとって萩尾望都は謎めいたマンガ家サンといった印象だったんですが、この本を読んでそれがガラッと変わりました。
文章も的確でわかりやすい。冷めた……というか、冷静な視点で淡々と文を綴っていらっしゃるのがちょっと意外でしたね。ところどころにユーモア散りばめてそれもナイス!!
私生活での、両親との不和と葛藤もネタにしてしまう……という裏?エピソードもあったりして。
萩尾望都という稀代のマンガ家の一面を知るには充分な1冊でした。個人的に大満足!

女子校育ち
2011/08/04 15:02
抱腹絶倒の女子校ルポ
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
女子校──なんて甘美で妖しげな響きなのでしょう……と、知らない方はそう思うに違いない。しかしリアル女子校はもっと雑多でタフで大雑把なのだ。
実は自分も女子校出身です。中・高・大(4年もいたし……さすがにイヤになった)と足かけ10年も女子校でお世話になった自称筋金入りです。なのでこの著作を一目見て即購入。女子校出身者はもちろん、そうでない方もネタとして充分楽しめます。爆笑できます!
第1部 女子校ワールドへようこそ!
1 女子校タイプ別図鑑
2 女子校イニシエーション
3 女子校をめぐる男たち
第2部 「女子校育ち」その後
1 女子校っぽさって何?
2 女子校育ちの男選び
3 「女子校育ち」のその後
女子校タイプ別図鑑 → 爆笑の3タイプ7分類☆
【勉強系】 ◎性超越 ◎努力型秀才
【ニュートラル系】 ◎モテ系 ◎良妻賢母 ◎温室・夢見がち乙女
【お嬢様系】 ◎お嬢様 ◎深窓お嬢様
という、著者独自の分類方法が施されていて笑えます。性超越とか、温室・夢見がち乙女とか……一体……(汗)。
ちゃんと著作では学校名も明記されているのですが、ここでは面倒なので省略させていただきます。
中でも特に愉快だったのがこちらの3点。
「女子校の儀式論」→クリスマス時の礼拝や伝統のダンス、文化祭などなどの各種セレモニーについて。バカバカしくも何故か伝統としい生き残っている儀式。
「女子校の制服論」→人気制服ランキング! ブレザータイプが主流で、憧れの制服も実はクリーニングをあまりしないとか、ダサい制服を着用していると皆あきらめモードで謙虚で貞淑な性格になる(!!)とか、ウソかホントか判別しかねる論述も展開されたりして。
「女子校の掃除論」→進学系女子校は掃除よりも勉強ということで、将来的に「片づけられない症候群」になる可能性が高いらしい。
逆にかなり掃除に力を入れている「掃除御三家」はハンパなくものすごい。あえて校名は挙げませんが、親の敵のようにトイレ掃除に力を入れている学校もあるそうで。そういう学校の卒業生はある意味トラウマに近い状態に陥って、完璧に掃除をこなしてしまうとか。
もう全編爆笑モノの女子校レポです。
その他男子校の学祭における女子校生の実態とか……自分的に、逆に男子校の学祭のあまりの過激ぶり(男子生徒2人による半裸ま○板ショーとか!!)の方が恐ろしかった。
さらにお約束!! の女子校における秘密のプラトニックラブとかも、なかなか客観的に分析していて面白い。
女子校にとっても興味ある方、もしくはこれからムスメさんを女子校にお受験させたい方には最適の書籍かと。
ただ、取材時期が長期に渡っているので、現時点とは若干ズレがあるかもですね。女子校出身者として、リアリティ充分で納得・愉快すぎる1冊でした。

おじさん図鑑
2012/05/02 01:07
愛すべきおじさんたち
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
お、おじさんがいっぱい! 表紙に思わず一目ボレしてしまいました!
さらに……なんかスゴイよ……自分的に帯の惹句にイチコロ……。
「すべての若者に捧ぐ。 おじさんになる前に、おじさんを知るべきだ」
とか。いやー、自分は女子なので一生涯かけてもおじさんにはなれないんだけどね。ついついこの惹句につられて……。さらにカバーの帯の 本書の使い方 とかも……。
「おじさんの仕草や言葉には、長年社会を歩いてきた人生が詰まっています。それはくだらなかったり、おもしろかったり、為になったり…と千差万別。
その隠れた素晴らしさ、若者にはまだ備わっていない味わいを伝えるべく、取材し、観察して図鑑としてまとめました。今まで気にしていなかった「おじさん」を楽しむガイド。これからの人生を歩むヒントが見つかるかも知れません」
とか。「おじさん」。この本に登場する数多の「おじさん」たちを写真に収め、分類して、イラストにし愉快なコメントを添える──というその発想に脱帽です。分類された「おじさん」カテゴリーはざっと数えただけでも50~60種。
「普通のスーツのおじさん」「偉いおじさん」「たそがれるおじさん」「仙人おじさん」……とか。うそでしょ? って思うかもしれないけれど、ホントにカテゴリーどおりの「おじさん」たちばっかりなんです……いるいる~こんなおじさん!! って思わず叫びそうになるくらいあてはまりすぎててビックリした。
著者のなかむらるみサンが足掛け4年をかけて取材した「おじさん」達はもうもう圧巻です。その洞察力と地道な努力と好奇心&行動力は称賛に値すると思う。なんたって ~ドヤ街で炊き出し体験~ とかしちゃうし。とてもとても恐ろしげな世界かと思いきや、実はドヤ街で暮らす「おじさん」たちは超個性的で優しくて面白い。一度ボランティアで参加したらけっこうハマってしまう人もいるのだとか。著者サンもまぎれもなくその一人となったようで。
もうもう自分がどんなに書いてもこの本の面白さ素晴らしさは伝えられない~! 興味持った方はぜひ読んでほしい~。超絶面白すぎるから! 自分は電車内で読んでて笑い堪えるのが正直つらかったし。
著者サンの、「おじさん」に対する優しいまなざしとほっこりする愛情をじんわりと感じられる書籍。自分の勤務図書館も来館者は「おじさん」が多いのだけど、分類を参照するなら「うるさそうなおじさん」が圧倒的だなと。
「近づくと怒られそうとか、にらまれそうとか、文句を言われそうとか悪い結果が予想されるので近寄りたくないおじさん」
ってまさにドンピシャだもんね。←コラコラ!鋭くて的確! 大変楽しませていただきました。大満足。脱力系のおじさんイラストがツボです。

