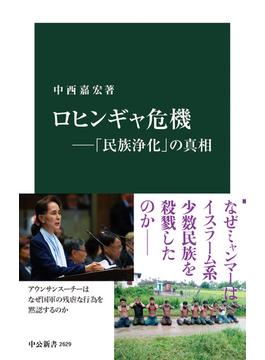1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:飛行白秋男 - この投稿者のレビュー一覧を見る
近時話題のロヒンギャについて知るために購入。
ちょうど軍事政権によるクーデターが起きる。
人種問題などが絡まり、複雑な歴史をたどるミャンマー。
巻末の関連年表は2020年11月まで掲載されていますが、
今、まさに続きが記入されている状況です。
平和に解決されることを望みます。
アジア最大の人道的問題の全貌をミャンマーを巡る国内・国際政治から読み解いた画期的な一冊です!
2021/03/01 15:43
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、ジョンズ・ホプキンス大学高等国際研究大学院・客員研究員、ヤンゴン大学国際関係学科・客員教授などを歴任され、現在、京都大学東南アジア地域研究研究所・准教授の中西嘉宏氏による作品です。2017年8月25日、武装グループがミャンマー、ラカイン州の警察・軍関連施設を襲撃しました。これに対し国軍は、ロヒンギャ集落で大規模な掃討作戦を実施し、人々は暴力を逃れるため、隣国バングラデシュへと避難し、半年という短期間に難民は70万人にのぼりました。この事件から三年が経過したが、帰還は進んでいません。同書は、アジア最大の人道問題の全貌を歴史的背景やミャンマーをめぐる国内・国際政治から読み解いた一冊です。
複数民族における争い
2022/10/21 19:07
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nobita - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本国内にいるとアウンサンスーチー氏が最善と思われていたが、実際は複数民族の争いがあり、被抑圧者の彼女も抑圧者でもある。日本も士農工商の下にエタ非人層を作っていた。他国のことは笑えない。この本は現地にいた人が見た真実であろう。このような真実を知り、世論を動かしていくことしか我々はできない。アジアの悲劇をなくしていくことが、日本政府の役割である。
複雑に絡み合う、宗教問題
2022/01/19 21:47
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
副題が「民族浄化」の真相、民族浄化って、ことばの響きが怖い。ミャンマー政府はロヒンギャはバングラデッシュから不法に入国した人々だといい、バングラデシュ政府はミャンマー国民だと主張する、そのうえに国民の9割以上が仏教徒のミャンマーにおいて、彼らはムスリム、複雑に絡み合う難問、スー・チーという平和の象徴を掲げていたミャンマーの影の部分が明らかになる書物だ
ベンガル人とスーチー
2021/07/02 17:16
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
民主主義の原則である多数決主義が中立性を欠き、少数民族排除を引き起こした結果、バングラデシュに隣接する無国籍ムスリムがミャンマーの被差別民族として難民化したことの事実解明と責任追及がどこまで進むのか。これからも注視していなければならないトピックス。
投稿元:
レビューを見る
ミャンマーの軍事政権が倒れてたとき、民主化されてよかったとか単純に考えていたけど、その後のロヒンギャ問題とか今回の、クーデターとかみるにつけそんな単純な話ではないとわかる
歴史的な経緯含めて理解しないとだめだと改めてわからせてくれる本であった
多民族国家であること、植民地時代や日本の影響などよくまとまっていた
多数決の論理こそが多数派の少数の排斥として働き、多くの民主化が頓挫している
それだけにp228にあるような画一的なジェノサイドとして一方的に糾弾する欧米の姿勢だけではかえって追い詰めてクーデターを誘発するのだろ思う
民主化して、経済的に発展してもそれだけでは安定した社会は実現できない
スーチーという世界的なアイコンをもってしても簡単には社会は変わらない
さらにいえば国家というのは統一への挑戦となれば、経済的な恩恵をあきらめて、世界を敵に回しても譲らないことがままあるとわかる
投稿元:
レビューを見る
大変難しい問題だ。
ロヒンギャとはミャンマーのバングラデシュ側にいる少数のムスリム。
宗教、歴史、国籍等多くのファクターが絡み合って、問題を複雑化している。
最後に日本の出来ることとして5つあげているが、たしかにやるべきだと思うがその反面他国に日本1国がそこまで立ち入る権利があるのかと悩む。国際機関が規律を曲げて介入するのが一番だと思うが、その際、差別は差別を生み、暴力は暴力を引き起こすことは教訓として覚えておいてほしい。
投稿元:
レビューを見る
ロヒンギャが抱える問題について、根本底なところから解説をしている。
単に難民を容認すればいいということではなく、もともと持っている偏見や、民族間での問題もあり、
根本的な解決が非常に難しいということではないことがわかった。
ミャンマーの滞在中も、ロヒンギャに対する不満は現地の方から聞いていたので、今回改めて本を読むことで民意という視点からスーチーさんがなかなかロヒンギャ問題に踏み出せないことがわかった。
投稿元:
レビューを見る
ロヒンギャと呼ばれる人たちがミャンマーでひどい目にあっているというニュースをよく目にするがどういう問題なのかわかっていないと思ったので手にとってみた。現時点、軍がクーデターを起こして政権を奪ってしまいロヒンギャの話をあまり目にしないけれども...。真面目な学者の作品らしくわからないことはわからない、と明記されていて好感を持った。ミャンマーというのは多民族国家で100以上の民族がいるらしい。まず政治経済を牛耳ったインド人、中国人への国民的な反感があり、ミャンマーの土着民族を優位にするという政治決定があったこと、またロヒンギャと呼ばれる人たちがミャンマーの中でも最貧のラカイン州という土地に暮らしており、ラカイン州の主要民族は少数民族のラカイン人で彼らは中央政府に反感を持っており独立運動もあったということ。そしてラカイン州がイスラム国家のバングラディシュと国境を接しておりロヒンギャもムスリムである、ということなどがベースにあったということがわかった。このような複合的な条件で、しかも軍政が民主化に移行したことによる自由化でいろいろな情報を得た一部のムスリムがミャンマーとラカインからの独立をもくろんで警察や軍にテロ行為を行い、その対応において軍の一部が暴走し虐殺を行ってしまった、というのがどうやら事の経緯らしい。虐殺を黙認したと世界的に非難されているスーチーさんも戦争犯罪は認めていた、ということもわかった。そのまま進むと軍の責任を追求せざるを得ず、しかし民主化したといっても軍は微妙な位置づけにいて、ということでスーチーさんも対応に苦慮しているうちに焦った軍が再度クーデターを行ってしまった、というのが現状ということのようだ。いろいろな複合要因を見てみると一方的に軍が横暴とも言えないなと思っていたのだけど...日に日に混乱を増す状況でこの先どうなるかわからないけれどわからない度合いが少しマシになったと思います。
投稿元:
レビューを見る
ミャンマー問題の背景を知ろうと購入。背景はおぼろげに見えてくるも、問題の複雑さと解決困難さに言葉を無くす。ミャンマーは長らくにわたり国内紛争と難民問題を抱えてきた国であり、ロヒンギャ危機もそれらの一つの側面である。民族間の対立、暴走する国軍、多宗教との軋轢等、あらゆるステークホルダーの板挟みに置かれるスーチーさんの立場は困難を極める。
スーチーさんを中心とした民主化運動により、長らく続いた軍事政権は終わらせることができた。しかしめでたしめでたしとはいかず、民主化自体が暴力を生みだしてしまうという皮肉な現実もある(民主化とは「人々」による統治であり、「人々」が民族を意味することになれば、民主主義は特定の民族が支配する理想の社会を目指すことになりかねない。また多数決主義も、多数派を占める主要民族に国家権力が集中する機会を与えやすい)。
ミャンマーにおいては、なによりも仏教徒の僧侶が国民から大きな尊敬を得ている。そして民主化による言論の自由に伴って、他の宗教を徹底的に攻撃することで、国民からの支持を集める僧侶も一部存在する(こういうやつは必ず出てくる)。そういった民族的な対立と宗教的な対立があわさり、問題をより複雑かつ深刻なものに変容させている。
弾圧されたロヒンギャ側から過激なレジスタンスが出てくることは、良い悪いは別として理解はできる。ミャンマー側としてそれらを野放しにすることはできない事情もわかる。かといって、ロヒンギャに対するジェノサイドを容認することはできない。外野からはそれくらいしか言えない。無力である。
投稿元:
レビューを見る
ミャンマーにおけるロヒンギャ問題の複雑さ。
差別の構造、なぜアウン=サン=スーチーは黙認するのか
そもそも国軍があれほどまでに力を持っているのはなぜか
解決の糸口はあるのか
今まで日本語の文献でこれほど広い視野で客観的に書かれたものを目にすることができなかったので、ミャンマーで起きていることに興味のある人は必読だと思う。
クーデター前に書かれているので、もちろん今とは状況が変わっているが、これを読むとクーデターの背景も見えてくる。
沈黙していることが我々のすべきことではないことだけは確かだ。
投稿元:
レビューを見る
2017年の武力衝突以降、100万超の難民が流出。アジア最大の人道問題を、歴史的背景やミャンマーをめぐる国内・国際政治で詳説
投稿元:
レビューを見る
「ロヒンギャ危機」中西嘉宏著、中公新書、2021.01.25
252p ¥968 C1231 (2021.05.23読了)(2021.05.17借入)
副題「「民族浄化」の真相」
ミャンマーの歴史に触れながらロヒンギャの問題を教えてくれるので、わかりやすいと思います。ビルマの歴史を知りたければ、下記の本がよさそうです。
「物語 ビルマの歴史 - 王朝時代から現代まで」根本敬著 (中公新書)
ミャンマーの西側の海岸は、ラカイン州と呼ばれている。ラカイン州の西側はバングラデシュに接している。陸続きなので行き来ができる。従って、この辺りには、バングラデシュと同じ民族が住んでいる。
ミャンマー政府は、この地域に住んでいる人たちは、バングラデシュからの不法入国者だとみなしミャンマー国籍を与えていない。生活は貧しく、教育も受けられず、文字も読めない。ミャンマーは、仏教徒の国といっているのに対し、彼らは、イスラム教徒です。
タリバンや、イスラミックステートの人たちと同様のイスラム原理主義者がこの地区に入り込み、この地域の人たちを先導して、ミャンマーの国境警備警察を襲撃した。
これに対して、ミャンマー国軍が、反撃を加えた結果、多くの難民がバングラデシュに逃れた。その数は、70万人といわれます。
ロヒンギャの難民たちは、ミャンマー国籍を約束されない状態では、帰還する気にはなれないでしょうし、ミャンマー政府もイスラム教徒を国民として受け入れるのは、難しいのでしょう。野次馬としての意見としては、ロヒンギャの難民たちが元住んでいた地域をバングラデシュに割譲して手放してしまうのがいいのではないかと思います。
国境を移すというのは、ミャンマー政府の方で言い出さない限り難しいでしょうし、バングラデシュの方でも国際的な援助が約束されないと受け入れがたいことだとは思います。
【目次】
はしがき
序章 難民危機の発生
第1章 国民の他者―ラカインのムスリムはなぜ無国籍になったのか
第2章 国家による排除―軍事政権下の弾圧と難民流出
第3章 民主化の罠―自由がもたらした宗教対立
第4章 襲撃と掃討作戦―いったい何が起きたのか
第5章 ジェノサイド疑惑の国際政治―ミャンマー包囲網の形成とその限界
終章 危機の行方、日本の役割
あとがき
主要参考文献
関連年表
☆関連図書(既読)
「ビルマの竪琴」竹山道雄著、新潮文庫、1959.04.15
「ビルマ敗戦行記」荒木進著、岩波新書、1982.07.20
「アウン・サン・スーチー 囚われの孔雀」三上義一著、講談社、1991.12.10
「ビルマ 「発展」のなかの人びと」田辺寿夫著、岩波新書、1996.05.20
「ビルマからの手紙」アウンサンスーチー著・土佐桂子訳、毎日新聞社、1996.12.25
「新ビルマからの手紙」アウンサンスーチー著・土佐桂子・永井浩訳、毎日新聞社、2012.03.20
「秘密のミャンマー」椎名誠著、小学館、2003.09.01
「ミャンマーの柳生一族」高野秀行著、集英社文庫、2006.03.25
「ミャンマー」乃南アサ著、文芸春秋、2008.06.15
「ミャンマー経済で儲ける5つの真実」小原祥嵩著、幻冬舎新書、2013.09.30
(アマゾンより)
2017年8月25日、武装グループがミャンマー、ラカイン州の警察・軍関連施設を襲撃した。これに対し国軍は、ロヒンギャ集落で大規模な掃討作戦を実施。人々は暴力を逃れるため、隣国バングラデシュへと避難し、半年という短期間に難民は70万人にのぼった。事件から3年が経過したが、帰還は進んでいない。本書は、アジア最大の人道問題の全貌を、歴史的背景やミャンマーをめぐる国内・国際政治から読み解く。
投稿元:
レビューを見る
ロヒンギャに対する外部の人道的な目線で書かれた本。公平ではない。
多分、日本語で書かれたどの本より理解しやすい。
しかし、異教徒を殺すと天国に行ける宗教を信じる領土略奪者が武装して、警察や軍隊を襲い武器を奪おうとヒャッハーしたのに世界の皆さんは優しいなと思う。
考えて欲しい。日本人の9割が邪教と思える宗教のもとに集まった外国から来た武装集団が、日本で土地を簒奪し居座り同化せず犯罪者を匿い地元警察や自衛隊を襲うなんて、貴方は許せるだろうか。
私には無理だ。
投稿元:
レビューを見る
ミャンマー西部に住むイスラーム系民族のひとつであるロヒンギャを巡る2017年の国軍による掃討作戦以降の大量の難民の発生等の一連の危機について、危機がどうして起きたのか、その余波が世界にどう広がっているのかといった点を、歴史的背景の考察も踏まえながら検討し、将来に向けての展望と日本が果たすべき役割についても考察。
ロヒンギャ危機はもちろんのこと、2021年2月に発生した国軍のクーデターに至る歴史的背景等についても理解が深まった。
民主化にもかかわらずロヒンギャ危機が発生したのではなく、民主化したからこそロヒンギャ危機が発生したとの指摘が印象深かった。
アウンサンスーチー氏がロヒンギャ危機に際して受け身のリーダーシップに甘んじていたことについて、国軍との関係悪化の回避を優先していたとの分析も、国軍のクーデターが起きてしまった今から思えば、非常に納得のいくものである。当時、NLD関係者と話をした著者は、彼らが国軍との関係に非常に神経をとがらせ、常に最悪の事態(クーデター)まで想定していることを実感していたということが述べられているが、残念ながらその懸念は現実のものとなってしまったわけである。
ロヒンギャ危機について日本が果たすべき役割についての指摘も、まさに現在、国軍のクーデターに対して日本が果たすべき役割にも通じるところがあり、非常に示唆的であると感じた。欧米の理想主義一辺倒で果たしてミャンマーの現実を動かせるのかどうかというところであろう。著者のいうように、理想主義と現実主義のバランスが問われているのだと思う。また、過去の歴史的背景を踏まえても、ミャンマーの行く末について中国が大きな鍵を握っているのだと思われる。
本書の最後に触れられている、自然権としての人権という理想と、国家あってこその人権という現実との間のジレンマとしてハンナ・アーレントが提示した「人権のアポリア」という概念は、まさにミャンマーの問題に当てはまるものであり、本当に難問だと感じた。