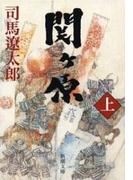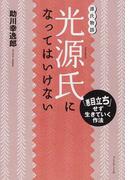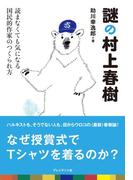司馬遼太郎を「過去」にできない日本人(インタビュー)
没後20年たっても、いまなお、ビジネスパーソンを魅了しつづける司馬遼太郎。その作品は、戦後、日本人が生きていく上でのバイブル的存在といっても過言ではありません。しかし、日本文学研究者の助川幸逸郎氏は、「司馬遼太郎の作品に感動ばかりしていてはいけない」と指摘します。
助川氏は横浜市立大学、東海大学などで講師を務め、これまで、文学にとどまらず、映画、ファッション、アイドルなど、多岐にわたるテーマと多様な切り口で、授業や講演、執筆を行ってきました。
助川氏が指摘するように、「組織に属しながら、心は坂本龍馬」という生き方は、司馬の作品を愛読するビジネスパーソンの理想像でした。一方、それでは21世紀のグローバルな情報化時代を生き抜くことはできないのではないかと、少なからずの人が疑問を感じていることも事実でしょう。
では、司馬遼太郎のどこに限界があり、その作品から、いかに日本が進むべき道をくみ取るか、従来とは異なる切り口で、助川氏に語っていただきました。
撮影:「麹町アカデミア・遊学堂」会場:ビジネスエアポート東京
なぜ、司馬遼太郎に感動ばかりしていてはいけないのか
まずはじめに、私は、作家としての司馬遼太郎が大好きです。しかし、司馬に感動ばかりしてはまずいのではないかという思いがあります。司馬は高度経済成長期に大変人気のあった作家で、20年も前に亡くなっています。本来なら、過去の人になっていなければおかしいはずなのに、いまだにリアルタイムで非常に人気がある。
これは、日本人が意識を変えて、前に進んでいかなければいけないのに、進めていないということとつながるのではないか、司馬を過去の人にできない日本人の問題ではないかという気がしています。本日はこの点について話をしていきましょう。
司馬遼太郎は大正12年生まれで、太平洋戦争では戦車部隊として従軍しました。戦争で非常に嫌な思いをしたということは、本人も繰り返し話しています。その根底には、「官僚的非合理主義」が日本を破滅にやった、損得勘定のはっきりした民間人の商売感覚、つまり儲からないことはやらないという「庶民的合理主義」があれば、軍部の暴走は防げたという考えがありました。
司馬の作品には、庶民的合理主義の人物がよく登場します。例えば、坂本龍馬がそうです。龍馬は自分で革命を起こしながら、革命政府の一員にはならず、民間組織である海援隊のリーダーにとどまろうとしました。『竜馬がゆく』では、そんな龍馬を最高にさわやかな人物として描きました。
逆に、官僚主義的な人は、そのためにつまずいたということを書いています。今度、『関ケ原』が映画化されますが、司馬の石田三成観は、非常に有能な官僚であったけれど、それゆえ観念的になりすぎて、人間を将棋の駒のように動かせると考えたために、徳川家康に勝てなかったというものでした。
関ヶ原
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
司馬遼太郎を愛読する戦後日本人の生き方とは
司馬は、歴史上の指導者を「体制製造家」と「処理家」の2つにわけられると指摘しています(「体制製造家と処理家」『手掘り日本史』所収)。「体制製造家」は既存の組織に縛られず、新たな体制を生み出してきた独創的な英雄です。
対する「処理家」は既存のシステムを運用することに長けた官僚で、組織をつくり、自分の野望を実現していきます。司馬は、織田信長、西郷隆盛、大久保利通などは「体制製造家」、徳川家康、山県有朋、伊藤博文は「処理家」に属するとし、前者を称賛する一方で、後者を嫌いました。
こうした司馬の作品を愛読するビジネスパーソンは、組織に従属しながら、気持ちの上では「体制製造家」という点に、生き方を見出してきました。しかし、司馬が肯定する体制製造家には、ある種の矛盾があります。
体制製造家というのは体制を作る存在です。なぜ、それが可能かといえば、既存のシステムに依存していないからです。だからこそ、織田信長も大久保利通も坂本龍馬も、既存のシステムを変えたり、新しいシステムを作ることができました。
ところが今の日本社会では、自主独立の作家やジャーナリストであっても、大手テレビ局や出版社、新聞社など組織で仕事をさせてもらわなければ生きていけません。ですから、みな、信長や龍馬にならなければいけないと言いつつ、現実は、組織の中でなるべく地雷を踏まないように生きようということになる。そこに、司馬遼太郎の問題点があります。これについては後述します。
村上春樹の描く個人と組織の黒い関係
個人と組織の関係について、司馬の子供世代にあたる村上春樹の作品には、司馬にない発想を見ることができます。
村上は、サリン事件について書いたノンフィクション『アンダーグラウンド』で、サリンをあびたサラリーマンが、具合が悪くても出社し、ラジオ体操をしているという光景を描きました。
表面的には何も述べていませんが、そこには、一生懸命やっているだけの個人が集まったとき、個人の常識や良心より、組織の論理が勝り、「悪」を生むという発想があります。
近年、問題になっているブラック企業もそうです。個人は会社を首になりたくなくて、懸命に働いているだけです。しかしそうした人間が寄り集まることで、ブラック企業という「悪」のシステムが生まれます。
先日、電通の若い女性社員がパワハラで自殺するという事件がありました。バブルのころも、若い人が過労で突然死するようなことがたくさんありましたが、当時は景気がよく、残業代も出ましたし、残された家族のための福利厚生もあったので、あまり大きな問題になることはありませんでした。
ところがバブルがはじけ、産業構造自体がかわりました。昭和の時代とは違ったがんばり方をしなければ勝ち抜けない時代が来ています。それなのに、日本人は、高度経済成長を支えた「会社のためにがんばろう、そうすれば明日がある」という昭和の論理から抜け出せずにいます。
「仕事なんて、アルバイトで食べていける程度にあればいい」と思う人もいるかもしれません。けれど現代の日本では、会社がそれに所属する社員と家族の身分保障になっていて、組織に属していなければ、居場所がないという社会システムが、いまだに存在しています。
アンダーグラウンド
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
戦後価値基準の崩壊がもたらしたもの
ただ、このシステムには、たかだか50年くらいの歴史しかありません。1960年代ごろまでの日本人は村落共同体に属し、川で洗濯しながら、村のおばさんたちが交流するような生活習慣が続いていました。
それが、1960年代に入ると、洗濯機が普及し、さらには車を持つようになります。その結果、生活が少し便利になっただけでなく、人間関係の作られ方が根源的に変わり、村落共同体の伝統的な地縁は崩壊しました。
その代替をこの間まで担っていたのが、企業です。でももはや企業も代替を担うことをしなくなってしまった。
こうした価値基準の崩壊を問題としたのが、1970年に自殺した三島由紀夫でした。日本の社会が伝統的なものをすべて解体したあと、経済効率性以外の価値観しか残らなくなる。それでは回らなくなったとき、次に日本人は何を価値基準に生きていけばいいのかということを、三島は考えていました。
そして、戦後的価値観に強い懐疑の念を抱き、切腹という過激な形で、戦後民主主義的や高度成長の論理に挑んだのです。その三島の死に際して、司馬遼太郎はほとんど動転といえるような反応を示しました。
三島由紀夫の死を矮小化した司馬遼太郎
戦後的価値観に強い懐疑の念を抱き、切腹という過激な形で、戦後民主主義的や高度成長の論理に挑んだのが三島由紀夫でした。その死に際して、司馬遼太郎はほとんど動転といえるような反応を示しました。
「毎日新聞」に寄せた「異常な三島事件に接して ―― 文学論的なその死」という文章の中で、「三島の死には、何の政治的リアリティもなく、単に芸術の範囲のことだ」ということを書いています。
「現実とかかわりがないというところに繰り返していう思想の栄光がある」と述べ、幕末の思想家で斬首刑に処せられた吉田松陰をひきあいに、「かれほど思想家としての結晶度の高い人でさえ、自殺によって自分の思想を完結しようとはおもっていなかった」「三島氏のは、三島氏独自の思想であり、日本人の精神の歴史的系列とは別個のものだ」と書いている。
司馬は本当に思想嫌いで、他でも「思想は国や組織をうまく運営していくための方便にすぎない」「日本人のえらいところは無思想なところだ」ということを言っています。
しかし、現実には、司馬が肯定した庶民的合理主義つまり損得勘定だけでは選択しえない局面があります。そのとき基準となるのが、思想や美意識です。それが崩壊した1960年代に、この先をどう生きるかということを問うたのが三島でした。
これに対し、司馬には、庶民の活力、すなわち庶民的な合理主義が、戦後の民主主義や高度経済成長を支えてきたという考えがありました。また、それに強く共鳴していました。
だからこそ、三島の提示した問題を吸い上げることなく、彼が命をかけてまで違和感を唱えたことについて、歪曲に近い形で矮小化し、無理やり芸術の範囲に押し込めようとしたのです。そこには、逆説的に、司馬が戦後的価値観を守らなければいけないと思っていたということがにじみ出ていると思います。
司馬遼太郎が生んだ理想像の行き詰まり
しかしその司馬も、バブル経済と土地ころがしに、庶民的合理主義の破たんを見ていました。バブル期は、土地を担保に、机上の空論で経済が進み、庶民の実感からは大きくずれていった時代でした。司馬は晩年、土地は公有制にするしかないといった、これまでの言説とは矛盾するようなことも書いています。
また、田中角栄のことも非常に嫌っていました。田中は庶民の代表的存在でしたが、司馬は田中に、投機的でバブル的なものと結びついた匂いを感じていたのでしょう。
それと同時に、庶民的な感覚に頼って生きていけばいいという戦後の高度経済成長の発想が、もう限界にきていることにも気づいていました。そして、それにかわる価値観を打ち出せないまま、司馬は亡くなります。
司馬の作品を見ると、上り坂の人間か、あるいは滅びていくことがわかっていて、いかに格好良く死ぬかという人物が書かれています。けれど、体制がある程度、固まり、次の手を打たなければならないところで、さて、どう打つかという段階の人間は書かれません。
国が行き詰りながら、滅びるまでにはまだある段階で、どういう目のつけどころをしていけばよいかという意識を、おそらく司馬は持っていなかったのではないでしょうか。
そして日本人は、司馬のもつ庶民的合理主義的なものに頼り、組織の中にいながら、気持ちは信長や龍馬という生き方ではたちゆかない時代が、とっくの昔に来ているのに、司馬の提示した以上の価値観を、見いだせずにいます。
江戸時代の小政府に学ぶ
ではこれからどうすればいいか。最近、司馬が批判した田中角栄がブームになったり、三島由紀夫が再評価されたりしています。けれど、だからといって彼らを神格化すれば済む話ではありません。そこで最後に、個人的な考えを少しだけお話しします。
これからの日本は、江戸時代化していかざるをえないと考えています。これだけ少子高齢化が進み、税金を払う若年労働者層が少なくなると、昭和時代のようなやり方はできません。そこで、政府が非常に小かったといわれている江戸末期の社会と歴史から学ぶべき点は多いのではないかと考えます。
まず大切なことは、庶民の教育レベルの高さです。江戸時代、庶民の識字率が高く、大衆文化の華が咲いていました。日本人の特長は、トップがすごいというより、例えばコンビニの店員でも、常連客のために、何も言われなくても商品を取っておくようなサービスができることです。
これはおそらく日本人のいいところです。こうした末端のレベルを維持していかないと、日本のレベルは維持できません。今、文科省がエリート教育に向かいつつありますが、中・下レベルの底上げというのをやめてはだめだと思います。
江戸末期の教育レベルの高さは、階級流動性とも関係しています。当時、経済は資本主義化していました。そこで、財政改革のスキルやアイデアを持った人は、百姓や下級武士であっても、藩の財政の中枢に入り、階級の上がる余地がありました。このために寺子屋が普及し、識字率も上がったのです。
また、政府に頼らない互助・自治のシステムもありました。もちろん江戸時代はいいことばかりではありませんが、こうした点に学ぶべきものがあると考えます。
ガラパゴス化した日本を生きるために必要なこととは
困難な新時代を生き延びるために、私たちは再生をもとめられています。
日本の歴史をさかのぼると、紀貫之が古今和歌集を編纂し、仮名文を発明した時代は、グローバル国家であった唐が衰退しはじめ、日本も国内に向け、和風のドメスティックなコンテンツだけでやっていこうという方向に、大きく舵をきりました。
私は、日本人が、英語が苦手なのは、紀貫之が日本をあまりに上手に日本をガラパゴス化しすぎたせいだということを提唱しています。従来、日本人は外国語である中国語を読むことができました。ところが、書き下し文前提の日本国内でしか通用しない漢文が生まれたことで、読めなくなった。その伝統が、今も残っていると思うのです。
このため、留学経験がないエリートが書いた英語は、文法的に正しいし、語彙も豊富だけれど、英語のロジックになっておらず、外国人には全然、何を言っているのかわからないということになります。
日本は、繭の中にこもり、ガラパゴス化している部分がある国です。そろそろ、本当の意味で、繭の外側を体験し、もう一度、国の有り様を考えていくということが必要ではないかという気がしています。
世界は今、グローバリゼーションの中でどんどん変わっています。日本ではこれまで、普通に勉強して大学を出れば、正社員になれました。ところが近年は、大学を出てもコンビニのアルバイトしかないというような現実があります。
そうしたとき、「他にうまくやっているやつがいるはずだ」と考え、例えば外国人に対して、差別的な発言をする人が現れます。これは日本だけの現象ではありません。
アメリカの大統領選で、「プアホワイト」がトランプ次期大統領を支えていたということがよく言われていました。
マイノリティには、彼らを差別から守ろうとするインテリがいます。ですが、プワホワイトは貧乏でも、白人なのでマイノリティ意識も薄く、助けてくれる人はいません。そうした人々がトランプ次期大統領を支持しているわけです。
この層をどのように救い上げていくか、彼らにどう対処していくかは、日本でも考えなければならない問題です。このとき、私はただ、グローバルという言葉だけではなく、上述したような江戸時代のシステムや伝統によりそった形で、日本社会をもう一度、見つめなおしていく必要があるのではないかと考えています。
それと同時に、もう一方で、日本という繭を破り、諸国とむきあい、外国とコミュニケーションをとるというのがどういうことなのかを考えなければならない時期に来ているのではないでしょうか。
本日は、司馬遼太郎の考え方とその限界点について話をしてきました。けれど、司馬さん自身がおそらく、こういう状況に対して、「俺よりも、若い人たちが考えてくれよ」と思っているかもしれません。
※本稿は「麹町アカデミア・遊学堂」主催の講演『没後20年記念:司馬遼太郎から学ぶ「21世紀日本のゆくえ」』を、再構成したものです。
講演者・著書紹介
本稿で「司馬から学んでいてはいけない」と切り込む助川幸逸郎氏。その氏の著作は、誰も知っている文学作品や人物を題材に、思いもよらない、けれど本質的に我々が考えるべきテーマが展開します。そこには、既成概念や常識にとらわれない、目から鱗の知的楽しみが詰まっているようです。
光源氏になってはいけない
光源氏になってはいけない 源氏物語 「悪目立ち」せず生きていく作法
-
税込1,540円(14pt) 発送可能日:購入できません
- 助川 幸逸郎 (著)
- 出版社:プレジデント社
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
女たらし、ロリコン、マザコン、回避依存症、自惚れ、官僚体質、家庭崩壊、アラフォー自分探し…。「なってはいけない」大人の事例集・源氏物語に描かれた人間模様をたどりながら、「停滞期の社会」を生き抜く知恵を紹介する。
謎の村上春樹読まなくても気になる国民的作家のつくられ方
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
なぜ好きでもないのに出るとつい買ってしまうのか? なぜ日本文学界で独り勝ちになったのか? なぜ黒髪ロングヘア・スレンダー巨乳美少女が登場するのか? 謎の作家・村上春樹に迫る。
小泉今日子はなぜいつも旬なのか
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
どの時代でも、どの世代からも、小泉今日子が愛される理由とは? 彼女が芸能界にデビューした80年代から現代までの「女の子変遷史」で読み解く小泉今日子論。
プロフィール

助川幸逸郎
日本文学研究者、著述家
1967年生まれ。早稲田大学教育学部国語国文学科卒業、早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。横浜市立大学、東海大学などで講師を務める。文学、映画、ファッション、アイドルなどのテーマを多様な切り口で交ぜ合わせ、授業や講演、執筆を行っている。著書に『文学理論の冒険』(東海大学出版会)、『可能性としてのリテラシー教育』『21世紀における語ることの倫理』(ともに共編著・ひつじ書房)、『光源氏になってはいけない』『謎の村上春樹』(共にプレジデント社)、『小泉今日子はなぜいつも旬なのか』(朝日新聞出版)などがある。
ライタープロフィール

hontoビジネス書分析チーム
本と電子書籍のハイブリッド書店「honto」による、注目の書籍を見つけるための分析チーム。
ビジネスパーソン向けの注目書籍を見つける本チームは、ビジネス書にとどまらず、社会課題、自然科学、人文科学、教養、スポーツ・芸術などの分野から、注目の書籍をご紹介します。
丸善・ジュンク堂も同グループであるため、この2書店の売れ筋(ランキング)から注目の書籍を見つけることも。小説などフィクションよりもノンフィクションを好むメンバーが揃っています。