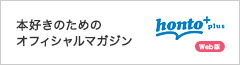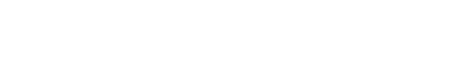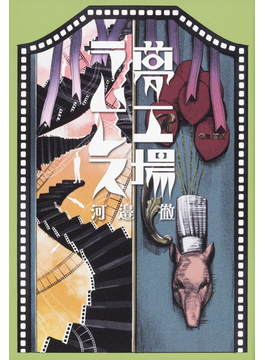第4話
- その2
- その1
眩しさで目を覚ました。また朝がやって来たようだ。
ここは……どこだ? 昨日の記憶が曖昧だ。確か俺は、真希の家に行って……。
しかしどうやらここは、自分の部屋である。いつものベッドの上にいて、向こう側の本棚には、見慣れた小説の背表紙が並んでいる。
徐々に記憶がはっきりしてきた。しかしはっきりすればするほど、どうやって自分の家に帰ってきたのかが不思議になる。フェリーの最終便はもうなかったはずだ。
確か階段から落ちて……。
まさか。
俺は起き上がってリビングへ向かった。
扉を開くと、昨日と同じように、那月が朝食を食べながらテレビを観ていた。
「またか……」
「何よ?」
那月がこちらに怪訝そうな顔を向けている。
『今夜は人工流星が流れます。幸運なことに天気もよく、壮麗な流星が見えることが予想されます――』
テレビからは、もう既に聞き飽きた言葉が聞こえてくる。この後広島市内のレストランが紹介されるのだ。
どうやらまた、新しい明日は来なかったらしい。半分諦めにも似た気持ちが湧き上がってきた。何度この日を繰り返せばいいのだろう。人工流星から離れても、神様にお願いしてもダメだったのだ。
俺はもう昨日のように取り乱すこともなく、逆に冷静に物事を考え始めた。せっかく今日起こることを知っているのだ。那月にも何か言ってあげよう。
「那月、今日先輩と一緒に人工流星を観に行くんじゃろ?」
俺はキッチンに入って、食パンをトースターに突っ込みながら言った。タイマーをグリっと回す。
「え?」
那月は信じられない、という顔でこちらを見ている。
「それなんじゃけどな、なんか……その先輩っていうのは……」
那月の顔が既に、何よ、と言っている。
「……那月には気がないらしいわ」
「なんでそんなん知っとるん!? ってかお兄には関係ないし」
「那月、受け入れんといけんことってあるじゃろ」
「……誰から聞いたんか知らんけど、邪魔せんとって! 行ってきます」
那月は不機嫌そうに立ち上がって、バンッ、と扉を閉めてリビングから出て行った。
悲しい現実を受け入れることは難しい。逆効果だっただろうか。乙女心を軽く見てはいけない。あの頃の年齢は、好きな人が全てである。
好きな人が全て……。俺も、人のことを言えないのかもしれないが。
学校に行くと、また同じ出来事が繰り返された。授業の内容も、聞こえてくる会話も同じだ。それでも、俺の行動によって全く同じ一日になるわけでもないことは、もう昨日と一昨日で証明されている。きっとどこかに、ループを抜け出すためのヒントがあるはずなのだ。
今日俺が何をするにしても、洋介と真希を放っておくことはできない。最初の休み時間、流星を観に行こうと誘う洋介に、俺は昨日と同じように未来予知を見せつけながら、お母さんに謝ることを勧めた。
昼休みには、また真希に会いに行った。彼女のクラスの教室まで行って呼び出す。昨日のことを知っている俺は、真希の姿を見ると、照れて顔が赤くなってしまいそうだった。昨日の告白はどこまで本気だったのだろうか……。しかしそんなことを、今日の真希に訊けるはずもない。俺は落ち着いて事情を話し、流星が流れ始める時間に、間違いなく上のお兄さんに電話をすることを約束させた。
「わかった……。りょうちゃんの言うこと、信じてみる」
真希は真剣な表情でこちらを見ていた。本当に昨日のことは何も覚えていないようだった。
こうして俺の記憶だけがなくなっていないところを思うと、俺だけが永遠に今日を繰り返すという洋介の冗談も、少しずつ現実味を帯びてきている。自分だけ年老いていってしまうのだろうか、と残酷な未来を思った。
このままずっと明日が来なければ、これからも広島で過ごすことを詩織に伝えられず、俺の決心は形にできないまま宙ぶらりんだ。
詩織……。
しばらく会ってないような気持ちになっていた。この三日間が濃過ぎたせいだ。今日も風邪をひいたという連絡が彼女から来ていた。
そういえば、最初の日に詩織に電話をかけた時、昼には随分体調がましになったと言っていたはずだ。
……詩織に相談してみるか。
気は進まないが、俺は放課後に電話してみることにした。
「ごめん、起きてた?」
しばらくコールして、電話は繋がった。
「うん、大丈夫。朝よりも楽になっとるよ」
思ったより元気そうな声なので、俺は安心した。
「ちょっと話したいことあるけぇ、聞いてくれるか?」
「うん。どしたん?」
風邪とはいえ、日常を過ごしている詩織にとって、俺の話すことはあまりに突飛過ぎるだろう。どう話しても不自然になってしまう。しかし話さないわけにもいかない。ずっと今日という日が繰り返されていることを、俺は順序立てて彼女に伝えた。
信じてもらえるはずがない。そう思っていたが、詩織は意外にもすぐに、俺の言っていることを受け入れてくれた。
「……そうなんじゃ」
証拠を要求することもなく、彼女は言った。
「ほいじゃ、もしかしたら、まだ何日も今日が繰り返される可能性があるってことじゃろ?」
「うん。そうかもしれん」
「……それなら、今日は私と一緒に人工流星を観に行ってくれる?」
意外な提案を、彼女はした。
「体調は大丈夫なん?」
「もう元気だよ、大丈夫。ってか、最初の日は私に黙って行ったってことじゃろ?」
恨めしそうな口調で詩織は言った。口を尖らせている表情が見えるようだった。
「で、でも、それは詩織が知ったら無理して来るかもしれんって思って」
「行くよ。だって私、天文部やけぇ。そんなん見逃したら後悔する。絶対行く」
詩織の口調には、意志の強さが感じられた。
「ね、せっかくじゃけぇ、去年一緒に星を観たところでまた観たい」
去年一緒に星を観たところ。どこのことだろうか。
「……長野?」
「違うよ、遠過ぎじゃ。高校の、屋上!」
それは、去年の春の話だった。
暗闇の廊下に、赤い非常灯だけが鈍い光を放っていた。冷たい空気に、俺の足音だけが硬く響く。
俺は一度家に帰って、鞄だけ置いてこうしてまた学校にやって来た。さすがにこの時間まで、校内で隠れているわけにもいかない。
「夜の学校、ちょっと久しぶりじゃなー」
詩織は鈴を鳴らしたような声で言った。俺の前を歩きながら、制服姿の彼女はまるでここに来ること自体が久しぶりなように、キョロキョロしている。
二十時半。学校に残っている先生もいないようだった。
「一・二年生の頃は、お泊まり会してたよな」
「うん。でも今日は先生もおらんし、こっそりじゃけぇドキドキするね」
サラサラと流れる髪を揺らしながら、詩織は嬉しそうに歩く。今日ばっかりは完全に不法侵入なので、見つかってしまうと思いきり怒られてしまうだろう。学校に入るのも一苦労だった。門を乗り越えるなんてことを、自分ができるとは信じられなかった。俺は内心ビクビクしていたが、詩織はそれさえも楽しんでいるようだ。
夜の学校の空気は昼のそれとは全く違う。施錠された門、誰もいない運動場、真っ暗な廊下。騒がしかった昼間の空気が、嘘のように静まり返っている。
後ろを歩いていた俺は少し歩を速め、詩織に追いついて並んで歩いた。
ここ数日、おかしなことばかり起きているからだろうか。こうして詩織と一緒に歩くこの瞬間さえ、まるで現実のものではないような気がしてくる。
「ね、屋上行ってみん?」
「だから、鍵が開いとらんじゃろ」
さっき電話で詩織が提案した時にも言ったが、屋上へ行くための扉は、普段鍵が閉められているのだ。
「いいから、行ってみんとわからんじゃろ」
行ってみるだけな、と言って、俺は詩織の手を引いて真っ暗な階段を上っていく。普通の生徒は、屋上へ繋がる扉がどこにあるのかさえ知らないかもしれない。
四階まで行き、右に曲がると小さな空間とエレベーターの扉がある。エレベーターは普段生徒は使用を禁止されているので、誰も近づくことのない場所だ。エレベーターの隣には、非常口のような無骨な扉がある。その先にある階段を上っていくと、鍵付きの扉があり、そこから屋上に出ることができる。
その鍵付きの扉の前まで来ると、俺は詩織から手を離し、ひんやりとした扉のノブをひねった。
「ほら閉まっとるじゃ……」
扉を押すと、予想に反して開いた。鍵は奇跡的にかかっていなかったのだ。
「え?」
「開いてたね! ラッキー!」
詩織が声を弾ませた。
戸惑いながらも、俺は重い扉を押して屋上に出た。
冷たい風が吹いて、どこからか運ばれてきた冬の匂いが鼻腔をくすぐった。
芝生の上を歩いて、正面の柵の前まで行く。去年の春、俺と詩織が二人で寝転んでいたのはこの辺りだった。屋上の逆サイドで、みんなで望遠鏡を覗いていたことも懐かしい。
柵に手を掛けて向こうを覗けば、教室の窓からと同じようにグラウンドが見渡せる。一瞬だけ、一年生の頃の、体育の授業を眺めていた一人ぼっちの自分に戻った気がした。
あの頃、俺は一人で何を考えていたのだろう。それを忘れてしまうほどに、今俺のそばには誰かがいてくれる。詩織が天文部へ俺を引っ張っていってくれたからだ。詩織がいなければ、俺は今も一人で、教室の隅で本を読んでいるだけだった。
「……俺、東京の大学の指定校推薦もらった」
背中に詩織の気配を感じながら、俺は言った。さっきまで言うつもりなんてなかったのに、言った。来るかどうかもわからない明日なんて、待っていられないと思った。ちゃんと説明したい。俺は、ちゃんと詩織に伝えたい。感謝の気持ちと、これからのことを。たとえ今日が何度繰り返されたとしても。
「……知ってたよ」
まさかの言葉に、俺は驚いて振り返った。
「まじか? 洋介から聞いたん? あいつひどいな。でも……やめようと思う。辞退しようと思う」
一呼吸置いて、俺は続けた。
「理由なんて適当に付ければええじゃろ。家族の事情でーとか。学校が来年から指定外されてしまうんかな、とか思ったけど……まぁ大丈夫じゃろ」
詩織は無言で俺の話を聞いている。その表情からは、彼女が何を考えているのか読み取ることができない。
「……だから、やっぱり広島の大学受けようと思っとる」
「本当にそれでいいの? どうして?」
風に吹かれるロウソクの火のような声で詩織は言った。
「……詩織と一緒にいたいから」
俺の声も、夜風に連れ去られてしまいそうだった。
一緒にいたい。そんなこと、お互いにわかり切っている。
俺は詩織のことが好き。詩織は俺のことが好き。お互いがそれを知っている。ずっとそうだったはずだ。
そのはずなのに、俺は自分の記憶から、何かが抜け落ちているような気がする。
俺の言葉に、詩織はまた微かに陰のある顔をしている。
「まぁ、それも全部、今日のループを抜け出さんと、そんなわけにもいかんけどな」
その沈んだ空気を払拭するように、俺は明るく言った。
「ループの原因に心当たりはないの?」
「うーん……わからんなぁ。洋介や真希に相談して、いろいろしてもらったんじゃけどな。やっぱり人工流星のせいじゃ思うけど」
そうかもしれないし、そうじゃないのかもしれない。
「人工流星のせいじゃないよ」
「え?」
詩織は暗闇の中で輝く炎のように、はっきりと言った。
「……どうして明日が来ないのか、もうわかってるくせに」
含みを持たせた言葉を口にするその表情は、まるで別人のように感じられた。
「どういうことじゃ?」
「本当は人工流星が原因じゃないことを、多分りょうは知ってるんじゃないの、ってこと」
スカートのポケットに手を突っ込んで、詩織はくるりと背を向けた。
「何を言うとるんじゃ。わかってたらこんな苦労しとらん」
「またそんなこと言ってごまかして」
俺は言葉に窮して、ただそこに立ち尽くしていた。
詩織はゆっくりと振り返って、まっすぐな眼差しでこちらを見た。
「受け入れんといけん、悲しみがある」
冷たい風が、俺と詩織の間を吹き抜けていった。
「詩織、さっきから何を言っとるんじゃ?」
「あれ? りょうさん?」
その時、場違いな声が響いた。
「ほんとだ、りょうさんだ。話し声が聞こえたから、誰が来たのかと思いました」
詩織の向こう側には、モナとレオンが並んで立っていた。二人とも制服姿で、モナはスカートの下に学校指定のジャージを穿いている。レオンは首から提げた一眼レフのカメラを、大事そうに両手で抱えている。
「お前ら、なんでこんなところに?」
俺はこんな場所に人がいたことに、それも、知っている後輩がいたことに驚きを隠せなかった。
「僕ら、顧問の先生にお願いして、人工流星の時間だけ屋上に上がることを許可してもらったんです」
屋上の逆サイドで、真面目に観測の記録をしに来ていたのだろう。だから鍵が開いていたのか。
「りょうさんこそ、どうして一人でこんなところに?」
「一人? 俺は詩織と流星を観に来たんじゃ」
「……」
二人は黙った。間に立っている詩織も、うつむいて黙り込んでいる。気まずい沈黙が生まれた。
「誰もいないですよ」
レオンは無表情で言った。その横でモナは、口を固く結んで弱々しい顔をしている。
「誰も……いない?」
俺は詩織の顔を見つめた。スローモーションのように、ゆっくりと目が合った。その瞳には、透明な涙がうっすらと光っていた。
もうすぐ、人工流星が流れる時間だった。
≪-テキストは横読み-≫
続きは単行本『流星コーリング』をチェック!
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g321803001187/
\インスト音源付き/
Movie
WEAVER「栞 feat.仲宗根泉(HY)」
Profile

WEAVER 河邉徹(Dr.)
1988年6月28日、兵庫県生まれ。関西学院大学 文学部 文化歴史学科 哲学倫理学専修 卒。
ピアノ、ドラム、ベースの3ピースバンド・WEAVERのドラマーとして2009年10月メジャーデビュー。バンドでは作詞を担当。
2018年5月に小説家デビュー作となる『夢工場ラムレス』を刊行。
WEAVER公式HP:
http://www.weavermusic.jp
Books
OTHER