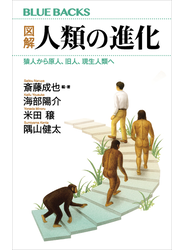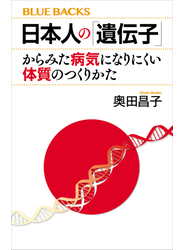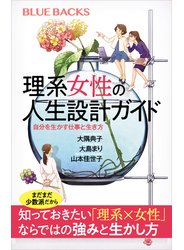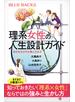ブックキュレーター小林武彦
ブックキュレーター小林武彦
小林武彦の推薦する名著5冊
小林武彦の「推薦図書」はこの5冊! ※こちらの推薦文は、クーリエ・ジャポン読者のために寄稿いただいたものを転載したものです。
- 8
- お気に入り
- 1330
- 閲覧数
-
-
新型コロナウイルスのワクチンもそうですが、日本はなかなか自前で薬やワクチンが作れない国です。外国製の薬は日本人にはしっくりこないこともあるのかもしれません。この本を読むと、その理由がよくわかります。
ではどうすればいいのか。その解決方法も日本人の生まれ持った体質的特徴を踏まえて、薬にあまり頼らずに生活習慣、環境の改善など、私たちの身近な事柄から提案されています。各章の最後にわかりやすい「まとめ」があるのも嬉しい。
-
池上彰さんは、職場の同僚です。時々廊下でばったりお会いすると、超短時間で世間話をします。テレビの中の池上さんと同様、非常に的確にわかりやすいご意見を述べられる。まさに「説明の天才」です。
私も教員の端くれで、相手に伝わる話し方を心がけてはいますが、池上さんの足元にも及びません。この本を読むと、池上さんは最初から「天才」だったわけではなく、ご努力されて習得された「技」であることがわかります。 -
海外の生命科学関連の学会に行くと、参加者の半分くらいは女性研究者です。女性の方が多い分野もあります。一方、日本はというと、ご想像の通り男性がほとんどです。日本では、研究者は女性が目指しにくい職種なのでしょうか? そんなことはないと、この本を読んだらわかります。
本書では、世界的に活躍する日本の女性研究者が、ご自身のキャリアを通じて、研究者という職業の魅力、将来性を紹介しています。理系研究者を目指す女子学生・生徒さんはもちろんのこと、男性も含めた多くの関係者に読んでいただきたい本です。 -
生物学の研究手法には主に3つあります。
1.細胞など生きている状態を詳しく調べる方法。いわゆる生物学の基本はこれです。
2.細胞からタンパク質などを取り出して働きを調べる方法。酵素の研究などです。
3.コンピュータで情報学的に解析する方法。遺伝情報の研究はこれを使います。
そして最近現れたのが、作って調べる合成生物学です。人工細胞が作れたら、それは生物の基本メカニズムを理解したと言っていいのかも知れません。大いなる挑戦です。
![]()
ブックキュレーター
小林武彦東京大学定量生命科学研究所教授(生命動態研究センター ゲノム再生研究分野)。九州大学大学院を修了後(理学博士)、基礎生物学研究所、米国ロシュ分子生物学研究所、米国国立衛生研究所、国立遺伝学研究所を経て、現職。前日本遺伝学会会長。現在、生物科学学会連合の代表も務める。著書に『生物はなぜ死ぬのか』(講談社現代新書)、『DNAの98%は謎』(講談社ブルーバックス)など。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です