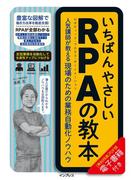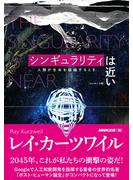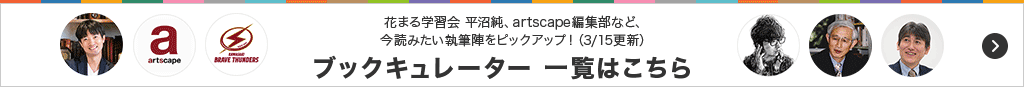ブックツリー
Myブックツリーを見る本の専門家が独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの”関心・興味”や”読んでなりたい気分”に沿ってご紹介。
あなたにオススメのブックツリーは、ログイン後、hontoトップに表示されます。
”第二次団地ブーム”到来?「団地萌え」の今を知る本から、団地の歴史、空間政治学、小説、マンガまで、団地をめぐる本は熱量が凄い。
- お気に入り
- 7
- 閲覧数
- 3473
戦後、高度経済成長期に続々と作られた全国の住宅団地。モダンなライフスタイルは「団地族」と言う呼び名まで生んだ。だが時代の変遷とともに団地は高齢化し、近年では孤独死や移民の増加など様々な問題が生まれている。その一方、リノベ団地がブームになるなど、若い世代を中心に新しい波も。団地の歴史と未来は日本の戦後を考えることでもあるだろう。
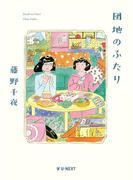
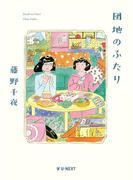


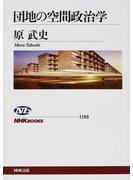
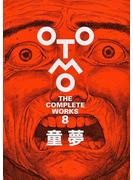
2020年代の「都市」を彷徨するために
- お気に入り
- 24
- 閲覧数
- 2194
自由に出歩くことのできない都市とともに2020年は幕を開けました。これからの都市を、私たちはいかに考えることができるのでしょうか。書をもって再び街を歩く日のために、都市のありかたを考えなおすヒントとなる5冊を紹介します。【選者:仙波希望(せんば・のぞむ:1987-:広島文教大学講師)、平田周(ひらた・しゅう:1981-:南山大学准教授)】
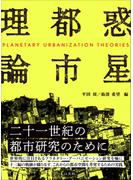
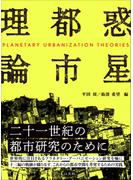




脅威?それとも救世主?AIについて理解を深めるための本
- お気に入り
- 21
- 閲覧数
- 3704
スマホが天気を教えてくれたり、ロボットが掃除をしてくれたり、人工知能(AI)の発達で世の中は便利で快適になってきました。ところが「人工知能の進化は人類の終焉を意味する」と、天才物理学者のホーキング博士はかつて警告しています。AIは人類の脅威なのか、それとも救世主なのか。AIについて理解を深めることができる本を紹介します。
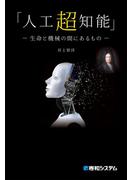
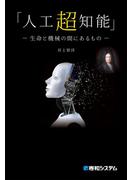

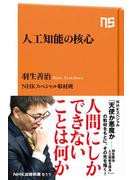

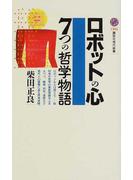
荒川修作+マドリン・ギンズと「意味」の湖を楽しく泳げるようになる5冊
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 38581
「意味」とは何か。「荒川修作+マドリン・ギンズ《意味のメカニズム》全作品127点一挙公開 少し遠くへ行ってみよう」展(セゾン現代美術館にて2023年10月31日まで開催)で出会えるのは、我々が思考のなかで圧倒的な力をもつ言語や論理を超えて、意味の構築を探る実験場。「少し遠く」への補助線となる5冊を紹介します。
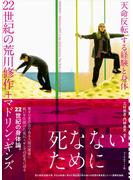
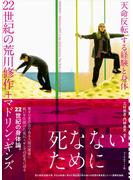

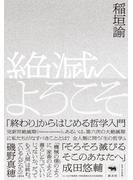
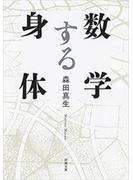
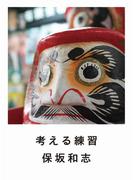
地球環境の保全と持続可能な社会を深く知り、これからの生き方を考える本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 275
プラスチックの削減、脱炭素、SDGsや賢い消費など、近年、環境保全や持続可能な社会の構築に関する報道を目にする機会が増えました。そのうえ、自然災害が年々深刻になり、人々の安心・安全が脅かされています。そのなかで私たちはどのように生き、暮らしていけばよいのでしょうか。希望ある未来への方向性を示してくれる本を紹介します。




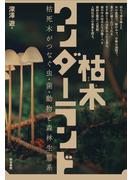

文化財を守る、受け継ぐ、蘇らせる。職人の知恵と最先端の技術を知る本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 414
文化財には仏像や城郭、絵画や工芸品などさまざまなものがありますが、継続的な修理や修繕があってこそ価値が保たれます。こうした文化財の保護に国や自治体が取り組み始めたのは明治以降のことで、時代の変化によってその手法も様変わりしています。昔ながらの職人の技と最先端の技術の融合による新たな文化財保護の世界を覗いてみましょう。





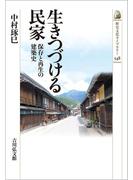
職人の世界を知る本
- お気に入り
- 50
- 閲覧数
- 31003
リモートで十分? AIを活用? そんな昨今の仕事環境と正反対なのが、「職人ワールド」。時代が変わっても、人による手づくりでしか生み出せないものがあります。それは「丁寧」「長持ち」といったワードと親和性が高く、実は今こそ求められているのかもしれません。「職人」「手仕事」に興味のある方に刺さりそうな本を紹介します。
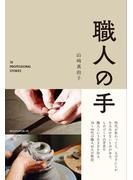
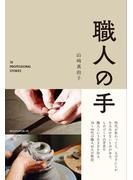
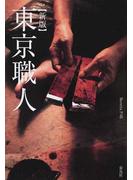
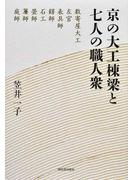


エンジニアでなくても大丈夫!電子工作の基本から実践までを解説した本
- お気に入り
- 11
- 閲覧数
- 1499
電子工作に興味を持っているけれど、専門知識がないことが理由でなかなか挑戦できない・・・という方も多いでしょう。だけど電子工作は、基本を学べばエンジニアでなくても挑戦できます。ここでは、電子工作の基本から実践までを知れる本をピックアップしてみました。回路の基本や必要な準備、部品などを学んで、電子工作にチャレンジしてみてください。
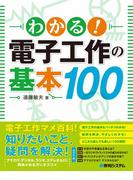
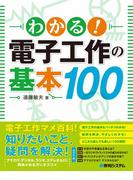


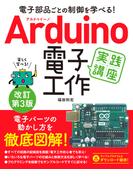

新たなテクノロジーを用いた生活って?近い将来を垣間見ることができる本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 356
近い将来、自分はどのような環境で暮らしているのか?実現直前の段階まで開発が進んでいるテクノロジーに触れつつ、それを用いた生活環境を予想できるようになる本を集めました。これまで普通だと思ってきた暮らしは、未発達の技術によって制限されたものだったのかも・・・。そんな気持ちにさせられる、未来への希望が詰まった本をそろえました。
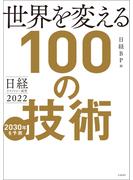
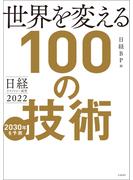


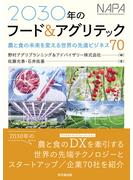
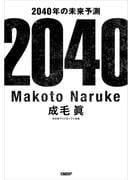
自然災害から身を守る。いざというとき役に立つ防災知識が学べる本
- お気に入り
- 7
- 閲覧数
- 511
地震や津波、洪水や土砂崩れなど、自然災害は毎年繰り返されます。100年に一度といわれる大きな災害も増え、これまで災害のなかった土地や都市部でも大きな被害が出ています。自然災害を完全に封じ込めることは困難、となれば、もしものときに備えることが大切です。自分や家族を守るため、まずは知識を得るところから始めてみませんか?




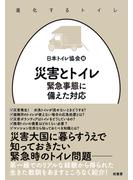

食の未来は明るい!?フードテックが持つ大きな可能性を知ることができる本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 320
ITの活用によってフードテックが発達し、これからの食生活に大きな変化が起ころうとしています。フードテックとはどのような技術で、どのような食材が食べられるようになるのか、気になっている方も多いことでしょう。ここでは、フードテックの秘めたる可能性を知ることができる本をそろえました。


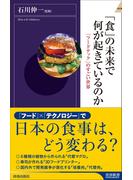
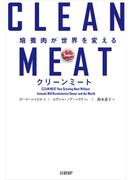
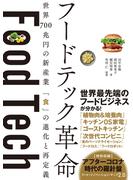

知れば知るほどハマってしまう!建築に興味を持った時に手に取りたい本
- お気に入り
- 8
- 閲覧数
- 574
時代の変化とともに発展してきた建築物は、デザイン性や機能性などさまざまなこだわりが詰まっていて、その魅力はひと言では語り尽くせません。ここでは建築への興味がさらに高まるような本を紹介します。アプローチの仕方によってさまざまな表情を見せてくれる、建築の世界にどっぷり浸ってみてください。




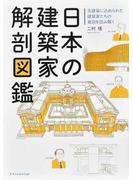
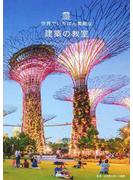
低い食料自給率で大丈夫?日本の農業の現在と未来を知るための本
- お気に入り
- 5
- 閲覧数
- 990
かねてから、日本の食料自給率は低いといわれています。そのうえ農業は「危険、汚い、きつい」と言われ、高齢化と後継者不足が深刻です。この先、温暖化の影響で生産量が減ることも心配されますし、国際紛争などで輸入が止まったら・・・と食への不安は尽きません。生きるために欠かせない食料生産の現在を知り、農業の未来を見つめてみましょう。





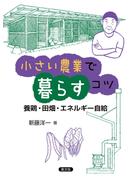
創立100周年を迎える人気校!芝浦工業大学附属中学校で出題された文章
- お気に入り
- 5
- 閲覧数
- 843
同校では、文系と理系の垣根を超えた理工系教育が行われており、教科の枠に収まらずに、今後の日本の科学技術を支える人材を育成しています。同校でしか、受けることの出来ない質の高いSTEAM教育を提供するなど、特色のある教育環境が備わっている事が魅力です。その人気は近年ますます上がってきていると感じます。
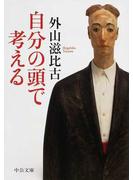
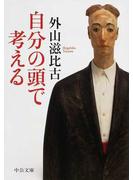
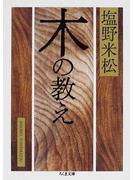
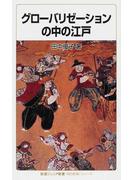
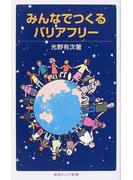

気候運動と現代思想
- お気に入り
- 15
- 閲覧数
- 2605
気候危機への対応は、経済・社会・政治・文化の今日的ありようを支え貫く種々の不公正と不平等の根本的な改革なしではありえない。全世界の多数多様な抵抗の歴史と実践と絡み合い、問題意識を先鋭化させる気候運動に学び、そこから思索する手がかりを与えてくれる著作を紹介する。【選者:箱田徹(はこだ・てつ:1976-:天理大学教員)】
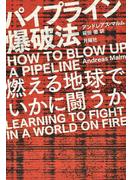
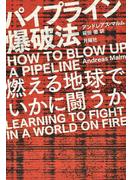

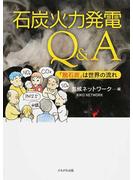
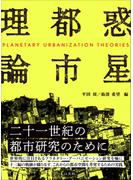

資源・エネルギーの大転換時代を生き残る
- お気に入り
- 12
- 閲覧数
- 806
気候変動問題に対処し持続可能な社会を構築するため、世界はエネルギー転換や循環経済(サーキュラーエコノミー)の構築など、資源・エネルギーの大転換を急ピッチで進めている。こうした歴史的な大転換では何が起こり、その変化に日本がどう対応し生き残るかを展望するための一助となる本を選書。
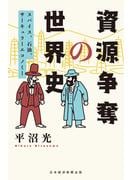
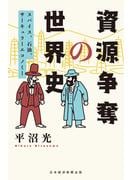
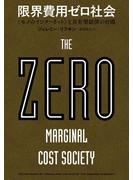
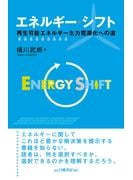
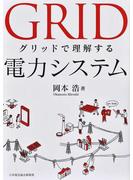

未来を守る新常識!人類のエネルギー事情を学ぶのに役立つ本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 321
私たちが日々お風呂に入ったり、明るい部屋で過ごしたりできるのは、エネルギーがあるおかげ。しかしエネルギーには課題が山積みで、全世界でこの問題の解決に向けた試行錯誤がなされています。そこで、私たちの暮らしに欠かせないエネルギー事情を学べる本をまとめました。エネルギー問題に対する関心を高めて、身近な対策を模索してみましょう。
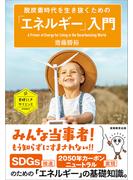
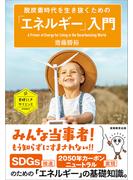


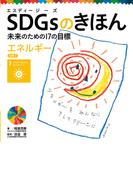
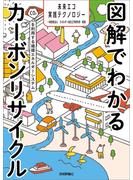
同じ地球のうえで、異なる世界を生きる
- お気に入り
- 32
- 閲覧数
- 13022
世界的に同じであることが求められる社会は、ひとつの病があっという間に全世界に広がる社会でもありました。今回のことで、私はその怖さを知りました。私たちは本来、同じ地球のうえで、人により異なる世界を生きています。それぞれの世界を大切にし、互いを認め合いながら共に生きていく。そんな未来を考えるための本を5冊ご紹介します。


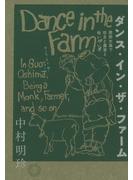
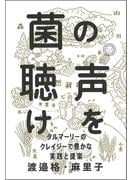
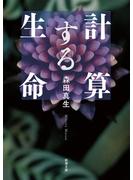
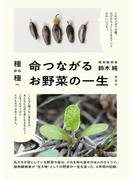
時代を変えるテクノロジー!人工知能について学べる本
- お気に入り
- 9
- 閲覧数
- 373
情報技術の発展は目覚ましく、新たなテクノロジーが次々に生み出されるなかでも、人工知能は私たちの暮らしを格段に便利にする存在です。とはいえ、何が人工知能を指すのかピンとこない方も少なくないはず。そこでここでは、人口知能について学べる良書をピックアップしました。時代を変えるテクノロジーに触れるきっかけにしてください。
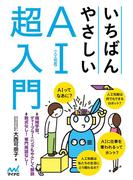
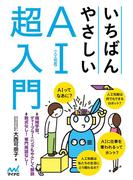
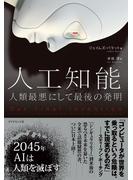

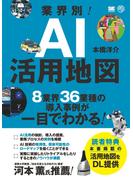

江戸時代の東京を見てみよう!変わり続ける東京を再発見できる古地図の本
- お気に入り
- 14
- 閲覧数
- 863
江戸時代と比べるとずいぶん様変わりした東京ですが、区割りや掘割には当時の計画を今も引き継いでいる場所が多くあります。江戸時代に行われた土地の高低を上手に生かした街づくりや、東京湾の埋め立てによる新たな街の開発などは、現在の都市開発の礎でもあります。古地図を眺めながら、変わり続ける東京の今を再発見してみましょう。
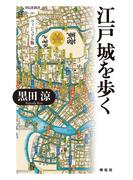
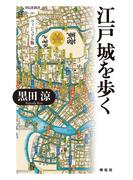


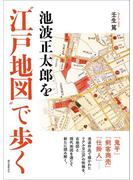
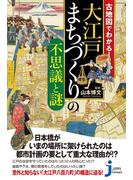
天守や石垣だけが城じゃない!「地味な」城の楽しみかた
- お気に入り
- 28
- 閲覧数
- 13090
城といいますと、白塗りの天守・櫓・塀がそろい、石垣・水堀がめぐらされた「豪華な」近世(江戸時代など)の城が、まずイメージされます。しかし、日本の城のほとんどは、建物がなく土塁・空堀などしか残っていない「地味な」中世(戦国時代など)の城で、近年、注目を集めています。天守や石垣がない城を楽しむための本を中心に紹介します。
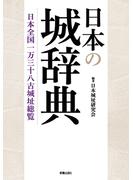
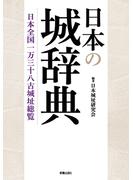
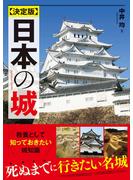
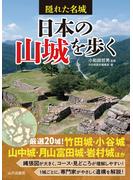
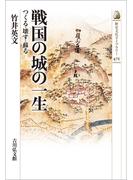
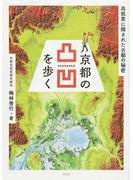
身近だけど目に見えない「電気」の世界を探求できる本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 1139
電気は私たちの暮らしを便利にしてくれるだけでなく、楽しませてくれることもあれば、危険をもたらすこともある不思議な存在です。目に見えず正体がわからないので、知的好奇心を感じる方もいるでしょう。身近にあるのに知らないことの多い電気の世界を、さまざまな観点から探求している本を紹介します。
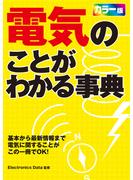
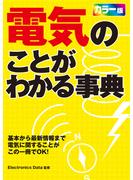
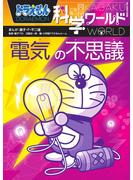


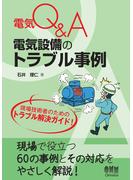
楽しさも苦労も知っておこう!農業に興味が出たらまず読みたい本
- お気に入り
- 6
- 閲覧数
- 4280
最近は若者の新規就農者数も増え、農業ビジネスに可能性を見出す人が増えてきています。しかし、いきなり農業の世界に飛び込むのは不安なもの。ここで紹介するのは農業の魅力はもちろん、イメージとのギャップや苦労まで赤裸々に綴られた「本音の農業本」です。まずは農家のリアルな声に触れてみましょう。
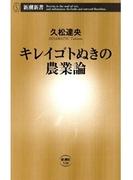
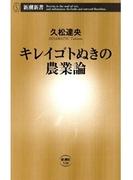
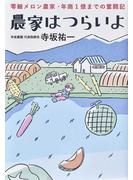
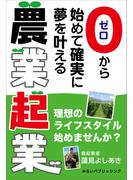
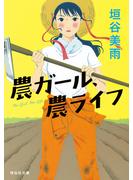
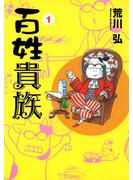
木ってすごい!森と暮らしを考える
- お気に入り
- 15
- 閲覧数
- 2262
映画『かもめ食堂』のロケ地を目指してフィンランドの森を歩いたことがあります。そのとき何とも言えない幸福感と深い心の落ち着きを感じ、森には不思議な力があることを知りました。日本でも、木々と触れ合うことでリフレッシュしている方は多いはず。私たちの暮らしを支え、癒やし、守ってくれる森のこと。もっと知ってみませんか。


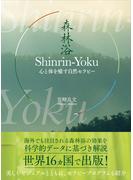
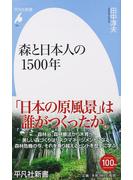

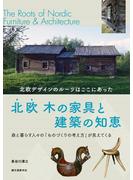
野菜と出会う、野菜を味わう、野菜を作る、にまつわる物語に触れる本
- お気に入り
- 14
- 閲覧数
- 1466
野菜には葉を食べる葉菜、果実を味わう果菜、根を食する根菜、香りや辛みを楽しむ香辛野菜などがあり、街では約200種類もの野菜が売られています。野や山に自生する山菜、食べられる野草も立派な野菜です。リモートワークで料理に目覚めた人、自宅で野菜を育ててみたい人も増えています。これを機に、野菜をもっと身近に感じてみませんか。
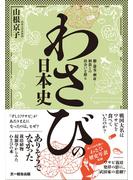
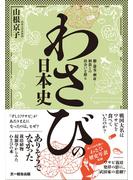

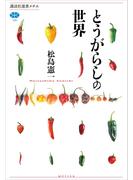
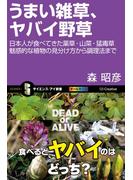

明治日本が生んだ文化遺産。富岡製糸場について楽しく学べる本
- お気に入り
- 3
- 閲覧数
- 665
富岡製糸場は明治時代に設立された官営模範工場であり、日本初の本格的な器械製糸工場です。日本の近代化を支え、絹産業の革新に貢献。ここで技術を習得した工女はその後、国内各地で指導にあたりました。2014年には、日本の近代化遺産として初めて世界遺産に登録されました。そんな富岡製糸場についてわかりやすく学べる本を紹介します。
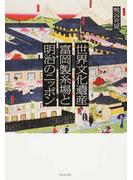
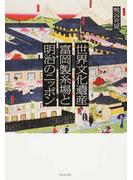
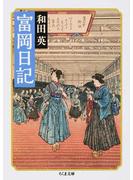
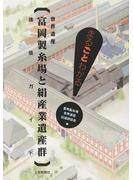
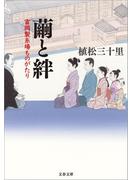
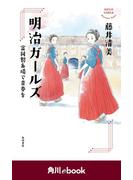
ヴォーリズの遺産をたどる
- お気に入り
- 15
- 閲覧数
- 1581
関西学院校舎、京都・東華菜館、軽井沢教会、東京・山の上ホテルなど、落ち着いた雰囲気をたたえる建築で知られるヴォーリズ。キリスト教伝道の使命を胸にアメリカを発ち、滋賀県近江八幡の簡素な駅にひとり降り立った時、彼は24歳でした。83歳で亡くなるまで、この地に根を下ろし活躍したヴォーリズとは、どんな人だったのでしょうか。
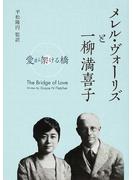
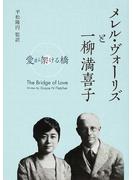

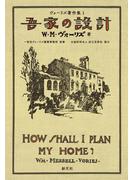
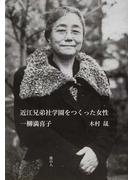
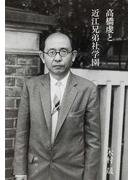
人間の心を理解するために、僕らはAI・ロボットを創る必要があるのか?
- お気に入り
- 24
- 閲覧数
- 3272
「人の心を知りたい!」という疑問は、自分が自分である理由を知りたいという、人間の根源的な欲求です。宇宙の始まりを知ること。生命の誕生を知ること。それらを物理学や生物学が果たしてきたように、人の心の原理を知るのが心理学、認知科学―そして人口知能(AI)とロボティクスなのです。



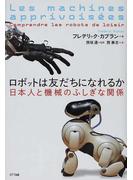

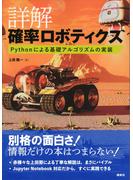
人工知能(AI)/情報/ロボット 知能を創ることでコミュニケーションの理解に近づいていく
- お気に入り
- 15
- 閲覧数
- 2605
コミュニケーションする知能を理解することは、コミュニケーションする知能を生み出すことだ。構成論的アプローチと呼ばれる科学では、創ることによって対象を理解する。僕らはどこまでコミュニケーションする知能を創ることができるのだろうか。






私たちのごく身近でも活躍中!人工知能のことを知るための本
- お気に入り
- 2
- 閲覧数
- 430
パソコンやロボットだけでなく、手のひらサイズのスマートフォンにも備わっていて、今や少し勉強すれば誰でも利用できるものになりつつある人工知能(AI)。仕事中も、街中でも、家庭でも、私たちは人工知能に囲まれて暮らしています。ここでは「RPA」「ディープラーニング」といった、人工知能に関わる話題を取り上げた本を集めました。