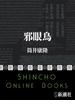レコードの調べに誘われて
2020/07/04 23:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
昭和の歌手の死去から始まる、遺産争奪戦に手に汗握ります。時空の彼方に置き去りにされる3人の子供たちと、静かに待ち続ける未亡人の姿が忘れられません。
ツツイストではない読者を
2002/07/07 05:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あおい - この投稿者のレビュー一覧を見る
近年の筒井康隆氏の読まれ方に僕は非常な疑問を感じている。
いわゆる「ツツイスト」と呼ばれる信者的なファンの盲目的な追従と、例の差別問題から断筆宣言に至る過程での浅田彰氏や金井美恵子氏などからの批判によって、「通俗小説を書いていればよかった」とでもいうようなあからさまな侮蔑に引き裂かれ、個々の作品の善し悪しはまったく等閑視されているように思えるからだ。もっともこれは筒井氏が「巨匠」となった証かもしれないのだが、しかし虚心にその新作を追っていけば、筒井康隆という作家は現在もなお「現役」であって、しかも毎回工夫を凝らし一心に作品を執筆し発表していることはわかるはずである。であるとするならば、やはり一作ごとに読者も作品をもっと気合いを入れて読むべきだと思うのだ。
とはいえ昔星新一が指摘していたように、筒井氏の作品では「狂気」や「錯乱」が重要な主題になることがあるけれども、作品そのものの構造はむしろスタティックであり、不気味すぎるほどの透明さにどこかリリカルな少年っぽさも感じられる作風でもあって、べつに気合いを入れて読むといっても肩肘を張って読むということではまったくない。そうではなくて、筒井氏の作品の、明快な主題や意図を楽しみながら、なおそこに「それ以上のもの」を読むことが出来るか、ということが、ファンならぬ「読者」が筒井康隆の小説を読むときに賭けるものなのだ。
本書は断筆宣言を解除してすぐに発表された中編小説である。派手さはないが筒井健在を知らしめるプラスティックな質感のある幻想小説の佳作で、こういう透明感のあるリリカルな不気味さを書くことが出来る初老の作家が存在することに驚きと感謝を憶えずにはいられない。文庫解説の東浩紀氏の文章は意余って力足らずという風情ではあるものの、よくある内輪誉めからの緊張感のある離脱の意志があって心強い。
投稿元:
レビューを見る
三年に及んだ「断筆」の後、復帰第一作となったのがこの作品。極端に読点を減らした切れ目も改行もない文章の連なりが、一歩進めば時間も場所も変わっているというものすごい緊張感をもたらす。時空も空間も越えて捩れていく家族の過去・現在・未来。裏表紙の紹介文では「ミステリ」という言葉が使われているが、ミステリとしての解決ははなから準備されていない作品だけに、この言葉は不適切かと。哲学研究者・東氏の解説を踏まえて再読したらなおさら興味深かったです。
投稿元:
レビューを見る
断筆解除後の短編二作,「邪眼鳥」と「RPG試案―夫婦遍歴」を収録.非常に端正だが息の長い独特の文体.最初こそ淡々と始まる物語は,だんだんと非現実的・異次元的流れを強くしてゆく.ついには,理不尽な時間感覚のなかで登場人物どうしが奇妙につながりながら,しかし序盤に張られていた伏線が見事に収束していく.再読するほど合点がいって,新たな面白さを発見するという印象.
投稿元:
レビューを見る
断筆宣言後の復帰作。息の長い超絶な文体を追いかけていくと、とつぜん何の前振りもなく時空間が飛び、物語の因果関係も(亡父と子どもたちの関係も)よじれていく。このスリル!
ファミリーロマンス/SFの形を借りた、実験小説の傑作。東浩紀による「邪眼鳥」解説も秀逸です。
「RPG試案―夫婦遍歴」の方は正直よくわからなかった……。
投稿元:
レビューを見る
フザけている。C級の小説。読みにくいうえに構造がわからない。筒井は読者に研究されることを望んでいるのだろうか。でなければフザけているとしかいえない。単なる自己満足に終わっている小説。人に読ませるものではない。
投稿元:
レビューを見る
・7/30 またしても筒井康隆だ.まとめて3冊ぐらい買ってしまったのだからしょうがない.それもたまたまエディプス以外はミステリーだったという偶然.慟哭の影響か.
・7・30 夜中に読了.一気に読破.前衛的な手法と変わった内容に、多少ついていけない部分もある.違和感があるからもう少し慣れが必要かもしれない.これはでもミステリーなのかなぁ.
投稿元:
レビューを見る
筒井さんの本について,私にとって七瀬シリーズから入っているので,「邪眼鳥」はとても難解なミステリー本だと感じました。
顔のあるものがいない・・・・・。大富豪である入谷精一の葬儀から入り,先妻の子供である英作,信子,雅司の三人兄妹弟の話が突然前振りなく時空を超え渾然と入り混じるストーリーは読んでいて難しく感じました。
断筆後の復帰作です。
筒井さんの作品について賛否両論あるようですが,断筆後のものはあまり人気がないような,,。
投稿元:
レビューを見る
死者による生者への呼びかけ、それは生きている人間の側の論理に内包されたものとして現出するといった複雑に入り組んだ構造の中から発せられるものでありながら、それでいて、絶対に到達不可能なもので、そこに到達しようとしたとき、生者の論理は崩壊していく。文体の息の長さは著者の個性である以上に強烈な横断性を意識させるもので、その横断性によって両者が縫合されかつその縫合によって激しい差異と断絶を露にしていく。論理は足元から崩れ始め、世界は入り混じり、不気味な断線を撒き散らす。そしてその断線が回収され得ないことを示唆しつつ、物語は閉じる。
技術的な面で言えば、最高傑作の一つに挙げられてもいいのではないかと思います。推理小説的な仕掛けによって、ラテンアメリカ的な秩序の崩壊感覚まで読者を誘い込んでいく手腕が、純文学的な梱包の中にエンターテイメント性をも高い水準で確立していて、そこにあきれるほどの凄みを感じます。適当に読んでいくと、何を言ってるのかわからないという感覚も強いけれど、その何を言っているかわからない感覚が迷宮に迷い込んだような面白さを伴っている計算高さが、私にはたまらない。
併録されている「RPG試案―夫婦遍歴」も面白いですが、こちらはより即興的な感性で書かれているように思います。使われているのは、回想体としての時間の混乱や非現実の流入、シュルレアリスム的な越境といったところ。それらが文学的に使い古されたモチーフを混ぜ合わされ、無機質でありまた無頓着さまで感じさせる文体はその上を滑ったりはみ出したりしていく。いい加減なのに、奇妙に整合が取れている、その感覚が、その感覚だけで面白い、という感じ。だから、私は即興だと思うんですが。
いずれにせよ、「何だかわからないけれど、すごい」の部分が一番大事で、それが一番面白いところになっている、だからすごい、そういう中篇二本だと思います。個人的には筒井さんの小説の中でも、一番好きなものの一つです。
投稿元:
レビューを見る
難しい。
どこかであらすじを読んでようやく見つけた本。
だが、思っていたのとまるで違う作品だった。
併録されている作品も全く分からない??
投稿元:
レビューを見る
父精一の死を受けて四人の子が父の面影、父への欲望を追い求めて時空をも超えて彷徨うお話。語り手が非常に分かりにくく変化し、そのうえ登場人物たちの時間にズレが生じたりもするのだから、兄弟たちが翻弄されついには亡霊になってしまうことに、読み手である私も妙に共感できた気がした。最終的に亡霊にならずじまいの春子が不気味で、その美貌すらもどこか恐ろしく感じる。私には難解でしっかりと理解できた気はしないけど、面白い作品だった。
投稿元:
レビューを見る
★2.5かな。可もなく不可もなく。
実験作ということのようですが、文字通りあまり読ませることを考えていない気がする。そういう意味で素描を鑑賞しているようなものかと。
投稿元:
レビューを見る
主体が欲望の対象とであうことがないと亡霊になるという発想が面白い。
タイムスリップなどのスリップが、ずれること、接地点をなくすことという解釈も言いえて妙だな