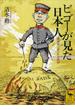明治初期に訪日したフランス人青年画家の目に見えた日本社会が解説されます!
2020/04/07 11:45
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、1882年から17年間にわたり日本に滞在し、その間に我が国の世相を伝える数々の絵を残したフランスの画家であり、漫画家であったジョルジュ・フェルディナン・ビゴーの目から見た文明開化の日本を解説した画期的な一冊です。当時は、封建的な江戸時代から文明開化、殖産興業と一気に近代化の道へと邁進するようになった我が国の刻一刻と変わる社会であり、その変貌をフランス人の青年が克明に絵として記録していきました。同書は、そうした彼の絵の中から100点を厳選し、そこに秘められた日本への愛着とアイロニーを分かりやすく解説してくれる書です。明治初期の我が国の社会を知る貴重な史料です!
当時の風俗を垣間見ることができる興味深いものでした
2023/12/25 17:39
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:キック - この投稿者のレビュー一覧を見る
明治15年に来日し同32年に帰国するまでに書いた3,000点に及ぶ風刺画の中から、著者が精選した100点を掲載。見開き2ページで半分は著者の解説という構成。全て「日本人とは何か」というテーマで貫かれ、当時の風俗を垣間見ることができる興味深いものでした。例えば「ふんどし」。当時は公道をふんどし姿で平気に闊歩。さらに混浴。バストは隠すほどのものではないという江戸時代のおおらかさが、残っていました。ただ拝金主義批判等、進歩的文化人である著者の、ビゴーに仮託した安っぽい現代人批判には辟易しました。
2002/01/20朝刊
2002/01/31 18:16
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:日本経済新聞 - この投稿者のレビュー一覧を見る
明治の日本社会を漫画や挿絵で描いたフランス人画家ビゴーは有名だが、一般に知られている作品は鹿鳴館を風刺した「猿まね」、明治中期の極東政局を描いた「漁夫の利」ぐらいだ。本書はビゴーの作品から百点を選び、当時の西洋人が見た日本人像を分析する。しゃがみ込んでひそひそ話をする大人たち、くどくてこっけいに見えるほどのあいさつ、子どもを背負って踏切の旗振りをする女性など、当時の庶民の日常生活をビゴーは鋭く観察していたことが分かる。
(C) 日本経済新聞社 1997-2001
投稿元:
レビューを見る
明治時代日本で活躍したフランス人画家、ビゴーが描いた風刺漫画100点を紹介したもの。ビゴーの絵は当時の日本をリアルかつシュールに描いてあり、毎度感心する。でも、その風刺画の中には日本人を軽侮する西洋人ビゴーの姿も時折垣間見える。
投稿元:
レビューを見る
歴史の教科書で誰もが一度は見たことがあるはずの、風刺絵を描いていたフランス人画家・ビゴーについての本です。めっちゃ面白い〜〜〜。お勧め!!
第三者たる外国人だからこそその日本独特の不思議さに気づき、かつ記録することが出来た昔の日本人の滑稽な姿。
明治時代の日本を知りたい方はぜひとも。
投稿元:
レビューを見る
リアルな描写で描かれた日本人が醜悪な風貌のため、ショックを受けた。前歯が飛び出ていたり、背が低いのは、栄養が足りなかったためだということがわかったのが個人的に印象に残った。ビゴーが日本人の欧化政策を皮肉り、その近代化が進んでいないことを強調していたのには、日本が不平等条約を改正してしまうと、治外法権が認められなくなって居留外国人である自らが仕事をするのに不利になるからだ、という私情が多分に含まれていたことは、新たな発見で面白かった。
投稿元:
レビューを見る
「ノルマントン号事件」の絵でお馴染み、ジョルジュ・ビゴーの作品100点を厳選し、それについて著者の清水勲氏が解説しています。
ジャポニズムが一斉を風靡した19世紀末期、フランス人画家ビゴーは浮世絵目的に来日するものの、日本の奇妙な魅力にとり憑かれて、日本人の生活を記録していくことに興味が移ります。また、永住を決意し、日本人女性佐野マスと結婚しています。
条約改正により生活不安を感じ、最終的には本国へ戻るものの、彼が日本滞在中に描いた作品はとても面白いです。
外国人ならではの視点で、当時の日本の姿を在りのままに描いています。
ビゴーの絵って本当に味があるなぁ。
ふんどし、混浴、西洋化…当時、フランスから来日したビゴーにとって、相当珍奇に映ったことでしょう。
120年以上経った今見ても、かなり珍奇なので。
諷刺画が有名なので、日本人を常に批判的に見ていると思われがちでしょうが、そこには危惧や示唆が含まれていたのだと思います。
ビゴーは日本が好きだった、それは確実に伝わってきます。
最近、今の日本人の「集団主義」的な面や、「勤勉」な面は何百年も前からの国民性(曖昧な言葉ですが)ではない、という事について勉強する機会があったので、尚更興味深いものでした。
その変化はやはり文明開化の影響によるものが大きいようです。
ビゴー自身、彼が滞在していた20年程の短い間に日本社会は目まぐるしく変化し、だんだんと彼らが金の亡者に変わっていったことを歎き、日本との決別を決めています。
ビゴーのような人が居たことは、日本にとって大きな財産であったのに、惜しいことをしたものです。
日本人の研究、面白いです。次は同著者の「ビゴーが見た明治ニッポンを」読もうと思います。
投稿元:
レビューを見る
絶対歴史の教科書で見たことある、あのイラストたち。
たとえば、ノルマントン号事件のイラスト。
それらを描いたビゴーの本がこれ。
ビゴーのイラストを通して
明治の民俗を知ることができるのが面白い。
発展途上の当時の日本は
外国人の目からはこう見えていたのか、
というのがよくわかる。
当時の日本では普通のことだから
日本人は記録しない。そんなものばかり。
その良い例がぺこぺこ頭を下げ合う日本人。
あとシャツを着て帽子をかぶり、ふんどしを身に着ける日本人。
ビゴーのなかなか見ることのないイラストが
多数収録されているのはうれしいが、
イラスト1枚1枚についている説明が
時々脱線するのがなぁ…と思ったり。
知識をつけるという点ではいいんですけどね。
投稿元:
レビューを見る
一枚一枚の絵を充分に愉しんだ。何とも言えない味わいのある作品ばかりだ。日本人の顔も時代の流れとともに変わってきたことが、過去を遡ることでよく判る。現在の日本人の容姿の特徴は、背が高くなり、顎は細くなり、美男美女が増えたことであろうか。
投稿元:
レビューを見る
日本人が気にも留めない日常のささやかな1コマを、
異国の画家ジョルジュ・ビゴーの目が鮮やかに切り取る。
明治期のありのままの日本人が映る、良資料。
投稿元:
レビューを見る
ビゴーとはジュルジュ・ビゴー、フランス人で明治期に着た漫画・写生画の画家のことで、有名な絵はノルマントン号事件の状況絵や日露対立の状況描いた風刺絵、あるいは選挙の投票風景、鹿鳴館外交の絵などが思い浮かぶが、それ以外にも多くの写生画を残していて、特に生活文化や庶民の生活に関する絵が多い。この書はそれらの多くのビゴーの絵画を解説する著作であり、ビゴーを授業などの教材で使おうという際には大変参考になるし、またビゴーの絵画の「絵解き」の参考になる。あと感じたのは意外と教科書にみられるような絵以上に、教科書に載せられない(掲載されない)様な男女間の諸相を扱ったものが多いというのも本著を観ると分かる。明治社会を一面において考える上で貴重な一冊であると思う。
投稿元:
レビューを見る
教科書で見覚えのあるビゴーの絵を100点選び、明治日本の生活や文化を解説している。当時の、日本人の目線では注目しえないような風俗なども切り取られており、資料としても一級の物だと思う。ビゴーが日本に17年も滞在していたこと、日本人女性と結婚し一児をもうけたことなど、初めて知ることも多かった。
日本におけるビゴーの政治的立場については、あまりにあっさり触れられているため物足りなさもあるが、眺めるだけでも非常に興味深い。女性の描写が美しかった。
(2012.7)
投稿元:
レビューを見る
よく資料集でみるヴィゴーの風刺画。
よくみるやつだけでなく、他のもたくさん見ることができて面白かった。
明治時代、どういう風に日本人がとらええられていたのかがよくわかる。
写真で記録する今では、新鮮に写る記録方法かも。
投稿元:
レビューを見る
中高時代、教科書で見て印象に残った風刺画。
風刺画の解説をしてくれるような本はないかと探していたところ丁度見つけたのがこの本でした。
再読の価値あり
投稿元:
レビューを見る
一度は教科書や資料集で見たことのあるビゴーの絵。本書は明治日本に来日したフランス人画家ビゴーの目を通してみた「日本人」論といっていいかもしれない。
1860年にフランスで生まれ、若くして画才を顕し、12歳で美術学校エコール・デ・ボザールに入学、その後退学し挿絵画家として家計を支える。
1882年にかねてより興味のあった日本に来日。しかし、ビゴーはかつてのフランス画壇の主流であった写実主義に固執し、印象派が主流になりつつあったフランス・日本両画壇に受け入れられることはなかった。ビゴーは仕方なく生計を立てるため、横浜居留地向けの挿絵画や風刺画の画集を売った。
ビゴーはフランス時代には浮世絵に興味を持ち、浮世絵での日本人の生活に魅せられて来日した。しかし、時に日本は欧米に倣えとばかりに近代化へひた走る。ビゴーはその野卑な姿に幻滅し、近代化しようとする日本人の滑稽さを風刺画として描いた。
居留地相手の商売をしていたビゴーとしては、条約改正による内地雑居は死活問題であり、近代化する日本人を風刺することで条約改正は時期尚早としたらしい。
ともかくビゴーが日本人の近代化を風刺してくれたおかげで、より「日本人」の特徴が際立ったりもする(第43図「排便スタイル-鹿鳴館の控えの間にて」・第46図「あいさつ-敬礼と土下座」)。
また、当時の日本人には当然と思えることも外国人ビゴーの目を通せば珍しく、貴重な近世以前の日本人の生活慣習の一端を絵画として残せた事例(第25図「商売-ごろつき」・第27図「商売-漁師」・第31図「フィルター-村いちばんの伊達男」・第32図「ふんどし-股間への送風」など)もある。
一通り本書を読んでみて、日本人の節操のなさとしたたかな感じを絵画で表現したビゴーの観察眼に驚かされた。