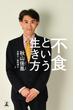不食という生き方
2022/10/30 14:38
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:読書好きな人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルに惹かれて、購入しました。弁護士の著者が、どのようにして、不食になったかが、書かれている。人間は、食べないと死ぬといわれていますので、お金を必死になり、稼いで、食べ物を買うようにしています。私もそうしてきました。この本を読んで考え方が変わりました。人間は食べなくても、生きていけるということがわかりました。著者によると、今、世界中に、不食の人は、10万人ぐらいいるそうです。私も、少しずつ、食事を減らしたいと感じました。実践していきます。ありがとうございました。
食べないことで健康に
2016/08/27 06:46
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者の不食に対するこだわりが感じられる1冊だ。食事に限らずに、自分にとって何がいらないのか何が必要なのか見極めることは大切なのかもしれない。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ハム - この投稿者のレビュー一覧を見る
食べないという健康法。人によっての相性が大きいんじゃないかなとは思いますが、こだわりが強く感じられる一冊。
投稿元:
レビューを見る
新書版の秋山さんの本。書かれていることは今までの本とほぼ同じだけど、要点が簡潔にまとめられているので、とても読みやすいと思う。
「恐れ」が対立の原因、罪悪感を持つことがいかに悪影響を及ぼすかとか、ジェンダーフリーの話とか、この方の言うことは本当にACIMに共通している。
・人間はプラーナの筒のような存在。エネルギーの通り道、パイプです。パイプだから力むと道が滞る。これが「気づまり」。~プラーナを整えるのが波動。~私たちの体を構成する細胞のすべてがこの波動で整えられている。
~肉食という行為は、その動物の悲しみや恐怖という感情が乗った波動を自分の体内に取り込む行為であり、食べるほどにその波動が拡大するのです。
・感情面で飢えているから過食になる。~心の満足感を得るには「やりたいことをやる」のがベスト。体を動かし、人と交流し、考えたりしていると、普通は過食にならない。
・自分が自分であることを否定しなければ、ストレスがたまりません。
投稿元:
レビューを見る
何を食べる、何を食べないではなく不食。
本当に不思議ですがそれで生きられるのだから身体の常識を覆していますね。
弁護士という職業がら人と争うのが仕事のように思われますが著者の秋山さんのスタイルは「争わない」ということ。
これもまた不食同様常識からのパラダイムシフトだと思います。
世の中どんどん変わってきています。
投稿元:
レビューを見る
もう何年もの間、不食をし水さえも必要ないという主張。
プラーナ(気)だけで生きていけるなんて!!
驚きとともに常識なんて人が作ったものなのかもしれないとさえ思ってしまった。
人が食べたくなる時は様々な感情が生じているからだとか。
悲しい、寂しい、暇、つまらない、悩みごとがある時に食べ物を口にしたくなるのだそうだ。
世界には不食の人が増え続けているらしい。
断食やダイエットとは違う不食はまだまだ理解までには至らないがちょっと興味が湧いたので他の本も読んでみたいと思った。
投稿元:
レビューを見る
フォトリーディング&高速リーディング。
大分スピリチュアル系になっているが、不食・小食へのモチベーションは上がった。
投稿元:
レビューを見る
おもしろかった! 持病ゆえに霞を食べて生きていけたらと思ってる私にとっては。
また著者本人が不食だからといって、それを読者に強くお勧めするような内容ではなく、自分はこういう流れで不食にいたったということがたんたんと綴られている印象。しかも半分ほどは生き方について語られている。
体のために食べなければ!と思っている私には肩の力が抜ける良い本だった。
投稿元:
レビューを見る
スピリチュアル・自己啓発要素が強めだったのが予想外。だが不食という著者の実践が本当であれば、それで健康体を保っているというのは一般的な信念体系を覆す興味深い事実である。
また、そうであるならば、科学的でないとなんでも切り捨てる近代的自然観を盲信する姿勢を持つのもいかがなものかと考えさせられる。(かといってスピリチュアルに傾倒する気はないが,そもそもプラセボ効果なのでは?)
そして自分はタレブの反脆弱性を信念としているので、大事なのは何かに対して科学的な理屈があるのかそしてスピリチュアルな理屈があるのかではなくそれがもたらす結果か自分にとって良いのか悪いのかだけだと思う。
投稿元:
レビューを見る
ゼロか百かという極端な思考の割には、中途半端な生き方をしている自分なので、ゼロの意見を読んでみました。
最初に思ったのは、図書館で借りたから良いけれど、この内容の薄さで税別1100円とは、高すぎる本だなぁ…ということ。
食べずに自然界にある「気」を栄養にしているようだけど、気から栄養と摂る方法は、おそらく別の本を読むとか本人の講演会に行かなくてはならないのでしょう。
ただ、白砂糖をゼロにするとか、食事の量を減らし質を観直すとかは、そのとおりだな…と思いました。
後半は、よくある道徳とか宗教的な話でした。
子供でも読みやすい文章で、新書として700円くらいの内容の本でした。
投稿元:
レビューを見る
一概に食べないことが良いとは思いませんが
食べないことで、世の中の見え方も随分違ってくるんだろうな~と想像できます。
投稿元:
レビューを見る
食べるか食べないかだけの話ではなかった。
人生観や哲学的なこと、考え方や生きる姿勢なども気づかされることが多かった。
投稿元:
レビューを見る
〈勉強になったこと〉
・大気中のプラーナだけを食べて生活できる。
・そもそも過食すると①眠くなる②体が重くなり意識が低下③直感、創造力鈍る。
・過食は心の飢え。
・人は昔から飢餓に強く過食に弱い。
・少食を推奨。体に良い。
・人を裁かなければ裁かれない。
・悩みはいかに「他人事のストーリー」という姿勢で聞くと辛くならない。
・過去の自分を認めると楽になる。
・訴訟相手に「ありがとう」「幸福になってほしい」と送り真摯に対応するとそれが返ってくる。対立は波動の低いエネルギー、調和は高次元のエネルギーを生む。お互い譲ればすべて解決する。
・親は子育てのストレスは自分にある。自分自身のメンツを気にしようとする。親は自分の怒りに気づき、裁かず認めることが大事。
・悩みは真面目さに比例し、いいかげんさに反比例する。
・家族は依存、拒絶しない。適度な距離感で。親は過干渉せず 子供を信じる。家族は、肉体の材料をわけてもらった程度。深いつながりはない。前世どこかの船で一緒に乗り合わせた程度。親だから子供だから。。魂レベルで存在しない。