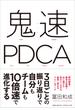こういう本欲しかった
2017/01/24 20:13
7人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:MinkyMami - この投稿者のレビュー一覧を見る
よくデキる方のメルマガやブログを読んでいると、
「自分自身をレベルアップするにはPDCAを回すこと」なんてことを何度か目にしたことがあるので
じゃあ、やってみるかと思ったのですが
枠を描いてみたはいいが、P・D・C・Aの中身を埋めようとしても
なかなかしっくり来ず、そのまま終了。
個人向けのPDCAの本を探してみたものの、これまでは本家の”産業向き”なものばっかりだったのが
ようやく登場してくれました。
PDCAを組み立てるまでの考え方もよく書かれていると思います。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:陽だまり - この投稿者のレビュー一覧を見る
Aがactionではなくadjustという発想がとても好きです。物事が上手くいかないかもしれないことを前提に調整しながら改善していく、当たり前のことですが案外できていないような気がします。
非常に勉強になった
2017/03/08 17:05
3人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:き - この投稿者のレビュー一覧を見る
信頼する先輩方複数人からこの本をオススメされて見てみたが構成や内容共に充実しており非常に良かった
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しば - この投稿者のレビュー一覧を見る
自分でPDCAサイクルを回すときに非常に参考になる教科書的な存在。ただこのやり方を一度にやろうとするとパンクするのでまずはサイクルを回していることを意識する必要がある。そこから一つ一つこの本のエッセンスをくみ取るべきだと思った
PDCAを実践する気を促す本。
2017/10/05 23:00
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mistta - この投稿者のレビュー一覧を見る
PDCAの良さを認めつつも、本格的に実践できない。
そんな私のような人向けの本。
PDCAで挫折してしまう人にありがちなミス、その対策について具体的に処方箋まで
書かれている。
作者の実体験に基づいているので臨場感があり、わかりやすく納得できる。
本書に倣ってPDCAを実践してみよう。
合理的ではあるが…
2019/04/27 18:11
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:sprout - この投稿者のレビュー一覧を見る
最近PDCA、PDCA言われるので、読んでみた。
ここまで細分化しないとPDCAは効果的に回せないんだな、というのはよく分かった。
でもそこまでしなきゃダメ?もっと遊びがないと創造的なものは生まれなくないか?とも思ったり。
なんで絶賛されてるのかな?
2017/09/22 02:19
3人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:マーケちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
仕事上で当たり前のことばかりだったので、何が目新しいのかが全く分からなかった。それだけマーケティングのスキルはバラバラなんだなーってのが分かった。
投稿元:
レビューを見る
鬼速PDCA 2016/10/24
著:冨田和成
著者は、㈱ZUU代表取締役社長兼CEO
2013年「世界中の誰が全力で夢に挑戦できる世界を創る」ことをミッションとして㈱ZUUを設立。金融機関のFinTech推進コンサルティングやデジタルマーケティング支援なども行い、リテール金融のIT化を推進している。
PDCAが「前進を続けるためのフレームワーク」である限り、それを、高速を超える「鬼速」で回し続けることで、会社、部署、そして個人が足つ等的なスピードで成果を出し続けることができる。さらに前進していることを実感することで自信が湧き、モチベーションにドライブがかかり、さらにPDCAが速く回る。これが鬼速PDCAの真髄である。
そんな著者が前職の野村證券時代に作り出した造語である鬼速PDCAについて以下の8章により紹介している。
①前進するフレームワークとしてのPDCA
②計画初級編:ギャップから導き出される計画
③計画応用編:仮説の精度を上げる因数分解
④実行初級編:確実にやり遂げる行動力
⑤実行応用編:鬼速で動くためのタイムマネジメント
⑥検証:正しい計画と実行の上に成り立つ振り返り
⑦調整:検証結果を踏まえた改善と伸長
⑧チームで実践する鬼速PDCA
著者が一貫して訴えている「PDCAこそ最強のビジネススキルである」という点については私自身も全く異論はない。まさしくそのとおりであり、PDCAより役立ちそして奥深いものはない。
PDCAの基本から入り、そして実践を一番の主眼として記されている。
以前からPDCAのAの部分について私自信も違和感があった。
A=ACTIONが通常ではあるものの本書ではA=ADJUST:調整と捉えそのサイクルをくるくる回している。
そしてそのPDCAサイクルも一つのサイクルを回すのではなく、大きなPDCAの中にある課題についてその課題を解決するために新たにPDCAをくるくると回すということを行なっている。そしてそれが連鎖的に連なっていく。
ひとつのPDCAでさえ回すのは困難である中、それを並行していくつも回す。しかし、その全てがリンクしており、難解ではあるものの全てを回して初めて成立するのである。
鬼速を今まで行なってきた著者により記されて本書は血と汗と涙の結晶と言っても過言ではない。PDCA等のフレームワークを活用するのは組織の改善には何よりも大きな力を発揮する。しかし、全てがカチッと当てはまるフレームワークは存在しない。自分で既存のそれをブラッシュアップさせ応用していくしかない。
難しいが成果が出だすとやめられない。
やり遂げる覚悟と使命感を持ち私もやり遂げたい。
そんな勇気を与えてくれる一冊であった。
投稿元:
レビューを見る
「鬼速」というタイトルから推察される通り、内容にも「圧倒的」「必死で」といった意識の高いワードが並ぶが、実態はストイックなPDCAの本。特に適切な調整をするための具体化の手法など、すぐに活かせるヒントも多い。
投稿元:
レビューを見る
コンサル的な仕事術を押さえている人にとっては目新しさはない。が、割と網羅されているので教科書としてはアリかも
検証のフェーズではうまくいかなかった原因だけではなく、うまくいった原因も分析する。うまくいった方法の再現性を見つける。
投稿元:
レビューを見る
P(plan)D(do)C(check)A(action→adjust)はよくわからないと思ってきました。
でもこの本を読んで思ったのは今やってることとそんなに変わらないのかなと。
今も目標に向かってトライアンドエラーは繰り返してます。
PDCAはそれで終わらせずその後に検証を加え目標にアジャストするということかもしれません。
具体的に言うと大目標から小目標に分解してその都度PDCAを回す。
この「PDCAを回す」という言葉がわかりにくいかもしれませんが「目標」を決め「トライアンドエラー」した後「検証」して「目標」や「トライアンドエラー」に「アジャスト」していく。
大目標から小目標に分解するには「マインドマップ」の手法が使えるのかもしれません。
詳細はこの本が詳しくてよくわかるので自己啓発本に行き詰まりを感じてる方に「とりあえずやってみる」手法を学ぶため一読をお勧めしたいです。
僕も一読しましたが再度深堀していきたいと思います。
投稿元:
レビューを見る
PDCAはよく聞く言葉だけど、実際に鬼のようにPDCAを回している人はいない。
やってるとしてもせいぜい、一週間とか月の振り返りだけで。
目標に進むために徹底的にプロセス分解して、それぞれに対してPDCAを回すということはない。この本は徹底的にPDCAをまわすとはどういうことかを説明している「。
1:PLAN
投稿元:
レビューを見る
著者の冨田和成氏は、株式会社ZUUの代表取締役。一橋大から入った野村證券で個人取引で類稀な成果を上げたのち、シンガポールのビジネススクールを経て独立。
感想。
PDCAをメインに扱った仕事術の本。でも僕が読んできた仕事術の本と比べると、非常に血が通ったというか、あ、本当に仕事で実績上げてこられた方というか。ご自身が試行錯誤し、血肉に変えたノウハウを体系立てた本。仕事ってこういうことだ、と共感。
備忘録
・「社会人になってから1日も休まず、やり続けてきただけです」
・PDCAのAはAction(改善)よりも、Adjust(調整)の方がしっくりくる。
・Planではゴールの定量化がポイント。期日設定も含め。期日設定は、1〜3ヶ月程度後くらいが理想。それより長いと課題が増えすぎる。
・ノミの実験。限界とは本人の思い込みにすぎないことが多い。他にやり方はないか?を自問自答すべし。
・MECEは最初の因数分解まで。それ以降もMECEを重視すると効率や精度の点でイマイチ。
・解決策→DO→ToDoの階層の違いを意識せよ。ToDoは実行時に迷わないレベルまで因数分解された行動であるべし。
・Check時にできてないと落ち込むよね。終わらなくても良いと割り切ろう。但し、それは優先順位の高い仕事から手をつけられていることが前提。
・タスクを捨てるためにはまず棚卸しから。
・課題が多いことはダメ社員の烙印ではない。課題に直面することを喜べ。課題解決=前進、成長。
投稿元:
レビューを見る
土井先生のオススメ
no3
p72〜
6フィンテックのベンチャー企業
7 ZUUオンライン
22 お客様はPDCAを回してくれる営業マンを求めるようになったのだ
→激しく共感
28 本の序章として、構成が上手。
『簡単だと思っている。』
編集会議の内容
32 PDCAの5割は計画で決まる
33 うまくいった原因も分析する
→ やっぱり。
44 不安を頂いたまま全力で向き合うことは、なかなか難しい。
55 実行するときは自信満々で。検証するときは疑心暗鬼で。
→ヒントを頂いた
56 調整項目
60 もう少し様子を見よう、というお決まりの文句
→こういうリーダーがいる組織は、PDCAが回りにくい
69 経営者や管理職は、社員や部下の定性的な側面(内面のメンタル、モチベーション)をムゲに扱ってはいけない
70 課題のための検討項目
投稿元:
レビューを見る
p48
「PDCAサイクルを回し続けている限り、その対象がなんであろうとゴールに到達するまでかならず前に進む。」
→
p112
「要因を見つける時は「なぜ(できないのか?/できたのか?)」を繰り返し、課題や解決策を見つける時は「どうやって(構成されているのか?/達成するのか?)」の問いをすればいい。」
→この切り分けはわかりやすいし、納得。
![]() 投稿者:き - この投稿者のレビュー一覧を見る
投稿者:き - この投稿者のレビュー一覧を見る![]() 投稿者:マーケちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
投稿者:マーケちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る