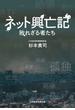当時何が起こっていたかがよくわかる!
2023/03/13 16:28
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:MACHIDA - この投稿者のレビュー一覧を見る
丹念な取材で描く現在にも続くインターネット黎明期の群雄割拠の物語。90年代後半から2000年代にかけて登場人物たちと遭遇したりすれ違ったりしてきたとも思われ、当時を振り返ってある種の感慨や懐かしさも...... とはいえこれらの出来事はほんの一時代前のことで、藤田、堀江、出澤他まだ50歳前後のバリバリの現役経営者も多い(三木谷、宇野、熊谷などは少し上の世代だが)。イノベーションを背景に展開した今にも続くビジネス三国志であり、分厚い書籍ながら飽きずに読める好著。10年後にはその後の歴史での続編も望みたい。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:わんわん - この投稿者のレビュー一覧を見る
インターネットが普及し始めた頃に大学生、その後ブランクがあり、気がつけば携帯は当たり前の時代になっていた。その意味で、ここに出てきたものは、ほとんど知らない。その分、日本でどうやってここまで普及したのか知るには絶好の1冊だった。
反省点は、やはりこの手の書籍は紙媒体でないと、もの凄く読みにくい。じっくり読むには電子書籍は向かない。
ITバブル期から現在に至るまでのIT群像劇
2020/10/01 22:28
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:もちお - この投稿者のレビュー一覧を見る
日経新聞オンライン版と日経産業新聞の連載を書籍化。90年代のyahoo japan、IIJ、i modeから、line、メルカリに至るまでIT企業創業期の物語を合計757ページで語る1冊。本を手に取るとボリュームがすごいことになっているが、どの章も面白く、よくできた企業小説のように、それぞれの人物が有機的に違う人物に絡んでいくあたり、そして、これらの人たちの大半が最前線にいる点もすごい。連載時も驚いたことだが、docomoとgoogleがスマホ開発で提携する可能性があったが、すでに官僚組織化したdocomoではもたもたと意思決定できずにandroidはgoogleの独自開発となったのは周知の事実と日本放送の子会社化に失敗したライブドアが次のターゲットをソニーにして、スマホを作ろうとした点である。
この本に出てくる人たちを虚構と言いたくなりがちであるが、工業品かサービスかの違いはあれども、戦後の起業家と同様、自分たちを信じて必死になっていいものを目指し、我々の生活を豊かにしたのは間違いないと改めて敬意を持つようになる。
投稿元:
レビューを見る
インターネット老人会のメンバーとして、私も酒に酔うと「最近の若い奴らはブラクラを踏んだことがないからダメだ。インターネットっていうのはそういう危険な場所で”素人にはお薦めできなかった”もんだ」とか、「1枚のXX画像をダウソロードするのに当時は5分くらいかかった」と語ってしまう癖があったりなかったりするわけだが、本書はそんな老人会の方々を始め多くの人に読んでもらいたいノンフィクションである。
舞台は日本のネットビジネス。ライブドア、サイバーエージェント、ヤフー、NTTドコモのiモード、LINE、メルカリ、GMOインターネット、USENといった日本のネットビジネスを代表をする企業を対象に、日経電子版の専用コンテンツとして連載された特集記事を大幅に加筆修正してまとめられたのが本書である。
部分的に見聞きしていた話であっても、実は真相がこんなことになっていたのかという驚きが多数。特にネイバー、ハンゲーム、ライブドアの3社のメンバーがそれぞれの事業の失敗を元に結集していき、LINEというアプリを成功させるまでのストーリーは胸熱。
投稿元:
レビューを見る
長い。
ノンフィクションものとして読むと現在の状況にもリンクしているので面白いと思う。
ホリエモンの話に長くページを割いており、それに準ずる濃い話が載っているとおもう。
1番かわいそーやなーと思ったのは宇野さん。
投稿元:
レビューを見る
・控えめに言って、かなり面白かった。個人的な年間ランキングで上位に来る。ミスミ三枝さんの会社改造とかと似た感じ。脚色を差し引いても、生の声が聞こえてくる。
・CA藤田さん、UNEXT宇野さんらの苦労話は、なんというか、底知れない感じがする。それがこの15年~20年くらいの話と考えると、その時代にインターネットにすでに触れてる自分との距離感を知り、変な臨場感がある。
・メルカリ山田さんの話まで入っており、比較的最近のテーマまで触れられていること、お恥ずかしながら、ヤフーサトカンさんなど、全然知らなかった。この辺のことに普段それほど興味がない一インターネットリーマンの自分みたいな人からすると、バラバラに存在する業界のスゴイ人が、あっちこっちでつながって切磋琢磨して今を作ってきたんだなあという気持ちで、インターネッツをより好きになれるのではないか。
・GAFAネタがほとんどなく、日本に閉じて話が展開されているのも、逆に良かった。
投稿元:
レビューを見る
皆さんがおっしゃるように、
胸が熱くなる内容でした。
自分も彼らと同世代で、
同じようにインターネットの黎明期に生きていたのに、
なーんにも関わる事がなかった自分の人生に、
とてつもない勿体なさを感じます。
が、ここに登場した人たちの中で、
まだ最前線で活躍されている方がたくさんいる事実に、
自分もまだまだやれる事があるはずと、
前向きにもなれる、
そんな内容でした。
投稿元:
レビューを見る
非常によく取材されていて、ネット社会で起こった出来事の裏側を知ることができ、大変興味深く読むことができた。
投稿元:
レビューを見る
サイバー、mixi、Yahoo、AmazonみたいなイケイケITベンチャーたちがどうやって日本で発展し、戦ってきたのかが楽しく描かれている。めちゃくちゃ学びがあるわけじゃないけど、小説感覚で読めて、登場人物ほぼ全員かっこいいからモチベ上がるしなかなか楽しい。やっぱコミュニティって激アツだなと。
とりあえずここで出てきた企業のことは基本好きになりました。あとなんかドラマ化もしてるらしい、あんま見る気はないけど。
投稿元:
レビューを見る
それなりのリターンを得るには、相応のリスクが必要と誰もがわかっているが、行動となると、なかなか難しい。
ここに出でくる起業家たちは、リスク以上の熱い思いが感じられる。本人たちは、本当に楽しんで仕事をしているようで、ある意味うらやましい。
チャップリンの言う、人生とは、勇気と想像、そしてちょっとのお金があれば、幸せになれるという言葉を思い出した。
投稿元:
レビューを見る
日本のネット企業の興亡が最初期から網羅されていて、非常に興味深く読める。
早くからネットの可能性に気づき、それに全てを注ぎ込んだ人達が今のネットの業界を形作って来た事が分かる。そして、多くの人が助け合い、刺激しあってネットが盛り上がって来たことも。
自分にもその可能性があったのか?、いや、自分の可能性を信じられる人だけが到達できるのだろう。
投稿元:
レビューを見る
日本経済新聞の編集委員である著者が今世界の中心にいるインターネットのサービスを展開する企業の経営にまつわる悲喜こもごもを丹念な取材に基づいて書いた一冊。
90年代のiモードやYahoo!、00年代のサイバーエージェントやライブドア、10年代にスマホの普及と共に躍進するFacebookやLINEやメルカリといった今や誰もが使うサービスの誕生や経営危機などの紆余曲折を本書で知ることができました。
多著で知っていた話の裏側やネットの普及に向けて覇権が次々に入れ替わる様を知り、ここ30年で生活に欠かせないものとなるまでの人間模様や紆余曲折を肌身で感じることができました。
私たちが普段使っているサービスがネットで天下を取るため渦巻く野心、情熱、戦略などの末に届いていることやAmazonやGoogle、Facebookなど外資発の企業を日本で普及させようとした裏側なども知ることができました。
そんな本書の中でもYahooの川邉氏と佐藤氏の最後の会話やトヨタ現社長の豊田章男氏が楽天の初期から出店して黎明期にネットの可能性を感じてたことや世間を賑わせていたライブドア事件の真相や内部での出来事などは印象に残りました。
どのサービスも当初はうまくいかず、決して順風満帆にここまで来ていないということを感じると共に個性的なメンバーがそれぞれの能力を活かし、化学反応を起こして飛躍的にヒットしていくまでの流れも知ることができました。
そして、表向きは華やかに見えているネットの世界でパソコンからスマホへとデバイスが変わる中生き残った者去った者がいることやネットが生み出した革新的なサービスの裏にある人間模様を知ることのできた重厚な一冊でした。
投稿元:
レビューを見る
1990年代後半から2000年代にかけての日本では失われた10年と呼ばれたその時期に現在我々の生活にかかせないIT産業の名だたる企業群、そして2020年代には当たり前となったサービスが若き起業家たちによって生み出されていました。
本書ではかつて異端と呼ばれた若き起業家たちの壮大な起業物語が総合的に読める一大エンターテイメントストーリーです。日本は何も失われてもいないし、いつの時代も挑戦者、そして敗れざる者たちによって歴史は前に進んでいるんだと感じられる一冊です。
投稿元:
レビューを見る
春秋戦国時代を思い出す興亡記。
スモールスタートでビジネスを始め、大きくなるにつれて株式譲渡やM&Aなど法人格をどうブロックしていくか異なるゲームが始まる感じが面白かったです。というかこの時代の人もほとんど全員繋がっている。外出ることが自身にとって財産になる典型例だと思う。
投稿元:
レビューを見る
取り上げられる人物の一部については、その自著などであらましとしては触れてはいたものの
時代の移り変わりの迅速さと、それが今日にまで及ぼす影響とを鑑みながら
読み物として優れた魅力を持つ、濃縮された時代性を感じる一つのクロニクルとして題材と筆力がマッチしている。