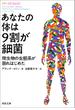「21世紀病」 防ぐには どうすれば
2024/12/21 21:40
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:清高 - この投稿者のレビュー一覧を見る
1.内容
いわゆる先進国において、自閉症、過敏性腸症候群、うつ病、肥満と、「21世紀病」と言えるような心身の異常が生じている。これらの心身の異常は、いわゆる発展途上国には少ないが、なぜだろうか。コリン,アランナが、疫学的な方法で調べたところ、抗生物質が関わっているようだ。抗生物質そのものは悪くない。細菌性の病気を治すのに多大な貢献をしている。しかし、それによって腸内微生物の割合が崩れると別の心身の異常が起こるようである。また、抗生物質は人間にのみならず、家畜にも用いられている(抗生物質を用いると成長が著しくなる。人間も同じ。だから肥満の人が増える)。このような抗生物質の過剰使用の弊害をなくすにはどうすればいいかも考察しており、抗生物質の過剰投与は控え(ウイルスが原因の病気には効かないうえ、耐性菌ができるから)、赤ちゃんは可能な限り母乳で育て(WHOの勧告も書いてある。6か月は母乳で育てるべきだそうだ)、植物を現在より多く摂取して食物繊維をとるようにすべきであることなどが書かれている。
2.評価
筆者は、既にテレビで、糞便移植だとか、食物繊維を多く摂取せよといった内容を観ているが、その根拠が詳しく書かれている本だと言える。腸内微生物の割合を正すためには健全な割合の人の腸内微生物を移植するのと献血との比較もあり、筆者は感心した。食物繊維を摂取することで短鎖脂肪酸を増やすことの理由も書かれており、テレビで得た知識がさらに深まった。筆者の現在においては食物繊維の摂取を増やすために植物を食べるくらいしか役に立ちそうな知識はないが、出産についてどうすべきかも書かれており、個人や社会が考えるべきことも分かり(おそらく、女性の育休は長くないとまずい。母乳で育てられないと「21世紀病」のリスクが高まるから)、それも良かった。以上の通りであるから、5点とする。
体内という、もうひとつの世界
2022/04/22 22:00
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:hachiroeto - この投稿者のレビュー一覧を見る
人体内部の「細菌」を主人公とした一冊。人間の体質や行動、病気を決めているのは、DNAよりむしろ共生する細菌たちだった、というショッキングな内容だが、大変面白く読めた。
中でも一番びっくりしたのは、自閉症をめぐるケース。耳の感染症を治すための抗生物質の投与が腸内細菌のバランスを乱し、神経毒素を発生させる破傷風菌が体内で増殖したため、自閉症が「発症」したという。そして、適切な抗生物質の投与で破傷風菌を退治したところ、自閉症の症状が全快したというから驚きだ。
出産をめぐるエピソードも意味深。赤ちゃんは産道を通り抜ける間に、母親から微生物の「プレゼント」を受け取る。また、母乳もさまざまな細菌が含まれていて、赤ちゃんの健全な体内環境を作り上げるという。では、帝王切開で生まれたり、粉ミルクで育てられた赤ちゃんは大丈夫なのか? 気になる方は、ぜひ本書を。
投稿元:
レビューを見る
この本が私に教えてくれたことは2つ。
1. 遺伝子調査だけでは人間含む人間を理解できない理由と事例
2. 細菌と付き合うための教養
とても丁寧解説されていて、読みやすい。価格も情報量に対してお手頃。
概要だけ知りたい人には詳細だと思う。生物学に対する踏み込んだ知識欲は必須!
読者層の制限はないと思うけど、バクテリアと人間を構成する細胞の知識はあった方が面白く読めると思います!
投稿元:
レビューを見る
この本は、「人間はほぼ細菌で出来ている❕」という衝撃の内容です。
細菌は、人間の体調だけでなく精神状態や脳にも影響を与えるらしいです。
恐るべし!細菌!!
「便の移植の勧め❕」など、なかなか濃い内容です(笑)
ぜひぜひ読んでみてください
投稿元:
レビューを見る
健康と美容に興味がある人は必読の1冊。
健康と美容については、本によって書いてあることがバラバラなことが多く、混乱していた。けれど、この本は人間の根本的なことに追求しているので、迷うことなく、面白く読めた。
投稿元:
レビューを見る
日本では10年くらい前に「もやしもん」という漫画が流行し、わたしたちの体には無数の微生物が存在しするという細菌叢という概念の普及に大きく貢献しました。皮膚には常在菌がいて、普段は外界の細菌を排除している一方で、免疫力低下の際には猛威を振るうという日和見感染という言葉も知られています。しかし、本書のタイトルのように「9割が細菌」といわれたら顔をしかめる人も多いでしょう。この9割というのはもちろん重量ではなく細胞数ということなのでしょうが。
本書を読めば、多くの生物が微生物と共生関係にあり、場合によっては糞を子に食べさせることで微生物環境を受け渡すこともあるようです。人間も例外ではなく、妊娠時に特定の菌が膣に集合し、産道を通る際に引き継がれたり、母乳から引き継いだりと、その無意識下で行われるシステムには長い年月をかけた共進化の関係性がみてとれます。欧米的な食習慣、抗生物質の使用はその摂理と逆行しており、リスクとメリットを天秤にかけながら使用すべきだ、と著者はいいます。
さて、微生物が脳に与える影響を考えたことがあるでしょうか?最近では腸ー脳連関(gut-brain axis)という言葉が出てきていますが、その一端を担っているのが腸内微生物。彼らは例えば好みの食べ物が腸へやってきたとき、それを代謝して宿主であるわたしたちに多幸感を感じさせるような物質を放出します。すると、わたしたちはまたその食物=微生物の餌を食べてしまう。つまり、わたしたちの好みが操られているのです。
もちろん、それだけではなく、様々な要因があるでしょうが、ある種精神に影響を与えるている証拠が上がってきつつあり、今後の研究に期待が持たれますが、わたしのような性別違和というのはどうか?とふと疑問に思いました。これまで遺伝子検査で、影響のある遺伝子群はあるが、これがあれば性別違和が現れるという責任遺伝子は発見されていません。むしろ性というのはスペクトラムだということになっています。もし、微生物がわたしたちの性の感覚にまで影響しているということがあれば……それを知るのは怖いような気もしますね。
本書の結論はある種の「健康増進指南」ではあるのですが、それらはデータに裏付けられており、議論が分かれる点は分けて明示してあるところが好感を持てます。また、流れるような文章、構成、きれいな読みやすい訳に著者と訳者の力量を感じる素晴らしい一冊になっています。
投稿元:
レビューを見る
10% HUMAN: How Your Body's Microbes Hold the Key to Health and Happiness
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309253527/
投稿元:
レビューを見る
おもしろかったし、とても勉強になった。
食物繊維をしっかりとろう。
あとボディーソープはあんまり使わなくてもいいかも。
投稿元:
レビューを見る
もっと早く読みたかった。必読書認定!
腸内細菌の組成、抗生物質のこと、食物繊維のこと、帝王切開と粉ミルク。
目から鱗落ちた。食生活見直そう。
投稿元:
レビューを見る
私たちの頭は、自分の体が自分だけでできていると考えているが、実は腸管内だけでも100兆個の微生物が存在し、我々と共生している。私たちは一生の間にアフリカゾウ5頭分の微生物の宿主になっているのだ。
そして私たちは遺伝子のことばかり気にしているが、私たちの9割が微生物でできているとすれば、その微生物が変化すれば、私たちも変化することになる。21世紀の病気は、感染症よりもアレルギーや肥満や糖尿病だが、それも微生物の変化が影響している。
とても良い本であった。
投稿元:
レビューを見る
著者 アランナ・コリン、イギリスのサイエンスライター
熱帯雨林にてコウモリを研究中ダニに噛まれ病原菌性の病に。治療のために用いた抗生物質により生じた身体の異常は腸内細菌の変化ではないかという思いと、研究観察から細菌と人間との関係性を追求する。
本書英語名は「10%HUMAN」、そのタイトル通り人体を成す90%が1000兆の微生物。微生物と人は共に進化してきたが、人が腸内細菌を見捨て、肥満や糖尿病を代表に21世紀病が蔓延、普通化してしまっていることに警鐘を鳴らす。
・虫垂は、人体が用意した微生物の隠れ家
・ニキビ、肥満、うつ病、セリアック病、過敏性腸症候群、虫垂炎、癌、、、
・糞便の重量の75%は細菌
・1.5キロ分の細菌が常にいる
・約4000種
・ニワムシクイ(渡り鳥)
6500キロの渡りに出る前に体重を増やす(人にして63キロ→140キロ相当に)。越冬地に着いたことには元の体重に戻っている。しかし、野生のニワムシクイが渡りに備へ太る頃にカゴの中のニワムシクイも肥満体型となり、渡りが終わる時期に元の体重へと戻る。
→摂取したカロリー以上を蓄え、カロリー以上の燃焼をさせることが自然と出来る。「カロリーイン、カロリーアウト法則があてはまらない」
・親友が肥満になるとその人も肥満リスクが171%に跳ね上がる
・過食と運動不足だけで肥満になるわけではない
・トキソプラズマ
猫からネズミに感染。トキソプラズマは猫に戻るために猫にネズミに捕まりやすい行動をとらせる。人間にトキソプラズマが感染すると性格が変わったり注意散漫な性質に。感染者は事故を起こす確率が3〜4倍と高い数値を示す
・家畜への成長促進剤(抗生物質)
投稿元:
レビューを見る
事例がどれも秀逸で、納得しながら読み進められる。
微生物の視点で自分の身体や生活習慣を考えることになる。普段の自分の行動や思考を、自然と客観的にとらえて微生物との関係性、影響を想像している自分がいる。
投稿元:
レビューを見る
事実と著者の仮定が混ざった感じで展開されていくので、読み辛さはあったが面白かった
微生物の影響
腸内の微生物の影響
肥満などの成人病
肥満のラットに痩せ型のラットの腸内細菌を移植すると太る
肥満は摂取カロリーだけでなくカロリー消費、貯蔵の影響も受ける
心の疾患
腸内バランスで回復する場合もあるが脳などの臓器に影響受けた場合は回復不可の場合もある
アレルギー症状
抗生物質
共生微生物も排除する
空白部分に悪性微生物が定着すると人体にも影響受ける
細菌にしか効かないのに処方される場合もあるので注意
食べ物
人体には直接有益でなくても共生微生物には有益なものもある
食べ物によって腸内微生物生態系が変わることも
母親からの継承
自然分娩、母乳は母親の共済微生物を継承する手段となっている可能性
生態系の修復
食事での微生物摂取
人体内の微生物数に対して摂取数が少なすぎるので効果なさそう
ふん便での摂取
良い共生微生物生態系を取得できる可能性あり
ドナーの健康状態、心理状態などに影響を受ける可能性はある
アメリカではドナー管理などもされ始めている
内視鏡カメラを使った腸への直接摂取
投稿元:
レビューを見る
副題、微生物の生態系が崩れ始めた。微生物研究の成果は、人の生活の何を変えていくのか。10% Human. How Your Body’s Microbes hold the key to Health and happiness.という原題なので、訳し方が全く逆になっているというのがポイントで、おそらく訳を見るかぎり、やや誤訳なのかもしれない。原書の方を読んでみたくなった。おそらく原書の作者は、(まだ原書を読んでいないけれど)、微生物こそが、10%しかない我々が認識している体、にとって最も大事な存在であって、性格や健康を左右する存在であるということなんだと思う。
100兆以上の微生物が暮らす人の体内。ダイエットも、代謝がいいとか、そんなことは関係なく、また摂取カロリー引く使用カロリーという単純な話でもない。その間に、微生物の役割が多く関与している。太りやすいというのは現代病であり、すでに普通ではない。ではなぜ、こうした普通ではない状態になるのか。抗生物質が、それかもしれないと。世紀を跨げば、致死に恐怖する伝染病などが人口を減らしてきたが、現代はまさにこうした微生物の役割がまた新たにあるということなのかもしれない。コロナがまさにそうなんだろうと思わされた。筆者から言わせれば、キスという行為さえも、将来生まれるかもしれない子供のための事前の微生物チェックの役割だと。微生物を交換するのは非常に危険だからだ。トキソプラズマがうつを併発するとか、微生物が性格まで決めていくというのも非常に面白い着眼点に感じた。マイクロバイオータが、人から人へ移るとすると、ハピネス系の微生物を移せる。または逆もだ。国を滅ぼすこともできるかもしれない。ただ、注意しないといけないのは、微生物も生存のために、繁栄のために人間に住まうだけであって、その戦略は決して親人間であるとは限らないことだ。
抗生物質の過剰な処方を止める、焦らずゆっくりと食物繊維をしっかり摂れる加工食品を減らした食生活に変更する、そして子供のことを微生物の観点からも考える。
投稿元:
レビューを見る
この本を読んでから食生活に対する意識が大きく変わりました。育児をしている方は読むと良いと思います。個人的に糞便移植には全く抵抗を感じないので、体質が変えられるならぜひやりたい。研究が進むのが楽しみです。もし自閉症が治せるようになったら、救われる人はたくさんいると思う。