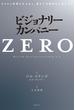2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しゅうろう - この投稿者のレビュー一覧を見る
「P46 勇気とは恐れを感じないことではなく、恐れを感じながらも行動する能力だ。」という言葉もあり、仕事の取り組み方、思いの持ち方の内容を教えてくれる本。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
色々と名言らしきことばが沢山出てきました。例えば、決定的なタイミングに全てを捨てて飛び込まなければ、夢を実現できる可能性は低いどころかゼロになる、たしかにねえ……これ。役立ちそう。じっくり読み返します
投稿元:
レビューを見る
経営者や起業家ではない、単なるひとりの会社員として読んでみて刺さったのは「何をするかではなく、何者であるか」だった。
企業の中にいると会社の方針を達成するために、アクションアイテムを決めて、担当者を決める、というように、今までのやり方だと「仕事」に「人」を当てはめてしまっている。
ある最高のプロジェクトがあっても二流の人がやる場合は結果も平凡になるが、二流のプロジェクトでも最高の人がやれば結果は最高になる可能性がある。
ひとりの人は何が持ち味か、その人を活かすには何をやるか、というように、「人」から「仕事」を考えられるようになりたい。
投稿元:
レビューを見る
世界1000万部超ベストセラーシリーズ『ビジョナリー・カンパニー』の原点で最新刊!
本書『ビジョナリー・カンパニーZERO』は、『ビジョナリー・カンパニー』シリーズが発行される前の1992年にジム・コリンズが記し、日本語訳されずにいた名著『Beyond Entrepreneurship』の改訂版。まさに、ビジョナリー・カンパニーの原点だ。
◆リード・ヘイスティングスNETFLIX共同創業者兼CEOも大絶賛!
「本書は誰よりもどの本よりも、私のリーダシップを一変させてくれた。10年以上この本を読み返した。起業家なら、86ページ分を暗記せよ」
◆スタートアップや中小企業が「偉大な企業」になるために必要なことを解説
偉大で永続的な企業になるために必要ことを1冊に凝縮してまとめた。誰と一緒に仕事をするか、リーダーシップ・スタイル、戦略、戦術をどうつくるか、パーパスやミッションなどをどう決めて実行するか重要になる。「偉大な企業」とそうでない企業との違い、規模が小さいうちから考えておくべきことなど、時代を超えて重要な内容が理解できる。
◆ジム・コリンズとビル・ラジアーの教えの例
・偉大な企業という目的地があるわけではない。ひたすら成長と改善を積み重ねていく、長く困難で苦しい道のりだ。高みに上り詰めると、新たな課題、リスク、冒険、さらに高い基準を探す。
・企業が追跡すべきもっとも重要な指標は、売上高や利益、資本収益率やキャッシュフローではない。バスの重要な座席のうち、そこにふさわしい人材で埋まっている割合だ。適切な人材を確保できるかにすべてがかかっている。
・起業家の成功は基本的に「何をするか」ではなく「何者であるか」によって決まる。
・真のリーダーシップとは、従わない自由があるにもかかわらず、人が付いてくることだ。
・重要ポストにいる人物を交代させると決めたら、「厳格であれ、非情になるな」と自らに言い聞かせてほしい。勇気と人情味を併せもつことが必要だ。
・失敗についてどう考えるべきか。成功というコインの裏面は失敗ではなく、成長だという考えに至った。
投稿元:
レビューを見る
価値観をもとに明確な強いビジョンを掲げる。
そのビジョンに心から共感して付いてきてくれる仲間に敬意を払いながら、リーダーシップを発揮する。
このビジョンが、ミッション、戦略、戦術へと落とし込めれば、偉大な企業へとなれる。
投稿元:
レビューを見る
「ビジョナリー・カンパニー」シリーズで知られる著者が、その原点ともいえる92年の著作を「ビジョナリー・カンパニー1〜4」で紹介された理論やその後の著者の研究内容を基にアップデートした一冊。
原著「Beyond Entrepreneurship」は、偉大な会社(継続的に高い業績を上げ、業界への影響が大きく、社会的な評価も高い企業)を確立するために必要なリーダーシップスタイルの要素や、ビジョン・戦略・戦術といった経営にとってあるべき必須の手法をフレームワークとして整理しているが、本書では理論体系は基本そのまま残しつつ、その後の著書のエッセンスを盛り込んだ「偉大な企業を作るためのマップ」を提示しており、その中で「規律ある人材」「規律ある思考」「規律ある行動」「永続する組織」という企業発展の4段階と、各段階で必要となる要素として、「ビジョナリー・カンパニー」の各著作で説明された理論が網羅されている。
92年といえば、日本ではバブル崩壊後の失われた30年が始まった頃であり、世界的にはIT革命やリーマンショックはまだ先の話で、CSRやESGといった概念もまだ知られていなかった時代であるが、原書引用部分は今日でも時代遅れに感じることはほとんどなく、また増補部分はその後の「ビジョナリー〜」シリーズの総集編という意味合いもあり、「ビジョナリー〜」シリーズを既読の人は網羅的な復習という意味で、また未読の人もまずは各理論の概要を知るという意味で、読む価値のある経営書となっている。
投稿元:
レビューを見る
ジムコリンズ、間違いなし。と感じることができるバイブルに値する内容でした。何回も読まなきゃな、と思わされる中身の濃い1冊。
投稿元:
レビューを見る
相手を信頼するほうがアップサイドは大きくダウンサイドは小さい。
時代を超える偉大な企業をつくる唯一の方法
正しい文化の下で正しい人材が働く状態を生み出すこと
最初に人を選ぶ それから目的を決める
仕事は業務ではなく責任
社員にパフォーマンスを望むなら、自分自身のパフォーマンスを高める
リーダーシップとは、やらなければならないことをやりたいと思わせる技術
リーダーは理想とする文化のロールモデルになる
幸運は諦めない人にやってくる
成功は巡ってきた幸運をどう活かすか、どう対処するかで決まる
イノベーティブな企業んあるための必要要素
1.どこで生まれたアイデアでも受け入れる力
2.自分が顧客になる
3.実験と失敗
4.社員がクリエイティブになる
5.自立性と分権化
6.報酬
投稿元:
レビューを見る
企業が追跡すべきもっとも重要な指標は、売上高や利益、資本収益率やキャッシュフローではない。バスの重要な座席のうち、そこにふさわしい人材で埋まっている割合だ。
重要な座席とは、1人材にかかわる重要な意思決定をする権限がある 2この職務での失敗は、会社全体に重大なリスクあるいは大惨事を引き起こす可能性がある 3この職務での成功は、会社の成功にきわめて大きな影響を与える必要がある
ビジョンは「コアバリューと理念」「パーパス」「ミッション」という3つの基本要素で成り立っていることを示している
組織の成功を左右するのは資金力、組織、イノベーション、タイミングではなく、基本理念、精神、意欲だ
パーパスは決して完全に実現されることはないという点だ。地平線、あるいは道標となる星を追いかけるようなもの
ミッションの4分類 1,目標 2,共通の敵 3,ロールモデル 4,内部変革
数字的ミッションを掲げるなら、誰もが意義を感じられるものと結びつける必要がある
「キツネ型」「ハリネズミ型」キツネは世界を複雑なものとしてとらえ、さまざまなアイデアを追いかけ、たったひとつの目標や原則にこだわることはない。一方、ハリネズミは物事を単純化し、あらゆる事柄を単一の原則にもとづいて考える
偉大な企業の強みは、運の「利益率」にあった。重要なのは「運に恵まれること」ではない、「恵まれた運をどう活かすか」だ。
戦力を集中させること以上に重要でシンプルな戦略の法則はない
倒産のほぼ半分は、記録的売上の上がった翌年に起こる
多角化は絶対にダメだということではない。ほとんどの企業が遅かれ早かれ多角化する。問題は「いつ」「どれだけ」多角化するかだ
リーダーシップ、ビジョン、戦略、イノベーション、戦術的卓越性が偉大な企業を生み出し、業績、影響、評価、長寿の4つのアウトプットへつながる
投稿元:
レビューを見る
面白かった!
4しか読んだことがないから,どうかな,と思ったけど,自分のような小さな組織で突破を目指す者としては,コチラの"0”の方がいいかも.
少し時間を空けてまた読んでみたい.
ただ,Appleの考察がJobsが追い出される前の事だったり,ちょっと検討材料が古いことが気になる…
でも,書かれていることはいつの時代にも変わらない価値観だとも思う.
投稿元:
レビューを見る
高度に自律的な人財なら本書に書かれた働き方が出来る。自分の組織のメンバーをそのような内発的なマインドを醸成したい。
投稿元:
レビューを見る
ビジョナリーカンパニーは、第1作から読んでいます。本作は超有名な大企業もスタートアップのタイミングがあって、その時に苦労していることがわかる1冊です。
可能性は秘めていたものの、スタートアップ期を乗り越えられなかった会社と飛躍できた会社との違いを知ることができます。多くの人に手に取って欲しい1冊です!
投稿元:
レビューを見る
全くもってその通りと言う内容でした。
人材と言う字を使った表現に人在(罪)、人材、人財などが有りました。
優秀な人は人財、可もなく不可もなしの人は人材、問題有り的な人は人在と良く聞いたものです。おまけに害を及ぼす人は人罪と言う話も聞き及んでました。
このホンを読んで、そうした評価は誰がしたものなのか?、どんな基準だったのか?と様々な疑問が過りました。また、指導者が代われば打目社員が有料記事社員と皆から呼ばるのも実体験で見て来ました。
企業を構成するのは人です、どんなに優れた商品やサービスでもそれだけでは拡がら無いんです。それが噛み合うととんでも無い素晴らしい成果出る。単純に人とものだけの関係では無いけど、根幹だとも思う。
そして永続的に成長させて行くのは、仕組みが必要になって来る。これは文書に書いてこの通りやりなさいと言う類いのものでは決して無く、頭でっかちな単一指向性の頭脳では成し得ない。
この類いの本を読んで知ったかぶりする輩はほぼこのレベル以下な自分をさらけ出している事に気付こう。
相応の経験値が試される本かも知れませんね。
投稿元:
レビューを見る
OPURになりたい。One Person Ultimately Responsibility 最終責任を負うもの
投稿元:
レビューを見る
ゼロから事業を生み出して偉大で永続的な企業になる為の考え方、方法を述べた本。
とても秀悦な本である。500ページとボリュームが多く、難しそうに思って読んでいたが、原理原則は極めてシンプルであり、わかりやすく、共感出来る内容が非常に多かった。
一回読んだだけではとても理解できたとは言えず、今後何度も何度も読み直して、自分の血肉として活用していきたいと思う。