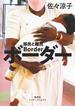移民や難民問題を考える入り口には最適な1冊
2024/11/13 17:44
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:flowerofzabon - この投稿者のレビュー一覧を見る
2024年9月に50代半ばで早世したノンフィクション作家の実質的には最後の単著。10年越しの労作であり、筆者が日本語教師経験者であることもあり、間延びすることない濃密な文章で満たされている。
移民や難民のルポ的な著作は活字、映像作品に限らず世にあまたあるし、統計的な数字、法律などを他国と比較しながら解説してあるものも多い。一通り勉強している人ならば、本書で新しく得られる情報などはあまりないかもしれない。それなのに、鼻白むことなく素直に心動かされ、素朴なヒューマニズムを出発点に、日本に住む者として移民や難民問題に正面から取り組もうとさせる文章を提示する筆者の力に圧倒される。
知識がない人のとっかかりとしても、この問題に取り組むも努力が報われず先が見えなくて挫折しかかっている人にもおすすめ。
個人的には、犯罪に手を染めてしまうような移民/外国人について佐々氏がどのように描くのか読んでみたかった。
ここは本当に日本なのか
2023/02/26 19:55
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:マッキー - この投稿者のレビュー一覧を見る
ニュースでも時々取り上げられていましたが、本当にここが日本なのか、疑問に思っていましたが、入管のひどさが常態化していることが知れて、ちょっと日本人として心が折れそうになっています。ぜひとも、皆さん方にも読んで、日本のことをもっと知ってほしい。
投稿元:
レビューを見る
佐々さんの本は『エンドオブライフ』『エンジェルフライト』『紙つなげ』に続いて4作目。しかしこれまでとは少し違う印象を受ける本だった。
難民と聞くと世界のどこかの話に思えてしまう。
でも少し考えればわかることだった。日本にも難民が来ないはずはない。
本書では、
・日本の難民認定について
・技能実習生の実態について
・日本で困っている移民難民の方々をサポートする組織について
佐々さんの取材を通じて知ることができる。
本書で私がハッとさせられたのは次の2点だ。
・日本人の差別意識が無自覚にとんでもなく高いこと
・日本の入管について、移民、難民について自分が驚くほど無知であったこと
・日本人の差別意識が無自覚にとんでもなく高いこと
昨今"Black lives matter"が取りざたされているように、アメリカにおける黒人差別問題は世界的に知られている。しかし、日本人に「あなたは日本で人種差別があると思いますか」と問えば、あまりない、とかわからない、という感想を抱く人が多いのではないかと推測する。
しかし、少し立ち止まって、ゆっくり考えてみてほしい。
近所にベトナム人の技能実習生が複数人で引っ越して来たら、日本語の不自由そうな大きな黒人がコンビニのレジに立っていたら。ハーフの人が日本代表として代表選手に招聘されたら。一抹の不安や違和感のようなものを抱かないと言い切れるだろうか。ただ単に、他国と比べて人種の多様性が低いだけで、少しでも接点があろうものなら排除してしまいたいという気持ちを持ってしまう人も少なくないのではないかと思ってしまう。(もうこの考え方自体が一種の差別なのかもしれないが・・・)
・日本の入管について、移民・難民について驚くほど無知であったこと
日本の難民認定のハードルは理解不能なレベルで高い。UNHCRが書面で「この人は自国で迫害の危険にさらされています、保護してください」という依頼を発行しているのに、難民とは認められない。では、一体誰が難民として認められるというのだろうか。それに入管での人の扱いは本当にひどい。現在の日本で実際にこんなことが起こっているとはにわかに信じがたい。
自分はまだまだこの問題を知らない。わかっていない。
これを機にもう少し勉強しなければと感じた。
投稿元:
レビューを見る
2023年9冊目。
佐々さんの本は必ず読んでいます。
イギリスがEUを離脱するというニュースが話題になっていた頃から、移民・難民の支援について関心がありました。
JICAから教材を取り寄せて、教科書的な情報以外のことも、自分なりには教えてきたつもりでした。
が。
この本を読んで、日本の移民・難民に関する政策や、入管の実態を知り、言葉を失いました。
また、何となく知っているつもりでいた技能実習制度についても、詳しく学ぶことができました。
日本が値踏みされる状況になっていることに気づかされた時、驚いてしまいましたが、驚いた自分に嫌悪を感じました。
この本曰く、一面では、日本は経済大国でも人権国家でもないのだから…
この問題は、関心ごとの一つになりました。
勉強していきたいと思います。
投稿元:
レビューを見る
2022年11月大雨の中開催された移民難民フェスの、テントの外はびしょびしょで本を売るには最悪の環境の中、出店されていたポルベニールブックストアさんで購入した。
読まないといけない本と直感した。
映画牛久、を見ないといけない映画と直感したのと同じ。ウィシュマさんの不幸な死(日本という国の全体の、法や行政やそこで雇われてる人らの悪意による、不可避出なかった、回避できたがしなかった悪意の死)と、あからさまにこれまでの難民認定、施策とは真逆でおかしいウクライナからの難民への対応、
もやもやしすぎているのできちんと知らなければならないと思って拝読。
冒頭の鎌倉のアルペなんみんセンター。
この様な場所があることを知り希望と安堵。
難民支援闘士である児玉晃一弁護士。
2001年アフガニスタン難民を解放する判決を出した東京地裁民事三部の藤山雅行裁判長(身柄拘束自体が個人の人権に対する重大な侵害であると明言、、、しかしそれから20年以上経っても何も変わらず、こりもせず改悪入管法再提出とかしてる)
強制送還されれば宗教独裁イランで死刑になるイラン人送還拒否で血まみれ、流血している人を無理矢理押さえつけ搭乗させようとする入管職員、イラン人機長への呼びかけで機長が搭乗拒否、送還をなんとか免れたという話など、壮絶な、しかし、一人ひとりの普通に生活する権利、それを人権というが、そんな人たちのありえない物語の数々。
日本は法治国家でもなんでもない、人権国家と嘯いて独裁政権を非難しあり、日本と違うなんてイメージをマスコミも政府もあおるがしらじらしいこと、甚だしい。
そのイラン人の言葉、
日本は難民条約に入っていると、先進国で法治国家だと信じていた。もしこれからも難民を受け入れる気がないなら、建前だけ掲げている人権国家の看板を下ろして難民条約から脱退してほしい。
全くその通りだと思う。
どんなに大変でも間違えて日本にだけは来ない様に!どうか他の国へ行き難民認定されて祖国にいるより良い生活と安全を手に入れてください、と逆説的に自虐的に思ってしまう。
劣等民族による選別と差別。
映画牛久を見て、この本を読むとよりよく実態、事実、現実を理解できるし、より読んでいて生々しい痛みと日本人としての恥ずかしさを実感し、息苦しくなる。
ウクライナ難民のことを書いてしまったが、本書でも、そのことの控えめにではあるが違和感として述べられており、ウィシュマさんについても、そもそも彼女が先に入管施設で死亡したアフリカの男性より、若くて美しい女性であったことも比較において報道や興味の対象となっただろうし、そもそも、全く同じ条件、留学生として来日、DV被害に遭いビザなしとして収容され体調が悪くという全ての条件が同じだがウクライナ人とか欧米系の女性であったならそもそもあんな酷い虐待にあっただろうか。虐待=犯罪レベル。そのことも著者の佐々さんは、きれいごとだけいうつもりてはない、と書かれている。
このことはとても大事。ウクライナ難民と、クルドやミャンマーやスリランカやアフガンやイランやさまざまな地域や国から来た難民との違いすぎる違いをいうこと���はしたなくもあり、ウクライナ難民の方を貶める意図は毛頭ないが劣等民族劣等国家である我々はそのことも
自戒を込め恥ずかしながらも言わねばならないだろう。
後半の実習生、研修生に関する調査と考察は、知らないことが多く、大変貴重な資料と感じた。佐々さんは、実習生は日本社会にとっての、こびとのくつや、とおっしゃっている。我々が知らないところで働いて経済を回してくれている、と。私も毎日、やすい食品やタオルなどが日本産であるのを見ると、ドキュメンタリーで見た制度の中で来日し毎日技能を学べずタオルばかりを縫製しそのことを隠す様に言われているアジア人の女性を思い出すし、食べながらも複雑な思いにかわれる。
こういう本を課題図書にしたら良いのではないですか。知らないことを知ることは、特に子ども、学生、若い人がこういうことを知理、おかしいことに気づくことは大事。
私たちを助けてくれるの?助けられるの?と最初の出会いのときに12歳の少女ナディアに問われた児玉弁護士。日本という偏屈で狭量な社会に生きる私たち一人ひとりに対して問われている言葉だと思う。
まずは、違法行為をしない法務大臣さんになってほしい
(入管法改「正」案のもとになったのは当時の法務大臣河井克行の私的懇談会である第7次出入国管理政策懇談会だそうだし。死刑執行のハンコつくだけの暇で目立たない大臣職などと嘯いた統一協会関係者とかですね、
下々のものは悪いことしてなくてもしよっぴかれますが、真の法治国家ではない適当国家人権侵害国家ではかなり悪いこと、違法行為してもお咎めなしです)
メモ
衆議院 2021年04月21日 法務委員会 での、難民審査参与員柳瀬房子(特定非営利活動法人難民を助ける会会長)の参考人としての話。難民として認定すべき人があまりに少ない、偽造難民が多い、入管法改正法案に賛成と述べていて、著書が驚きガッカリしている記述あり。106ページ。難民を助ける会ではないのか?疑問。
投稿元:
レビューを見る
とても読みたかったノンフィクション。
2024.2.16(金)0:17 読了
入管の酷さ、人権意識の低さ
日本人の差別、偏見意識の高さ…
一人一人の人生や苦悩に焦点を当てられたルポ
読んでいてずっと苦しかった
最終章の鎌倉の難民受け入れ施設には希望が見えた
単一民族、先進国としての驕りは、今の凋落してきている日本では通用しなくなってきているのに
現に、もう、来てくれなくなっているではないか
日本人が出稼ぎに行っている、優秀な研究者などは海外に行ってしまうような現状で
どこまで世界に取り残されるんだろう
投稿元:
レビューを見る
「入管」
ニュースで耳にしたことがある言葉
そして、入管について、ウィシュマさんの報道で「知らなくてはいけないことがある」と思っていはいたが、日々の生活とかけ離れていて、なかなか報道以上のことを知ることは、知ろうとすることはなかった。
この本を読み、ウィシュマさんは氷山の一角であることを知る。
これはすべてにおいて言えることだけど、やはり「知ることから始まる」。
読みやすく構成された本なので、中高生にも読めると思う。
おすすめ。
投稿元:
レビューを見る
世の中の出来事をこんなにも知らない自分に気がつき、日本人の難民や差別への無関心が事態を悪化させていると痛感する。まずはこの本で知ったことを家族や友人に伝えることが自分にできる一歩だろうか。
日本人は国籍で差別している…本当にそうなのだと思う。
SDGsなど耳障りの良い言葉が流行り、都合の良い解答を求めるようなことが既に間違っているのではないか。
投稿元:
レビューを見る
日本への移民と難民の話。難民と言われたら今のウクライナ難民のイメージ。また、不法残留となれば入国管理センターで亡くなった女性のニュース、中島京子さんの「やさしい猫」で読んだ話が思い浮かんだ。それだけしか知らない。そしてどこか遠い世界の話と感じていた。だが。そこから外国人技能実習生の話となり、それは近所のコンビニにいる方、近所の工場にいる方、よく見るそれらしき方たち。少し身近だと感じた。日本は難民に優しくない国、外国人労働者に優しくない国。だけど、それは多くの人にその事実が知られていないからだと思う。どんな扱いを受けてどんな生活を強いられているか知らないから。学校でも習った記憶、ほとんど聞いたこともない。まずはこのような本やニュースを通して一人でも多くの日本の人に知ってもらうこと、それが支援の輪が広がったり国を動かすことに繋がるのではないかと思った。
投稿元:
レビューを見る
偏見は拭えない。時々、庭の草を採るように自分自身で点検する。印象深いエピローグに載った言葉。
自分にも当てはまる。現実は、知らない事が多く、情報は黙っても入ってくる。ただし、正しい情報ばかりじゃない。自分で考えて、取捨選択して行動しよう。と思わせてくれる一冊。また1つ、出会えて良かった著書。
投稿元:
レビューを見る
中島京子さん著『やさしい猫』を読んで、入管問題に興味を持った。興味を持って日々過ごしていたら、テレビや新聞、本など、入国問題を扱っているものが目につきはじめ、改めて自分が今までどれほど無関心だったかを日々感じている。
著者もあとがきでこう書いている。
○「日本に難民は来ていない、ほとんどが偽装難民だ」といわれれば、そんなものかと聞き流し、思い返すこともなかった。つまり入管問題を作り出し、放置していたのは、他ならない、無関心な私自身だったのだ。今私たちは平和を享受している。しかし、これからも戦火に巻き込まれないと言い切れるだろうか。その時、私たちに手を出し差し伸べてくれる国が果たしてあるだろうか。
日本は1981年に難民条約に加入している。しかし、難民として受け入れることはかなり珍しく、自国に帰すか、それを拒否する人は、入管収容所に長期に渡り閉じ込める。収容所では人権などなく、本当に日本人がそんなことをしているのか?と直ぐには信じられないような残酷な対応をしているという。
(日本に助けを求めにきた外国人の話・本文より)
○俺は、日本は難民条約に入っていると信じていた。日本は先進国で法治国家だろうと。もしこれからも難民を受け入れる気がないなら、建前だけ掲げている人権国家の看板をおろし、難民条約から脱退してほしい。だって実際、この国は人権国家じゃないんだから。そうすれば間違って日本に助けを求める外国人も減るだろう。お互いハッピーじゃないか。俺も他国に助けを求められる。
こんな状況を看過している国のトップを私はとてもじゃないが信用できない。現在、歴代の総理大臣を思い浮かべて、え?あの人もあの人も、何もしてこなかったのかと愕然とする。日本人であることが、恥ずかしく、罪深く感じた。
佐々さんはもともと日本語教師をしていて、その関係で、第二章は、日本語教師の視点で外国人技能実習制度について詳しく書かれている。個人的にはこの章が一番よく書かれていると感じた。
この章で、衝撃を受けた。日本の国力は下がっており、近い将来、日本に出稼ぎに来るメリットがなくなり、実習生が来なくなるだろう。そして後々、日本人が外国に出稼ぎに行くことになるかもしれない。というのだ。日本に実習に来ている、または行こうと用意してくれている外国人に日本語を教えている人達がそう見ているのだ。生の感想だろう。
入管問題をもっと知りたいとこの本を手に取ったが、取材した個々の案件の事が主だったので、全体像はまだよく掴めなかった。これからも関心を持ちつづけていきたい。
投稿元:
レビューを見る
あの治安維持法でさえ拘禁するには裁判所の決定が必要で最長二年までだったにも関わらず、入管は独自の判断で無期限に拘禁している実態。拘禁されているのは、なんらかの理由で母国に帰ることを拒否している人たちだ。特に母国に帰れば殺害されてしまう危険がある人も相当数いるという。それでも入管は難民と認めない。
そんな入管(国家)と戦う児玉弁護士の活躍を軸に、著者が出会った関係者への取材が描かれている。この問題に関しては「怒り」しかない。ほんとに恥ずかしい国だ、日本は。
投稿元:
レビューを見る
まだ読んでる途中だが、ウシュマさんの事件意外にも入管内での人権無視の体制
日本でこんなことが起きてるのか?!と悲しくなる。
また弁護士の児玉さんのTwitterに多数の「即帰れ」などのコメント
一部とはわかっていても同じ日本人なのかと悲しくなる。
自分自身も今まで無関心でいたことも同様に情けなく思う。
自分がもし海外に行って、このような待遇を受けたらと思うといたたまれないし、その国を憎むだろう。日本はすごいだろ?良い国だろ?と心から言える国になってほしい。
投稿元:
レビューを見る
待ちに待った新刊。
「紙つなげ」も記憶に新しいと感じていたのだが
それでもすでに読み終えてから8年ほど経っていたのに驚く。
今作も骨太で読み応えあり。
著作に一貫されている表舞台では輝かないスターへの愛あるスポットが感動的でキャラクターも想像しやすく描かれている。
改めて移民と難民について普段意識することなどなく全く無知であったことに気づかされて愕然とする。
たまにニュースでチラ見する程度で当事者意識など微塵も無いに等しい。
他の先進国との難民認定数の差に驚き憤りを覚えるが現在の世界情勢を鑑みると今やいつ私たち日本人が他国へ亡命しなければならなくなるかは現実問題として直面する時期がすごそこまで来ているのではないかと考えると全く時代錯誤な入管政策を続けているのだなとなんだか滑稽に思えてくる。
文中にあるように「情けは人のためならず」
明日は我が身と考えて人に接することの大切さが問われているように思います。
次回作はどんな地上の星を見せてくれるのか。
首を長くして待っておきます。
投稿元:
レビューを見る
◆首藤淳哉: 『ボーダー 移民と難民』私たちの内なる境界を考える(HONZ 2022年12月14日) https://honz.jp/articles/-/52663