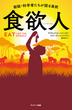食生活を見直すきっかけに
2023/12/31 19:44
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:BB - この投稿者のレビュー一覧を見る
野生動物は自分に適切な食事を知っているそうだ。
では、どうして人間は食べ過ぎて、太ってしまうんだろうか。
本書は科学者たちが食欲の謎に迫った一冊。
どうやら私たちはタンパク質欲?を満たすまで、食べることをやめられないみたいだ。
生物の食欲による反応から、食品メーカーの戦略まで、私たちの食を取り巻くノンフィクション。
この問題に興味があろうがなかろうが、誰もこの話に関係ない人はいない。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
食べ過ぎる前に、満足感を得られたならば、そりゃダイエットにもなるし、暴飲暴食を防ぐことが出来るだろうし。しかし、なかなか、人間は、食欲を抑えきれません。だから、肥満や成人病の原因になるのでしょうね
投稿元:
レビューを見る
「タンパク質欲が満たされなければ、動物はそのまま食べ続ける。いったん十分なタンパク質が得られれば、摂食を促していた食欲は止まる。」
健康のためにも、タンパク質、食物繊維ファーストで食べるのを意識しようと思った。超加工食品を避けて、ホールフードを食べよう!
投稿元:
レビューを見る
生命の食欲がタンパク質の摂取量に起因する。なるほどと思わされる視点でした。人類が「精製」されたものを食するようになってからの時間は進化の速度からすると極めて短い時間であり、それが本来必要とするバランスを検知する能力を混乱させてしまっているのだろうなと考えさせられた。トレーニーとしてはタンパク質濃度が高い食事を続けていると寿命が縮まるという点については非常に悩ましい思い。。
投稿元:
レビューを見る
お腹がいっぱいなのに、何か食べたい。
そんな時がよくあるが、その理由がわかった。
タンパク質の必要量を摂取するまで食べ続けてしまうのだ。
また、超加工食品の恐ろしさを改めて再確認した。
スナックが食べたくなったら、タンパク質が足りないということ。
健康でいるために気をつけよう。
投稿元:
レビューを見る
とても読みやすかった。仮説のたて方、検証方法、分析と考察も、納得できるものだった。
p401『いま流行りの、ヴィーガンからケトンまでの様々な栄養哲学は、特定の状況では健康的な食事になるが、ほとんどの人は続けることができないし、経済的な既得権益や怒り、狂信が深く絡んでいる。』
投稿元:
レビューを見る
一生し続けていかなければならない「食」。「糖質」「脂質」に比べタンパク質の知識はちょっと不足気味。本書を読み、「食」に関する知識をレベルアップしたい
#食欲人
#デイヴィッド・ローベンハイマー
23/5/30出版
#読書好きな人と繋がりたい
#読書
#本好き
#読みたい本
https://amzn.to/42hL7fw
投稿元:
レビューを見る
現代人の食生活に警鐘を鳴らす一冊。
食欲の根源は虫もヒトも【たんぱく質欲】、たんぱく質量が少ない食事だと食欲が満たされず、まだ食べられる感覚になる、というのには納得。(ポテチに手が伸びる感覚)現代人がどれ程身体に悪いものを摂っているのか。。企業の目論みも怖い。
論文であれば目にすることがないであろう程の研究結果が掲載されていたが非常に読みやすい一冊だった。
必要量のたんぱく質を摂取する→15-20%、超加工食品の摂取を控える、繊維を取る
は即実践しようと思う。
投稿元:
レビューを見る
わたしたち人間を始めとする
哺乳類や猿人類、そして昆虫やマウス
などを元にした食餌実験によって
重要な栄養素がタンパク質であることを
結果を元にわかりやすく説明してくれる。
またそれ以外にも
現代の食環境を取り巻く背景と
わたしたちの健康が密接に関わりをもち
どういう意識改革が必要なのかもわかる。
定期的に読み返したい。
投稿元:
レビューを見る
食事、ダイエットについてお悩みの方におススメの本。
帯に書いてある通り、人間を含むあらゆる動物は一定の「タンパク質」の接種を求める、という内容。
いろんな研究をドキュメンタリーみたいに読ませつつ伝えてくれるので、論旨は単純だが面白いしなかなかの説得力。
お金に困っている人に肥満が多いのも、安い食品には糖質や脂質が多いわりにタンパク質が少ないものが多いから、一定のタンパク質を取るために摂取量が増えてしまうからとのこと。
つまり痩せたければ、食事を高タンパク質の食品へ置き換えていくことが大切と考えられ、だとすれば大変シンプルでよい(逆に太りたければ低タンパク質の食事にする)。
投稿元:
レビューを見る
食物繊維・高タンパク質が大切。甘いものや油ものに惹かれがちだけど、それは食品会社が戦略として健康よりも売上のために加工食品を作っている。美味しいものはやめられないが、健康に気を遣って考えて食べていきたい。
投稿元:
レビューを見る
少し前に話題になっていたので読んでみた。
35年以上の研究を経て、食欲の謎に迫った本。
結論から言うと、もっと早く読んで食生活を改善しておけばよかった。
本の9割はさまざまな事実の解明とそれに至ったあらゆる実験について書かれてあるので、途中で少し飽きてしまったけど、根拠を示すという意味では重要だし、科学的なアプローチに興味がある人には面白いのかも。
結論だけ見たい人は、最後の1割読めば実生活に活かせそう。
★一番のポイント
タンパク質は大事だけどとにかくたくさん摂ればいいというものではなく、ターゲットを決めて摂るのが大事。また、人生のフェーズによってターゲット分量も異なる。低タンパク・高カロリーな食事ばかりしていると、タンパク質欲を満たしたいがためにどんどん食べてしまってカロリー過多になる。
★個人的なメモ
・タンパク質が乏しいカロリーが豊富な食環境では、ヒトはタンパク質の摂取ターゲットを達成しようとして、炭水化物と脂肪を過剰摂取する。だが高タンパク質食しか得られない場合は、炭水化物と脂肪を過剰摂取する。
・子ども時代の食の嗜好は一生ついてまわり、そのまた子どもにも引き継がれる可能性がある。
・子どもは「マーケティング担当者」の格好の餌食。ジャンクフードを親しみあるゲームやキャラクターと絡めて食べさせようとする。
・タンパク質ターゲット:ハリス・ベネディクト法で一日のエネルギー必要量を計算→子ども・青少年は0.15、若年成人は0.18、妊婦・授乳婦は0.2、成人(30代)は0.17、中年(40-65歳)は0.15、老年(65歳超)は0.2を掛ける→その数値を4で割って、一日に摂取すべきタンパク質のグラム数を計算
投稿元:
レビューを見る
生物の「食欲」は、必要な栄養素を必要な分だけ食べるように促す。現代人みたいに健康に気を遣ってあれこれ考えていなくても、野生のヒヒや実験室のバッタは、自然と最適な栄養バランスで食事をする。農耕が始まる前の古代人の骨格を見ても、みな健康体だ。(冬眠前などを除けば)食べ過ぎて肥満になることもない。
では、何らかの理由で適切でない栄養バランスのものしか食べられない場合はどうだろうか。実験室のバッタたちに、2大栄養素であるタンパク質と炭水化物の比率変えながら餌を与えて育てたところ、高タンパク質/低炭水化物のグループは食事量が少なく成長が遅かった。逆に低タンパク質/高炭水化物のグループは食事量が多く、肥満になった。つまり、タンパク質欲と炭水化物欲を比べると、タンパク質欲が勝つ、ということだ。タンパク質欲が満たされるまで永遠と食べ続けてしまう。
人類は狩猟採集生活をやめて、低タンパク質/高炭水化物の穀物を作り始めた。現代の美味しい超加工食品も低タンパク質/高炭水化物だ。しかもその食品には繊維が少ないから、なお満腹感が得られない。こうしてみんな肥満になっていく。
じゃあ、タンパク質をたくさん摂ればいいかというとそうではない。たしかに高タンパク質な食事はダイエットには向いているが、体に悪い影響もおよぼす。実験室のハエに、これまたタンパク質と炭水化物の比率変えながら餌を与えてその一生を追ったところ、高タンパク質/低炭水化物な食事が与えられたハエは寿命が短かった。
現代人は、食欲に従うだけではバランスの良い食事は取れない。意識的に適度なタンパク質を摂り、超加工食品を繊維の入った自然食品に切り替えよう。
投稿元:
レビューを見る
食事法に関するベスト本。
日経新聞の広告を見て、そのタイトルと「タンパク質が食欲を決めていた」というフレーズに興味をそそられて購入。
タンパク質ターゲットという概念、食物繊維の役割、現代の加工食品の問題点、これらが科学的知見・実証から記載されているため、納得感があり、学び・発見となった。バッタの実験からクモやゴキブリ、ネコと犬、そして人間にまで実験を拡大しており、科学的なアプローチ・思考法も勉強になったほか、著者の熱い想いも伝わり、ある種の感動を覚えながら読み進めることができた。
この本を読んでからかなり食事に気を使うようになり、健康に繋がっていると思う。とても良い本でした。
投稿元:
レビューを見る
知的好奇心が刺激されまくって脳内物質がドバドバ出た。 自分の脳みそに収まりきらない本はこれまで苦手意識があったけど、キャパが広がったこともあって、自分のこと、人間のことをもっと解明したい欲に駆られた。