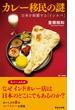インドカレー屋の話は前フリにすぎない
2024/04/25 09:59
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:温泉春巻ロールスロイス - この投稿者のレビュー一覧を見る
インドカレー屋の話は前フリにすぎない。日本の食文化史にだけ興味がある人は後半は期待はずれかもしれないが、本書の価値は後半の「カレー屋の子どもたち」についてのルポのほうにある。
「インネパ移民」の実態をルポした1冊です。
2024/05/12 22:39
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
今、国内のどこでも見掛ける「インド人、ネパール人が経営するカレー店」。当書は日本でカレー店を展開する「インネパ移民(インドもしくはネパールから来日した移民」をクローズアップし、著者が実際にお店に足を運んで実態を探ったルポ記です。
様々な視点からインネパ移民を調べ上げて行きます。飄々とした感じの軽めの文面が特徴の、今売れている新書の1つになります。こういう書籍がヒットするのか、と思いながら読み進めました。面白かったです。
移民とどうつきあっていくかを考えさせられる
2025/04/21 15:49
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:チップ - この投稿者のレビュー一覧を見る
「インド料理」と聞いて思い浮かべるのは表紙や裏表紙にあるようなバターチキンカレー、タンドリーチキン、ナンの組み合わせ
インド料理を名乗っているが、実は経営者はネパールが多いという事実
なぜネパール人は自分の国の料理でなく「日本風インドカレー店」を出店するのか?
日本の移民政策の転換や景気など、複雑な事情を丁寧にレポしてある
移民が多く寂れるふるさと
故郷に残るのがいいのか、日本で忙しい親のもとで暮らすのがいいのかインネパの子供たち問題
移民とどうつきあるべきか考えさせられる一冊だった
簡単じゃなくて人生がかかってた。
2025/03/23 19:12
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:*iroha* - この投稿者のレビュー一覧を見る
良く調べてあるし読みやすかったです。
街のインドカレー店について
不思議に思っていたことが全て書かれていました
お気に入りのインネパカレー店
とにかく美味で感動的だったのですが
背景を知り、ある種の重みを感じました
人に歴史あり
次に来店するときはよりいっそう
おいしく感じることでしょう
投稿元:
レビューを見る
<目次>
第1章 ネパール人はなぜ日本でカレー屋を開くのか
第2章 「インネパ」の原型をつくったインド人たち
第3章 インドカレー店が急増したワケ
第4章 日本を制覇するカレー移民
第5章 稼げる店のヒミツ
第6章 カレービジネスのダークサイド
第7章 搾取されるネパール人コック
第8章 カレー屋の妻と子どもたち
第9章 カレー移民の里、バグルンを旅する
<内容>
『エスニック街道国道354号線』の著者の、アジア系の日本移民を描く第2弾(なのか?)。確かに、ここ数年(もうちょっと前から)日本のあちこちにカレー屋が増えた。勤務先にも1軒。自宅近くの1軒はすぐ潰れた。また知り合いのインド料理店のオーナー(日本人)が、増えたのはブローカーが斡旋するからだと喝破していた。自分はそのブローカーは日本人だと思っていたが、この本を読むと、ネパール人らしい。
カレー=インドなのだが、こうした雨後の筍のような店は、ほとんどネパール人の経営なので、著者は「インネパ」と呼ぶ。どんどん奥を極めていくと、哀しい現実が次々と浮かび上がる。ただ前著よりは、上滑りな感も…。
投稿元:
レビューを見る
昔、都会にしかなかったインド料理屋は高級な店でした。今、街を歩くとどこでも見かけるインド料理屋はネパール人が経営していることが多いらしい。国内産業が育たないネパールの国情を反映した出稼ぎで、著者はヒマラヤの奥地の村を訪れると、“私も日本に行ったことがある…”、“今は休暇で日本から帰ってきてるところ、また行く…”と多くの村人から声をかけられたらしい。何故、インド人ではなくネパール人なのかの理由の1つにカースト制があるらしい。インド人ではオンオペが成立しない。
私は高級感のあるインド料理も、あまり辛くないバターチキンカレーとナンがおおきなインネパ料理も、どちらも好きです。南インドのミールスも大好き。
投稿元:
レビューを見る
学生時代(今から20数年前)にインド料理店でバイトをし、その後海外に出て30台半ばで帰国した私にはずっとなんとなく抱えていた違和感があった。いつの間にか、インド料理屋はみんなネパールの人がやってるし、メニュー構成が同じ。標準的にはおいしいけど、以前のような発見や意外性が消えておもしろくない。新宿三越脇の地下にあった店も、三越裏の2階にあった店も、消えてしまった。インド料理店のランチタイムといえばビュッフェだったのに、セットメニューだけの店ばかり。安いのはありがたいけど、つまらない…。
その違和感にズバリ答えてくれる本だった。一気に読んだ。
私がかつてハマっていたインド料理はムグライ料理で、つまりインドの人々にとっての外食の味だったこと。三越裏の2階にあった店には確かに「宮廷料理」と書いてあって、ディナータイムは学生がおいそれと入れる料金帯ではなかった。バイト先もこの類だった、ということを認識できた。そこはオーナーがパキスタン人(別に中古車輸出業もやっていたらしい)で、同僚のホール担当君と、広い厨房を1人で回していたコックはインド人だった。ホール担当君は独身だったが、コックさんは国に家族を残して来ている出稼ぎ者だった。ラッシーやチャイの作り方を教わったし、初めてビリヤニという料理を食べたのもバイト先でだった。店のメニューにないその料理は、「お祭りとかお祝い事の時の特別な料理」だと言っていた。今日はインドでは大きなお祭りかなにかなの?と聞いたら、「君がバイトで来る日だからだよ」と言われてものすごく嬉しかった。初めて食べたビリヤニの感動は忘れられない。最近はずいぶんいろんなところで食べられるようになったけど、今でもあの時のビリヤニが一番おいしかったと断言できる。
その後ネパール人コックの流入があって、出稼ぎ大国のネパールからどんどん人がやってきて、独立して増え…。なるほどなるほど、となんどもぶんぶんうなずいた。以前岡山で入ったインド料理店は典型的なインネパで、グリーンカレーやパッタイも出すという「エスニックひとくくり」みたいなタイプ(最近じわっとタイ料理やベトナム料理を出すインネパ店、これまた増えてきていると感じる)だったのだが、これがまあびっくりするほどおいしくなかったのだ。マズいというか味がない。マトンカレーかなにかを食べたと思うのだが、とにかくおいしくなくて驚いた。インネパってまあ標準的なものを出すというイメージだったから。
でも、後半の章を読んで納得した。
筆者は冷静に、客観的に起きていることを観察しているが、その視線には彼らへの純粋な興味と温かさがある。陽があれば闇もある。どこからの移民でも2世は苦労するものだけれど、今まさにその問題にぶつかっているのが大量のネパール人2世なのだと初めて知った。
最近はダルバートが静かにブームだし、スリランカカレーという新勢力もいる。インドで修行した日本人が作る、パレットのように色鮮やかで美しいミールスを出す店や、インドの各地方料理に特化した店も増えてきた。私にとっては嬉しい変化だが、インネパど真ん中のコック、経営者にとっては厳しい流れなのかもしれない。でも、より本流へと移行していくのは当たり前のことのようにも思う。どんどん細分化され、本格化していく。
インネパはやがて、ごくごく一部を除いて淘汰されていくのだろう。それが自然な流れのように思う。少なくとも今のような、どこの駅にも必ず一軒はインネパがある、ような状況はなくなっていく。
その時、適切な教育を受けられなかった2世はどこへ行くのだろう。
投稿元:
レビューを見る
実家のあるド田舎の小さな町にはスタバは無いがインドカレー屋はある。今や全国どこに行ってもインドカレー屋があって、チェーン店ではないのに判で押したように同じフォーマット、大きなナン(またはライス)おかわり自由、チキンカレー、キーマカレーとダル(豆)カレーなど何種類か選べる、こういうお店がある。インドカレーだけど実はインド人じゃなくてネパール人がやってるとか、インドではこういうナンは実は食べないとかの知識はなんとなく耳に入って来る。
エスニック街道の著者、室橋さんによる、丹念な取材、今回は日本にあるお店だけでなく、ネパールの奥地まで足を運んで、こういうお店が増えた背景を解き明かしている。
近所に、わりと長くやってるインネパ店があり、周囲に似たような店ができてはつぶれして、現在はもう1件少し毛色の違う店が安定して営業している。カレーは好きなので、以前は嬉々としてインネパ店に足を運んだが、最近は食傷気味で、初めて訪れる地でランチに入る店を決める時、自然とインネパは除外している。最近は南インド風とか非インネパ店が増えている。しかし、インネパ店も入ってみると微妙に違ってたりして、それはそれで趣きがある。二郎が店によって違うみたいに。
食べていくだけなら自給自足で足りるネパールの田舎暮らし、スマホを持つだとか少し現代風の暮らしをしようとすると現金が要り用になって、海外に出稼ぎせざるを得ない。そうして若者から働き盛りの人がいなくなり、過疎が進行して格差が生まれるという構造的欠陥は、日本も同じだ。
バブル期ならともかく、不況下の日本が出稼ぎ先として選ばれるのはいつまで続くのだろうか。
そんなことを考えながら今日もマトンカレーを激辛にしてナンで食べている。
投稿元:
レビューを見る
バターチキンカレーにバカでかいナン、オレンジ色のドレッシングがかかったサラダとラッシーで、ランチで1000円切るくらいの価格帯のカレー店。メニューも似てれば、看板や内装も似ている。あれっ?あそこにあったカレー屋が移転してきたのかな、と思ったら、もとのお店もちゃんとある。二号店? にしては店の名前が違う。
こんな現象があちこちで起きている。その謎に迫った本。
似たようなカレー店が増えたのは2000年頃からで、規制緩和でビザがとりやすくなり、ネパール人が出稼ぎ先として日本を目指しはじめた。ネパールの平均月収は1万円。失業率も高く国内にいても仕事はない。キツくても儲かる海外に行こうとする若者が多い。そんなときに渡りに船だったのが、日本でカレー店を営むネパール人たち。日本にある上記のような形態のカレー店のほとんどがネパール人が経営、運営している。理由としてはネパール料理とか言っても日本人に馴染みがないから。カレー店なら日本人にもすぐわかかる。あとは、料理経験のない人でも簡単に作れる(とネパール人は思っている)から。
バブル期に起こったエスニック料理ブームで老舗のカレー店で修行したネパール人たちが、この頃は独立して自分の店を持っていた。そして、そのネパール人たちが、今度は自分の家族や親戚を日本に呼びはじめた。そしてチェーン展開など店舗拡大に伴い人手が足りなくなると、もっとネパールから人を呼び、そのうちブローカー業を商いにするネパール人も出てくる。あとはネズミ算式。あっという間に似たようなカレー店が日本に増えた。なぜ似たような店ばかりなのかというと、失敗したくないから、の一語に尽きるらしい。もはや大手牛丼屋やハンバーガーチェーン並の価格で日本人好みカレーがランチで食えるのだから、それはそれでいいのかもしれない。本格的なカレー店は良い迷惑だろうが、カレー好きな人からすればもはや別物だろうから、そんな影響は受けていないんじゃないかと自分は思う。
インド人ではなくなぜネパール人なのかというと、インド人はカースト制の中で生活してきているので、調理や接客、掃除までするワンオペカレー店では働かないから、ということらしい。料理なら料理しかやらない。掃除は使用人がするもの、という感覚。そもそも日本にくるインド人は教育レベルが違うらしい。ネパール人は国が貧しいので教育に力を入れていない。だから出稼ぎでくるネパール人はキツくても、ブローカーに金をピンハネされても、ネパールにいるよりは良いと、カレー店で働き続けるらしい。
それでも働けるだけ良かったが、入管も、なんだかネパール人たちが、コックの経験も資格もないのに、証書を偽造して店を開いているらしいぞ、と気づきはじめ、近年は入国も在留資格の更新も厳しくしなったらしい。
煽りを受けるのは大人よりこどものほうで、経済的理由で日本語がわからないのに公立校に入ったり、いつ滞在資格が無くなるかもわからないしで不安だらけ。というか不安しかない。
日本のコミュニティに根付こうと努力しているお店はどこも繁盛しているらしい。入国した動機は抜きにして、そういう人たちの家族が日本で暮らしやすいようにする義務は、日本にあるんじゃないかと思う。
個人的な希望として、第2弾で「なぜ横浜中華街に同じような立て看板の食べ放題の店が増えたのか」を取材して欲しい。この著者ならいい記事をかけると思う。
投稿元:
レビューを見る
私のようなアジア・エスニック料理好きからすると実に興味深い本だった。思いがけず土地勘のある名古屋のインネパが深掘りされ、行ったことのある店がバンバン出てくるのでニヤけながら読んだ。
友人や家族とインネパあるあるを言い合ったりして楽しむことはあったが、「それはなぜ?」を本書はとことん追求しており疑問を解決しまくる。執念の取材力だ。
ネパール人の国民性、世界情勢の変遷からインネパが生まれた理由を知ることができ、教育の問題、ネパールの空洞化といった新たな社会問題まで提起されている。
非常に面白いが、読んでると腹が減ってくるのが問題。笑
投稿元:
レビューを見る
副題は「日本を制覇する『インネパ』』「インネパ」とは「ネパール人経営のインドカレー店」のことだという。我が町でもかなり前、まさにこの表紙にあるようなメニューのカレー屋がオープンし、店はネパール人がやっているとのことだった。
「インネパ」カレーの味の誕生と伝達、ネパール事情、日本でのインネパカレー店の事情、ネパール人の出稼ぎ事情などについて、ジャーナリストの室橋裕和氏がリポ。
この日本でよくあるカレーのメニューは、インドのムガール朝の宮廷料理がもとになっているという。日本にカレーが入ってきたのは、明治初年でイギリス人が持ち込んだといわれるが、表紙にあるようなカレーは、新宿の「アショカ」という店が初めだという。1964年の東京オリンピックを機に日本でも食の国際化が進むだろうと、1968年に創業し、いろいろあった末、ムガール朝の宮廷料理を基にしたメニューを作ったというのだ。
そしてネパール人はインドの飲食店に出稼ぎに出て重宝されるという。インド人はカースト意識が強く、料理する人は店の掃除はしないが、ネパール人にはそれがなく、雇えばなんでもするところで重宝されるという。で、修行して味を覚え、親戚知人を呼び、また味を教え、さらに独立し、そして日本へ、という流れがあるのだという。
しかし日本へくるネパール人家庭では働きづめで、子供たちが言葉の問題などで地域になじめず、反グレになってしまう例もあるようだ。特に10代半ばあたりで親に呼ばれると語学習得も幼児にくらべ難しくなるという。
いろいろあるが、ともかく「インネパ」はおいしいので、長く店が続けられるような状況を祈る。
2024.3.20第1刷 図書館
投稿元:
レビューを見る
https://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO80137000Z10C24A4MY5000
投稿元:
レビューを見る
「北関東の異界 エスニック国道354号線 絶品メシとリアル日本」に続いての室橋裕和の本です。引き続きレストラン一軒一軒に丁寧に寄り添う取材からいつの間にか大きなテーマに触ってしまっている、という室橋節(?)が冴え渡っています。彼が開く異界の扉は、今回はカレー屋さん。この10年ほどでネパール人が経営するインド料理のお店が急増したことの秘密を探索します。前著の異界は国道354線という結界で都心からは見えていなかった世界ですが、今回の異界はすぐ身近にあり、気づかず利用していたことに軽く動揺を覚えました。そもそもネパール人がインドカレーのお店を開くことに何も違和感がなかった、という自分の内向きな感覚にちょっと恥ずかしさを感じました。実は自宅の駅の近くに10年前にポツンと出来たカレー屋があり、開店時に割引のチラシをもらった時とコロナの際に空いている店を探して入った時の2回しか利用したことが無かったのですが、読了後すぐに行ってみました。確かに壁にはエベレストなのかダウラギリなのか山の写真とネパールの国旗が飾られていたので「インネパ」のお店でした。思い切ってお店の女性と話をしたら彼女は本書にも出てくるポカラの出身でした。バターチキンを食べながら、この味、彼らの故郷の味じゃないんだよな、と思ったらなぜかお腹いっぱいになってナン、お代わりできませんでした。ちなみにランチタイムなのに自分以外はテイクアウトのお客だけでした。また行かなくちゃ。本書がこじ開けた異界の扉は、カレー移民というネパール経済の問題ではなく、それを受け止める日本の移民政策の問題に繋がるのだと思います。戦前、沖縄などからアメリカに渡った日本移民が苦難の道を歩みながら、アメリカ社会でのポジションを獲得していったように、バグルン出身のカレー移民の「セカンド・ジェナレーション」たちが日本社会での居場所を見つけることができるかどうかは、人口減少社会の日本の自分ごとのテーマなのだと思います。近所のお店のバターチキンは辛口にしてもまだ甘かったですが、カレー移民問題は、きっともっと辛くて、そして苦い味なのだと思います。
投稿元:
レビューを見る
最近読んだ新書のなかでダントツに面白かった。
読後に改めて自分の住む街を見晴らしてみると、たしかにある、インドネパール系のカレー屋さん。飛び抜けて美味しいカレーお店もあれば、どこかで食べた味と同じだなと感じることもあり、その違和感というか類似性の謎が解けた一冊でした。
この本のすごいところは、インドネパール系のカレー屋さんのルーツから、そこで働く人が日本にやってきた背景や社会情勢、それからカレー移民第二世代の現在の生活までも綿密に書き込んでいて、カレーのように味わい深い、と同時に課題がたくさん煮込まれた書籍になっていること。まさか現地にまで取材に行くとは。タイに暮らしていた経験がある作者さんらしく、グローバルなフットワークの軽さには驚きました。超濃密。
おいしいなぁと思って食べていたカレーが、移民とその市民を迎え入れる日本の問題点も炙り出していて、読後に後をひく“辛さ”。それでいて、読む対象を選ばないバターチキンカレーみたいな親しみやすい文体で、読んで良かったと思えました。
多分、読んでいるほうからして、かなり身近に感じることができる異文化理解のサポート本だと思う。あと単純に、明日はカレーにしよう、と思ってお腹が空いてくるので、ダイエット中の方はご注意を!笑
投稿元:
レビューを見る
街かどで何となく本格的なカレー料理を出す店
を見かけたことがあると思います。
店員もインド人っぽく、カレーをナンで食べさ
せるスタイルはきっとインド本国の味をそのま
ま日本に持ってきたのだろうと、想像してしま
います。
でもその割には店構えは何となく安っぽかった
り、「ナン食べ放題」とか出ていて上品さに欠
けるような気もします。
実はこれらの店はほとんどネパール人が営むカ
レー屋なのです。
歴史を辿れば、ある一人のネパール人が成功し
たことにより、その暖簾分けや模倣が続々と生
まれてきて今に至るとか。
「なぜネパール人が?」
そもそもネパール料理とは全く関連性もないカ
レーを日本人好みにアレンジしているのはなぜ
なのでしょうか。
いわゆるカレーライスが日本以外の国のどこに
も存在していないのと同様に、ネパール人のカ
レーは日本だけのものであるらしいです。
この驚きの事実の謎に迫るのが本書です。
ネパールという国の事情も背景にあり、こうし
た「カレー移民」が生まれている訳を知ってし
まいますと、何となく今まで入りづらかった近
所のカレー店にも足を運んでみようかな、と思
わせる一冊です。