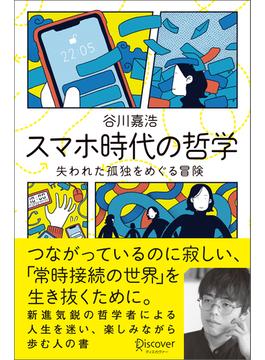- みんなの評価
 2件
2件
スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険 【購入者限定】スマホ時代を考えるための「読書案内」付き
著者 谷川嘉浩
“つながっているのに寂しい、常時接続の世界”を生き抜くための書。
スマホは私たちの生活をどう変えてしまったのか ?
いつでもどこでもつながれる「常時接続の世界」で、
私たちはどう生きるべきか ?
ニーチェ、オルテガ、ハンナ・アーレント、パスカル、村上春樹、エヴァetc……
哲学からメディア論、カルチャーまで。
新進気鋭の哲学者が、様々な切り口で縦横無尽に問いかける !
「常時接続の世界」において、私たちはスマホから得られるわかりやすい刺激によって、自らを取り巻く不安や退屈、寂しさを埋めようとしている。
そうして情報の濁流に身を置きながら、私たちが夢中になっているのは果たして、世界か、他者か、それとも自分自身か。
そこで見えてくるのは、寂しさに振り回されて他者への関心を失い、自分の中に閉じこもる私たちの姿だ。
常時接続の世界で失われた〈孤独〉と向き合うために。
哲学という「未知の大地」をめぐる冒険を、ここから始めよう。
★三省堂書店神保町本店 人文社会ランキング1位!(2022.12.5~12.11集計)
・現代人はインスタントで断片的な刺激に取り巻かれている
・アテンションエコノミーとスマホが集中を奪っていく
・空いた時間をまた別のマルチタスクで埋めていないか?
・常時接続の世界における〈孤独〉と〈寂しさ〉の行方
・〈孤独〉の喪失――自分自身と過ごせない状態
・スマホは感情理解を鈍らせる
・「モヤモヤ」を抱えておく能力――ネガティヴ・ケイパビリティ
・自治の領域を持つ、孤独を楽しむ
・2500年分、問題解決の知見をインストールする
・「想像力を豊かにする」とは、想像力のレパートリーを増やすこと
・知り続けることの楽しさとしての哲学
etc…
◆目次
はじめに
第1章 迷うためのフィールドガイド、あるいはゾンビ映画で死なない生き方
第2章 自分の頭で考えないための哲学――天才たちの問題解決を踏まえて考える力
第3章 常時接続で失われた〈孤独〉――スマホ時代の哲学
第4章 孤独と趣味のつくりかた――ネガティヴ・ケイパビリティがもたらす対話
第5章 ハイテンションと多忙で退屈を忘れようとする社会
第6章 快楽的なダルさの裂け目から見える退屈は、自分を変えるシグナル
おわりに
あとがき
◆購入者限定特典 スマホ時代を考えるための読書案内つき
スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険 【購入者限定】スマホ時代を考えるための「読書案内」付き
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険 【購入者限定】スマホ時代を考えるための「読書案内」付き
2024/11/19 12:55
自己を見つめる濃密な一書
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:岩波文庫愛好家 - この投稿者のレビュー一覧を見る
書題は今風で、著者も若手ではありますが、その実かなり哲学的です。本書に於いて扱っている論題が「孤独」や「寂しさ」であり、それをスマホ世代の現代人に確りとリンクさせてあります。現代を生きる若手世代、否、中高年とて当てはまる内容です。
「孤独」や「寂しさ」というワードは一時期流行りましたが、本書では深掘りして論述されてあります。アニメネタ(エヴァンゲリオン)などを引き合いに堅苦しさを出さず親近感が湧くように仕向けてあるものの、抑えきれずに難解さが零れ出しています。とは言え、じっくり読み込めば読み手自身に考えさせるように投げ掛けられています。
会社生活を髣髴とさせるトピックスがありました。それは、『新しい目標が立てられたら、昨日までと違っていたとしてもそれに飛びつき、これまでのスキルが役立たなくなったら、研修や教育を厭わずに新しいスキルを身につけることができる人材』というセンテンスです。この様な人材が求められる時代だからこそ人々は疲弊していく・・、そういった中で「孤独」や「寂しさ」を感じていくのが現代なのだ、という事が痛烈に感じ取れました。
スマホが普及し、ゲームもネットでオンライン化し、コミュニケーションもスマホで済ませる現代。スマホに依存せざるを得なくなった、或いは依存したくなった老若男女不問の現代人。それはスマホに逃げ込むしかなくなった世知辛い現代社会の癌だと思います。
スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険
2023/11/23 21:14
ネガティブ・ケイパビリティの重要性。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゲイリーゲイリー - この投稿者のレビュー一覧を見る
ネットの普及により常時接続を可能にする諸々のテクノロジーや習慣が、我々を覆いつくしている。
情報の内実や質ではなく人の注目それ自体が価値を持つようになってしまった経済(アテンションエコノミー)や、FOMO(Fear Of Missing Out 見逃す/取り残されることへの恐怖)を駆りたてるSNS。
誰にとっても身近なそれらは、明快でジャンクな刺激や即自的に達成しやすいものばかりを求め、説明がすぐにはつかない事柄に対し即断せず分からないままに留め飲み込まずにとっておく力を奪い続けている。
そうした現代社会に警鐘を鳴らすのが本書だ。
我々が奪われ続けている力の正体とは何なのか、なぜそれが必要なのか、どう取り戻すべきなのかを多様な視点で次々と提示されていく。
様々な小説や漫画、映画といった馴染み深い作品とハンナ・アーレントのような先人の哲学者たちの思考を関連付けて説明してくれるので、私のように哲学に明るくない読者も道に迷うことはない。
むしろ本書をきっかけに哲学に興味関心を抱く読者は多く存在するのではないだろうか。
それほどまでに著者の語り口は敷居の高さを感じさせず、我々読者の足元を常に照らしてくれる。
そんな著者が提示するネガティブ・ケイパビリティの重要性は誰もが知っておくべきだろう。
コスパやタイパといった、チェリーピッキング(都合のいい箇所だけを拾うこと)的価値観が重宝される現代。
しかしチェリーピッキングとは正反対である、自分の中に安易に答えを見つけようとせず把握しきれない謎をそのまま抱え、そこから新しい何かをどこまでも汲み取ろうとする姿勢(ネガティブ・ケイパビリティ)は、今だからこそ必要であると痛感させられた。
また、自分を一枚岩にしてしまう自己啓発文化にも著者は言及していく。
「内なる声に従え」や「本当にやりたいこと」といった文言は、たった一つの真実としてどこかに必ず定まるはずだと前提条件の元成り立っている考えであり、自身の多様性を押し殺し時間的変化の可能性を否定することに繋がるのだと。
加えて、自己啓発の論理はすべてを各人の問題に回収することで、社会や集団のゆがみや問題点を放置することを促す手助けとしても機能する側面を持ちうるのだ。
そこから脱却するためには、孤独を保ち、自己対話をする他ない。
「書く」といった行為を通じて、自身に他者性を持たせること、つまり「書かれた私」と「書き直す私」に自己を分裂することで自ら色々な問いを受け取るのだ。
そうした思考の痕跡を通じて発生する自身との対話、ラリーがどれほど発生したかによって文章の完成度は左右されるという著者の一文に深く共感したのはきっと私だけではないはず。
そう、本書は自身の未熟さ不完全さを受け止め、臆することなく自己対話という一歩を踏み出してみようときっかけを与えてくれるのだ。