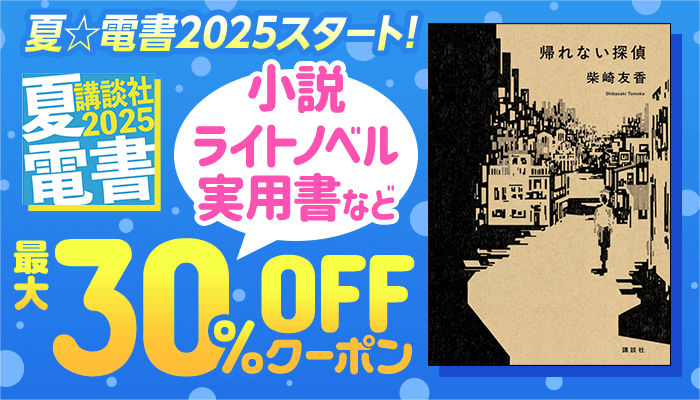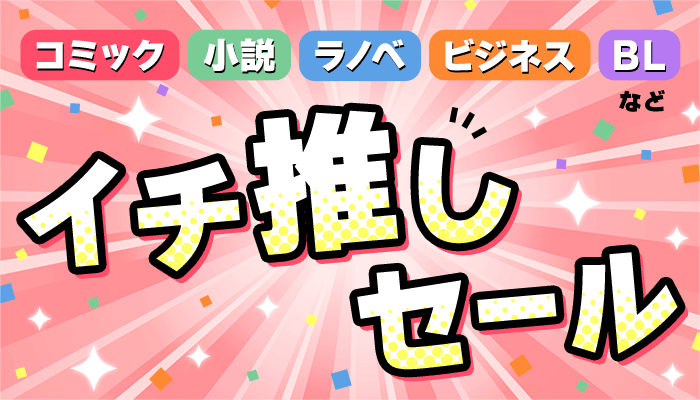- みんなの評価
 7件
7件
ローマ亡き後の地中海世界
著者 塩野七生
476年、西ローマ帝国が滅び、地中海は群雄割拠の時代に入る。「右手に剣、左手にコーラン」と、拉致、略奪を繰り返すサラセン人の海賊たち。その蛮行にキリスト教国は震え上がる。拉致された人々を救出するための修道会や騎士団も生まれ、熾烈な攻防が展開される。『ローマ人の物語』の続編というべき歴史巨編の傑作。※当電子版は単行本上巻(新潮文庫第1巻、第2巻)と同じ内容です。地図・年表なども含みます。
ローマ亡き後の地中海世界(下)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ローマ亡き後の地中海世界 上
2009/02/11 02:21
海賊、拉致...現代日本にもかかわる重大問題
8人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コーチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
西ローマ帝国が崩壊し、ゲルマン人の移動がひと段落した8世紀以降、西ヨーロッパの人々を恐怖のどん底におとしいれたのが、地中海の反対側、北アフリカからやってくるイスラムの海賊だった。彼らは聖戦の名のもと、おもにイタリア・フランスの海岸地帯を襲い、キリスト教徒に対する略奪、拉致、殺害を幾世紀にもわたって繰り返した。彼らによって拉致された者たちはほとんどが奴隷となり、悲惨な人生を送った。
中世の地中海におけるイスラムの海賊については、私も本書を読むまではその存在さえも知らず、彼らの蛮行と被害者の不幸についての記述にはただショックをうけるばかりだった。ローマ人の物語全15巻を書き終えた塩野七生が、西ローマ滅亡後の地中海世界の悲惨をここまでえぐりだした理由は、パクス・ロマーナに象徴される平和と秩序の意味を、その反転としての無秩序と混乱と対比させることで、より鮮明に浮き立たせることにあったのではないかという気がする。
悲惨な物語はそれでも、数々の感動的な出来事も伝えている。
シチリアは、海賊のたび重なる攻撃により9世紀にイスラム教徒の手におちるが、それをふたたび、キリスト教徒の手に戻したのは、11世紀にその地を征服したルッジェロ率いるノルマンの騎士たちであった。しかし征服後、彼らはイスラムの住民を一切差別せず、イスラム教徒が異教徒に課したような重税も課さず、完全なる信仰の自由と平等を全住民に保証したという。両シチリア王国として教科書にも登場するノルマン人の国家はこのように、いにしえのローマと同じく宗教的にはすこぶる寛容であった。ノルマン人とは、一般に「ヴァイキング」と呼ばれた中世の典型的な海賊のことなのだから、なおのことおもしろい。のちに第五次十字軍を率いながら、イスラム教徒の血を一滴も流さず、巡礼者の保護など平和的な協定をイスラム側と結んだ神聖ローマ帝国皇帝フリードリッヒ2世も、このシチリア王国で育った人間の一人であった。
そして、限界状況においてこそキリスト教の愛の精神は真に試され、また強い力でもってそれが発揮されうることの大きな証しともいえるのが、海賊による拉致被害者を救う団体の涙ぐましい活動である。フランス人修道士マタの始めた救出修道会と、スペイン人騎士ノラスコの始めた救出騎士団二つの団体はともに、ヨーロッパ中の教会や信者から寄附を集め、それを身代金として、北アフリカに奴隷としてとらわれている名もない人々を数多く救出した。時には救出者自らが人質となったり、宗教上のいざこざ、航海中の事故(彼ら自身海賊に出会う危険と隣り合わせである!)等で身の危険を伴う仕事を彼らは、ただ苦しんでいるキリスト教徒を救わんがためにおこなった。実際、救出者の多くがこの活動を通じて命を失った。
この活動には当然ながら、身代金目当ての海賊行為を間接的に助長しているというジレンマがつきまとう。実際、教皇が彼らへの寄附の奨励をやめた時期もあったが、それでも彼らの献身的な救助活動は、その後も長く続けられたという。
最後に一言。本書で扱われているのは、遠い時代の遠い国の出来事などでは決してない。北朝鮮による拉致被害、ソマリア沖の海賊船被害と、程度の差こそあれ、国民の生命・財産をおびやかす同様の事態に直面している点では、現代の日本も同じである。本書に描かれた悲劇を深刻にとらえるならば、これらの問題に安穏とした態度でのぞむことはもはやできまい。
ローマ亡き後の地中海世界 下
2009/03/28 10:54
恒久平和はいかに実現されるべきか
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コーチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
本巻では引き続き、地中海を暴れまわるイスラムの海賊とヨーロッパのキリスト教国との攻防が描かれる。
ときは15世紀、暗黒の中世が終わり、ヨーロッパも次第に強大化してゆく。しかし、海賊被害は減るどころか増える一方であった。その主な原因は、ビザンツ帝国を滅ぼし、西方への勢力拡大を狙うオスマン帝国が、海賊をヨーロッパかく乱の道具として利用したためである。
その後の地中海の平和は、キリスト教徒VS海賊+オスマン帝国の間の力関係によって左右される。キリスト教側が、海賊とそのバックにあるオスマン帝国に打撃をあたえれば、それに比例して罪なき民衆への拉致や略奪は減り、負ければ逆に、これらの被害が増大し、地中海はますます無法地帯となった。
キリスト教側の政治的利害や打算もまた、海賊をのさばらせる原因となった。当時成長しつつあった君主同士の、あるいは君主と教会との対立は、オスマンや海賊との妥協、同盟を生み、海賊の首領ハイルディーン(通称「赤ひげ」)を国賓として招待するフランス王フランソワ1世のような恥知らずな人物も現れる。「海の狼」と呼ばれた海賊退治の名将アンドレア・ドーリアも、常に相手を圧倒しつつ、彼らを撲滅する決定打をあたえなかった。もしかしたらそれは彼らがいなくなっては職を失うという彼自身の計算にもとづいての行動かもしれないとは、作者の皮肉まじりの分析である。
逆に純粋に宗教的な熱情だけで結集し、オスマンの大艦隊の襲撃をわずかな兵力ではね返したラ・ヴァレッテ率いるマルタ騎士団の勇姿は、感動的である。戦いを伝える本書の記述にも迫力があり、海賊の親玉ドラグーが騎士団の打った弾に当たり絶命する場面など、痛快でさえある。この1565年のマルタ島攻防戦は、後のイスラムに対するヨーロッパ世界の反撃の口火を切る重大な戦いとなり、数年後のレパントの海戦では、ヨーロッパ連合軍はオスマン帝国を負かし、地中海の制海権は完全にキリスト教徒のものとなった。
しかしながら、キリスト教徒の英雄となったマルタ騎士団も、普段は一般のイスラム船から略奪をし、イスラム教徒と融和したヴェネツィア船にも攻撃をしかけるなど、敵と変わらぬ海賊行為を行っていた。地中海の制海権をめぐる争いは、正義や公正の観念よりむしろ不寛容な復讐の原理にもとづいたものだったのかもしれない。その後も海賊行為は続き、完全にそれが地中海から消えるのは、19世紀も半ばになってからであった。
このような問題を考えるうえで、ローマ亡き後の地中海の何百年にもおよぶ悲惨を記した本書の最後に添えられた「附録1」という文章は、暗示的である。それはローマ帝国、ヴェネツィア共和国、スペイン王国それぞれが行った海賊対策とそれによって有効となった平和の期間について伝えている。ローマは、海賊を退治しただけでなく、彼らを海賊業から足を洗わせ、内陸部に移住させ農耕の民に変えた。それによる平和は600年続いた。ヴェネツィアも、海賊を撃退すると同時に、彼らを船の漕ぎ手や修理工として雇うことにより、自国の共同体に組み入れて行った。それによる平和はアドリア海という自国の貿易に関わる地域に限られるものの、800年続いた。スペインは、北アフリカの海賊の本拠地を占領し、そこに砦を築いた。しかし、付近の海賊被害はまったく減らなかった。したがって、海賊対策の有効期間はほとんどなし。
たがいの利害を調整しながら敵との共存・共生を実現したローマ人やヴェネツィア人の現実主義は、恒久的平和がいかに実現されるべきかについて、大きな教訓をあたえてくれるものかもしれない。
ローマ亡き後の地中海世界 下
2009/07/03 20:25
スペイン王カルロスの、人の命をゲーム感覚でしか捉えられない無神経さには本当に苛々します。これが政治というなら、今の自民党政治と何にも変わりません。パワーゲーム?子供の遊びとおんなじじゃない・・・
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
読んでいて苛々してしまうのは、「第五章 パワーゲームの世紀」におけるアンドレア・ドーリアの動きであり、ドーリアをしてあえて敗戦の道を選ぶことをさせたスペイン王カルロスの、人の命をゲーム感覚でしか捉えられない無神経さなのですが、実はこれこそが政治でありパワーゲームであることを知ると、やはり政治家と軍人だけはなるものじゃあない、と思います。
それでも、インカ帝国を滅ぼしたコルテスを例にひきながら、最後まで英国のような世界戦略を持ちえなかったこのスペイン人の動きを自己中心的な民族性ゆえと断じれば、ああ、そうかと得心が行きます。それに比べてヴェネツィアの視野の広さ。でも、その視野をもっていても大国の思惑に左右されてしまう国そのものの規模の差、そういうこともよくわかります。
この時代のスペインは、ヨーロッパ一の強国であっただけでなく、新大陸までも支配下に収め、軍事面に留まらず経済面でも超がつく大国であったのだ。
「パクス・ロマーナ」とは「ローマによる世界秩序の確立」だが、この時代、「スペインによる世界秩序の確立」が成り立ったとしても不思議ではなかった。スペインは、大植民地帝国にはなった。だが、「パクス・ブリタニカ」になる以前に、「パクス・ヒスパニカ」の時代は訪れなかったのだ。その要因の第一は、近視眼的、とするしかないスペイン人の政治感覚、にあったのではないかと思う。つまり、自分たち以外の他の民族を活用する才能に欠けていた、ということである。インカ帝国を滅ぼしたのもスペイン人だった。
と、まさに一刀両断。
そして、ちょっと楽しいのが数多く掲載されている当時の君主たちの肖像画で、65頁(215頁とも)のアンドレ・ドーリアのそれがピカイチだと思う私は図版出典一覧をチェックして、それがドーリア・パンフィーリ美術館(ローマ/イタリア)セバスティアーノ・デル・ピオンボ画 Bridgeman Art Library,London、とあって、このにある「ドーリア・パンフィーリ」はアンドレ・ドーリアと関係があるのだろうかと思ってしまいます。
それと59頁(97頁とも)のジュリオ・デ・メディチとレオーネ十世の画のただならぬ雰囲気、それも図版出典一覧でチェック。げげ、けの鬼太郎、ウフィッツィ美術館(フィレンツェ/イタリア)ラファエッロ画 AKG-images、だそうです。ラファエロか、でも私にはセバスティアーノの筆の現代性に軍配をあげましょう。
現代的、ということでいえば183頁の法王パオロ三世がいい、と思ったらやはりティツィアーノですか。国立カポディモンテ美術館 Alinari Archives,Firenze 、これなら当時の肖像画の多くが彼の手になる、というのも肯けます。133頁のジュリア・ゴンガーザの肖像は、画の出来というよりは彼女の美女ぶりを伝えるので注目。ウフィッツィ美術館、セバスティアーノ・デル・ピオンボ画 Scala Archives,Firenze。
それとこの本では、巻末に附録二 関連する既刊書として、塩野自身の著作の一部が、簡単なコメントととともに掲載されていますが、この本を読む限りは塩野には旧作にはほとんど手直しするところがない、と思っている気配があって、小説であればともかく歴史にかんする本で20年以上も前の作品なのに、その姿勢って偉いなあ、って思います。
基本的には『海の都の物語』、『コンスタンティノープルの陥落』『ロードス島攻防記』『レパントの海戦』三部作とともに読まれるべきなんだろうなあ、って思います。ヴェネツィアの視点から見た地中海世界と、地中海世界の真中からイスラム世界、スペイン、フランス、イギリス、ローマ、ジェノヴァなどを見れば、確かにその時代の相がいっそうはっきりと見えて来ます。
詰まらないことで気になったのが、第六章 反撃の時代の291頁の図版。右の人物は「ヴァレッタ」と表記されていますが、本文ではジャン・ド・ラ・ヴァレッテ・パリゾンで、ヴァレッテと書かれることはあっても、ヴァレッタとは一度としてかかれません。ギョエーテは俺のことかとゲーテいい、です。
以下はデータ篇。
第四章 並び立つ大国の時代
コンスタンティノープルの陥落/読者へのお願い
スルタン・マホメッド二世/エーゲ海へ/海賊・新時代
法王庁海軍/イオニア海へ/西地中海へ
海賊クルトゴル/法王メディチ/「神聖同盟」
パオロ・ヴェットーリ/ジェノヴァの海の男たち
第五章 パワーゲームの世紀
若き権力者たち/法王クレメンテ/「ユダヤ人シナム」
海賊「赤ひげ」/アンドレア・ドーリア
赤ひげ、トルコ海軍総司令官に/チュニス攻略
フランソワとカルロス/フランス・トルコ同盟
対トルコ・連合艦隊/プレヴェザの海戦/海賊ドラグー
アルジェ遠征/ヴェネツィアの「インテリジェンス」
国賓になった赤ひげ/海賊の息子/ドラグー、復帰
マルタ騎士団/「ジェルバの虐殺」/海賊産業
海賊ウルグ・アリ/聖ステファノ騎士団
第六章 反撃の時代
マルタ島攻防記/「マルタの鷹」/攻防始まる
ドラグー、到着/眼には眼を/防衛成功
トルコとヴェネツィア/キプロスの葡萄酒
レパントへの道/キプロス攻防/連合艦隊結成
「レパントの海戦」/「レパント」以後
第七章 地中海から大西洋へ
ハレムのヴェネツィア女/騎士と海賊
地中海世界の夕暮
附録一 民族によって異なる海賊対策
附録二 関連する既刊書
年表
参考文献 図版出典一覧
カバー ローマ時代の遺跡の向こうに広がる夏の地中海(北アフリカ・リビアのレプティス・マーニャから)撮影 青木登(新潮社写真部)
装幀 新潮社装幀室