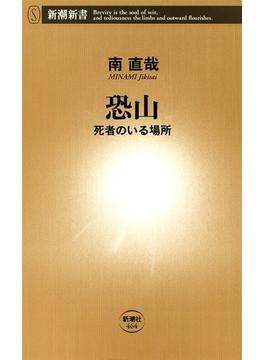- みんなの評価
 1件
1件
恐山―死者のいる場所―(新潮新書)
著者 南直哉 (著)
死者は実在する。懐かしいあの人、別れも言えず旅立った友、かけがえのない父や母――。たとえ肉体は滅んでも、彼らはそこにいる。日本一有名な霊場は、生者が死者を想うという、人類普遍の感情によって支えられてきた。イタコの前で身も世もなく泣き崩れる母、息子の死の理由を問い続ける父……。恐山は、死者への想いを預かり、魂のゆくえを決める場所なのだ。無常を生きる人々へ、「恐山の禅僧」が弔いの意義を問う。
恐山―死者のいる場所―(新潮新書)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
恐山 死者のいる場所
2022/09/24 12:48
「恐山とは巨大なロッカーである」(137頁)
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Haserumio - この投稿者のレビュー一覧を見る
ふと思い立って一読。一昨年に父を、昨年母をいずれも病気で喪ったこともあり、心のどこかで(あるいは無意識裡に)「死者との向きあい方」について思念し続けていたのだということを、本書を読み終えて気づかされた次第です。それは人それぞれでいい、「そもそも、どう弔い追悼するかは、弔い追悼する人の意志の問題」(160頁)であるという著者の言葉に安堵するとともに、恐山という存在について、いや恐山という存在から、多くのことを学ばせて頂きました。(余談ですが、イタコについては、昔、中学生時の修学旅行で恐山に行き、友人の長谷川君が生徒を代表して「口寄せ」を体験。本人がその内容について「当たっている」と驚いていたことを思い出しました。)
「「無記」のカードだけでは割り切ることのできない、動かしがたい、圧倒的な想いの密度と強度―それを私はリアリティと呼んでいます-がそこにはある。・・・ 二年が経つ頃でしょうか。突然、「あっ、ここには死者がいるんだ」。そう思ったのです。死者は実在する-。」(104~6頁)
「生者は、死者という「不在の関係性」を持ち切れません。その代わり、死者にその「不在の意味」を担保してもらう他ないのです。死者に関係性や意味を預かってもらうしかないのです。そしてそのための場所が、ここ霊場・恐山なのです。」(133~4頁、死者が亡くなる前に存在していた強い相互関係性から生じて生者の側にある息苦しいばかりの重荷(負担)を吐き出して楽になる =「おろす」(74頁)場が恐山なのであろう。)
「死者は彼を想う人の、その想いの中に厳然と存在します。それは霊魂や幽霊どころではない、時には生きている人間よりリアルに存在するのです。」(143頁、同旨160頁)
「死者儀礼と仏教の関係には、何か必然的なものがあるわけではありません。・・・ 仏教の世界観に基づいてお葬式をやってほしい、という人がある程度いたからこそ、その役割を担っただけであって、仏教の教義から必然的に導けるものではありません。」(178頁、それは単なる葬式仏教に過ぎない。)
「仏教が恐山を規定しているわけではないけれど、その思いを汲む器として仏教は機能しているのです。人間は水を飲むのにもコップという器を使います。人間の衝動というものは、何かで汲み上げられない限り感情にはなり得ません。死に対する衝動を汲み上げるにも、何らかの器が必要なのです。その器として機能したのが、日本の場合は仏教だったのです。それは恐山でも同じです。仏教の器があるからこそ、そこに入っているものの匂いや味、形がわかるのです。人が死を思い、故人を拝むには器が必要なのです。目に見えるものをよすがとしなければ、死者というものも立ってきません。何もないところで、「自由に死者を想い出してごらん」と言われても、思考は次第にとりとめなく拡散するばかりで、しまいにはどうしてよいかわからなくなるでしょう。そこには何らかの器が必要なのです。」(180~1頁、あるいは、形のないものを一応の形あるものにするための「仕掛け」といってもよいのであろう。)
「恐山というところは、死者に近づくことができる場所ではあるのですが、さらに深く考えていくと、死者と距離を作るための場所でもあるのです。・・・ それゆえに人々はひきつけられる。恐山とはそのような場所なのです。」(186頁、適度な距離感の保持!)
なお、恐山が臨済宗(総本山は永平寺)の系列(同じ宗派)であることや、元来、恐山とイタコ(民間信仰上の霊媒師・巫女さん)の間には何らの関係もない(別の存在である)ことも、勉強になりました。