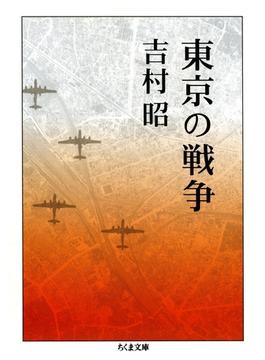- みんなの評価
 6件
6件
東京の戦争
著者 吉村昭 (著)
物干台で凧を揚げていて、東京初空襲の米軍機に遭遇した話。戦中にも通っていた寄席や映画館や劇場。一人旅をする中学生の便宜をはかってくれる駅長の優しさ。墓地で束の間、情を交わす男女のせつなさ。少年の目に映った戦時下東京の庶民生活をいきいきと綴る。抑制の効いた文章の行間から、その時代を生きた人びとの息づかいが、ヒシヒシと伝わってくる。六十年の時を超えて鮮やかに蘇る、戦中戦後の熱い記憶。
東京の戦争
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
東京の戦争
2007/01/08 00:09
戦時の東京での生活が描かれている希少なエッセイ
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ドン・キホーテ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は吉村昭が第2次大戦に関する記憶を綴ったものである。終戦から62年も経たこの東京も戦争という悪夢の中に存在した都市であった。さすがに62年も経過するとあれほどの辛い経験をした人々も世代交代によって少なくなり、存命の人も記憶が薄れていくばかりである。
米軍機B−29による空襲の猛烈さは何回も聞かされたことがあるのだが、戦後世代にとっては実感が伴わない。空襲によって非戦闘員一般に犠牲者が多数出たわけだが、当時は処理出来ずに道端に黒焦げになった死体が遺棄されていた。今だったら、食事がまともに喉を通らないであろう。これがこの大都市東京で実際におきていた事実なのである。
かなり些細なことにも戦時特有の現象が出ていたようだ。空襲によって鉄道も相当の被害があり、戦後の買出し客で長距離であるにもかかわらず、列車は超満員であった。家の着物などと物々交換した上に得た食糧を、また超満員の列車に乗って東京まで運ぶわけである。要所要所で取締りが行われ、没収の憂き目にあう。
かと思うと、吉村少年(中学生)はそういうさなかに一人旅を敢行した。旅行許可証がなければ長距離のたびは禁止された時代だが、100キロ以内であればまだ自由であった。甲州でブドウを分けてもらって味わったり、一晩宿泊させてもらったり、人々の親切に触れたりで貴重な経験をしたようだ。
戦中の世相は空襲一色ではなく、それ以外の生活があったことは当然であるが、戦災だけが強調されるあまり、それ以外の生活はどうであったかについては、あまり知られていない。戦災以外は現在と変わらないものなのか、違うものならばどのように違うのか、戦争を知らない世代の好奇心はそれなりにある。
本書はそれに答えている希少なエッセイである。石鹸、タバコ、戦争と男女、進駐軍、蚊、虱、食べ物など、戦時生活のまとまった話が得られる書である。
東京の戦争
2023/08/10 16:46
忘れてはいけないこと
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
作家吉村昭さんは昭和2年(1927年)東京日暮里に生まれた。
生まれた頃から「事変」と称する戦争が続いていて、
昭和20年の敗戦まで戦争とともに生きてきたという。
ただ吉村さんは年齢が少し満たなかったおかげで入隊もせず、
疎開もせずに東京に残っていたという。
「日本人が過去に経験したことのない大戦争下の首都」で、
庶民はどのような生活を送っていたのかを書いておくことに意味があると綴ったのが、
この『東京の戦争』である。
2001年に刊行されている。
そのあと、2006年に吉村さんは亡くなっているから、
戦争の記憶としてこの一冊が残された意義は大きい。
「空襲のこと」「電車、列車のこと」「蚊、虱・・・」「戦争と男と女」
「人それぞれの戦い」「進駐軍」「父の納骨」など
16篇の回想記から成り立っているが、
その一篇一篇がまるで短編小説のような雰囲気だし、
実際ここに書かれた事実がいくつかの短編となって遺されてもいる。
吉村さんは戦時中に母を亡くし、終戦後間もなくして父も亡くしている。
23歳であった兄も戦争で亡くし、東京大空襲の際には多くの死体を目にしている。
それは吉村さん固有の経験というより、
当時の多くの日本人がそうであったといえる。
そんな中でも、普段と変わらない生活を多くの人たちが営んでいた光景も描かれる。
戦争がおわって78年。
誰もが忘れかけている時代だからこそ、
何度も読み続けていきたい。
2025/03/30 12:24
良いですね
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
昭和2年生まれの著者が15歳の時に東京初空襲を経験し、18歳で終戦を迎えたとのことです。その間ずっと東京で日々を暮らし、その庶民生活を記したものです。これは凄いです。