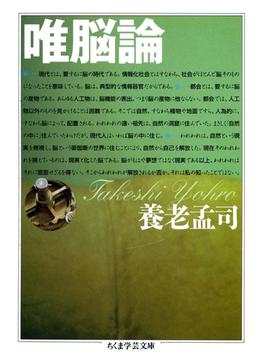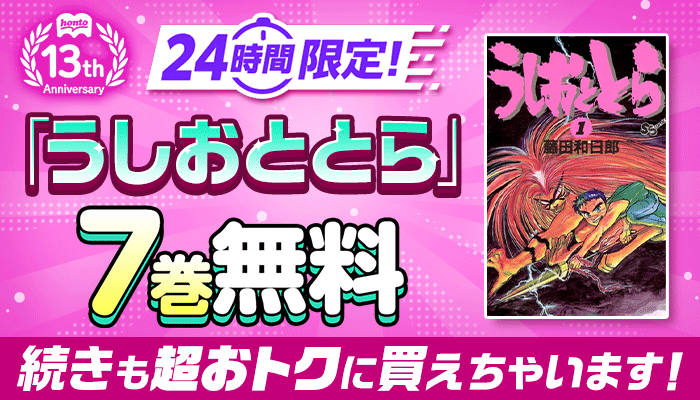- みんなの評価
 3件
3件
唯脳論
著者 養老孟司
文化や伝統、社会制度はもちろん、言語、意識、そして心…あらゆるヒトの営みは脳に由来する。「情報」を縁とし、おびただしい「人工物」に囲まれた現代人は、いわば脳の中に住む。脳の法則性という観点からヒトの活動を捉え直し、現代社会を「脳化社会」と喝破。一連の脳ブームの端緒を拓いたスリリングな論考。
唯脳論
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
唯脳論
2002/06/30 19:30
あの一撃は忘れがたい
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:のらねこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
さて、思えばこの本を読んだのも随分と昔になるな。昔のことであるけれども、ずこんと脳髄にしたたかなる打撃を感じたことは覚えておる。
本書の趣旨は、極めて単純。
人間が感知しうる事物は脳の構造によりあらかじめ規定されている。人類の文明、脳内のイメージを現実化させることにより、発達してきた。都市という「人工物」のなかで一生を終える現代人は、すでにヴァーチャルな世界に生きている。
なかなかに卓見であった。
著者の養老教授は、この本を上梓した当時、東大に何十年も勤めていた解剖学の先生であった。この本が評判になり、以降、多数の著作を発表される。「脳」というハードの制約から人間の限界や言動の理由を解く発想は、そうした経歴からきている。
この本から得た「もののみかた」は、今では、自分の血肉になっている部分がある。
唯脳論
2020/04/12 13:58
近年の脳ブームの端緒を拓いた一冊です!
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、近年の脳ブームの端緒を拓いたとも言われる養老孟子氏による作品で、脳の法則性という観点から人間の活動を捉え直し、現代社会を「脳化社会」と呼ぶと同時に、脳化とともに抑圧されてきた身体、禁忌としての「脳の身体性」について言及した画期的な一冊です。同書の構成は、「唯脳論とはなにか」、「心身論と唯脳論」、「<もの>としての脳」、「計算機という脳の進化」、「位置を知る」、「脳は脳のことしか知らない」、「デカルト・意識・睡眠」、「意識の役割」、「言語の発生」、「言語の周辺」、「時間」、「運動と目的論」、「脳と身体」となっており、非常に興味深く読めます!
唯脳論
2004/10/12 01:46
養老孟司はここからはじまる。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ナミスケピエール - この投稿者のレビュー一覧を見る
脳という器官の仕組みを元に、人間にまつわるさまざまな事象を(文化までも含めて!)説明する。作者のこの後の全ての著作の根底に流れる考えを正面から説いた本。
本来は時間の流れを持たない視覚と、時間と切り離せない聴覚を、脳内でどうにかして結合させたところから言語が生まれたというのは興味深く感じた。そこから説明すると聴覚言語と視覚言語が能力的には同時に生まれたという事になるのだけれど、言語学をやる人の目からみたらこの議論はどうなんでしょう?
また、脳という器官の機能する形が、文化を含めて人間の考え出す全てのものに投影されている、と言う。貨幣経済や言語や進化論や、それこそ本当に全てのものに。しかしまぁ、人が考え出し、人が納得して受け入れるものが、全て脳のシステムの模倣なのだとしたら、人間の文化とその中で暮らす人間は<究極のナルシシズムの表現>ということになってしまうのじゃないだろうか。もし、思考する器官のシステムが人間と違う異星人が地球にやってきて、人間の作ったものを見たら、全く理解できずに「なしてそないなんのや!(なぜかエセ関西弁)」と叫ぶのだろう。
氏の理論を拡張すると、というかそのままうけとっても、人間は、いや生き物は永遠に外界をありのままに受け取ることはできないということだ。これはなんとも切ないが、今ではどこででも言われている。(そういや京極夏彦も「ウブメの夏」でそう言っていた。彼もこの本を読んだのだろうか。)
養老氏がこれを書いたのは今から15年前、1989年のことである。やはり氏は時代を一歩先どっていたといえるだろう。