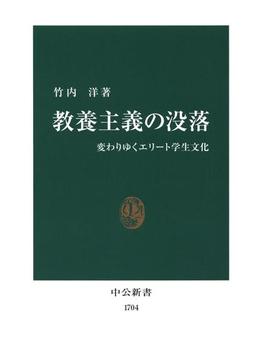- みんなの評価
 6件
6件
教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文化
著者 著:竹内洋
一九七〇年前後まで、教養主義はキャンパスの規範文化であった。それは、そのまま社会人になったあとまで、常識としてゆきわたっていた。人格形成や社会改良のための読書による教養主義は、なぜ学生たちを魅了したのだろうか。本書は、大正時代の旧制高校を発祥地として、その後の半世紀間、日本の大学に君臨した教養主義と教養主義者の輝ける実態と、その後の没落過程に光を当てる試みである。
教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文化
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文化
2016/06/08 09:01
日本の大学教育の考え方の変遷がわかります!
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、教養主義、すなわち書物などから得た知識をよりより多くもつことを目的とした教育のあり方、が1970年代まで我が国においては当たり前であったにもかかわらず、それ以降急速に変化を遂げ、今や教養主義は完全に没落したことを解説した書です。本書は、大学教育に焦点を当て、大正期にまで遡って、そこに横たわっていた教育的思想について検証していきます。日本の高等教育を考える上で、非常に画期的で興味深い一冊です。
教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文化
2011/02/04 00:03
没落した教養主義にとってかわるものとは?
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Kana - この投稿者のレビュー一覧を見る
明治以来の日本の教養主義について書いている. 旧制高校に発したエリート学生文化における教養主義はやがてマルクス主義にとってかわられていく. 1930 年代にマルクス主義が弾圧されるようになると教養主義が復活するが,戦後はふたたびマルクス主義とのむすびつきがつよくなる. しかし,石原慎太郎に代表されるあたらしい世代は教養主義ともマルクス主義とも距離をおく. 戦後つぎつぎに新設された文学部に教養主義はささえられるが,全共闘運動のあと 1970 年代にキャンパスから駆逐されていく. そして,教養主義への反乱を最終的に完成したのがビートたけしだと著者はいう.
終章で著者は現代の大学生が人間形成の手段として従来の人文的教養ではなく,友人との交際を選ぶ傾向が強いこと,そして前尾繁三郎や木川田一隆にみられるように教師や友人などの人的媒体が教養がやしなわれる場として重要であり,これからの教養を考えるうえで大事にしたいと書いている. 教養主義が没落したといっても,今後もべつの教養主義がいきのこっていく可能性を指摘しているといえるだろう.
この本には海外の教養主義についての記述もわずかながらみられるが,ほとんどの記述は日本にフォーカスしている. 海外とのつながりについて,もうすこし語ってほしかった.
2025/04/28 14:31
教養主義の流れ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
教養とは何かを考えてしまう。日本の場合、明治以降西洋文化に追い付けとばかりに西洋の考えや思想を知的エリートとしての旧制高校、帝国大学で教え学び始め、それが学生の主体となってきた。「三太郎の日記」「三四郎」マルクスの論文等を読むのが当たり前であり、それが教養として流れてきたと。また、それらを読む道具として出版社の翻訳本、文庫、新書が売れ戦後ピークを迎えたが学制改革や高等教育の普及により古い教養主義は崩壊してしまった。と著者は述べている。現代における教養とは何か。本を読むこと、教養を深める事とはを考えさせられる。