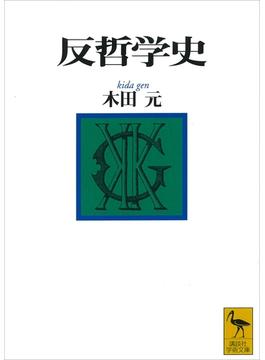- みんなの評価
 5件
5件
反哲学史
著者 木田元
ニーチェによって粗描され、ハイデガーによって継承された「反哲学」は、西洋2500年の文化形成を導いてきた「哲学」と呼ばれる知の様式を批判的に乗り越えようとする企てである。この新しい視角を得れば、哲学の歴史も自ずからこれまでとは違って見えてくる。古代ギリシアから19世紀末にいたる哲学の道筋をたどり直す「反哲学史」。講談社学術文庫『現代の哲学』の姉妹編。
反哲学史
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
反哲学史
2020/04/08 08:39
ニーチェやハイデガーによる「反哲学」の視点をもつと、これまでの哲学の歴史が違って見えてきます!
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、西洋諸国で打ち立てられ、それ以降2500年もの文化形成を導いてきた「哲学」という知の様式を批判的に乗り越えようとした画期的な「反哲学」という企てについて分かりやすく解説された一冊です。同書によれば、実は、この「反哲学」はニーチェによって粗描され、ハイデガーによって継承されたようです。そして、この「哲学」という視点をもつことで、これまで私たちが信じてきた哲学の歴史も自ずから違って見えてくると主張されています。同書では、「ソクラテスと哲学の誕生」、「アイロニーとしての哲学」、「ソクラテス裁判」、「ソクラテス以前の思想家たちの自然観」、「プラトンのイデア論」、「アリストテレスの形而上学」、「デカルトと近代哲学の創建」、「カントと近代哲学の展開」、「ヘーゲルと近代哲学の完成」、「形而上学克服の試み」、「19世紀から20世紀へ」といったテーマで話が進行され、非常に興味深い内容となっています。
反哲学史
2004/02/08 20:40
現代の文人・木田元の語りの藝
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オリオン - この投稿者のレビュー一覧を見る
文庫解説で保坂和志が「この本を読んだら『現代の哲学』や『哲学と反哲学』へ進むのが自然なのかもしれないけれど、まずはもう一度この本を読み直してみるのが一番いいんじゃないかと思う」と書いている。
だからというわけではないが、年末から年始にかけて繰り返し繰り返し読んだ。たとえばイデア論という不自然な知(形而上学的思考様式)の起源をめぐってプラトンとユダヤ系思想とのあり得たかもしれない出会いの可能性やプラトン‐アウグスティヌス主義的教義体系とアリストテレス‐トマス主義的教義体系との関係にふれた箇所、通りすがりに「近代哲学の枠組に収まりきれない」とスピノザに言及されたところや「「生きた自然」という概念を復権することによって形而上学的思考様式を克服しようとする試みを、もっとも壮大なスケールで展開した」ニーチェを取りあげた節などは少なくとも五度は読み返したし、いまもまた最初から読み直している。
実際のところこれほど再読のしがいがある本というのはそうざらにあるものではない。なにしろ大学の一般教養科目の「哲学」で何十年もしゃべってきた講義ノート、それも哲学とはいったい何だろうと自問し考えなおし、そのつど書き替え書き足して形を整えてきた講義ノートが元になっているというのだから、たとえ別の本で読んだのとそっくり同じ文章がいたるところで目についたとしても、それはもう著者の血となり肉となるまで繰り返し語り直されてきたものであって、だからほとんど名人とよばれる噺家の藝の域に達している。
実をいうと私はこれまで木田元の手になるハイデガー哲学紹介にいまひとつ惹かれなかった。ちょうど一年前に読んだ『マッハとニーチェ』だけはすこぶる滅法面白かったけれど、どういうわけか後が続かなかった。『反哲学史』を読んで分かったことがある。『マッハとニーチェ』の面白さは木田元という希代の読書家にして文章家の語り口にあったのだ。(『哲学以外』に収められた「私の文章術」に文章とはリズムだということが書いてある。だとするといまや現代の文人の風格を漂わせる木田元の文章のリズムが私に合う、いや私の方が合うようになったということなのかもしれない。)
というわけですっかり木田元さんの文章に魅了されて、保坂和志が「自然」な流れと書いた『現代の哲学』や『哲学と反哲学』はもちろん、はては『哲学以外』とか『哲学の余白』といった「雑文集」にまで手を出していった。(『反哲学史』の元となった講義ノートの話は『哲学以外』に収録された「『反哲学史』の楽屋ばなし」に書いてあった。『哲学以外』ではそのほか「わが文学の師」日夏耿之介と「わが友ホサカ和志」について書かれた文章がよかったし、『哲学の余白』ではなんといっても「山田風太郎明治小説全集」全七巻の解説が白眉。)
そうなると不思議なものでこれまで喰わず嫌い、いや喰っても好きになれなかったハイデガー哲学の紹介までがやたらと新鮮かつ興味深く読めるようになって『わたしの哲学入門』は『マッハとニーチェ』『反哲学史』に続く反芻本になったし、その余波で同時に読み進めていたハイデガーの『形而上学入門』にまで深い味わいを覚えるようになった。
反哲学史
2004/12/05 22:43
肉声が聞こえた
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:仙道秀雄 - この投稿者のレビュー一覧を見る
若い頃ニーチェの「神は死んだ」という判断に深く感じ入ったことがあった。今もその感覚は残っているし、いろんなことが起こるたびにその判断の正当さを確認している。この本はその延長線で哲学という世界もまたすでに死んだと言っている。その視野はソクラテス→プラトン→アリストテレスに始まり、スコラ哲学を経て、デカルト→カント→ヘーゲル→マルクス、フィヒテ→キルケゴール→ショーペンハウエル→ニーチェ→ハイデガー、サルトルにいたる。最重要人物はプラトンとニーチェである。
ただ、それだけのことならある意味教科書的、哲学辞典的な主張ともなりかねないが、ここにある言葉は、この本の著者、木田元さんの肉声から発せられているように思え、わたしには大変面白く読めた。二読三読する価値はあると思う。木田さんなりにソクラテスやプラトンなどと対話して書かれた言葉だと思う。ここが教科書とは大きく違う。聞くところによると木田元さんは「哲学はケンカだ」と言っているそうで、1972年(木田さん44歳のとき)から毎週月曜日のハイデガーの原書購読をずーっと続けているらしい。半端なコメントをする参加者には「二度とこの場に顔を出すな」と言って罵倒するそうである。こういう野蛮さになにかこの人の本物らしさを感じてしまう。