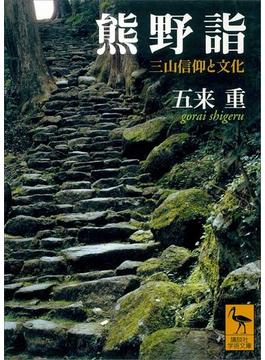- みんなの評価
 3件
3件
熊野詣 三山信仰と文化
著者 五来重
院政期の上皇が、鎌倉時代の武士が、そして名もなき多くの民衆が、救済を求めて歩いた「死の国」熊野。記紀神話と仏教説話、修験思想の融合が織りなす謎と幻想に満ちた聖なる空間は、日本人の思想とこころの源流にほかならない。仏教民俗学の巨人が熊野三山を踏査し、豊かな自然に育まれた信仰と文化の全貌を活写した歴史的名著が、待望の文庫化。
熊野詣 三山信仰と文化
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
熊野詣 三山信仰と文化
2006/12/22 13:59
神仏と死者と僕達
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:SlowBird - この投稿者のレビュー一覧を見る
熊野と言っても広うござんす。行ってみたいとは思っても、観光で満足できるような旅行になるとはとても思えない。とりあえず気分だけでも、などと思って読むと、実は熊野を象徴するいくつかのテーマ毎に掘り下げられていて、むしろ深い精神史に玄妙な心持ちになる。
熊野を象徴すると言えば、サッカー日本代表のシンボルでもあるヤタガラス。なぜこれが神鳥となったかは、日本古代の葬送方法に関わりがある(ゾクゾク)。これと死者の国の観念から、日本人の死生観が解き明かされる。
補陀落渡海もよく知られる伝説だが、山の国であると同時に海の国でもあるニ面性が、この実相に妖しい魅力をもたらす。
一遍上人にとっても、熊野は特別な地。念仏に開眼し、一遍と名乗るきっかけとなった場所である。仏教史と離れて、神仏習合の世界における熊野巡礼の一つとしてこの道筋を辿るのは、視野の広がりを感じる。
それから熊野が重用な役割を果たすのが「小栗判官」の物語。病の体の小栗の乗った土車を、行きずりの巡礼者が少しずつ紐で引いて熊野湯まで連れて行く。これは当時の風習としてあったことで、現代の奇蹟は科学の力で病を治すが、中世の奇蹟はみなの善意で病の者を慰めることであったと著者は述べる。中世という時代の人々の心のありようを掴むのは難しいが、この言葉はそれを見事に表現していていると思う。現代とは価値観も宗教も社会も異なるのに、そうして人の心の連続性が感じられるのは、ひどく嬉しい。
庶民の熊野詣と同様に行われた、天皇、上皇による熊野御幸については、御鳥羽上皇に伴した、というか設営に働いた藤原定家の足跡を、定家の日記を元に丹念に追った記述が楽しい。つまり一行の本体よりも常に一足先に進んで、宿や催しごとの準備をするのだ。宮仕えの役人として汗をかき、早朝、深夜を問わず走り回る。それでいて歌会にも出席しなくてはならず、目が回るような忙しさ、実際に回ってしまったらしい。このあたりの心情にも共感してしまう。
こういった旅路を著者が実際に足を運び、目にした風景、生活と対比させながら語られ、伝統のあるべき姿というのがぼんやりと読者の中に形作られるだろう。伝統をいたずらに振り回す必要もないが、知っておくことには大きな価値がある。改めてそれを刻み込まれたように思う。
熊野詣 三山信仰と文化
2020/03/13 09:50
今なお謎と幻想に満ちた熊野を、歴史書の記述をもとに、その真相を追った名著です!
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、古くから様々な人々が救済を求めて歩いたと言われる熊野を、古事記や日本書紀、さらには多くの仏教説話などの記述を参考に、その「聖地」とも言うべき地域における意味を解き明かそうとした名著です。著者によれば、熊野には、今なお謎と幻想に満ちており、この空間は私たち日本人の思想と心の源流が存在する場であると主張されています。それは一体どうしてなのでしょうか。この疑問を解くには、ぜひ、同書をお読みください。
2025/02/22 17:06
熊野詣の源流
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
蟻の熊野詣で知られる「熊野」。訪れた人は、その神秘や社・地形・巡礼道に何かを感じその源流を知って考えたいと思うのではないだろうか。源流は日本人が古代から信仰していた神仏習合や修験道、葬送の儀式から由来していると。著者は熊野研究の第一人者。庶民信仰や都の上皇や貴族の熊野詣等を史跡や文書をもとに詳細に考察している。宗教史を考えるときに紐解きたい。