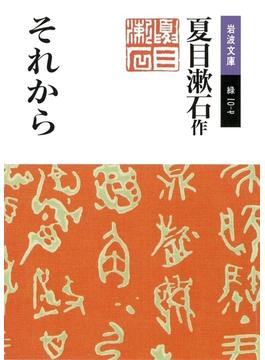- みんなの評価
 9件
9件
それから
著者 夏目漱石 (作)
若き代助は義侠心から友人平岡に愛する三千代をゆずり自ら斡旋して二人を結びあわせたが,それは「自然」にもとる行為だった.それから三年,ついに代助は三千代との愛をつらぬこうと決意する.「自然」にはかなうが,しかし人の掟にそむくこの愛に生きることは二人が社会から追い放たれることを意味した. (注・解説 吉田熈生)
それから
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
それから 改版
2008/09/05 19:19
茫乎と
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
戯れに傍らの白い紙に悪戯書きをしてみる。天の余白に<『それから』相関図>と大書する。左側に両矢印の線を引き、上に「富」、下に「貧」と書く。今度は下部に同じように両矢印の線をひき、左側には「貴」といれ右側は「俗」とする。左側は「意思」としてもいいかもしれない。そうすれば右は「行動」だろうか。次に左側上部の空白に点をいれる。やや大きくいれてもいい。物語の主人公なのだから。点の近くに<代助>と書けば分かりやすい。その点と極になるところ、すなわち右側下部に別の点をいれる。ここにも<平岡>と代助の友人の名をいれてみる。つまり点<平岡>は、貧であり俗に片寄ったところにある。<平岡>の妻三千代の点は、先につけた二つの点を結ぶ真ん中あたりが落着きいいかもしれない。貧しさということでは点<平岡>と同じ高さでもよい。
夏目漱石の『それから』の登場人物を図にしているばかりだ。代助の父や兄はもちろん上流生活を営んで豊かであるから上部でいいが、俗ということでは右側にある。ただ点<平岡>を越えることはない。嫂梅子は代助に言わせれば俗なのだが、私的には三千代と上下の対極する箇所に点をうちたいところだ。この物語の概ねの登場人物の点がこれではいったことになる。代助と三千代を除く点をひとつの囲いにして<世間>と書いてみた。<社会>とでもいい。あるいは、代助の言い草のように<敵>としてもいい。代助と三千代の点が淋しそうだから二つの点を線で結ぶ。線の上に<愛>と書く。あるいは<追放>と書いてみるか。
それから、点<代助>を中心にしてぐるぐる渦を書いてみた。その際には「ああ動く。世の中が動く」と、物語の最後の代助の言葉を唱えてもよかろう。先に代助と三千代の間に引いた<愛>の線がゆがんでみえる。代助が行った行為が<世間>という枠組みからみればいかに馬鹿げたことであるか、どのように代助が釈明しようと、渦は強くつよくひく。やがてその渦が<世間>の囲いの中にはいってしまうまで。代助は「ただ職業のために汚されない内容の多い時間を有する、上等人種と自分を考えている」「遊民」ではあるが、実際には愛する三千代ひとりさえ(もちろん友人の妻であるという障害があったとしても)仕合せにできない存在なのだ。兄がそんな代助を「不断は人並み以上に減らず口を敲くくせに、いざという場合には、まるで唖のように黙っている」と罵倒するが、そこにはなんら論理的矛盾はない。<世間>は正しい。しかし、という気持ちは誰にでもある。そのしかしは、三千代との間を結ぶ線があるからだ。斯様に<愛>の感情ほど強いものはない。
漱石の『それから』はただ恋愛小説としてだけ読むのは勿体ない。登場人物たちの、それぞれの位置関係を描いてみればより深い人間ドラマが見えてくる。代助の書生の門野の点はどこにうつか。友人として点景されている寺尾、この人物は結構面白い人物である、はどうか。そうして、代助の渦が白い紙を黝々と塗りつぶした頃、ただ茫乎(ぼんやり)と、はてさて自分の点はどこに打つべきかと思うばかりである。
それから 改版
2001/02/26 00:24
軽いノリで不倫しちゃうより、道ならぬ恋に懊悩する方が、男っぷり・女っぷりが上がる…と考えさせられる名著!
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中村びわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
「あんまり本を読まない人が増えているが、旧い本を読むことほど、前向きな行為は他にないのである」という素敵な言葉を、山川健一氏の著書『不良少年の文学』で見つけた。その影響もあって漱石の本を意識的に読んでみようという気になっている。
が、漱石の本はなぜか一気にも、まとめても読めない。じっくり味わうことを強いられる。決して苦痛というのではない。一日に20ページぐらいずつ読んでは、その部分を味わう。本を閉じて日常生活の中で引きずるように思い出しては考える。
考える中身は、真面目くさくて嫌味に聞こえるかもしれないけれど、「生きるとは?」「人を恋うとは?」といったこと。哲学する機会の訪れを楽しむことになる。
そもそも読書の目的の一つは、哲学するきっかけを得ることだ。「bk1に書評投稿してお小遣いを稼ぎたいから」という下心が優先すると、ついつい読みやすい本を日に3冊などというペースにハマってしまう。「読んで書いて稼いで楽しときゃいいさ」という気分も大切。でも、自分を耕す読書がなおざりになってはまずい。消費するような読書では、もったいないと反省する。
「恋」も同じではないだろうか。
「あなたが好き。今の私には、あなたが必要」と言えずに深く思い悩む。それを相手に伝えて受け入れてもらうことは至上の喜びだけれど、安易にそうしてしまい、その恋を終え、また新たな恋を…という循環をこなしていくのは、ただの消費かと思う。
むしろ、あふれ出さんばかりの思いを身の内にかかえて、この切なさを今日はどう乗り切るかという日々の方が、辛いけれど人生にとっては大事だという気がする。それがまた楽しい。「禁欲を知る者が真の快楽を得ることができる」というのが私の考え。
この本は、今風に言えば「不倫」の恋の話。しかし、この言葉はどこか計算高いゲームのような響きになってしまってイヤだから、やはり「道ならぬ恋」というのがしっくりする。
主人公の代助は、大学を出たあと、実業家の父や兄の援助を受け、働くことなく家を構え、書生やお手伝いさんを置き、好きな本ばかり読んで暮らしている。結婚を薦められるが、経済的にも夫婦関係面でも苦境にある友人の妻・三千代のことが気になり、縁談を断り続けている。
今なら「離婚してもらって再婚でもすれば?」というところだが、明治の社会では、人妻を恋い、それを成就させたいと願うことは、人の掟に背き身を破滅させることを意味していた。
代助にしてみれば、親の援助を放棄して自由な趣味生活を諦め、その代わりに三千代への愛を取るというシビアな選択になる。彼は理性では分かっていながらも、「自然」にかなった破滅の道を選ぶ決意をするのである。
恋の苦悩を描きながら、倫理が失われつつある明治という新しい時代を嘆いている。それを「20世紀の堕落」と呼んでいる。
設定はクラシカルであっても、代助の懊悩には、100年たった今なお普遍的である「個人」と「社会」の在り方というものを、じっくりと考えさせる深みがある。
本当に、読みつがれていくべき堂々たる名著なのである。
(岩波版は脚注がマニアックなぐらい丁寧で楽しめます。)
それから 改版
2020/10/03 16:06
それから
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
就職を拒否して、父の仕送りで生活し、書生まで置く高等遊民の代助が、以前思いを寄せながらも、親友のために結婚の中を持ってやった人妻と思いを遂げる話。高校生のときに始めて読んだ際には、父から勘当され、親友と絶交しながらも、意中の人と結婚し、職について新しい生活を送る話かと思っていたが、今改めて読んでみると、ところどころに死をイメージさせる場面があり、さらに親友と談判する場面や、職を求めて町に飛び出す場面は狂気すら感じさせる。こんな小説だったかと思い直した。