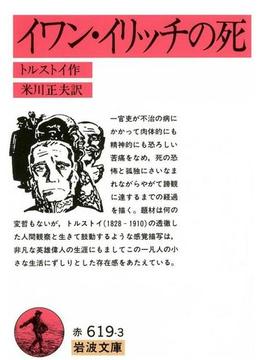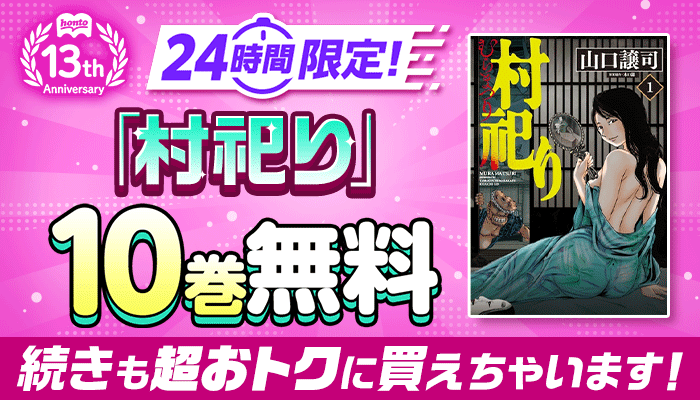- みんなの評価
 4件
4件
イワン・イリッチの死
一官吏が不治の病にかかって肉体的にも精神的にも恐ろしい苦痛をなめ,死の恐怖と孤独にさいなまれながら諦観に達するまでを描く.題材には何の変哲もないが,トルストイの透徹した観察と生きて鼓動するような感覚描写は,非凡な英雄偉人の生涯にもまして,この一凡人の小さな生活にずしりとした存在感をあたえている.
イワン・イリッチの死
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
イワン・イリッチの死 改版
2005/12/03 21:05
MementoMori(死を忘れるな)を教える名著
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
多くの哲学者からも「死を描いた優れた書」と評価されている、トルストイの短編。文庫の中でも薄い方に入る一冊です。一人の中年の男が不治の病に罹り、何を考え、死んでいったのかを描いただけ、と言えばそれだけ、の物語です。しかし、短編だからこそ、それだけ、を切り取り凝縮した形で読ませてくれます。同様のテーマを扱った文学は少ないないですが、ポイントに絞り込み、深く切り込んだ文章は、やはりさすが、と言うしかありません。
本当に「自分の死」に直面して読む気力など無くなるまえに読んでおきたい本だと思います。若くで元気一杯の人が読んでも、忘れてしまう一冊なのかもしれませんが、そろそろ健康が気になりだした、ぐらいの年齢になったら読んでおいても損はないでしょう。
お話は、何度でも何度でも、至るところでくり返している情景です。急に調子が悪くなり、治らない病気ではないかと主人公が不安を感じ出した時、「大丈夫」と励ますだけで主人公の不安には答えられない家族。自分自身も、仕事のあるうちは仕事をすることで不安な気持ちを紛らし、死を考えないようにしてしまう。そして彼の死が伝わったとき、職場の同僚たちはポストの移動について考え、妻はお金のことを考え、弔問に来た友人もその後のトランプ遊びの予定について考えているのです。いえ、おそらく死んでしまった主人公自身もこれまでは同じように行動し、「死」など考えずにいたのに違いありません。
死の恐怖が身近になって、彼が周りの人に求めたものはなにか。彼が問い続けたのはなにか。最後に何を考えたのか。自分もいつかそう考えるのだろう、と思わせるリアルな心理描写です。
重くて皮肉さも含まれるお話の中、「だれでも死ぬんだから親切にするだけ」と明るく看病する下男に少しだけ救われた思いをし、死の直前、泣いている息子をみて「彼らを苦しめないように」と考える主人公に、自分はそうなれるのだろうか、と自問してしまいました。
必ず自分にも死が訪れることはわかっているつもりでも、それを考えない生活を続けていくのが現実です。そうでなければ生活などできない、と言えるかもしれません。それでも時々、こんな短編を読んだりして「死」を思い出してみることも必要かも。自分なりに「よく生き」たと思うために。
イワン・イリッチの死 改版
2009/08/25 21:51
世界の文豪トルストイの円熟期の作品
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:萬寿生 - この投稿者のレビュー一覧を見る
第1刷発行が1928年10月10日、この第70刷発行が2003年4月4日である。超ロングセラーである。まさしく古典と言えるものであろう。書かれたのは、1884〜6年。ロシアのというより世界の文豪トルストイの、円熟期の作品だそうです。
時代はロシア帝政期の作者と同時代、主人公は平凡な小市民的判事。農奴が大部分の人口をしめる当時のロシアにあっては、そこそこの収入と財産がある中流階級と言えるのであろう。その凡人が、ちょっとした事故がもとで不治の病になり、死にいたる経過を書いている。
社会的地位の向上と収入の増加を自己の幸福と信じてきた主人公が、自分の死に直面し、それまでの人生や生き方に疑問を持ちはじめ、苦悩し、死を受け入れる過程が、克明に描かれる。内容、描写ともに世界の文豪にふさわしい。官界における栄達と快適な私生活の充実を求める俗人を主人公にしながら、誰もが迎える死の問題の本質的を捉え表現している。最近の小説のように大事件が起きるわけでもないのだが、不治の病になり、だんだんと激しくなる肉体的苦痛と体の衰えと、営々苦心して築き上げてきた生活への執着と、死に直面しその生活の無意味さ無価値さに気づいていくまでの苦悩は、すべての人間に共通するものであるが故に、またその表現力故に、読むものの心に働きかけ訴えるものがある。非常に短い短編ではあるが、世界の文豪の一級の文芸作品である。
2021/04/22 22:09
まあ、ざまあみろと思わないでもないのだが
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
イワン・イリッチの死因となった病名は本当は何だったんだろうか、医学からは遠くに居すぎている私には見当がつかないが、新居の飾りつけをしているときに梯子を踏み外してわき腹を強打したことが始まりだったことは確かのようだ。名作「アンナカレーニナ」が完結したのが1877年、この作品はその9年後の1886年に発表されている。主人公・イワン・イリッチの裁判所の判事を勤めて、上流階級とも付き合いがあり、カードも上手な人生の成功者が「自分は山へ登っているのだと思い込みながら、規則正しく坂を下っていたようなものだ。世間の目から見ると、自分は山を登っていた。ところが、ちょうどそれと同じ程度に、生命が自分の足元からのがれていたのだ」と悲しむ有様は胸を打つ、まあ、ざまあみろと思わないでもないのだが