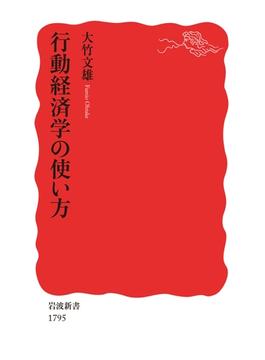- みんなの評価
 6件
6件
行動経済学の使い方
著者 大竹文雄
学ぶだけではもう足りない。研究と応用が進み、行動経済学は「使う」段階に来ているのだ。本書では「ナッジ」の作り方を解説する。人間の行動の特性をふまえ、自由な選択を確保しつつ、より良い意思決定、より良い行動を引き出す。その知恵と工夫が「ナッジ」だ。この本を通して、行動経済学の応用力を身につけよう。
行動経済学の使い方
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
行動経済学の使い方
2019/10/18 21:21
『行動経済学の使い方』
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:百書繚乱 - この投稿者のレビュー一覧を見る
伝統的経済学では説明しきれない人間の“不合理な”意思決定
たとえば
老後の貯蓄が必要だと思っていてもなかなかできない
宿題や仕事の締め切りがあるのにそれを先延ばししてしまう
ダイエットの計画は立てられるのに実行できない
など
本書は、行動経済学の知見を活用して人間の意思決定を合理的でよりよいものにするためめのヒントを紹介する
人間の意思決定のクセを説明する行動経済学の4つの観点(第1章)
・プロスペクト理論(確実性効果と損失回避)
・現在バイアス
・社会的選好
・ヒューリスティックス
合理的な意思決定に導くキーワードは「ナッジ」(第2章)
《行動経済学はいまや「使う」段階に来ているのだ。》──カバー紹介文より
医療・健康活動への応用(第7章)、公共政策への応用(第8章)の解説にはなるほどとうならされる
記述の正確さとわかりやすさを両立した岩波新書らしい一冊
行動経済学の使い方
2019/10/30 16:44
人間の意思決定は必ずしも合理的とは言えない
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
望ましい行動を促すために、どのように制度設計や説得を行うべきなのか、ナッジを中心に論じる。バイアスやヒューリスティックスなど非合理的な行動の特性を持つ人間に、自由な選択を確保しつつより良い意思決定をうながす(=ナッジ)方法が紹介されている。伝統的な合理的経済人の仮定に物申したい方は是非。血液型による性格の差異はないのにO型の人がよく献血をするという調査結果はおもしろい(私もO型でよく献血するので)。行動経済学ブームがきているか。この本を読んだら、ちょうどタイミングよく文庫化された『行動経済学の逆襲』をはじめ、『セイラー教授の行動経済学入門』、『実践 行動経済学』『ファスト&スロー』あたりを読んでみるのもおすすめ。
行動経済学の使い方
2019/10/27 09:54
読みやすい
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
行動経済学の基本が、わかりやすく解説されていて、よかったです。私たちの生活を豊かにしてくれるように願います。