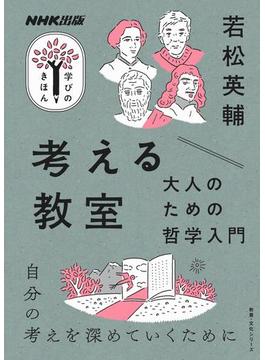- みんなの評価
 35件
35件
NHK出版 学びのきほん
他者だけでなく、自分も利する「利他」の本質とは。
「利他」という言葉は「自分ではなく、他者のためにおこなうこと」だと捉えられがちだ。しかし、日本の起源から利他を見つめ直してみると、それとは全く異なる姿が見えてくる。空海の「自利利他」、孔子の「仁」、中江藤樹の「虚」、二宮尊徳の「誠の道」、エーリッヒ・フロムの「愛」……彼らは利他をどのようにとらえ、それをどう実践して生きたのか。彼らの考える利他は、現代とどう違うのか。「自分」があってこその利他のちからとは、どんなものなのか。日本を代表する批評家が、危機の時代における「自他のつながり」に迫る、日本初・利他の入門書。
三大一神教のつながりをよむ
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ブッダが教える愉快な生き方
2021/02/23 22:54
愉快な修行っていいな
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なのはな - この投稿者のレビュー一覧を見る
仏教については詳しくありませんが、本書を読んで少し仏教に対する難しいものという見方のハードルが少し下がりました。前半はブッダそのもののことをコンパクトに説明していて興味深かったし、後半は坐禅など修行について踏み込んだ内容でした。学校での学びではないオーガニック・ラーニングというものや「愉快な修行」という考え方は初めて知りました。修行とはとにかく厳しいものというイメージしかなかったのですが、愉しくやりましょうというとても前向きな本でした。
教養としての俳句
2023/06/20 17:42
俳句のテクニック教本ではないのでご注意を
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「教養」という言葉を『広辞苑』で調べると、結構長い説明文がついている。
「単なる学殖・多識とは異なり、一定の文化理想を体得し、
それによって個人が身につけた創造的な理解力や知識。」と、
この説明文そのものが教養的文章のようだ。
NHK出版の「学びのきほん」シリーズの一冊である、
青木亮人(まこと)氏の『教養としての俳句』には、こうある。
「俳句を教養として学び、味わうこと」を目的としたこの本では、
「俳句を通じて私たちの生き方がどのように変わり、いかに深まるのか」を
解説している。
よって、ここには季語の話はあるが、切れ字とか句つながりといったような
俳句を詠む上のテクニックは書かれていない。
そのあたりを注意して、本書を手にするのがいい。
そのあたりを章のタイトルで読むと、
「俳句とその歴史を知ろう」「「写生」って何?」「「季語」を味わう」、
そして「俳句と、生きているということ」となる。
こうしてみると、やはり最後の章に重きをおいた一冊ということがわかります。
そして、それは「季語」を味わうということと密接につながっているのも理解できる。
俳句とは、日常にあるがままをどう詠み、どう鑑賞するかということで、
俳句を日常の生活に組み入れることで生活そのものが豊かになるとすれば、
『広辞苑』のいう「文化理想の体得」になるのではないだろうか。
2022/05/30 16:05
自利利他
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かみめくり - この投稿者のレビュー一覧を見る
利他と自利
難しいテーマを、比較的、飲み込みやすく学べる
とても実りある一冊でした。
読むだけで終えてはならない。
難しいけれど、読んだら明日からの自分が、
何かがちょっと変わるような、
変えたくなるような気持ちになれます。