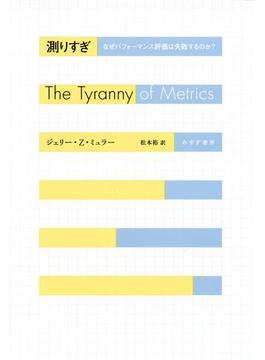- みんなの評価
 3件
3件
測りすぎ――なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?
著者 ジェリー・Z・ミュラー(著) , 松本裕(訳)
「測定基準の改竄はあらゆる分野で起きている。警察で、小中学校や高等教育機関で、医療業界で、非営利組織で、もちろんビジネスでも。…世の中には、測定できるものがある。測定するに値するものもある。だが測定できるものが必ずしも測定に値するものだとは限らない。測定のコストは、そのメリットよりも大きくなるかもしれない。測定されるものは、実際に知りたいこととはなんの関係もないかもしれない。本当に注力するべきことから労力を奪ってしまうかもしれない。そして測定は、ゆがんだ知識を提供するかもしれない――確実に見えるが、実際には不正な知識を」(はじめに)
パフォーマンス測定への固執が機能不全に陥る原因と、数値測定の健全な使用方法を明示。巻末にはチェックリストを付す。
測りすぎ――なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
測りすぎ なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?
2019/05/08 14:58
データの取り扱いに関して、考えさせられる一品
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:undecane - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書において著者は、「データ至上主義」的様相を呈する現代社会に関して疑問を呈している。データをどこまで信用していいのか、運用は適切なのか、改竄はされていないか、等々。実際の事例(米国が主であるが)に即して、データ運用に問題が無いのか、考えさせられる。
測りすぎ なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?
2019/09/29 14:52
もどかしい
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:怪人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
アメリカの歴史学教授がいわゆる成果主義のもとになる物事の測定基準について考察し、大学や学校、医療、警察、軍、ビジネスと金融などの分野について、広範囲に記述されている。アメリカやイギリスが対象地域となっているが、両国の事情を知ることができ、おもしろい。
成果主義の功罪については日本でも批判的な本も出版されてきているが、多くの分野に亘って論述されているのはあまりないのではないか。
はじめにのところで、著者は述べている。
本書では全く新しいことは非常に少ない。
本書な内容の大部分は多くの執筆者から引用したものを組み合わせている。 測定基準への執着による組織的機能不全についてはすでに指摘されている。 これらをとりまとめ、組織の指導者や労働者に利用し易いものはなかった。 そして、結論の最後に、
組織や測定対象を実際に知るために重要なのは、経験と定量化できない技術である。重要な事柄の多くは標準化された測定基準だけでは解決できず、判断力と解釈力が必要である。判断のもとになる情報源として 1つ1つの測定基準について、その重みづけや特徴的ゆがみなどよく認識しておくことが重要である。しかし、各界のリーダーたちはそのことを見失っている。
と記し、まとめている。
都合の良いデータを使って自分たちに都合のよいように解釈し、意思決定していくリーダーも多くいるが、そのような人達は確信犯なので著者の指摘には耳を貸さないだろう。
国民や労働者から見れば、リーダーの判断力や解釈力に疑問を持ったときには、客観的なデータということで測定基準等による補完的説明、証拠を求めたくなるだろう。
なかなか難しい問題である。
測りすぎ なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?
2019/06/28 15:28
反主流派
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
測定基準への執着による過剰な測定や不適切な測定が問題で、判断力と解釈力無くして説明責任の証明としての測定実績は有用たり得ない。それでもトップに立つ人間は測定可能な結果を見たがるものだんですのねぇ。