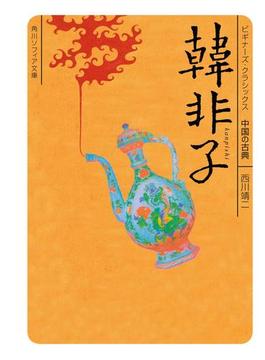西川先生の本をもっと読みたい
2019/02/25 02:23
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:TaKIK2 - この投稿者のレビュー一覧を見る
韓非子の本の中で、いままで読んだ中でいちばん腹落ちした良書。西川先生のほかの著作も読んでみたいけど、あまりかかれて居ない様子なのが残念。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
処世術をも唱えた韓非だが自身は身を滅ぼしてしまう。そんなことも教訓になる解説を交えて初心者向きにわかりやすく抜粋している。その先のおすすめ本も巻末に紹介されている。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しましま - この投稿者のレビュー一覧を見る
このシリーズ、日本の古典と中国の古典はほぼ揃えてます。部分抜粋ですが、読み下し文と訳文と解説と原文が並んでいて、入門編にはよいと思います。そうか、「矛盾」の出典はここだったか、というレベルの私でもわかりやすく読めました。
投稿元:
レビューを見る
韓非子っていう人のことをほとんど知らなかったのですごく興味深く読めました.以下メモ.韓非子・・・韓の国の公子.法家.儒家の旬子に教えを受ける.同じく旬子に教えを受け秦に遣えた李斯(リシ)によって秦に呼ばれ,その才覚のため殺されてしまう.[2006.09.28.]
投稿元:
レビューを見る
卒論が無事終わり久しぶりの更新
今回は韓非子です。
一言でいうならドライ
でもそのドライは単に冷たいという意味ではなく、次から次へと覇権が変わる時代において生き残るための術とも言える。たとえ、妻子であっても隙を見せてはいけない。
また王に使える者として、どのように進言をすべきか、その仕方によっては自らの命を失うこともある。
孔子のように徳による政治ではなく法と術による政治を説いた韓非子には好き嫌いがあるかもしれないが、心得ておくべきと思うことが多々あった。
これは自分の勝手な解釈だが、日本人(内資)に受けるのが、孔子なら外国(外資)に受けるのは韓非子かもしれない。
面白いと思ったのは、マルサスの人口論のような内容を韓非子も言っている点だ。2000年以上も前にこの内容を説いたことはすごいといえる。
マキャベリの君主論は王としての立場から書かれたものだが、この韓非子と同じにおいを感じる。
矛盾や守株などのエピソードのもとも、この韓非子にあります。
投稿元:
レビューを見る
20/5/1
英明な君主が臣下を養う場合、臣下は官職の職域を越えて業績を得ることが許されず、言葉を陳べて業績がその言葉に合致しないことも許されない。
七術
1>いろいろな人の言行を照らし合わせてみる
2>必罰をもって威厳を明らかにする
3>信賞をもって能力を尽くさせる
4>いちいち臣下の言を聴き、その結果が言に一致することを求める
5>故意に疑わしい命令を出したり、逆の命令を出したりして臣下を惑わせる
6>知っていることを知らないふりをして臣下に尋ねてみる
7>誉めるべきものを反対に謗ったり、憎む相手を可愛がったりする
平均的人間のための支配の術>それが法家韓非の関心
【利」こそが道徳や倫理よりももっと根元てきなところで人間の行動を決めていることになります。
社会は時間と共に変化します。>これが韓非の歴史観>守株>まちぼうけ
大体>老子に通ずる
投稿元:
レビューを見る
覇権争いの真っただ中での出世学?
社長になった時もう一度読みたいなぁ・・・。
韓非子の入門書的な感じですので初めての人にはおススメ!
わかり易いです。
投稿元:
レビューを見る
絶大な権力を持つがゆえに命を狙われる君主が、いかに臣下をうまく制御するかを述べた法家思想の書。キーワードは「法」「術」そして「利」。
投稿元:
レビューを見る
なんという人間不信、なんという冷徹さ。「矛盾」も「守株」もここまで重い話だったとは。
善悪に意味は無くただ「利」を説く姿勢はとても2200年前の古典には見えない。ただ、「大体篇」に読み取れる黄老思想は、血みどろの現実に疲れた韓非が見た一縷の理想だったのかと思うと、「100分de名著」老子の回でのドリアン助川氏よろしく、つい韓非の肩をたたいて「あんたも大変だったんだね。まあ、一杯どうだい」と声を掛けたくなる。
今回はダイジェスト版だったので、次は岩波文庫で全巻読みたい。
投稿元:
レビューを見る
末世の低級な王の無理解や家臣の専横を批判することの危険を膚に感じながら、己の主張を展開した韓非の姿や思想を、原典に触れつつわかりやすく描いている。法家思想といえば、一般の人々を法に厳しく従わせるようなイメージが強いが、実はその厳しさの矛先は、まずは君主に近い家臣たちが君主の権力を私物化しようとすることに向けられていたという。そしてまた法治主義は、聖人でない普通の君主が普通の人々をうまく治めるにはどうしたらよいか、という現実的な問いに答えるものとして説かれているという。人間の性質を善悪でなく功利でとらえる立場に立つ韓非子の思想は、思っていたより単純ではなかった。
投稿元:
レビューを見る
中国のマキャベリとも言われる韓非子
戦国時代の思想だけに、厳格な法治と冷徹な権謀術数による君主権力の強化こそが民を混乱した世の中から救い出し、儒家のいう「仁」にも叶うのだという。現代の感覚からするとやや姑息なニュアンスが強い内容になっているが、こういう時代背景では仕方ないのかもしれない
君主は「術」すなわり、臣下を操るため密かに用いる技術(他人に悟られてはいけない)と「法」として公開した上で厳しく思考する制度の二つを運用すべし。戦争に勝った時、君主でなく臣下が尊敬され、勝ち取った領土が臣下個人の領地になってしまうのは、君主に臣下の悪事を知るための術がないからだ。いくら法を整備しても臣下たちはそれを自分の利益のために用いる。刑罰と恩賞を君主自身の判断で実施することで臣下を意のままに操ることができ、君主が権力を我が手に握るための方法でもある。
術の秘訣は利と威にある。人の欲望を操る餌である恩賞が利である。そして人の恐怖心を煽り君主の威厳を示す手段である刑罰を威とよんだ。
色々な君主の術を七術として分類しており
1.いろいろな人の言行を照らし合わせてみる
2.必罰をもって威厳を明らかにする
3.信賞をもって能力を尽くさせる
4.いちいち臣下の言を聴き、その結果が言に一致することを求める
5.故意に疑わしい命令を出したり、逆の命令を出して臣下を惑わせる
6.知っていることを知らないふりをして臣下に尋ねてみる
7.褒めるべきものを反対に謗ったり、憎む相手を可愛がったりする
投稿元:
レビューを見る
ごめんなさい、今までナメてました。これからの自分に必要なのは韓非子と荀子の思想でした。改めてきちんと全編読みます。
投稿元:
レビューを見る
誰もが知る「矛盾」、「守株」、「逆鱗に触れる」。
それはいずれも、韓非子による。
韓非の生涯と、思想について、コンパクトにまとめた本。
儒者と異なり、理念ではなく「利」に基づく人間観を持っている。
つまり、人間は本来善でも悪でもなく、その場の利益に基づいて動くものだ、ということ。
それゆえに、君主は、法と術にのっとって臣下をコントロールしなければならなく、臣下や家族に気を許してはいけない。
臣下は君主の利害関心がどこにあるかを冷静に見極めて、何を伝え、どう接するかを考えねばならない。
寵臣の中へ入り、まず喜ばれない立場にいるにもかかわらず、君主に自説を聞き入れさせるのは難しい。
こういった場合の状況分析と対処を論じていく。
冷徹に分析したはずの韓非自身が、結局、始皇帝の威を借りた李斯に服毒自殺に追いやられていく。
法術の士の行く道が、険しく孤独であるとわかる。
韓非の考え方は、切れ味鋭く、何というか、振り切れてしまっている。
だから、ある意味では理解しやすいのかもしれないが、何かやりきれない気分になる。
投稿元:
レビューを見る
「 韓非子 」
君主と臣下の心得術の本。人間は利で動くとする人間観
「君主の弊害は 人を信頼することにある」
「君主が法を整備し賞罰を握り術を巡らすことによって権勢を維持できれば 世の中は治る」
投稿元:
レビューを見る
非常にわかりやすく、とっかかりとしては最適。既にある程度の知識がある人が読むには物足りないかもしれないが、私のように凡人程度の知識レベルならば、変に気合入れて岩波とかちくま学芸文庫とかに手を出すより、まず本書をインプットしてからの方が理解が深まりそう。「わかりやすい=低レベル」という感じではなく、理解させるための配慮が行き届いていると感じた。結局理想のリーダー像、トップのあるべき姿の実現って永遠の課題なのかな。周囲の思う理想をわかっていても、実際トップに立った時に実現出来るかはまた別の問題。