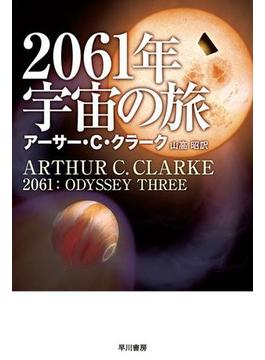ちょっと説明しすぎ…!?
2001/02/24 01:04
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:YU - この投稿者のレビュー一覧を見る
アーサー.C.クラークのファンとしてはちょっと期待はずれの一冊でした。『2001年…』以来、内容がわかりにくいとの評判を、さすがの巨匠も気にしすぎたか……?
マニアとしては、やっぱり2−3回読み直さないと分からないぐらいがいいかも。
クラシックとして
2016/11/26 19:14
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:koji - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本が書かれたのが1987年ですので、ほぼ30年後の今からすると現実とかなりずれている部分もありました。
もちろんSFは予言の書ではないので物語として、素直に楽しめば良いのでしょうね。
小説版ではなく映画「2001年宇宙の旅」でしか観ていないので、その印象が強いのですが、もっと観念的な世界観の物語がこの作品でも描かれるのかなと思ったいたのですが、割と淡々とした太陽系内の木星の衛星探索旅行記みたいな内容でした。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トリフィド - この投稿者のレビュー一覧を見る
『2001年宇宙の旅』、『2010年宇宙の旅』と続くシリーズの3冊目である。
幕間劇的な作品であり、はっきり言って作品自体の力は弱い。しかし興味深い点もある作品である。こういう楽しみ方は本筋ではないのだろうが、この連作の各作品で描かれる宇宙船の進歩の様子が面白いのだ。
この作品の舞台である2061年というのは、宇宙船技術の進歩により、まさに太陽系全域が人類の活動範囲になる時代を目前に控えた時期として設定されている。2001年の〈ディスカバリー号〉、2010年の〈レオーノフ号と、時代が進むにつれ宇宙船は進歩してきた。そして2061年の科学技術の粋が建造した〈ユニバース号〉〈ギャラクシー号〉は、祖先たちと比べて帆船と飛行機くらいの差がある高性能機なのだ。
ただひとつのミッションのために建造され、それを果たしたら寿命を迎える〈ディスカバリー号〉と〈レオーノフ号〉、だが〈ギャラクシー号〉と〈ユニバース号〉は、顧客の要求に応じて太陽系内をあっちへ行ったりこっちへ行ったりする貨物と客を運ぶ船なのである。
「太陽系」というものの意味が変革した時代、「太陽系」が行く場所から居る場所へと変化したその時代なのである。
しかしこのユニークな点も、あの残念なクラークのちゃぶ台ひっくり返し『3001年終局への旅』を知ってしまった今となってはあまり高く評価できない。
クラークには、モノリスの出てこない太陽系開発ものの連作を書いてほしかったなと思ったりする。
投稿元:
レビューを見る
あまりHAL9000が出てこないので、これはとりあえず2001、2010、3001を買った後に集めればいいと思います。
投稿元:
レビューを見る
2001年宇宙の旅、2010年宇宙の旅につづくシリーズ3作目。前2冊はどっかにいってしまってコレだけ残ってるのはなぜだろう。正統派の宇宙モノであるが、そこはクラーク、ちょっと哲学入ってるわけで。単体で読んでもオッケーだが、やはりシリーズを通して読むのが面白い。
投稿元:
レビューを見る
ぱらぱらとページがめくれてしまう、不思議。
2001も、2010も、2061も、
全部ちがう小説だと思えるけれど、
2001年以降は読者サービスだよね。
投稿元:
レビューを見る
「2001年・・・」「2010年・・・」の2冊しか読んでいなかったのですが、図書館の書架をbrowsingしていて目に止まり、読みたくなったので借りました。シリーズ最後の「3001年・・・」も続けて読むつもりです。アーサー・C クラーク氏は昨年お亡くなりになっていたのですね。ニュースになったはずなのに、なぜか記憶にありません。自分の死後も読み継がれる作品を残せるというのは、すばらしいことですね。
投稿元:
レビューを見る
なんだかSFばかり読んでいたんだなあ
簿記ばかりしていたから現実逃避したかったんだろうか
それはともかく古本屋で2010年が見つからないので先に読んでしまう
金額は不明
2001年の時も感じたけどこの人も発想力が命なのかなあ
文章が下手なわけではないけどこの一言凄いなあとかは特になかった
ああでも、こんなあり得ない世界観を過不足なく説得力を与えて書いている時点で凄いのか
とりあえず2010年と3001年も読まなきゃなあ
投稿元:
レビューを見る
ハレー彗星と共に、着陸を禁じられた衛星・エウロパについて焦点が当てられています。
第二の太陽となった木星の光のもとで発展した生物たちの描写は面白いですが、前作・前々作に比べると盛り上がりに欠け、散漫な印象を受けました。
また、続編の3001年へと続く幕引きとなりますが、そちらまで読んでみると、このラストの意味深な会話に本当に意味があったのかやや疑問。ウッディいないし。
投稿元:
レビューを見る
良かった。これこそ、クラーク作品だと思う。実はこれを読むのは2回目なんだけれど、それでも良かった。2001年宇宙の旅、2010年宇宙の旅と続いているシリーズもののような作品群なんだが、3つの中では特に2061年がよい。
クラークが好きであるところの、人類より高い知性を持った異星人がテーマとなっているんだが、この高次の知性を「遥かなる地球の歌」でみられるような哲学&宗教的な「神」とするのでもないし、「宇宙のランデヴー」のように隠しきってしまうわけでもない。高次の知性を、もっと人間くさく描いているという感じだ。
高次の知性に憧れるのはよく理解できる。これを第二の神としてあがめる気持ちも理解できる。不老不死ではないけれど、未来の人類と高次の知性というのはけっこう同一視される場合が多いのだが(キングギドラがはじめて登場したときに宇宙人はガンを直す薬で人類を釣った)、未来の人類が地球ベースであるのに対し、高次に知性は常に宇宙スケールだ。
2010年で木星を爆発させて新しい太陽を作ったその後が2061年の出だしであるわけなんだが(同時にこの新しい太陽が消えるのが2061年のおわりである)、その木星に存在する生命体を描く感じはアシモフを思わせるのがユニーク。
今回の2061年で、とにかく目新しいのは、人間は死ぬがその魂は別の次元で生き続ける(こんな言葉ではないがわかりやすいように私が翻訳した)という古来から有る概念だ。この概念を用いて、人類とそれより高い知性体、低い知性体を描いている。で、私が思ったのは、これってクラーク自身じゃないかなってこと。クラーク自身が、今より1秒でも先を見たいだろうに、寿命には限界がある。だから、魂はより高いところから未来を見ているんだと信じたいってな感じかなぁ。
他にも新しいのは、愛よりも正義や真実が大事であるという概念ね。これって好きだなぁ。愛が全てと言うような映画や本は私は苦手だから。
とにかく次の「3001年宇宙の旅」が楽しみだ。
投稿元:
レビューを見る
SFとしては地味。宇宙史のような淡々とした展開に、人間ドラマと当時の最新宇宙事情(…はぁ?)を絡ませたような内容。
地味だけど、面白い。
投稿元:
レビューを見る
2001年宇宙の旅のシリーズ3作目。
続編ですがストーリーが続いているわけではありません、色々な辻褄も合っていませんが、登場人物は共通です。
正直、面白くなかったです。
投稿元:
レビューを見る
2061年、それはハレー彗星が地球に最接近する年。医学の進歩により100歳を過ぎてなお矍鑠としたヘイウッド・フロイド博士は、ハレー彗星に着陸調査する宇宙船に賓客として招待され、未知の世界を楽しんでいた。しかし、そんな楽しい旅の途中で彼が接したのは、孫に当たるフロイド宇宙飛行士が搭乗する宇宙船が「禁断の星」エウロパに不時着したという知らせだった。自力でエウロパから脱出する術をもたない宇宙船を救うために、フロイド博士が採った奇策とは?
あの歴史的名作「2001年宇宙の旅」、その続編「2010年宇宙の旅」に繋がる"Space Odessey"シリーズの1作。シリーズのお約束として、モノリスもボーマン船長もHAL9000もばっちり登場します。
が、これ、別に"Space Odessey"シリーズに位置付けなくとも良いのでは。
SFとしては、普通に面白いです。でも、たぶん執筆当時のクラークとしては「ハレー彗星がらみで何か書きたい」ってだけだったんじゃないかなー、という思いがちょっとします。100歳越えた高齢のフロイド博士を無理に主人公に据える理由はないし、ボーマン船長(であったもの)が登場する理由もないし・・・繰り返しになりますが、SFとしては、普通に面白いんですよ。だから、独立した作品として書けばそれで済むのになー。看板を背負わせたがために、不当に評価が下がってしまう作品だとしたら、ちょっともったいない気がします。
投稿元:
レビューを見る
やっと読み終わった。
何か、前の2冊もそれぞれ雰囲気やテーマが違うような印象を受けたんやけど、これもまた違う感じ。SFというより冒険譚?な感じで、ミステリー?サスペンス?な雰囲気が漂っているよ。宇宙船ハイジャックてこわすぎー。だってまだ2061年だもの!
あとフロイド、てめーはいつまで現役なんじゃい。と思ったらお前もか。デイヴィッドほど魅力的な主人公じゃないと思っていたので、はーん、ふーん。
このまま3001年を続けて読みたい感じやけど、たぶん疲れてしまうと思うのでちょっと間を空けるぜ。
投稿元:
レビューを見る
SF。冒険。シリーズ3作目。
前作の直接の続篇ではない、とのことですが、自分はハッキリと続篇だと思って読みました。
場面が転々とし、登場人物も多いため、少し分かりにくさを感じる。
エウロパの生物の描写が一番印象的でした。
スケール感は流石。続篇が気になる終わり方。