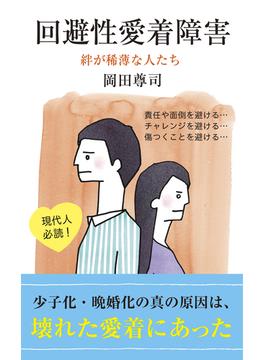0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ごんざ - この投稿者のレビュー一覧を見る
障害について書かれているだけでなく改善方法、改善した事例などが網羅されている。
事例も多いが多くの人が知っているであろう人物を採用していて興味が沸いた。
内容も適度に簡略化され分かりやすい文章で読みやすい。
なおかつ、障害に苦しむ人に向け背中を押すような啓蒙的な要素もあり、知識を取り入れるだけでなく読み物としても楽しめた。
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:るん - この投稿者のレビュー一覧を見る
同じ著者の本と一緒に読みました。
愛着障害にも種類があるということがわかりました。
ACの勉強本としてもいいかもしれません。
「回避性」ではなくても参考になった点
2016/04/19 20:19
5人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:austin - この投稿者のレビュー一覧を見る
辛い現実や不安に向き合う恐怖よりも人生の可能性を失ってしまう恐怖の方が大きくなり、逃げていた現実や不安に立ち向かっていこうと、心のありようが180度転回。回避を乗り越えるためにはこのプロセスが必要。
そういう場合に有効な方法は、一番恐れている状況を勇気を出して思い描き、その状況に陥ったとき、どれほど辛い気持ちになるか味わってみる。しかし、思い描き続けているうちに「大したことではない」と思ったりする。
立ち向かっていく際に大事なのは、いつ不安が襲ってくるかわからないとか、そうしたことに注意を奪われるよりも先に、積極的に行動し、自分のペースで物事を運ぶこと。そこで、成功体験を積めば、克服へのきっかけとなる。
人を癒し回復させる効果を左右するのは、治療者と患者との関係の質。
マインドフルネス体験は、通常のカウンセリングを超えた、不快では浸透効果の秘密があるのではないか。
人生に立ち向かうことが良いことなのか?
2023/11/09 18:05
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たつ - この投稿者のレビュー一覧を見る
筆者は、自らを刺激溢れる環境に置いて、人生を切り拓いていくことこそが絶対的に正しいと考えているようですが、
超回避型の私には響きませんでした。
逃げるところまで逃げて、追い詰められたらあの世に転生の方が私には魅力的なのですが…
まあ、ハードワークしている人ほど何かアドレナリンが効いて生き生きとしがちなのは事実なので、
本書に取り上げられている事例に説得感は大いにあります。
「頑張りたい」人とか「何かを変えたい」人であれば、この本の言うことを信じて良いと思いました。
私は現在、絶賛ニート生活中ですが、そのうち心境が変わることもあるかもしれないので、その際は高評価レビューに変更させていただきたいと思います。
回避性愛着障害?
2019/08/25 03:49
4人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:きりん - この投稿者のレビュー一覧を見る
回避性の愛着障害って、いわゆる「面倒なことは避けようとする」なんでしょうか。昔も今も似たような子はたくさんいますが……
投稿元:
レビューを見る
本の帯の内容に思い当たる節がありすぎたので思わず購入。
中身はいろんな回避型の人のエピソードが。山頭火なんかはすごく印象的。
でも、結局回避をなんとかするには自分で、なんとかするしかないのかな。
一人で勝手に助かるしかないということですね。
回避型の人を見守るひとは腫れ物に触るくらいでちょうどいいというのはなかなか印象的でした。
投稿元:
レビューを見る
★2014年1月15日
愛着障害の中でも深刻な様相を呈する「回避型」についての紹介。
なんだか人づきあいが苦手。
多くの人といるよりも、一人でいるほうが気楽で苦痛もない。
働かないで生きるのが理想。
現実に直面するより逃げ回り、なんとか責任を背負わずに済ませたい。
その割には理想や希望が高く、そのギャップに悩む。
そういう自分やパートナーとどう向き合うかに、大きな指針を与えてくれる。
投稿元:
レビューを見る
■回避性の例え話として,一匹で暮らすサンガクハタネズミの事例が
あげられている。
サンガクハタネズミが,その回避性(?)ゆえに絶滅したのであれば,
その回避性は改善すべきものなのかもしれないが,
ちゃんと生き残っているのであれば,問題ないのでは?
■山頭火,ヘルマン・ヘッセ,キルケゴール等,
回避性愛着障害と思われる人物のエピソードが,
読み物として面白かった。
投稿元:
レビューを見る
久しぶりに堅い本読んで目がしぱしぱした。
何の気なしに読んだけど、子育てに関することで驚き。
愛着持ってもらえるように頑張ろう。
投稿元:
レビューを見る
「なぜこんなに生きづらいのか」
「なぜ自分は人と違うのか」
そう思って、精神医学やカウンセリング、心理学なんかの本をぽつぽつ読むけれど、
回避性愛着障害
うーん、あてはまるところはあるけれど、そればかりではない。
不安型なところもあるし、恐れ・回避型のところもある。
(少なくとも安定型ではないのだけれど…)
」自分がこの型だ」と、
断定してしまえばその診断や病名にすがることができるから、楽っちゃ楽だと思う。
「わたし、プチうつなんだ」
なんていう小賢しい言葉が一時期流行ったのもそういうことだと思う。
でも、本当に人って色々な側面があるから、一概に自分が愛着障害だと断定出来ないし、断定したところで所詮、主観的な断定だから客観性はないわけで。
でも、太宰治やムンクは間違いなく愛着障害を抱えていたろうなとは思う。
種田山頭火やトールキン、キルケゴールといったわたしの大好きな人々の名前も出てきた。
ということは、わたしは、このような人々を嫌いではないのだな、と思った。
自分が愛着障害を克服するために、愛着障害を抱えている人を救ってみたいな。
そんな風にも思えた。
投稿元:
レビューを見る
回避性愛着障害というものに、自分自身思い当たる節が大いにあったので手に取りました。
自分と両親との関係や育ってきた環境等を思い返し、そこに"愛着"という視点を入れた時、自分がなぜ回避型の愛着スタイルを持っているのか、すとんと腑に落ちた気がします。
※私の養育環境は、ごく一般的なものです。
また昨今、その回避型愛着スタイルを持つ人が増えており、そしてそれは現代化情報化等、社会レベルでの生活スタイルの変容に伴っているのでは。という著者の意見にはとても納得。
回避性愛着障害をいち個人(およびその家庭)の問題として書かれているわけではなかった点、非常に興味深い一冊でした。
投稿元:
レビューを見る
先進国がどうして少子化になるのか納得した。近代化するにつれ回避型愛着(人との関わりが希薄な人)が増えるからだ。どういう風に対処したら良いのか書かれているので、自分は回避型では?と感じた人は是非読んでみてほしい。
投稿元:
レビューを見る
借りたもの。
対人関係への嫌悪は、家族の愛着が希薄であるが故に傷付く事を回避するためだという。
近代以降の社会の脱愛着化、それらは性生活にも及んでしまうことを指摘している。
晩婚化や少子化など、今、社会で問題視される現象の根底には、これが深く関わっているのではないだろうか。
後半の回復のためのプログラム例は一読の価値あり。
その大まかな工程は、傷付いた愛着を認識し、自己を肯定した上で、対人関係から逃げない事だった。
著者曰く、キルケゴールなどの文豪もそうらしい。
学生時代に慣れ親しんだそれらは、共感故だったのだろうか……
この本は夫婦分業(男は外で働き、女が家事・子育てをする)を推奨するものではない。それは父親が子への愛情から逃げているに過ぎないからだ。そして母親の自己犠牲で、愛着が成り立つのではないと思う。
何故なら母親自身が自信を持っていなければ、愛情を分け与える事はできないだろう。そのためには、個人の幸福と充実が必要だからだ。
著者は‘回避愛着スタイルと、個人の幸福や生物としての生存が共存する持続可能なライフスタイルを、われわれは近い将来見つけ出すことができるのだろうか。’と書く。私はそれを切に願う。
巻末には愛着障害の傾向のチェックシート付き。
投稿元:
レビューを見る
回避性パーソナリティ障害の話だけというものではありません。広範囲の精神病者の背景に、愛着障害が存在するという内容で話しがすすんでいきます。「境界性パーソナリティ障害」の次に同著のこの本を読み終わりましたが、自分自身の内面にあるものに納得できました。
投稿元:
レビューを見る
【生き方】回避性愛着障害/岡田 尊司/20140428(37/211)
◆きっかけ
・日経広告、自分に当てはまることが多そう。
◆感想
・冒頭、「われわれは、日々の対人関係や家族との生活、性生活や子育てといった親密さを前提とする関係において、ストレスや困難を抱えやすくなっている。結婚率や出生率の低下は、主に経済問題の側面から論じられることが多いのだが、実際には、今よりはるかに貧しい、食うや食わずの時代でも、高い結婚率と出生率を維持してきた。飢餓ラインぎりぎりで暮らしていても、家庭を持ち、子どもをつくり続けてきたのである。ところが、今では、多くの人が、自分一人で過ごす時間や自分のために使うお金を削ってまで、家族をもちたいとは思わなくなっている。
それは経済問題とは別のところに原因がある。そこには愛着が稀薄になり、回避型愛着が浸透していることが関わっている。われわれの身には、人間から別の種へと分枝していると言えるほどの、生物学的変化が生じているのである。」には納得。
・有名人やカウンセラーに来た人含め、抱負な事例があり、読書前の想定通り自分に当てはまるケースが多々あった。それを確認できただけでも収穫か。巻末の診断テスト結果では、A安定型愛着スコア16、C回避型愛着スコア11、安定-回避が5以上だと、愛着回避の傾向がみられるが、全体的には安定したタイプ、との結果。納得。
・それに対する解決策が良く分からない。おそらく、仕事とプライベートでも違うのだろう。以下引用部分がヒント。
◆引用
・成長するにつれ、子供は母親のもとをはなれるのようにあるが、母親との愛着が安定した子供ほど、活発に冒険し、外界を模索し、他者と交わろうとする。愛着した対象への信頼感や安心感が、子供が積極的に活動する上で後ろ盾となる。(=この後ろ盾機能を「安全基地」と呼ぶ)。また知能も高い傾向を示す。
・安定した愛着を育む上で不可欠なのは、安全で安心できる環境であり、応答性(=求められれば応えるという相互的反応)と共感性(相手の立場になって気持ちを汲む)。
・現在のわれわれは、ノートを広げる余地もない机の状態。情報がありすぎるために、肝心な情報がみえづらくなっている。これではたまたま目に入った情報で判断を行う状態になりやすい。
・回避の克服法①=回避を突破する(暴露療法)。一番恐れている状況を勇気を出して思い描いてみる。そして、その状況に陥ったとき、どれほど辛い気持になるか、どれほど悲しい気持ちになるかを生々しく想像し、それを味わってみる。最初は辛いが、次第に、それほど怖い事でないかもしれない、実はたいしたことない、となる。
・回避の克服法②=高すぎる期待値を下げる
・回避の克服法③=情報通信依存を脱する。
・回避の克服法④=人とのつながりが人生を動かす。=人生を動かす最大の力。
・運命が自分に何をさせようとしているのか、そういう視点で状況を振り返る。
・自分の人生から逃げない。もう逃げないでやるしかない、という気になるもの。=コミットメント
・われわれに結果を選ぶことはできない。我々に選べるには、今この時を、いかに生き���かということだけだ。チャレンジするか、しないかだけだ。逃げて生きるか、不安や恐れに立ち向かって生きるか。傷つくのを避けようとして、自分の人生から逃げ続けることもできれば、逃げるのをやめて、傷つくのを恐れずに向かっていく生き方もある。それを選ぶのはあなた自身だ。逆に言えば、どんな状況でも、われわれはチャレンジすることができる。結果は失敗であっても、チャレンジする自由をもつのだ。失敗という結果ばかりに捉われるか、そこから自由になって、可能性というプロセスを味わい、それを生きるか。結局、人生は結果に意味があるのではない。その醍醐味はプロセスにある。チャレンジにあるのだ。それを避けていては、人生の果実を味わうことなく、腐らせるようものだ。どうせ腐ってしまうのだ。腐る前に食べて、何が悪かろう。(=いずれ死ぬ。逃げれない。)