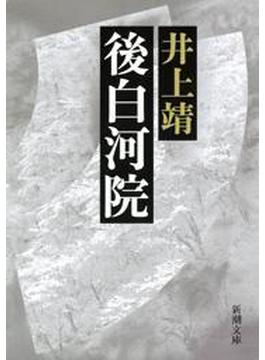日本国第一の大天狗の生涯
2022/06/03 07:02
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
井上靖といえば、昭和を代表する作家の一人だ。
昭和25年に『闘牛』で第22回芥川賞を受賞し、その後自伝的小説『しろばんば』『あすなろ物語』や『天平の甍』といった歴史小説、『敦煌』などの西域小説と、その活動の幅は広い。さらにいえば、井上は生涯詩を書き続けた詩人でもあった。
そんな井上に、2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で俳優の西田敏行が熱演している後白河法皇を描いた歴史小説がある。
それが昭和47年に刊行された『後白河院』とタイトルのついたこの作品である。
物語はそれぞれ証言者が違う四つの部で構成されている。
時代時代で後白河院の表情が違うように、ましては平家の時代から源家の時代に移ろうとする際の討つものがたちまち追われる側になるといった目まぐるしい采配をして、後に源頼朝から「日本国第一の大天狗」と揶揄されるほどの人物であるから、院を見る証言者の眼も様々といっていい。
証言者が違うものも、順にたどれば天皇になるところから法王として権力を握っていく過程、さらには武家の時代にはいったのちの崩御まで、院の生涯が巧みに描かれているのは、さすが井上の筆力の確かさをいえる。
特に面白かったのは、第一部で、ここでは若い後白河が歴史の渦に巻き込まれていく保元と平治の乱が描かれている。その渦が収まったあと、後白河が浮かびあがる姿が活写されている。
読み応えのある歴史小説だった。
積読からの再チャレンジ
2022/08/09 02:02
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:扇町みつる - この投稿者のレビュー一覧を見る
この作品は結構前から積読していて、一回読もうとしたんですけど、ずーっと語り口調で鉤括弧のセリフが無い文体なので挫折したことがあり、今回再チャレンジで読了。
最初は後白河というよりも保元平治の乱についての昔語り。次に建春門院について、後白河院について、合計四部構成となっており、それぞれ語り手は違います。
やはり印象的だったのが第三部。
後白河の近臣が語るのですが、後白河のイメージが私の中では大河ドラマ「平清盛」や「鎌倉殿の13人」の影響で面白キャラというかエキセントリックというか、特異な人物になってるせいか、
ちょっと上げすぎじゃね?
という感想でした。
それだけ後白河への熱い思いがにじみ出ていたという事なんですけど、何せイメージが西田敏行になってしまっているので、院もお苦しみだったみたいなことが書かれていると、ブフッとなってしまい吉田経房卿すみません!という感じでした。
語り口調の文体で、改行も少ないので私のように慣れてない方は怯むかもしれませんが、保元平治の乱〜平家滅亡〜鎌倉幕府あたりの事が京の貴族や女房目線で描かれていて面白いです。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みみりん - この投稿者のレビュー一覧を見る
先日、司馬遼太郎の義経上下巻を読み終わったばかりなので、本書の中に知っている名前がここかしこに出てきておもしろかった。平信範、建春門院中納言、吉田経房、九条兼実が後白河院について語る形式をとっている。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
公家政治から武家政治への大きな転換期に朝政の頂にいた後白河法皇。この人物の政治的動きは多く述べられても、その時々の心情はいかような思いであったかを伺う本は少ないのでは。歴史小説の大家が後白河院側近四人にその時々の朝廷内の動きや中心人物の動きを語らせながら院の心情に迫ろうとしている。三部までは、なかなか心情を伺うことはできないが四部でやっと心情の一部を説いている。台頭してきた勢力には信を置かず優柔不断。従う姿勢を見せながら実は院一人で決断を下している。何とかして朝政を守ろうとしていた後白河院。やはり「日本国第一の大天狗」か。
投稿元:
レビューを見る
朝廷・公卿・武門が入り乱れる覇権争いが苛烈を極めた、激動の平安末期。千変万化の政治において、常に老獪に立ち回ったのが、源頼朝に「日本国第一の大天狗」と評された後白河院であった。保元・平治の乱、鹿ヶ谷事件、平家の滅亡…。その時院は、何を思いどう行動したのか。側近たちの証言によって不気味に浮かび上がる、謎多き後白河院の肖像。明晰な史観に基づく異色の歴史小説。
2010年12月30日読了
投稿元:
レビューを見る
「若しもこの世に変らない人があるとすれば、それは後白河院であらせられるかも知れない。左様、後白河院だけは六十六年の生涯、ただ一度もおかわりにならなかったと申し上げてよさそうである。」
「院はご即位の日から崩御の日まで、ご自分の前に現れて来る公卿も武人も、例外なくすべての者を己が敵としてごらんにならなければならなかったのである。誰にも気をお許しになることはできなかった。」
(本文、第四部より、各々一部引用)
------
朝廷内の不和、摂関家の内部争い、武士の台頭、平家滅亡と源氏台頭...平安末期の動乱の時代に、まるで一本の太い幹のようにひたすらそこにあり続けた存在、雅仁親王(後白河院)。大天狗とまで称された後白河院の生き様を、院の周囲の4人の人物の語りによって描くという手法が、非常に効果的に機能している。おそらく院自らがその生涯の上で何かを働きかけたわけではなく、周囲の皇族たちが、摂関家の人間たちが、平家の思惑が、源氏の思惑が、後白河院という人物に対して幾重もの光を当て続け、そのことで背後に幾重もの大きな影を造り出していたのではないか。本書を読んでいると、後白河院自身は一度も語らないものの、いつのまにか院の姿が立体的に浮かび上がってくる心持ちがする。それこそが、後白河院という人物の本質なのかもしれない。
-----
永井路子の「王朝序曲」(藤原冬嗣の視点を通して、桓武帝・平城帝・嵯峨帝の生き様を描いた小説)と系統は似ていますが、客観的な視点(語り手である4人の人物の主観的な視点を、外から読み進めることで、読み手は常に批判的な立場をもって後白河院の姿を客観視することが可能となる)の積み重ねで立体的な人物像を生み出す、井上靖の綿密に構築された見事な構成による、渋い味わいのある作品。
-----
投稿元:
レビューを見る
後白河院をそばで見ていた貴族・女房の回想録で
後白河院の人物像を描く。
その技法がより一層、肉感を感じさせる。
いいね。
投稿元:
レビューを見る
1975.09.30発行
(1978.07.24読了)(1977.07.24購入)
(「BOOK」データベースより)
朝廷・公卿・武門が入り乱れる覇権争いが苛烈を極めた、激動の平安末期。千変万化の政治において、常に老獪に立ち回ったのが、源頼朝に「日本国第一の大天狗」と評された後白河院であった。保元・平治の乱、鹿ヶ谷事件、平家の滅亡…。その時院は、何を思いどう行動したのか。側近たちの証言によって不気味に浮かび上がる、謎多き後白河院の肖像。明晰な史観に基づく異色の歴史小説。
☆関連図書(既読)
「蒼き狼」井上靖著、新潮文庫、1954.06.
「あすなろ物語」井上靖著、新潮文庫、1958.11.30
「敦煌」井上靖著、新潮文庫、1965.06.30
「西域物語」井上靖著、新潮文庫、1977.03.30
投稿元:
レビューを見る
後白河上皇の一生を4人の側近が語る。
後白河院は、保元の乱、平治の乱など藤原家摂関政治から平家、源氏の武士の時代へのパワーシフトの転換期にあって政治の中心であり続けた人物。
その他登場人物として気になる存在は信西入道。当時の摂関政治という旧弊に立ち向かった、という意味では彼もまた時代を動かした中心人物。
そのような人材を登用したところにも、後白河院の政治力の凄みを感じることができる。
一貫して書かれているのは、後白河院が時の権力者(平清盛、源義仲、義経等)を自らのコントロール下においていた、ということ。それには孤高の判断、つまり、それら権力者と一定の距離感を保ってきたこと、が挙げられるのではないか。
まさに源頼朝が評した「日本第一の大天狗」であったのだろう。
投稿元:
レビューを見る
後白河院本人は出てこない後白河院の小説。
後白河院の近くにいた4人の人物の口から、保元の乱から平家滅亡あたりまでに起こった様々な事件について、院とその周囲の様子が語られる。
歴史書とは違って、口伝という形なので当時院の周りにいた人々が何を考え、武家政権の萌芽にどう反応したのかよくわかって面白い。
あまり状況説明はないので、年表や系譜図を片手に読むとさらに面白いかも。
平家物語を読んだあとに読んでみると、また違った目線で堪能できると思う。
投稿元:
レビューを見る
四人(平信範・建春門院中納言・吉田経房・九条兼実)の同時代人を語り手に
保元・平治の乱から晩年にいたる後白河院の姿を浮かび上がらせていく。
文章生出身の蔵人、院の女御の女房(俊成の娘にして定家の姉)、硬骨な近臣、
院に疎まれていた右大臣のそれぞれの立場に即した語りの内容や口吻も巧み。
話者の一人はこれまで陰気にくすぶっていた皇室や公卿たちの対立が、
武士たちの合戦であっという間に片が付いてしまうことに素直に驚き、
世人の心に小気味よさが萌したと付け加える。
その武士たちも歯が立たない信西入道さえその自害の原因を院の心が離れたからと推測する。
このような時代に実力者の器量を確かめ使い方を考えてでもいるように凝視する後白河院。
そこにひんやりとしたものを覚えるが、それは冷酷さというよりも、
むしろ誰にも心の内を打ち明けることが出来ない帝王の孤独といったものだろうか。
院は公卿朝臣が日和見で役には立たないこと、そして自身も武家の力を借りなければ
ならないことを十分に承知している。だからといって屈服するわけではない。
四人が語り終えても何か得体の知れない不気味さが残りはする。
投稿元:
レビューを見る
朝廷・公卿・武門が入り乱れる覇権争いが苛烈を極めた、激動の平安末期。千変万化の政治において、常に老獪に立ち回ったのが、源頼朝に「日本国第一の大天狗」と評された後白河院であった。保元・平治の乱、鹿ヶ谷事件、平家の滅亡…。その時院は、何を思いどう行動したのか。側近たちの証言によって不気味に浮かび上がる、謎多き後白河院の肖像。明晰な史観に基づく異色の歴史小説。
投稿元:
レビューを見る
4人の視点からみた後白河院にまつわる様々な出来事。
誰にも本音を言うことなく、人や時流を見極めて自分で決めて行動してきた孤高のひとという印象。それに比べていまの時代のひとは、何でもかんでも人に喋りすぎなのかもしれない。そんなことをふと思った。
投稿元:
レビューを見る
以前読んだ時はこの時代の事をよく知らなかったのでわからないとこも多かった……のですが、今年の大河(平清盛)見ててふと思い出したので再読。
後白河法王の行動だけ見ていると、ちょっと場当たり的だったりとか一貫性がないように見えたりすることもあるんですけど、それも院政期から武家中心の社会へと変わっていく激動の時代の中で、朝廷と武家(というか平家か?)の間のバランスをとろうとしていたのかも知れない……と思うと腑に落ちるものがあります。
そしてそれをどこかで楽しんでやってたのならやっぱり日本一の大天狗だなと。この本読んでてそんな事を思いました。
投稿元:
レビューを見る
201210下旬~1127読了。大河でやっているから、登場人物がオーバーラップして分かり易い。後白河院について、4人の関係者が独白する形で書かれている。やはり“日本一の大天狗”だったのかなあ、余計に興味がわいた。