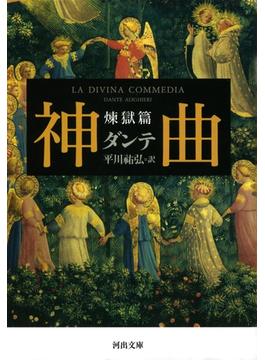中世イタリアのダンテによって著されたイタリア古典文学の傑作です!
2020/05/21 09:59
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、13世紀から14世紀にイタリアの詩人であり、政治家でもあったダンテ・アリギエーリによって著された代表作です。「地獄篇」、「煉獄篇」、「天国篇」の三部から構成される長編叙事詩です。同書は、その「煉獄篇」です。煉獄とは、地獄を抜けた先の地表に聳える台形の山で、ちょうどエルサレムの対蹠点にあります。「浄火」あるいは「浄罪」とも言えるでしょう。永遠に罰を受けつづける救いようのない地獄の住人と異なり、煉獄においては悔悟に達した者、悔悛の余地のある死者がここで罪を贖うことができます。地獄を抜け出したダンテとウェルギリウスは、煉獄山の麓で小カトと対面します。ペテロの門の前でダンテは天使の剣によって額に印である七つの 「P」を刻まれます。「P」は煉獄山の七冠で浄められるべき「七つの大罪」を象徴する印です。そして、ウェルギリウスに導かれて山を登り、生前の罪を贖っている死者と語り合います。ダンテは煉獄山を登るごとに浄められ、額から「P」の字が一つずつ消えていきます。中世イタリアの文学的傑作です。ぜひ、読んでみてください。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:H2A - この投稿者のレビュー一覧を見る
煉獄篇には地獄篇のような極彩色のイメージがやわらぎもっと淡い印象がある。ここでは地獄に墜ちるほどではないが浄化すべき7つの罪があって、その罪、短所を時間をかけて自らの足で登山していくことで清めていく。ダンテの友人たちも登場するが生きている人々の祈りによって浄罪も早まったりするというところがおもしろい。その山頂にある地上楽園に到達したところでとうとうベアトリーチェに再会。喜ぶダンテは彼女から叱責される。いつのまにかウェルギリウス師は姿を消す。そしていよいよ天国篇へ。
投稿元:
レビューを見る
地獄と比べてここ煉獄にいる人たちは KiKi にとってあまり馴染みのない人が多かったです。 そうそう、それとですね、地獄と煉獄って形からすると地獄をひっくり返したのが煉獄・・・・みたいな形になっているみたいです。 要は地獄はすり鉢状・・・というか漏斗状で下へ行くほど狭まってその先っちょにあるのが氷漬けの世界なんだけど、煉獄はそれを上下ひっくり返したような形の急峻な岩山でその天辺にあるのが天国・・・・らしい。 地獄から天国に移動する際には地獄の底に埋まったルシフェロの体づたいにダンテはウェルギリウスに負ぶさって、地球の球体のど真ん中を突き抜けてエルサレムとはちょうど反対側に突き抜けていくような形で浄罪山のほうへ脱出していったということらしいです。 何となくネジをどんどん下がっていくみたいな感じがしてちょっと面白いと思いました。
(全文はブログにて)
投稿元:
レビューを見る
ベアトリーチェに会いに!
その思いで辛く、険しい山道を登る。
ところどころ一息つけるものの、なかなか読み進むのがつらかった。
頂上に着くとベアトリーチェに会えるが、ベアトリーチェがなかなか手厳しい。
気づくとヴェルギリウスが消えているし。
地獄に落ちなくても7つの大罪の罪を煉獄で償わなければならない。
ああ、天国への道はかくも厳しいものなのか。
途中、フランスのカペー朝の王たちの名前があげられていたのでカペー家の歴史がついでに読めてしまった。
投稿元:
レビューを見る
ダンテの神曲の2篇目、煉獄篇です。地獄篇を無事に抜けたダンテが煉獄山を登り、地上楽園を目指していきます。
「煉獄」という語は少しなじみのない言葉ではないでしょうか。私は本書を読んで初めて、こうした世界が地獄と天国との間にあることを知りました。そこに描かれるのは、地獄篇に立ち込めているような悲惨さではなく、「ここを最後まで登り切れば必ず天国に行ける」という希望をよすがとして苦役に耐える魂たちの姿です。しかし一方で、突然現れたダンテ一行に「あの人には影があるぞ」と驚いたり、そのような表情のまま恐る恐る近付いて「自分のことをどうか現世の人に伝えてほしい」と口々に懇願したりする姿は滑稽でもあります。そのためか、登場人物からはあまり悲愴な印象を受けませんでした。
現世で山を登るときには、たいていは(私は山登りの経験はないのですが)頂上に近づくにつれて疲労が増していくものだと思うのですが、煉獄山ではそうではないようです。煉獄の門をくぐるとすぐに急峻な岩場が現れ、ダンテは息も絶え絶えにそこを越えていきます。その描写も巧みで、読者としては「まだ先は長いのに初めからこんなに疲れるなんて」という感情に襲われます。通常の山とは逆に、煉獄では登れば登るほど身体が軽くなっていくようなのですが、読みながらその軽やかさを追体験できるか、と言えば、私にはとても同意できません。このもどかしさはやはり私が現世に生きているからなのでしょうか。ですが、このような描写もやはり滑稽なものなのでしょう。
そして、地獄をずっと2人で旅してきた一行ですが、本書中盤の第21歌からはもう一人、ラテン詩人のスタティウスが加わります。ウェルギリウスを心底尊敬していたというこの人物の登場によって、作品の雰囲気はがらりと変わります。彼とのやり取りを通じて、ウェルギリウスの人柄が、主人公であるはずのダンテ以上に伝わってくる気がしました。地獄では厳格な人物という印象のあった彼の、スタティウスの一途な(?)想いに触れた時に表す心情などは、とても親しみやすいものに感じられます。このような描写のおかげか、本書は先の地獄篇よりもずっと明るい印象を与えるものとなり、原題の「Commedia」にずっとふさわしい内容になったような気がしました。そうした意味では、私個人としては地獄篇より煉獄篇の方が好みであるかも知れません。平川祐弘訳。
(2009年7月入手・2011年2月読了)
投稿元:
レビューを見る
二人の詩人、ダンテとウェルギリウスは二十四時間の地獄めぐりを経て、大海の島に出た。そこにそびえる煉獄の山、天国行きを約束された亡者たちが現世の罪を浄める場である。二人は山頂の地上楽園を目指し登って行く。永遠の女性ベアトリーチェがダンテを待つ。清新な名訳で贈る『神曲』第二部煉獄篇。
投稿元:
レビューを見る
日本人におよそ馴染みのない『煉獄』が舞台。地獄に行く程ではないが天国に行くまでに改悛が必要な人が来る場所。天国行きが確定している人が来る場所です。ヴェルギリウスがいなければ意味が分からなかったと思います…。地獄ほど生き生きした文章ではないものの、変わらずサクサク読み進められました◎煉獄では生きている身内に祈ってもらうと天国行きが早まるので、生きているダンテに我先にと話を聞いてもらいたがる下りが非常によく出来ているなぁと思います◎面白かったです!
投稿元:
レビューを見る
其れが目的のひとつであるからには当然のことなれど 宗教文学のとどのつまりは その宗派に属する者の祝福にあるから 何れを採っても私などは蚊帳の外 お陰で公正な眼でもって その教義が宗派を超えた処で——つまり万民にとって普遍の真理たり得るか否かを観察することが出来る。熱狂や戦慄からは一線も二線も画されて在り 個人的反省や呵責を別としたなら 所詮他人の土俵上の取組を観覧しているに過ぎない。
外国文学を採る限りは そうした一抹の無益は付き纏う訳だが このように小さな 旗頭をもたない国土に産み落とされたのは運の尽きで 彼方の人類史に占める面積も質量も大きい以上 理不尽でもこれに組み拉かれて往くより仕方はない。
なれど 一体 本来で在れば得られた筈の処のどの程度 異教の民は読み取るだろうか。
投稿元:
レビューを見る
地獄篇から煉獄篇(Purgatorio)へ。
全ての霊は、死後、肉体を離れ、地獄行きか煉獄行きか分別される。生前の信仰のため、地獄に堕ち永劫の罰を受け続けるのを免れた霊が、天国界へ昇るのに相応しくなるべく罪を清める場所がこの煉獄界、浄罪界とも訳される(なお、聖書に煉獄界の記述は殆ど無く、のちのプロテスタント教会ではその存在を認めていない)。
浄められるべきは七つの大罪。傲慢・嫉妬・憤怒・怠惰・貪欲・大食・色欲。地獄で罰せられる罪よりも日常的なものであるため、キリスト教の倫理的厳格さが却って身に詰まされる。
「私の血は嫉妬に煮えたぎっていたから、/もし人の幸福を見ようものなら、/顔面は、君の目にも見えるほど、蒼白となった。」(第十四歌)
□
キリスト教の世界観では、神の絶対性・神に対する人間の無力さが公理として前提される。
「おまえらにはわからないのか、われわれは守りもなく/裁きに向かって飛ぶ天使のような蝶となるために/生まれついた虫けらだということが?/なぜおまえの気位はそう高く舞いあがるのだ?/おまえはいわば片輪の虫、それも/まだ発育不全の蛹のようなものではないのか?」(第十歌)
「三位一体の神が司る無限の道を/人間の理性[ratio=計算的理性――引用者]で行き尽くせると/期待するのは狂気の沙汰だ」(第三歌)
次の引用に云う「自由」も、当然のことながら、「神への自由=罪に塗れた肉体という鉄鎖から解放され霊が神へと合一していく自由」であって「神からの自由」ではない。勿論、近代的な政治的「自由」でもない。
「自由を求めて彼は進む、そのために/命を惜しまぬ者のみが知る貴重な自由を」(第一歌)
愛の志向も美への陶酔も、一方で人間に自由意志を認めておきながら、最後には神の裁きと地獄の罰を持ち出して、愛や美への自由を矯めようとするのがキリスト教の教えだ。
「人間は善や悪を愛し、/その愛を集めて選り出すことができる・・・。」(第十八歌) 「・・・善悪を知る光や自由意思が君らには与えられている」(第十六歌)
「愛がおまえたち人間のあらゆる徳の種であり、/かつ罰に値するあらゆる行為の種である・・・。/・・・およそものは自己嫌悪におちいることはありえない・・・。/そしてあらゆる存在は原初存在[神]から切り離されて/それ自体で存在するとは考えられぬ以上、/およそ被造物はそれを憎むことはできぬわけだ」(第十七歌) 「およそ愛と呼ばれるものなら/それ自体でみな称賛に値すると主張する人の目には/真理は隠れ、真相は映じていないのだ」(第十八歌)
「天はおまえらを呼び、おまえらの周りを回って、/その永遠の美の数々を示しているが、/おまえらの目はもっぱら地上に注がれている」(第十四歌)
神の絶対性を志向する、則ち神と云う審判者の赦しを日々希求し続ける、その強迫的なまでの目的論的世界観とは、何と窮屈な生だろう。想像するだに息苦しい。
□
"永遠の女性"と云われるベアトリーチェも、要は自分の死後にダンテが自堕落な生活に陥り「よその人の許へ走った」ことを、キリスト教の用語を用いて責めている。そもそもダンテのこの彼岸行自体が、堕落した彼の眼を覚まさせるには「破滅した人間を見せるより外に/もはやない」と、彼女によって図られたものだった。
"永遠の女性"とまで云われる彼女が、言葉ばかりは宗教的な説教で飾り立てているが、その実は高慢で世俗的な女であったことに対して、率直に云って失望を覚えた。「世の中の人々が苦労して方々の枝に探し求めた/あの甘い樹の実」「おまえの餓えをいやしてくれる」(第二十七歌)天国に於いて、彼女はどんな言葉を語るのか。
□
内面に於て最も清浄たるべき神的合一を憧憬する精神的営為を、世俗に於いて支えるはずの教会。そんな内面に於ける宗教的権威が世俗に於ける政治的権力と一致してしまっては、その権威の源泉たる清浄な信仰心は、世俗の泥濘に何処までも墜ち込んでいくだろう。現に、政治活動家でもあったダンテの本作にも、信仰の清浄な静謐さとはほど遠い、俗世の政治状況に対する憤怒怨恨を露わにしている場面が多々見られるではないか。天皇制批判にも通じる一節を引用する。
「・・・。ローマ教会は/[世俗と宗教の]二権力を掌中に握ろうとしたから、/泥沼に落ち、自分も汚し、積荷も汚してしまったのだ」(第十六歌)
加うるに、内面を支配する宗教的権威が世俗を支配する政治的権力と一致してしまっては、神の絶対性へ合一しようとする宗教的心性は、世俗に於ける絶対的な暴力へと容易に転化してしまうことも歴史を顧みれば看て取れるだろう。
□
最後に、我が身へ向けての叱咤の句を記しておく。
「風が吹こうがびくとも動ぜぬ塔のように/どっしりかまえていろ。/次から次へと考えが湧く男は、/とかく目標を踏みはずす。/湧きあがる力が互いに力をそぎあうからだ」(第五歌)
投稿元:
レビューを見る
地獄や天国と違って煉獄というのは日本人になかなか馴染みがないのだけど、そもそもキリスト教内でもプロテスタントや正教会は煉獄の存在を認めてないのだから仕方がない。地獄が信心を持たない者がその罪によって裁かれる場所なのに対して、煉獄は信者として救済を約束されていながらも生前の罪を浄化するために設けられた苦しみの場であるというのも始めて知って興味深かった。内容は一層混み入ったテーマやさほど有名でない人物議論に入っていくが、ウェルギリウス先生と共に行く煉獄山の登山光景は地獄の重苦しい雰囲気と違ってどこか爽やか。
投稿元:
レビューを見る
すいぶんかかって読破。
地獄篇~煉獄篇~天国篇と、あわせて1000ページを軽く越えるボリューム。
ちなみに、宗教的な興味がとくにあったわけではない。
「分かりやすい」と好評の訳だけあって、さながらダンテと旅する気分。地獄篇では、さまざまな罪によって罰を受ける人々を見て、ちょっぴり自分の罪を悔いてみたりもした。
煉獄から徐々に抽象的になっていき、天国はまったく理解を越えていた。まだ私の魂はそこに到達できないらしい。(笑)
投稿元:
レビューを見る
地獄編に続いて煉獄編。
煉獄とは、生まれ変わるために魂の浄化が行われる場所で、巨大な山になっている。
地獄編よりも。情景の描写が一層文学的になり、また思想も多く散りばめられている。
しかし、地獄編よりも面白みは薄くなってしまった印象。
ダンテと会話をする人物それぞれの個性が立っていないので
全体的にぼんやりしているのかも。
後半でベアトリ―チェにやっと逢うことができるが、まさか遭遇した時のベアトリ―チェが結構強烈な人で驚いた。
それにしても、ウェルギリウスがここでお別れしてしまったので、「先生」の言葉と素敵な振る舞いが、これから天国編でみられないのは、大変に惜しい。
地獄の罰を受けることも、煉獄で浄化されることも、天国に行く着くことも、生まれ変わることも出来ない、永遠の魂の放浪者・ウェルギリウス。
少し遅く生まれたスタティウスが、最期に改宗した故に煉獄山を登ることを許されたのに、死後はるかに詩人としての評価が高いウェルギリウスがこうした扱いを受けてしまう、キリスト教の考え方に、理不尽を感じてしまった。
いつかウェルギリウスの「アエネイス」も読んでみたい。
投稿元:
レビューを見る
煉獄とは、天へ昇る前に自らの罪を浄める場所です。煉獄の山を登り終えたとき、全ての罪が浄められるとされています。
ダンテは星を見上げ、ベアトリーチェの愛を感じ「信じること、希望を持つこと、そして人を愛することこそが、人を支える基本的な力である」ことに気付きます。
煉獄の山では、かつて自惚れたり高慢であった人々は重い石を担ぎ、嫉妬深かった人々は目の瞼を縫い付けられ、怠惰であった人々は走り続け、貪欲であった者は腹這いで伏し続けるという試練に遭っています。
詩人ウェルギウスは説きます。
愛とは人の好みの感情に似ていて、好きな方に流れていく。人は本来の努めの度が過ぎてしまったり、道を逸れてしまう結果、償いをするために善をつむこととなる。つまり良い行いも、悪い行いもともに愛から発しているということなのだと。
また煉獄ではひとつの魂が浄化されると、天と地が呼応します。
そこでダンテは、魂は個人的な存在ではなく、ひとつの存在がその他全ての存在に関わっており、誰かを思う気持ちや愛があってこそ魂は浄化され、すべてのものが、ひとつの魂の浄化を喜ぶことを知ります。
煉獄の最後の試練である、炎を浴び身を浄めることで、ダンテは降臨するベアトリーチェとついに再開することができます。
ベアトリーチェは母の優しさをもってダンテを責めます。
あなたは私が死んでしまうと悲しみのあまり我を忘れ、正道を見失った。
失望したが、どうしても見捨てることはできなかった。だからウェルギウスに頼み、地獄を見せー煉獄の炎で身を浄めさせー神の真実を示すほかに道はないと考えたのだと。
そしてダンテはベアトリーチェに導かれます。光り輝く神の国ー天国へ。
投稿元:
レビューを見る
ダンテはウェルギリウスに導かれ、最上部の地上の楽園(エデンの園)を目指して七つの圏(わ)を登っていく。そのそれぞれの圏(わ)では、キリスト教の七つの大罪(高慢、嫉妬、怒り、怠惰、貪欲、大食らい、色欲)を犯した魂たちがその罪を浄められている。
その浄められ方がなるほどそうなのだろうという感じ。
地獄編もそうだったが、ダンテさんの想像力、描写力はやはり凄い!
Mahalo
投稿元:
レビューを見る
ダンテ(平川祐弘訳)『神曲』河出書房,2009(初版1966)
全33歌。ダンテはウェリギリウスに導かれて、地獄からはいあがってきた。一応、煉獄は南半球にあるらしい。カトーに出迎えられ、船でついた魂たちと煉獄の山を目指す。煉獄(Purgatory)は古代にはなく、中世にできあがった概念らしい(ル・ゴフ『煉獄の誕生』未読)。ダンテによれば、死者の魂は現世で死ぬと、海を越えて、煉獄に運ばれてくる(この点、あの世を海の向こうと考える日本神話の一部とも共通していて、興味深い)。煉獄は死の前に神と和解した魂が、七つの大罪(高慢・嫉妬・怒り・怠惰・貪欲・大食らい・色欲)を清めるところで、ダンテは煉獄の入口で天使に七つのP(peccato:イタリア語の「罪」)を額に刻印され、煉獄の七重の山を上っていく。一つの罪をみるごとに天使にPを消してもらい、賛美歌が聞こえてきて、身が軽くなる。地獄は下りだが、煉獄は上りである。高慢の罪の魂は岩を負わされていたり、嫉妬の魂はただ座り込んでいたり、貪欲の罪は寝そべることを強いられていたり、色欲の魂は火で灼かれていたりする。興味深いのは「大食らい」の罪で、この罪を犯した魂は痩せこけている。ダンテは食物を摂る必要のない魂がどうして痩せこけるのかと疑問を発する。ここで、煉獄の浄罪を終えて旅を共にするスタティウスが答える。スタティウスは西暦50年前後の詩人で隠れキリスト教徒だったという設定、ウェリギリウスを尊敬している。彼の知識では、心臓の血から精液が生じ、「自然の器」(子宮)で血と結合し、生命がうまれるが、その脳を作るに及び、魂が生じる。魂は死んでも、その活動をやめず、生きていた時と同じく形成力によって霊魂の体をもつようになる。これを鏡が姿をうつす例で説明する。要するに死んでも体があるから、痩せこけるのである。この他にも水蒸気が冷やされて雨になるなどの気象学の知識も披露されている。
ダンテとウェリギリウスとスタティウスは七つの大罪の浄めを通りぬけ、最後の炎を通り抜けると、頂上のエデンの園で、ベアトリーチェと再会する。ベアトリーチェはいきなりダンテを叱りつける。ダンテは9才のときに、ベアトリーチェとはじめて会い、18歳のときに再会、その後、ベアトリーチェは銀行家に嫁いで、25歳で死んだ。要するに初恋の人である。天国に上ったベアトリーチェは、ダンテが自分が死んだ後に他の女性にうつつを抜かし、身をもちくずして、このままでは地獄落ちになるのを心配して、ウェリギリウスに泣きついて、ダンテに地獄と煉獄をみせたのであった。ダンテは十年ぶりに会ったベアトリーチェから小学生のように叱られて声もでない。それでも、なんとか前非を悔い、マテルダに助けられて忘却の川レテで罪の記憶を洗いながし、ダンテはベアトリーチェとともに天に昇ることになる。
要するに、35歳のいい年をした男が、初恋の人に子供のように叱られる話であるが、仏教でも観音さまは慈悲深い女性のようだし、なんか恋した人に叱られたい願望ってあるのかなと思う。
ウェリギリウスは第30歌で静かに姿を消す。ベアトリーチェは結構自意識過剰。
「私がその中にいた美しい肢体ほどお前の目を/喜ばせたものは自然にも人工にもありませんでした。/その肢体はいまは大地へ塵となって散りました。/私が死に、それで至上の喜びが脆くも失せたというのなら、/どうしてはかない現世のほかのものが/おまえの心を惹き得たのでしょうか。」