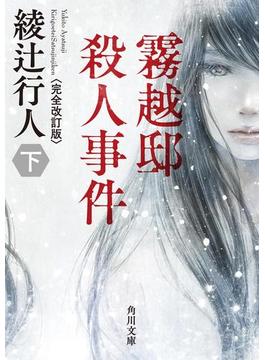死を予言する館(下)
2015/05/10 23:25
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:翠香 - この投稿者のレビュー一覧を見る
下巻に入ると一気に物語は加速。
でもまさかあの人まで殺されてしまったのはショックでした。
実は途中まで犯人と疑っていたのですが・・・。表紙の絵を深読みし過ぎたかも(^^;)
北原白秋の『雨』の歌詞に見立てた「見立て殺人」。
読んだのが梅雨の時期だったので、雰囲気満点でした。
犯人に関して、分かりやすい伏線を見逃してしまったのが不覚。
動機は到底理解できるものではないですね。やっぱり犯人狂ってます。
結局3F部分は何も関係ありませんでした。
幻想的な雰囲気がとても好みでした。
本格ミステリ×幻想
2024/01/16 00:28
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ミ - この投稿者のレビュー一覧を見る
雪の山荘の中で起こる殺人事件を解く物語。推理に非現実的なところがあるので、現実主義者は受け付けない作品かも。
なんとも不思議な読後感
2018/10/31 22:42
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:沢田 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ミステリー特有の生臭さがなくて、現実感が希薄な気がする。
真の名探偵が出てきて真相を明かすところは、ちょっと強引な気がしたけどあとは満足できる出来ですね。
投稿元:
レビューを見る
下巻。
内容をすっかり忘れてしまったと思っていたが、流石に謎解きのキモはしっかり覚えていた。
新本格として世に出た作品だけあって、幻想はあくまでも『風味』に留まっている……と思うのだが、巻末の対談によると、これでも賛否両論あったらしい。そういうものなのか……?
この巻末対談は、当時の時代背景や執筆の動機などが解りやすく纏められていて面白い。但し思いっきりトリックと犯人について語っているので、本編のあとに読んだ方がいい。
投稿元:
レビューを見る
え、そんなところで終わっちゃう?
っていう驚きで終わるはずもなく。
やっぱり綾辻さん、期待を裏切ることはないな、と。
投稿元:
レビューを見る
完全改訂版再読。
館シリーズ番外編ともいえるような作品。変な仕掛けはないけれど、館自体が意志を持っているかのような「霧越邸」の魅力は随一かも。館が未来を予言し示唆するという幻想的要素が作品を支配してはいますが、事件の謎解きに関してはばりばりの本格です。
吹雪の山荘・見立て殺人という道具立ても万全。事件現場の光景もあまりに美しくて印象的。どこをとってもミステリ・幻想の魅力がいっぱいいっぱいに詰まった傑作です。
投稿元:
レビューを見る
一番興味深いのは、巻末の特別インタビュー402ページ。最初から本格ミステリと幻想小説のハイブリッドを書こうとしていたわけではなく、本格としての整合性や完成度を追及した結果、このようなジャンルの定形から逸脱したような形になってしまった、という箇所。どうやら本格の形式を突き詰めていくと、最終的には本格の壁を打ち破ってしまうらしい。それと本書の四六判オリジナルって、『暗闇坂~』と同じ年に出てるのね。これぞまさしくシンクロニシティ?
投稿元:
レビューを見る
【あらすじ】
外界から孤立した「霧越邸」で続発する第二、第三の殺人…。執拗な“見立て"の意味は? 真犯人は? 動機は? すべてを包み込む“館の意志"とは? 緻密な推理と思索の果てに、驚愕の真相が待ち受ける!
【感想】
投稿元:
レビューを見る
訪れる者の未来を写すという霧越邸。
幻想的な世界と永遠の美。
生々しい生への執着を描く本格ミステリと
浮世から乖離した死への憧れを描く幻想小説。
矛盾する二つを併せ持った綾辻行人の創作する世界。
彼の作風を決定づける一作。
投稿元:
レビューを見る
しっとり、みっしり、込められた、偏執的ななにか。
館シリーズとは違った方向からの、館への狂気性。館そのものから受け取るなにかというよりも館が暗示するもの、見せるもの、用意された小道具に後押しされた犯罪。狂気といわれたらそうなのだろうけれども、一言で狂気とは片付けられない。
山奥の洋館、吹雪、見立て殺人、「本格」の要素がこれでもかというほどてんこ盛り。双子が出てこなかったのが不思議な感じ。
見立てに使う道具、要素も館自体も好きなんだけど、今一歩館シリーズに及ばないのは、犯人のラストが納得いかないからかもしれない。犯人の思考は好き。どちらかというと犯人よりの感覚を持ってるのだろうな、とも思う。死してこそなお、というつもりはないけれど、今この場で生を絶ってこその美、完成形がある、というのは分かる気がする。生きているものに興味がないからだろうね。生物は飽くまでも観察対象であって、鑑賞対象にはならないから。だから犯人の感性は好きなんだけど、最後がどうにもね。
態度があからさま過ぎるんだよなぁ。自分に都合の悪い話題が出たときと、都合のいい話題になったときと。それすらも隠してスマートに物事を運んだ上で、最期があれだったら賞賛する。悪あがきとか保身はよくないよ。かっこ悪いよ。
要するに、本格ミステリというものは、被害者、犯行方法、犯行動機はもちろんのこと、犯人自身も含めて一つの「芸術」足り得るものとして描かれてこそ至高なんだろうな、とね。その芸術性がこの話の真犯人には欠けていたので減点。だからっつって、どうしたら良かったのかとか、作品としてそっちのほうが良かったのかとかは分からないけど。
あ、ちなみにこれ、再再読くらいですが、全力で真犯人を忘れてました。
表紙が角川のこのシリーズに揃えてイラストなんだけど、上巻の深月嬢(だよねたぶん)が伏し目なのに対し、下巻だと視線が上がってる。作中の言葉で表せば「未来を見始めた」ってことなのかもしれないけど、伏し目のまま生きて天寿を全うするのと、この時、この場で美として完成して死ぬのと、どっちが良かったのかって話。問題は、「完成」だと思ったのが彼女自身ではなく無関係の第三者だったという点か。
抜粋は上巻より、物語に入る前、登場人物紹介の次の一文。
――もう一人の中村青司氏に捧ぐ――
投稿元:
レビューを見る
感想は上下合わせてのものです。
雪山の山荘で連続殺人で見立て殺人で怪異的なものもプラスという「全部盛り」なミステリ。こういうオーソドックスな鉄板ものは時々無性に読みたくなるw
とはいっても、逆にいうと手垢がつきまくっているジャンルでもあるので残念ながら今作も読み終わって「奇想天外なトリック」とかそういうこともなかったんですが、まあそれも含めての鉄板ということで。
でもそもそも書かれたのは随分昔なんですね。改定版だからなのか、あんまり古さを感じませんでした。文章を読みやすく直してもどことない古臭さがでたりするもんなんですけどね。元々が「古典的」な分野だからなのか、綾辻行人の文章が昔から洗練されているのか・・・
投稿元:
レビューを見る
上巻の表紙を捲ると、まず舞台となる館「霧越邸」の見取り図があります。
湖に張り出した広大な館の見取り図を眺めるだけで、これからここで何が起こるのか期待で胸が高鳴るというもの。
隅々まで豪華絢爛な館の描写は謎めいていてとても美しいです。
吹雪で閉ざされた館で起こる連続殺人といういかにもな設定ですが、この館の神秘さがありきたりなストーリーにさせていません。
館を訪れる人々の運命を暗示するかのように「動き出す」館、その意志に沿うように起こる事件。ファンタジーかSFかと読者を惑わせますが、非論理的な現象を論理的な解釈に取り入れて幻想的な雰囲気のまま本格ミステリとして終着していくのが見事。
豪華な調度品が並び不思議なバランスで調和している霧越邸と同じように、非現実と現実が上手く調和された素晴らしい1冊でした。
ネタバレ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最初に間取り図を見た時に「これは館を使った壮大な物理トリックがあるに違いない」と勝手にワクワクしたのですが、意外に理詰めの堅実な展開で、良い意味で予想外でした。
「館」をこういう風に使うのは新鮮。
予言するかのような現象が堅実か?という話もありますが、これはもう一人の犯人である槍中が現象の中に何かを見出したということが重要であり、館の現象が事実かどうかは関係ないのでこのあたりも上手く出来ていると思います。
4度の事件で、途中から槍中が便乗したことにより事件が重層的になっているところがおもしろいのですが、4度目の事件で介入し逆に槍中を惑わせたのが真の探偵役だったという事件の展開にはニヤリとします。
第一の事件の死亡推定時刻のごまかしがあそこまで上手くいくかは疑問ですが、見立て殺人の理由には納得です。
見立て殺人はちょっと無理があるんじゃ?という事が多いですが、その違和感が「雨」殺人事件→実は「童謡」殺人事件という真相に繋がっていくのもすごい。
登場人物一覧に丁寧に本名まで書いてあるので何かあるのだろうとは思っていましたが、槍中の名前には気づきませんでした。
作中内で名前が変わる、しかも霧越邸で変わることで槍中へも影響を与えるというのが憎い演出。
吹雪に閉じ込められた幻想的な館が、槍中の心理的な動揺に説得力を持たせています。
霧越邸の人々にとっては本当に迷惑な話だと思いました。
投稿元:
レビューを見る
かなり久しぶりの綾辻行人。
この改訂版は発売日に買っていたのですが、なんだかんだで今日まで読まずに来てしまったのです…
さて、内容はというと…
一部に館シリーズとのリンクがあるらしい(時間が空きすぎて覚えていない)のだが、単独作品としても楽しめます。
巻頭の見取り図を見ているだけでワクワクするような館(邸)で見立て殺人が次々と起こるのですが、幻想的な雰囲気と相成ってどこか夢の中の物語を見ているような気分で読み進めました。
解決編は質、量ともに圧巻で、細かな伏線を元に繰り出されるロジックはかなりの説得力を持っています。
一見、意味のないように思える行為にも、館(邸)のもつ観念的なものをうまく組み込み必然性を生み出しているあたりも流石です。
館シリーズに見られる大胆なトリックこそありませんが、本格ミステリの醍醐味がこれでもかと詰まった良作でしょう。
投稿元:
レビューを見る
次々と巻き起こる雪山山荘での殺人事件.オカルト的な雰囲気も相まって背中に冷たい汗をかいてしまう.典型的な推理小説.著者にちょっと不信感を抱いてしまうセリフがあり,個人的にはあまり好みではない.
以下あらすじ(巻末より)
1986年、晩秋。劇団「暗色天幕」の一行は、信州の山中に建つ謎の洋館「霧越邸」を訪れる。冷たい家人たちの対応。邸内で発生する不可思議な現象の数々。見え隠れする何者かの怪しい影。吹雪で孤立した壮麗なる“美の館”で舞台に今、恐ろしくも美しき連続殺人劇の幕が上がる!日本ミステリ史上に無類の光芒を放ちつづける記念碑的傑作、著者入魂の“完全改訂版”!!
投稿元:
レビューを見る
ネタバレあり。
雪山で遭難して下様ったら劇団「暗色天幕」一行は山奥に立つ洋館「霧越邸」へと避難するが、そこで不可思議な現象とともに連続殺人事件が起きて…というのがあらすじ。
綾辻さんの本は館シリーズを何冊か読みましたが、これはけっこう読み辛かった…。それほど複雑では無いのですが、洋館の内装、外装がイメージしにくかった。館シリーズに登場する館のほうがよほど複雑な構造だと思うのですが、なぜでしょう。あとはやはり、探偵役の彼が哲学科だからでしょうか。「小難しいことはいいからさっさと推理しないさいよ」とちょっとイライラしながら読んでしまいました(笑)なので個人的には読みにくかったのです。
ですが幻想的な要素と本格ミステリ的要素が入り混じっていてこれはこれで初めて読むジャンル?だなと思いました。犯人もわかったけれど霧越邸最大の謎は残されたまま、そしてその謎をどう捉えるかは読者次第。