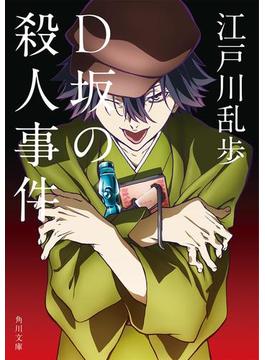0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:帛門臣昂 - この投稿者のレビュー一覧を見る
江戸川乱歩の怪奇と謎を織り交ぜた推理小説を楽しむのに最適な詞花集。
その特徴的な描写の切り取り、場面の切り替わりを楽しんでほしい。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
名探偵・明智小五郎の無名時代を垣間見える、表題作は貴重です。「D坂」の文京区界隈の町並みと、江戸川乱歩とも縁のある古本屋と蕎麦屋も味わいがあります。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:マー君 - この投稿者のレビュー一覧を見る
久しぶりに読み返してみたが、いつ読んでも名作。
中でも地獄の道化師は秀作。心理試験もよい。
帯に、僕は人間を研究しているんですよ、とあるようにトリックよりも人の心理を用いた推理小説。
個人的にはD坂はどうかなと。
投稿元:
レビューを見る
実は江戸川乱歩はこれが2冊目。1冊目が「人間椅子」の入っている短編集だったので、実質、彼の探偵ものを読むのは、これが初めてということに。
明智小五郎の名前が出てきたときに、なんともいえない気持ちになりました。そうか、彼が本家本元か。彼のあとに、たくさんの和製探偵が生まれ、江戸川コナンが生まれ毛利小五郎が生まれ、明智警視が生まれたのだなと思うと、なんていうんでしょうか。家元、降臨!みたいな。
「D坂の殺人事件」「二銭銅貨」「何者」「心理試験」「地獄の道化師」の5編が入っています。明智さんが出てくるのは、このうち4編。「何者」では明智さんが盛大にディスられています。口だけなんだよなーあの男とかって。ここに、ちょっと笑ってしまいました。
このうち、「何者」と「心理試験」が好きでした。どちらも後味悪いですが。「何者」はタイトルが秀逸。「何者」では見取り図が、「心理試験」では表(というか、心理試験結果というか)が載っていて、それも、ここからすべての和製推理小説が始まったのかと胸が熱くなりました。
面白いものは、時代を経て尚面白いのですね。そして、怖いものもいつの時代も怖いのだと思いました。屏風から出てくる白い虫のような指は、背筋を寒気が上下いたしました。終始、ここから伝説が…!みたいな気分で読んでいたため、没頭できなかったかもしれませんが、推理もの、探偵ものの歴史に直に触れた気がして、ワクワクしました。
投稿元:
レビューを見る
有名所過ぎて食指が動かなかった著書。
面白いは面白いのだが現代作家に比べると会話を極力減らし、推理も地道な調査はせず、探偵(あるいは探偵役)が天才的なひらめきで解決していく。
現代では古い手法だが、半周して逆に斬新。
あえて不満を言うのならキャラクターの書き分けがないので読みつらいところ。
投稿元:
レビューを見る
明智小五郎が初めて登場する表題作をはじめ短編5編。
乱歩作品をきちんと読んだのは初めてかも知れない。
倒叙ものに入れ替わりトリック、暗号などミステリーの醍醐味満載の一冊。時代が違うので、少し読みにくさはあるけれど、十分面白い。明智さんと犯人の心理戦が光る「心理試験」が特に好き。
最近よくあるキャラものに慣れてるせいか、最後まで明智さんの風貌や人となりが読みきれないまま終わってしまったのが残念。ほかの作品も読んだら分かるかな。
投稿元:
レビューを見る
実は初江戸川乱歩。
いつか乱歩読まなきゃなーって思いつつ、乱歩さんの表紙が可愛くて衝動買いしてたもの。歌野の新刊がD坂~だったから、じゃあ先に読んでおくか、と。
D坂含め、五編の短編が入ったもの。書かれた時代が時代なので、今だったらこういう展開にはなりえないし、こういう推理は成立しないなっていうのはまあ多々あるんだけど、心理合戦はとても面白い。
「二銭銅貨」、暗号も面白かったけど、最終的なオチがすげー好き。これはひどい。「何者」「心理試験」もそうだけど、このころの男性間の友情ってよくわからない。
一番最後の「地獄の道化師」が好きです。うすら寒くてぞっとする。
抜粋、「心理試験」より。
彼はナポレオンの大掛りな殺人を罪悪とは考えないで、むしろ讃美すると同じように、才能のある青年が、その才能を育てるために、棺桶に片足ふみ込んだおいぼれを犠牲に供することを、当然のことだと思った。
投稿元:
レビューを見る
中学生長男に「D坂の殺人事件」が必要だったので図書館で取り寄せたら、こんな萌絵?みたいなのが来てしまって、私が読むのがこっ恥ずかしかった…orz
最近の”名作”がどんどん萌絵になってますが若い読者獲得の役に立っているんでしょうかね。
短編集。若かりし頃の明智小五郎がちょっと顔を出してくる。
最初の「D坂の殺人事件」では無職の推理好きの25歳、次第に探偵として世間に名を知れていき、最後の「地獄の道化師」では探偵事務所を開き助手小林少年も出てきます。
名探偵明智小五郎初登場。
『それは九月初旬のある蒸し暑い晩のことであった。
私は、D坂の大通りの中ほどにある白梅軒という行きつけの喫茶店で、冷やしコーヒーを啜っていた』
美味しそうだなー”冷やしコーヒー”。アイスコーヒーよりも甘くてトロンとした印象。
この冷やしコーヒーを啜っている語り手は学生上がりで無職でゴロゴロしている青年。
同じようにゴロゴロしている明智小五郎というちょっと変わった男と知り合う。
そしてたまたま明智小五郎の幼馴染の女の死体を見つけ、素人探偵として推理を行う。
すると明智小五郎こそが殺人犯としか思えないではないか!
/D坂の殺人
投獄された泥棒の盗んだ大金のありかは?
たまたま手に入った二銭銅貨に隠し場所の暗号が?!
/二銭銅貨
上流階級の邸宅で起きた殺人事件。
素人探偵たちが繰り広げる各々の推理。
最後に笑うのは…
/何者
金を溜め込んだ老女を殺す計画を立てた秀才貧乏学生の殺人に至った経緯と、その心理過程を見ぬき殺人犯を暴く名探偵…、と、ロシアかどっかの文学で聞いたようなお話を下敷きにした心理ミステリー。
/心理試験
すっかり名医探偵として認められ探偵事務所を開く明智小五郎の元に舞い込んだ依頼。
石膏像から出てきた女の死体。
誘拐、犯罪予告、放火…それらの影に現れる道化師の影。
/地獄の道化師
投稿元:
レビューを見る
ゆっくりと読んでやっと読み終わりました。
短編なので、一本読んだらしばらく休んで、という読み方をしていたら、読み終わるまでに結構かかっちゃいましたが、一本一本は一気に読みました。
なかでも、私が好きなのは
「D坂の殺人事件」
「地獄の道化師」
の二本。
特に
「地獄の道化師」
はヒリヒリしたものが心に残る、最近ではあまり見ない終わり方だったような気がします。
ちょっと現代にも通じるものがあるような…
もう少し時間が経ったら、また読み返すであろう、一冊のような気がします。
投稿元:
レビューを見る
「D坂の殺人事件」
明智小五郎の初出。喫茶店にいた「私」と探偵小説好きの明智小五郎が話していると、向かいの古本屋で殺人事件が…
「二銭銅貨」
工場から大金が盗まれた。しかし捕まった泥棒は金の在りかを吐かない。
世間が泥棒ネタでもちきりのところ、二人の若者が泥棒が残したと思われる暗号を見つけて…
「何者」
ある邸宅で発砲事件が発生。家の息子が足を打たれたが命は助かった。
犯人探しが始まるが、犯人が侵入した窓の外の足跡は途中で不自然な位置で消えていた。
「心理試験」
秀才の学生が金目当てに老婆を殺した。
犯人と探偵明智との頭脳・心理戦が面白い。
「地獄の道化師」
石膏像と殺人事件。そして背後に忍び寄る道化師。薄ら寒くて、狂人的な犯行に気味が悪いが、最後はなんとも言えない気持ちになった。
二銭銅貨以外は明智小五郎が出てきて、少しずつ出世(笑)
二銭銅貨と何者の終わり方が好きな感じ。
二銭銅貨は読者に対してもいたずら心があり洒落てるな。
江戸川乱歩はじめて読みましたが、自分は推理ものでもすかっとするものが好きなんだなとわかった。
投稿元:
レビューを見る
「D坂の殺人事件」
「二銭銅貨」
「何者」
「心理試験」
「地獄の道化師」
明智小五郎。
地獄の道化師は、子供向けの(少年探偵団の方て)既読。
他の作品は読んでみたかったものばかりで、読めて良かった。
「何者」は、ドラマでやってたのを思い出して、(池松壮亮か満島ひかり)そちらもまた観たくなりました。
投稿元:
レビューを見る
江戸川乱歩の短編集です。
・D坂の殺人事件
・二銭銅貨
・何者
・心理試験
・地獄の道化師
私の中で江戸川乱歩と言えば「人間椅子」や「屋根裏の散歩者」のようなエロミステリーの印象です。
もちろん小林少年率いる「少年探偵団」の印象も強くあります。
「D坂の殺人事件」はD坂にある古本屋の美人おかみが殺害される事件で、普段から彼女の身体には傷がたくさんあったという噂が。
殺人事件が起きた古本屋の様子を、主人公の「私」と明智小五郎が向かいの喫茶店で見ていて、その事件を推理し、解決していくお話です。
明智小五郎といえば「変装」という先入観もあり、色々と考えを巡らせながら読み進めましたが、なるほど江戸川乱歩という結末に満足しました。
「何者」「地獄の道化師」も良かったですが、個人的には「心理試験」が好きです。
投稿元:
レビューを見る
江戸川乱歩の本は内容がイメージできてしまうと勝手に決めていて、なかなか読もうと思わなかった。夏休みの時期は、休む時間がとれてセミの声に後押しされ、子供に戻れる気がした。そんな訳で手に取ったこの作品は面白いと感じた。台詞の言葉遣いが硬い感じがあり、作品の古さがよくわかる。トリックを解く筋には深さがあり、引き込まれてた。夏のうちにもう一冊くらい・・
投稿元:
レビューを見る
カドフェスの対象本のため購入。D坂の殺人事件を含む5編からなる短編集。江戸川乱歩の作品は読んでみたかったが、古典ミステリーということで手を出しづらかった。しかし、なぜ早く読まなかったのかと思うような作品だった。明智小五郎による推理は面白い視点から行われており、想像していたより緻密で引き込まれた。個人的には何者と地獄の道化師が好きだった。
投稿元:
レビューを見る
この作品は、1925年(大正14年)に発表された江戸川乱歩の短編探偵小説である。また、江戸川乱歩が創作した代表的人物である名探偵明智小五郎が初登場した作品でもある。実際読んでみて、私が特に印象に残ったところは3つある。
一つ目は、言葉だけで事件の様子が詳しく書かれていることで自分の中でイメージしやすかったため印象に残りやすかった。例えば、「女は荒い中形模様の湯衣を着て、殆ど仰向きに倒れている。併し、着物が膝の上の方までまくれて股がむき出しになっている位で、別に抵抗した様子はない。首の所は、よくは分らぬが、どうやら、絞められた跡が紫色になっているらしい」、「絞殺ですね。手でやられたのです。これ御覧なさい。この紫色になっているのが指の跡です。それから、この出血しているのは爪が当った箇所ですよ。拇指の痕が頸の右側についているのを見ると、右手でやったものですね。そうですね。恐らく死後一時間以上はたっていないでしょう。併し、無論もう蘇生の見込はありません」といった部分だ。
二つ目は、この事件を一緒に解けるように読者に投げかけるところだ。本文でいうと、「この二人の学生の不思議な陳述は何を意味するか、鋭敏な読者は恐らくあることに気づかれたであろう。実は、私もそれに気附いたのだ。併し、裁判所や警察の人達は、この点について、余りに深く考えない様子だった」と述べている部分だ。この問いかけによって読者はどこに答えがあるのかをまた前のページに戻って探すきっかけになる。ただ読むだけでなく、このような問いかけがあることでまた同じ作品を二度楽しむことができると思った。
三つ目は、他の作品を引用している所だ。例で挙げると、明智小五郎が江戸川乱歩に「君、これを読んだことがありますか、ミュンスターベルヒの『心理学と犯罪』という本ですが、この『錯覚』という章の冒頭を十行許り読んで御覧なさい」と言った場面にあったものだ。その『錯覚』の一部として、“嘗つて一つの自動車犯罪事件があった。法廷に於て、真実を申立てる旨宣誓した証人の一人は、問題の道路は全然乾燥してほこり立っていたと主張し、今一人の証人は、雨降りの挙句で、道路はぬかるんでいたと誓言した。一人は、問題の自動車は徐行していたともいい、他の一人は、あの様に早く走っている自動車を見たことがないと述べた。又前者は、その村道には二三人しか居なかったといい、後者は、男や女や子供の通行人が沢山あったと陳述した。この両人の証人は、共に尊敬すべき紳士で、事実を曲弁したとて、何の利益がある筈もない人々だった”と述べられていた。私は推理小説で他の作品を引用しているものを読んだことがなかったためすごく新鮮に感じたため印象に残りやすかった。