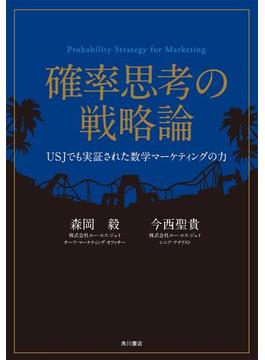数字に強くない人にも読んで欲しい!
2016/08/15 01:55
5人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なきぁ - この投稿者のレビュー一覧を見る
とてもおもしろいです。interestingです!
タイトルからは想像できない程、内容には熱が入っているように思います。
そして読みやすい!正確には、ほとんどの部分は読みやすい!数学的な補足部分は手を動かしながら読んだ方が楽しく読みごたえがある感じです。
数学的な部分は全部無視して読めます。ですので、数字が得意でない人に特にオススメです。数学的な部分を無視して読んで、数字で考える人の考え方が分かるからです。数字を求めてくる上司、数字で語ろうとする部下の気持ちの片鱗が分かるようになるかもしれません。
マーケターやリサーチャーの方はもともと数字には強いと思いますが、そんな数字に強い人たちにも読みごたえがあるように、説得力があるように配慮されてます。
組織に属する人は、数字に得意な人も不得意な人も是非読んでみてください。
この本をきっかけにして、日本で「数学マーケティング」ブームが起これば良いな!と読み終わって真っ先に思いました。
価格は上げた方が良いこともある、それがマーケティング
2017/08/03 09:03
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ルイージ - この投稿者のレビュー一覧を見る
良い本だと思います。
一般的に統計学の本は学者が書いた専門書である一方で、実務家が書いたマーケティングの本は(たとえ著者が数学を用いていても)あまり数学のことが書かれていないことが多い。この本は実務家としてマーケティングと数学を結びつけ、事例を含めて紹介しているのが良い。
また、マーケティングを知らない人はしばしば「消費者には価格は安ければ安い方が良い」と信じて疑わない人がいるが、そうとは限らないことを彼らに説得するのはなかなか難しいことである。本書は、マーケティングにおいては「場合によっては価格を引き上げることも合理的である」という点を書いてあるのが良い。
マーケターには必須知識
2021/12/18 13:32
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:戦略家 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者の経験を元に理論を俯瞰し実践でどう使うかが書かれてある。B2Cのみならず経営者、戦略担当の方はぜひ読んで欲しい
数学マーケティングという考え方を教えてくれます!
2018/11/17 15:01
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、数学マーケティングというあまり馴染みのない概念を丁寧に教えてくれる一冊です。数学マーケティングとは、ビジネスの成否は確率である程度決まっており、その確率はある程度人為的に操作できるということです。市場構造や消費者のニーズなどを深く知り、分析していれば、勝ち目がないと思われる状況においても、成功の確率を高めることが可能というのです。非常に興味深い内容ですので、ぜひ、多くのビジネスマンの方々に読んでいただきたいと思います。
大きな方向性が大事
2017/05/15 16:26
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ミスターマーケット - この投稿者のレビュー一覧を見る
確率というタイトルがついていますが、
数式のところは読み飛ばしても十分理解できる
マーケティングの本だと思います。
戦略を立てる上で、大きな方向性を間違えないよう
分析とフィードバックを行いたいと思います。
マーケティング理論にのっとり定量評価手法を開設した良書
2016/10/20 13:28
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toppie - この投稿者のレビュー一覧を見る
従来のマーケティング本では、セールスプロモーションのやり方やアンケートの作り方といったやり方のみを解説するものが多く、どの程度の効果を見込む必要があるのかがわかりにくいという欠点があった。
本書は、ポアソン分布を利用して市場ポテンシャルを測定し、現状とのギャップを算出したうえで、認知率や配荷率(量/室)を向上させる施策をとりつつ、プレファレンスを高めることで自社製品が選択される確率を上げるといったビジネス面での具体的な進め方を詳述してくれている。
当然、1人の年間購入回数と全体販売量によって、本書の内容が適用しやすい業界、適用しにくい業界もあるので、実業務で活用する際には、その点の意識は必要。
マーケティングの基礎を学習された方が、定量評価に向け学習をさらに進める場合にはおすすめです。
数式はむつかしい
2023/10/24 13:07
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽち - この投稿者のレビュー一覧を見る
数学の不得手な自分にとっては難しい部分が多く、理解できず読み飛ばしたところも多かったです。
でも、確率をあげることが大事ということは勉強になりました。
投稿元:
レビューを見る
・ 本質(人間の欲)によって構造が形作られて、さまざまな「現象」がうまれる
・ 「勝てる戦いを見つける」「市場構造を利用する方法を考える」
・ 市場構造とは、ある商品カテゴリーにおける、人々の意思と利害と行動が積上った全体としての業界の仕組みのこと
・ 異なるカテゴリーでも消費者は同じ法則に基づいて購買行動を行っている
① 消費者一人ひとりが独自に購買決定をしている
② 購入行動はランダムに発生している(多項分布)
③ それぞれのカテゴリーに対してほぼ一定のプレファレンスを持っている
④ プレファレンスの高いものはより高頻度で購買される(ガンマ分布)
・ 消費者の頭の中には、今までの購入経験から買ってよいと思ういくつかの候補となるブランドがある= Evoked Set
・ プレファレンスによって購入回数も支配されている
・ 消費者視点を最重視して、プレファレンスの向上に経営資源を集中せねばなりません
・ 戦略、つまり経営資源の配分先は、結局のところ、Preference(好意度)、Awareness(認知)、Distribution(配荷)の3つに集約されるのです。
・ Aided Awareness=知っているかどうか、Unaided Awareness=第一ブランド想起(Top of Mind Brand Awareness)消費者のEvoked Setを測るには最適
・ 配荷率(Distribution)とは、市場にいる何%の消費者がその商品を買おうと思えば物理的に変える状態にあるかという指標。配荷率が10ptのびればほぼ確実に売上も20%のばすことができる
・ 配荷をのばすための戦略としてフランチャイズやM&Aも手段のひとつとなる
・ 配荷率を上げて面積を広げるだけでなく、質をプレファレンスにあわせて改善することによっても、ビジネスを飛躍的にのばすことができます
・ 戦略の本質とは、市場全体の中で自社ブランドへの一人当たりの投票数をどう増やすかを考えること
・ 「K」はプレファレンスが大幅にますことによって、より全体に広がって(ばらつきが大きくなるように)変化していく。より魅力があるものはよりみんなが好きになっていく。同時に結果として、垂直方向にももっと好きになっていきます。
・ 消費者を区切ってターゲティングすることは、Mを増やすためであって、決して自社ブランドのMを狭めるためではないのです。市場全体におけるM魅力度を拡大するためのひとつの手段
・ マーケティングは、どれだけ成功確率を高められるかを模索し続ける「科学」を基本としなくてはならない。科学である以上、その理論には論理的再現性が求められる。
・ 戦略は「つくる」より「さがす」
・ 消費者の購買フローの漏れ分析
全世帯母数×認知率×配荷率×過去購入率×Evoked Set率×年間購入率
・ 差別化は市場全体から自社へのMを増やすためにやっている。こだわりだけの差別化は意味がない
・ 消費者と企業は、プレミアム・プライシングや値上げによる果実を共有している
・ マーケターの仕事は、ブランディングによってエクイティーを強化し、ブランド価値を大幅に高めて、その結果として中長期に投資可能な水準の価格を消費者からいただくことを可能にすること。一流マーケターの仕事は値上げしながらもMを増やすこと
・ 同じ目的を、ベストシナリオとはできるだけ違う道筋で達成する戦略(プランB)をもうひとつ考えてみる。それにより、ベストシナリオの脆弱性に気づくことができる。
・ 戦略とは、到達したい高い「目的」にたどり着くために組んでいく足場のようなもの
・ 人間はデフォルトに従う傾向が強い。デフォルトからはなれることを避ける、つまり面倒なことや負荷のかかることが嫌い。できるだけ意思決定などしたくなくて、独自の判断などしたくないということです。
・ 意思決定ができない際の真実は「会社のために正しい意思決定をすること」よりも「自分が直面するストレスから逃れること」を優先している自己保存の本能に基づいた行動。
・ 正しい目標からたった1標準偏差ずれただけで、正しい決断に対して成功確率は7割になってしまいます。
・ 意思決定そのものに熱は要りません、むしろ熱は邪魔になります。きわめて冷徹に、目的に対して純粋に角度が高いものを選ぶだけです。熱量がいるのはその後、決定した方向に人を説得したり、戦術を実施したりする次の段階です。
・ 人にいい仕事をさせるのが戦略家の仕事
① 自分自身の時間をどこに集中して使えば戦果が最大化するか
② 自分以外の人々をどこにどう集中させて使えば戦果が最大化するか
・ 総合評価の5段階に加重をかけて、統計的有意差を持って勝つシングル・プロダクト・ブラインドテスト。これをすることで、プレファレンスを構成している3つのドライバー、しなわち、ブランド・エクイティ、価格、製品パフォーマンスの重要度とプレファレンスの相関が図れる。
・ ただし、生活に密着していないでこだわりすぎると、イノベーターが出てきたときに食われる
・ 消費者の視点から商品の購入、自宅への運搬、使用、パッケージの廃棄、環境への影響などの一連のサイクルをトータルで見る必要性がある
・ われわれの行動はほとんど感覚に対する反射であり、もっともらしい理由は後付けである
・ この100年の消費者用の製品・サービスの生産活動の本質は、「生活を便利で快適、そして楽しく」だったのではないか
・ 子どもが言葉やアイデアを学ぶ際、同時にそれぞれの言葉やアイデアにある感情が付随し、全体としてある文化圏において特定の意味合いを持つようになる。これらがそれぞれの文化の無意識そうとなり、その文化圏で育った人々の行動に影響を与える。ある言葉、商品、サービスの持つ無意識化した意味をコードと呼びます。商品・サービスそのもの、及びそれらの広告は、このコードと整合性があると効果的である
・ 文化が先行し、産業は後からついてくる
・ 予測モデルにインプットすべき項目が多くあり、それらインプットの値に大きな振れ幅がある場合、モデル自身は非常に正確でもこのモデルを中心に予測することはできません
・ 未来に対する質問においては、消費者データの絶対値は怪しいですが、相対の順位は比較���正しいのです。
留意点① 値段による影響はどうか
留意点② 選択肢が同等に比較できるようになっているか
留意点③ 票割れを起こさないか
・ 価格弾力性は事前データで持っておく(価格が1%変わると、売上に何%影響するのか)
・ 組織システムとしてマーケティングをインストールしない限りは、ほとんど意味がない(マーケターは会社レベルの意思決定にずけずけと踏み込む存在)
・ 作ったものを売る、から、売れるものを作る会社へ
・ ポアソン分布は、まれに独立してランダムに起こることがどのように分布するのか分析するのに適しています。
・ 購入回数や浸透率は、この確率とわれわれが直接コントロールできない玉を袋から取り出す回数の結果なのです。すべての人の総和として選ばれる確率プレファレンス(消費者の相対的好意度)の正体です。
・ ガンマ分布は成功は成功を呼ぶ現象を反映できる
・ Order of Entry Model:新しいカテゴリーをうまく創造したらどのくらいのマーケットシェアを維持できるか、また送れて参入したとき、その順番によってどのくらいのマーケットシェアを獲得できるか
・ 新製品の売上=トライアルモデル+リピートモデルで算出
・ 判断に迷った時は、目的を明確化する
・ 日本人はもっと合理的に準備してから精神的に戦うべき
投稿元:
レビューを見る
確率思考を用いて客観的に戦略を建てる事が大事であると力説した本。
森岡さんの結論は、ビジネスに成功するためには、消費者のプレファレンス(好みの要素)を獲得する事。これに尽きると。
あと戦略策定、判断に感情は不要。熱く語るのは戦術の段階になったときだ、と言う森岡さんの力説が非常に心に響いた。
確率に関する数式は理解できなくても、言わんとされていることが分かりやすく書かれており、その点は非常に良かった。ただ実践に適用しようとしたらやはり数式理解は必要になりそう。これはかなりの勉強が必要になると思う。
投稿元:
レビューを見る
前半は森岡さん
1市場構造の本質は、購買行動の仕組み がどのカテゴリーでも同じ。そして、その購買行動はプリファレンスによって支配されている。その仕組みはブラントレベルでも言える。
2戦略の焦点は、認知・配荷・プリファレンス。プリファレンス(好意度)はM、K によって決まる。コントロールできるのはM。Mは自社ブランドへの一人当たりの投票総数。選択肢は、水平拡大か垂直拡大しかない。基本的に、水平拡大がよい。
3プリファレンスは、ブランドエクイティ・パフォーマンス・価格で決まる。これらの要素は最終的にブランドエクイティに収束する。パフォーマンスはリピートビジネスかトライアルビジネスかによる。価格は消費者が決める。プレミアムブライシングは消費者・企業にとって善。
4感情は目的からズレさせる。意志決定に感情は邪魔。人間は意志決定したがらない。
後半は今西さん。話がやや難しい。主張はデータの扱い方についてと需要予測の様々な方法。需要予測はいろんな切り口でやることが、大切。
ある消費者の単位期間あたりの購買回数はカテゴリー、ブランドの平均購入回数をポアソン分布させたもの。
ある期間における消費者全体の購買回数の分布は、負の二項分布。(成功は成功を呼ぶ補正)
投稿元:
レビューを見る
USJのV字回復やハリーポッターのアトラクションを仕掛けた森岡さんの著書。事業戦略の成否は全て確率で求められるというものだが、実際に成功してるんだから説得力が違う。先日の「仮説思考」よりハラ落ち感が高い。経営資源の最適配分は、顧客の好み(プリファレンス)、認知、配架の3点で全て決まる。特に顧客の好みが重要など、理論が豊富に解説されているが、最も重要なのは「数字に熱を込める」ということだろう。
投稿元:
レビューを見る
最後の数学ツールの説明のところは飛ばし読みしてしまったが、実に興味深い本であった。数学を勉強し直ししようかと思った。数学マーケティングか、今からどう勉強したらいいのだろうか。
P127で、私はサイコパスではないのです。自分の心の中で暴れる激烈な感情といつも戦っています。だからとっても痛い!という記述にほろっとした。
投稿元:
レビューを見る
マーケティング、経営戦略の本質とは何か?を筆者の目から捉え、指標を作り、そこからデータ分析を行っている。
マーケティングの本質をとらえているところが「データ分析」という道具に振り回されていなく、納得性のある説明となっている。
投稿元:
レビューを見る
本当に勉強になった。Mが大事。Mしかコントロールできない。そしてプレファレンス。一生持ち続けて何度も勉強したい。マーケティング勉強したい人は読むべき!
きっとお二人ならこんなレビューでもチェックしてくれてそう(笑)。こんな二人の下で仕事ができたらなんてエキサイティングで幸せなんだろうと思う。
もし森岡さんが起業するとしたらどんなアイディアがあるのか、聞いてみたい。
投稿元:
レビューを見る
「オススメ」
マーケ部署2、3年目で読むと一番楽しそう。
いつも思うが採用だと金を払ってもらうスキームとは若干違うから話を自分に置き換えるのが難しいなーと。
「学び」
・スタンスと、そのためなら手段を選ばない辺りがすげー!!と思った。
数式だったり実際の事例をこれだけだしても大丈夫なのは、ある意味この人が一番の強みはそこではなくそれを考え出せる最初の発想力、これをやりきる実現力にあるということを認識されてるからなんだろうなーと思った。そこは本当にすごい。
・後ろの方の組織論の話も好きだった。マーケの一番の仕事と言ってもいい部分は、マーケティング(もっというとコミュニケーション)の意識を組織に持たせる事だという考えに同意。