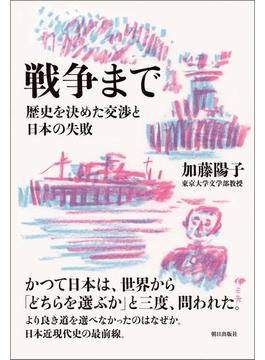2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本の近代史は、高校の日本史の時間でも時間切れになって、教科書を読んでおいてください、ということになることが多いのですが、本当は知りたい歴史だったりするんですよね。高校生でも読める日本の近代史として、本書はおすすめです。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Freiheit - この投稿者のレビュー一覧を見る
コンパクトに要点を伝えてくるので、退屈にならず、視点を展開してくれる。交渉事に突き当たったときに、よりよき選択ができるために歴史を学ぶ意義を感じた。
うれしくなります
2025/02/28 10:30
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
一次資料を中心に他の最新の知見を踏まえながら丁寧に解説されています。各単元がいずれも新書レベルと思われ、有害無益な陰謀論を排除する意味でもよいと思います。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:坊主 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者の講演を纏めた作品、講義を纏めた作品を好んで読んでいます。
毎回、知的刺激を受けていますが、今回も期待通りの読後感に満たされています。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ハム - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本がどうして、戦争の道に突き進んでしまったのかというのが、わかります。やはり読んでいて、辛かったです。
投稿元:
レビューを見る
日本が歴史上戦争で負けたのは2回だけ。と、昭和天皇が白村江で負けた天武天皇に習おうとしたのは、天皇制の深遠さを感じさせるエピソード。全体的には「交渉とは何か?」「認識とは何か?」について教訓的な所があり、考えさせられた。ただし、史料を都合よく引用し、主観的に解釈していると思える部分もある。が、歴史学はそういう事から逃れる事はできないので仕方ない。また、肝心の南部仏印進駐と全面禁輸のところが、想像とか仮説に留まっており、解明されていない点が残念。また、日独伊+中提携の汪兆銘政権承認の方針転換所も原因がよくわからないので説明が欲しかった。あと、犬養は満州国を承認しないから殺されたとあるが、満州国は犬養内閣の国策(閣議決定もしている)なわけで、承認しないという事はありえないと思うのだが。
投稿元:
レビューを見る
第二次世界大戦、太平洋戦争を冷静に振り返る本。右左でいえば左ということになるだろう。最近は右寄りの歴史修正主義の本が多い気がするので、そういった本を読む前、読んだ後に加藤陽子さんの本読むことは、極端な結論になるのを防ぐ意味で役立つと思う。一次資料に基づいた考えが多いので、その点で信頼性が高い。
投稿元:
レビューを見る
以下の点が興味深い。
・中国は、リットン報告書を日本寄りだと評価し、日本は、中国寄りだと判断した。
・三国同盟は、植民地宗主国を抑えたドイツによる東南アジア植民地再編の可能性を、参戦していない日本が封じるための掛け声
・1940年8月4日の『蒋介石日記』には、「敵(日本)が南下の野心に狂っているときに乗じて、我が国に有利な条件で講和を図ることは悪くない」と書かれている。
・ドイツ外相リッペントロップは、駐独中国大使陳介を呼んで、三国同盟に加わったらどうですか、日本との講和に応 じなさいと説得していた。
・「絶望から開戦する国はないという、あの日本に対する判断の間違いです。そもそも日本は、絶望したから開戦したのではありません。あと二年間、石油という資源を確保できている時期に開戦しようという発想は、ありえなくはない。」
・「アメリカは日本に第一撃を打たせた。真珠湾攻撃のことを、ローズヴェルト大統領やハル国務長官とか、何人かは知っていた。けれども現地の人には言わず、日本に騙し討ちさせるようにした、という見方があります。でも、これが全く嘘であることは、アメリカの国防総省が研究し続けていることからわかる。」
・憲法制定史に詳しい古関彰一先生が明らかにしたところでは、戦争放棄という主旨は、確かにGHQ草案に起源を持っていたけれども、平和主義の発想は、日本側の発案によって憲法の条項に入れられた、というのです。
投稿元:
レビューを見る
<目次>
第1章 国家が歴史を書くとき、歴史が生まれるとき
第2章 「選択」するとき、そこでなにが起きているのか
第3章 軍事同盟とはなにか
第4章 日本人が戦争に賭けたのはなぜか
終章 講義の終わりに
<内容>
東大加藤陽子先生の「アジア・太平洋戦争」に入るまでの過程を、中高生に講義したもの(学校でではなく、書店の主催の講義(講演ではない))。とても刺激的だが、同じ教える立場で言うと、この講義のために先生がどれだけ史料を吟味し、どのような授業を組み立てようとしたかの苦労が感が見える(「おわりに」を読むと特に…)。
さて、内容は戦後70年での天皇の「お言葉」(沖縄と「戦没者記念式典」のとき)、安倍首相の談話の分析から始まり、満州事変の「リットン報告書」、三国軍事同盟、太平洋戦争直前の日米交渉、この3つの分析、解釈、可能性が語られます。受講者の中高生もかなりレベルが高く、いい質問をして、講義は展開していきます。こういうある意味、微に入り細にいる話はとても大事なのだと感じました。高校の授業ではなかなかできないけど…。様々な立場や歴史的な背景を見据えて、歴史を分析していくことが、今後の歴史を過ちへと進めない、大事な行程であり,歴史学の使命でしょう。ことにきな臭い昨今の日本において、「いつか来た道」を求める輩が闊歩している状況では…。
投稿元:
レビューを見る
東京大学の加藤陽子先生が、池袋ジュンク堂書店にて計5回にわたり行った中高生向け日本近現代史講義を一書にまとめたものである。
「はじめに」によると、中高生向けの講義ではあるが中高年も読んでも構わないとのことであったので、意を強くして今回手に取ってみた。(笑)
本書の「戦争まで」とは、「太平洋戦争が始めるまで」のことで、そのターニングポイントとなった3つの交渉事案をそれぞれの史料を丹念に読み込みその本来の意図を再現した上で、交渉の行方を辿り世界史的な観点に位置付けて、どうしてそのような選択がなされたのか、他にどのような選択肢があったのか等を問う内容となっている。
その3つの交渉事案とは、①満州事変に対するリットン報告書と国際連盟脱退②日独伊三国軍事同盟の締結③日米開戦前の日米交渉、である。
その前段として第1章では「国家が歴史を書くとき、歴史が生まれるとき」と題した講義を行って、「歴史」とはどのようなものか、国家や民衆は「歴史」に対しどのように関わってきたか、世界史の分岐点で人はどのような判断をなしてきたのか、という今後の講義への前振りがなされており、最初からなかなか面白くなっている。
第2章では本講義の最初のターニングポイントである「満州事変に対するリットン報告書と国際連盟脱退」について取り上げられる。
自分も高校時代等の知識から日本に不利な報告書が提出されたものかと思っていたら、実はリットンは日本の侵略を胸の内で確信しながらも報告書では外交上のバランスを優先させ、日本の行為に対し決定的な断定を避け、国際協調を前提とした自由貿易による利益確保を追求する「世界の道」を切に訴えていたということである。
また面白かったのは国際連盟内での交渉で、後に強硬派となる松岡洋右が国連を脱退することにならないように粘り強く交渉していたということで、このあたりの後の変化については本書にも記述がないので気になったところであった。
日本がどのような「道」を選択するのかは悩ましい問題であったが、一般的に選択肢を作成する際の実験で「偽の確実性効果」についての説明があり、現在もニュースとかで政治家の発言をみていると必ず「しっかりと」とか「確実に」という言葉を盛り込むのを聞いて胡散臭く感じていたので、今も昔もこういう言葉の操作を行うところは同じだなあと思ってしまった。いや、むしろ今の方が無責任で露骨かもしれない。(笑)
また、国が進めていたナショナリズムの高揚が、以降歯止めが効かなくなり、国のトップがそれを怖れていく緒になっていることにも興味深い。
第3章では「日独伊三国軍事同盟の締結」について取り上げられる。
これも自分は高校時代等の知識から、日本はアメリカに対抗し、「バスに乗り遅れないため」の目的でドイツ・イタリア側に与したのかと思っていたら、その本心は、ドイツがイギリスに勝利することを前提に東南アジア等のフランス、オランダ、イギリス等の植民地(大東亜に含む)をドイツにとられないようにし我がものとするためであった、とのことである。
面白いと思ったのは、条約文書で日本語と英語のニ���アンスが微妙に違うこと、「大東亜」の範囲を日本も含め誰もが自分のいいように解釈していたこと、ドイツ・イタリアへの第3国(=アメリカ)の敵対攻撃で自動的に日本もドイツ・イタリア側に立って参戦すると解釈していたドイツであったが、日本は自由に選択できると考えていて齟齬があったこと、などであった。「大東亜」がどこの範囲を指すのかを誰も確信を持ていなかったことなどは、いまから考えるとジョークとしか言いようがない・・・。
第4章では「日米開戦前の日米交渉」について取り上げられる。
最終段階ではハル・ノート提示に行き着く交渉であるが、交渉途中で日本の南部仏印進駐によりアメリカは戦略物資の全面的禁輸に踏み切ることになってしまう。日本はというとその前の北部仏印進駐の際のアメリカの手心を加えた一部禁輸措置などの経験から楽観視していて、南部仏印進駐でアメリカがそういう挙に出ることを見誤ってしまっていた。一方のアメリカでも南部仏印進駐後に対日穏健路線であったローズベルト大統領とハル国務長官が休暇や葬儀参列等により政治決定から除外されていて、強硬派路線の委員会が対日全面禁輸を決めてしまったという話には驚いてしまった。重大局面でそんな偶然のボタンの掛け違えってあるものなんだな・・・。
また伝説?となっている、在米大使館員の無能力のせいで日本の真珠湾攻撃前に国交断絶文書(=宣戦布告)をアメリカ側へ提出するのが遅れたという話(いわゆる騙し打ち論)も日本海軍や外務省がわざと暗号文書を発送するのを遅くしたということで、やっぱりそういうことだったんだなあ。
最後の第5章ではこれまでの講義の総括的な話となっている。
現代に起こっている事象に対する、歴史から学ぶということの視点をわれわれに教えてくれているとともに、中高生がここまで学んだ成果というものを実感させてくれる。
これまで加藤教授はたびたび受講の中高生に当時の視点でどういう選択があったのか、当時はどう考えていたのかなど、時には現代の視点で、また時には関東軍参謀になったつもりで、あるいは参謀本部の計画立案者になったつもりで回答を求めているが、こうした視点は当時の立場からみる政治選択の理由を明らかにするとともに、複雑に利害がぶつかる政治選択の行方をも考えさせてくれる。
自分もこれまで近現代史はともすれば責任論に収斂されがちであったのを歯がゆく思っていて、現実の政治の場でどのような選択がなされた結果だったのかを総括する必要があると考えていたので、今回はとてもよい勉強になった。
あと加藤教授は中高生のどのような回答に対してでも、必ず「はい、そうですね。」のような返しをしていて、議論を肯定的に深化させていたのが興味深かった。
学校での近現代史教育が疎かになっている昨今、加藤教授には引き続きこうした取り組みを継続してもらいたい。
最後は「おわりに」から。
「学問は歴史に極まれり」(荻生徂徠)
全く同意見だ。
投稿元:
レビューを見る
面白いし、分かりやすい。聴講している高校生達は本当に賢いと思うし、高校生とは思えないほど。私も歴史を勉強して、思考に深みを持たせたい。
投稿元:
レビューを見る
歴史を学ぶ醍醐味は、ある事態へと進んでゆく連鎖の要因を知ることであり、別の可能性を考えることで将来の糧とすることです。加藤先生の姿勢は常にそこにありますね。今回は、先の大戦の前に、交渉の機会が3度あり、そこでより良き道を選べなかった実情を明らかにします。リットン報告の対応は明らかに大局観の欠如だと思います。ただ、その後の2度の交渉機会というのは、開戦時期を後ろ倒しにすることはできても、既に米国にロックオンされていたのではないでしょうか?
投稿元:
レビューを見る
16世紀半ばのポルトガル製の世界地図には、日本列島全体が沖縄を意味するポルトガル後で表記されていた。そして、琉球諸島の島の一つに日本という名前が当てられていた。
世界恐慌で大打撃を受けたのはイギリスで、日本はそれほど深刻ではなかった。
日本は倭国として隋と戦い、唐の時に日本を名乗って、前とは別の国です、心機一転国交を、というアクロバット外交をしts。
日独伊三国同盟は、アメリかが三国を攻撃した時に発動するもので、三国からアメリカを攻撃した時ははつどうされなかったが、ヒトラーはアメリかに宣戦布告した。
チャップリンは、独裁者のシーンを、ヒトラーがパリ入城した翌日にぱりで撮影した。
日独伊三国同盟は、太平洋諸島の権益をドイツに奪わせない趣旨も持っていた。
日米交渉での日本側にはカトリック関係者がいた。これはソ連に対抗する反共として。
南部仏印に侵略してアメリカが経済制裁をしたが、これはルーズベルトやハル国務長官が不在時に、対日強硬派が行ってしまった。
投稿元:
レビューを見る
すごいです。面白いです。中身が濃いです。
前作「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」が面白かったので、本書を手に取りました。本書は、戦前日本の3つの重要な選択に題材を絞ってはいますが、実に深く広く分かりやすく、解説いただいています。国内の賛成反対意見だけでなく、交渉相手の思惑まで理解できます。全体の歴史の流れが把握でき、歴史から現在を考えるうえでの参考になります。
投稿元:
レビューを見る
ゆっくりと時間をかけて読んだ。学校では戦争の悲惨さばかり学んだ気がするけど本当に大切なのは戦争に至る経緯。それを丁寧に解説してくれている一冊。