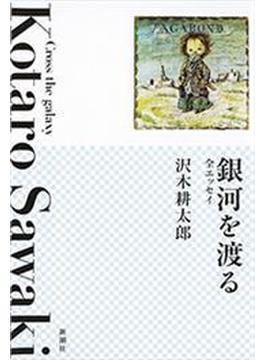0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:おどおどさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
小説を読んだことはあるが、エッセイは読んだことがなかったので、是非読んでみたいし、沢木さんがどういう人なのか知って小説を読むと違う感じ方もありそうで面白い。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽん - この投稿者のレビュー一覧を見る
正月休みのお陰で、日頃より読み進みました。今までのどの作品よりも丁寧に読んだので、心に残る一冊になりました。次は、『作家との遭遇』です。
やっぱり沢木さんだなあ
2019/01/30 16:54
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
この25年の間に書かれた全エッセイが収められているということなので、当然、「人の砂漠」に収められているものや「深夜特急」「テロルの決算」などは省かれている。この人のすごいところは淡々と普通のことを言っているようだけど、実はすごいことを言っているというところで、例えば、昔、久米宏氏の「ニュースステーション」でほとんどの人が大成功だと持ち上げていた日韓ワールドカップについて「韓国で取材をしていたら、日本に対してのブーイングが結構あった」とさらっと言っていたということがあった。これから僕はすごい発言をしますよという前振りないし、普通の表情で激しことも言う。これからも読んでいきたい作家の一人だ
やっぱり沢木耕太郎はカッコいい
2018/12/19 15:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本のどのエッセイから読み始めたとしても、実際私は「歩く」「見る」「書く」「暮らす」「別れる」という五部編成となっている最後の「別れる」の章「深い海の底から」から読み始めた、すぐさま沢木耕太郎の世界にはいっていることに気づく。
そして、こう思うだろう。
やっぱり沢木耕太郎ってカッコいいな。
このエッセイ集は「全エッセイ」という紛らわしいサブタイトルがついているが、決して沢木のすべてのエッセイをまとめたものではない。
沢木にはすでに『路上の視野』と『象が空を』という2冊のエッセイ集がある。今回のエッセイ集は2冊めとして刊行された『象が空を』のあと発表されたエッセイをまとめたもので、その期間が25年にもなるという。
25年の間に沢木は『檀』や『無名』といったノンフィクションだけでなく、小説家としていくつかの作品を書き上げている。
あるいはシドニーやアテネのオリンピック取材など、初期の頃のスポーツ関連のエッセイも数多く書いている。
それでも沢木は颯爽と私たちの前に現れた『敗れざる者たち』の時のまま変わっていないようにも思える。
それは何故か、このエッセイを読みながら随分考えたが、それは沢木の文体にあるのかもしれない。
彼はいつも兄貴然としながら杯をあけ、時には弟風に落ち込んでみせもする。友人のような顔をしながら、先輩のように少し背伸びもしてくれる。
いつも顔を突き合わせる、そんな文体を沢木は若いうちから手に入れ、それは今に至るまで変わらないということだろう。
いつもながら、何とも心地よい、沢木耕太郎の世界だった。
きっかけはゴロウデラックス
2020/05/02 12:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kittihei - この投稿者のレビュー一覧を見る
沢木耕太郎といえば『深夜特急』のイメージが強かった。白状すれば、一冊も読んでいなかった。この本を手に取ったきっかけは、『ゴロウデラックス』という番組だった。
番組で取り上げられた、『キャラヴァンは進む』を読みたくなったのだ。だが読み進めるうち、そんなことはどうでもよくなった。「私」の一人称で書いているのに、いやらしさがない。
最後の第五部<別れる>に収められたエッセイはどれも心にしみ、自然と涙が出てくるものもあった。エッセイに書かれた人に対するリスペクトが感じられ、とても暖かい気持ちになった。
投稿元:
レビューを見る
著者と接するとたいがいの人はみんな懇意になっていく。
人たらし。教授には何かをなしうる人物とみなされ、
バーで隣に座ったオッサンとはその後もいろいろな世界に(花見、酉の市、ふぐ)に誘ってもらうことのなったり、(そのオッサンは小学館の偉い人)
と、きっと若い頃から魅力的だったのだろうな。
高倉健との繋がりも。かなわなかったけど、著者原作の高倉健主演の映画、観てみたかったな。
田辺聖子さんの家に泊まりにいくほど仲良しなのも意外だった。
かもかのおっちゃんも口癖、”それが何ぼのものじゃ”のエピソードもしみじみしてていい。
著者の他のエッセイも読んでみたくなった。
投稿元:
レビューを見る
沢木耕太郎氏のエッセイ集です。これで三冊目
だそうですが、深夜特急はあるもののエッセイ
集は初めて読みました。
多くの媒体で書かれた作品を集めたらしいが、
初出が記されていないのが少し残念です。でも
新聞や堅い週刊誌が多いのではないかと思います。
小説のようなエッセイを書くとよく言われます。
確かに情景が目に浮かぶ。決して私自身には
感じることができない情感を描写してくれます。
沢木氏自身の高校時代の体験が現在の自分へと
繋がっているという描写も嘘っぽくなく、
文学小説のような味わいがあります。
読後の余韻が素晴らしい一冊です。
投稿元:
レビューを見る
どうしてこの人の文章はこんなに素直に入ってくるのだろう?
特徴的なところがある訳では無い。朴訥と言うか、ごく普通の言葉を選んで淡々と素直に綴られた文章です。
物を買ったり持つことに頓着しない。雨の日に傘を持つのが嫌い。そんな似ているところもあれば、私とは全く違う所も多くあります。でも、この人が語ると心の中で反発は起こらず、そんな生き方、考え方もあるんだと素直に受け入れてしまうのです。
何かを強く批判するという事が無いせいかもしれません。ノンフィクションライターゆえのきらびやかな人々との付き合い、旅人としての現地の人々との触れ合い、そしてごく普通の社会人としての交友関係、いずれにおいても接した人達に感謝を忘れない(少なくともネガティブなことは一切書かない)そんな沢木さんの姿勢のせいかもしれません。
この本の中で沢木さんは”ただひとつ、本を出すに際して変わらずに守りつづけてきたことがあるとすれば、どんなものであれ、決して「手を抜かない」ということだった。”と言ってます。物書きとして当然のことかもしれませんが、それが本当に出来ているところが凄いのでしょうね。
投稿元:
レビューを見る
生まれ育った町の商店街にあった小さな本屋で見つけた本を貪るように読んだ。
それが「敗れざる者たち」。
こんな本を読みたかったんだ。
「深夜特急」「檀」「流星ひとつ」といったノンフィクションはもちろん、エッセイもほぼ全部読んだ。
そんなこんなで、以来40数年。
このシリーズを大切に読みたいと思う。
投稿元:
レビューを見る
沢木耕太郎、てんこ盛り⁈ 人、旅、食、映画、その他多岐に渡るエッセイの数々、どの文章も切り口があり引き込まれます。深夜特急以来の彼のファンだが、関連文章もあり興味深く読めました。
投稿元:
レビューを見る
その文章を深く味わいたいという作家が何人かいて、私にとってはそのうちの一人が沢木耕太郎さんです。沢木さんの文章は、感性で書かれたものではなく、計算され構築されていったものという印象があります。だからといって無機的では決してなく、どこかウエットでメロウな文章。その絶妙なバランスに惹かれるのです。新作ではないので、本書に収載されたエッセイの大半は既読でしたが、こうしてまとめて読むとまた深く楽しめます。
投稿元:
レビューを見る
ゴロ―デラックス最終回で紹介
『分の悪い戦いをしている人に味方したくなる』
『なんでも人に聞く(旅先で)』
投稿元:
レビューを見る
家にいて時間があるときに、一遍ずつ時間をかけて読了した。知ってる話も多かったが、新発見もとても多く、非常に興味深い内容だった。今までどんな作品を見ても、娘さんのことは書かれても奥さんのことは頑なと言ってもいいぐらいに出てこなかったが、今回初めて書かれていた。エッセイなので交遊記も多く、改めてネットワークの広さを知った。エッセイ集としては3作目だが、全2作、路上の視野、像が空を、は読めていないので、ぜひ読みたいと思った。最新のエッセイ集ということで、新しい情報もあり、今この時期に読めて本当によかったと思う。
投稿元:
レビューを見る
Wikiで沢木耕太郎を調べてみると、デビュー作は「若き実力者たち」で、1973年の発行ということなので、デビュー作から、もうすぐ50年ということになる。その間、ノンフィクション、エッセイ、小説と幅広く、息長く活躍している作家だ。
私自身は、ノンフィクションは、ほとんど読んでいると思うし、エッセイも、この第3エッセイ集まで全て読んでいる。一番好きな作品は、なんと言っても「深夜特急」であるが、いずれにせよ、一番好きな作家の一人だ。
ノンフィクションとエッセイのどちらが好きかと言われると、ノンフィクションの方だ。エッセイは、長いものは、それなりに楽しめるが、短いエッセイは、あまり上手くはないように感じる。
本エッセイ集も、私としては、面白いものと、やや退屈なものが混じっている印象。スポーツに関するもの、特定の人物にかかるものは読ませるが、その他の、特に短いものは、そんなには楽しめなかった。
投稿元:
レビューを見る
学生時代に読んだ『深夜特急』は確実に自分の人生観を変えた。できるだけ沢山の国や場所を訪れて、多くの風景を自分の目で見てみたい。深夜特急のような長期旅行は無理なのだが、それでもちょこちょこ外国へ旅行に行くようになったのは間違いなく深夜特急の影響だ。
その後、沢木耕太郎さんのノンフィクションは何篇も読んできた。でもエッセイはほとんど読んだことがなく、本書のように一冊にまとめられているのはありがたい。
本書に収められている「カジノ・デイズ」というエッセイを読んでいて思わず「えっ」と声が出た。バカラを始めたきっかけや自身のカジノ通いについて書かれたこのエッセイの中で、沢木さんが『新麻雀放浪記』のあとがきを書いているのを知って驚いたからだ。
理由は二つある。沢木耕太郎さんにギャンブルのイメージがまったく無かったというのが一つ目の理由。もう一つの理由は『新麻雀放浪記』をそれこそ何回も繰り返し読んでいたのに、解説を書いたのが沢木耕太郎さんだと知らなかったということ。信じられないことに解説の書き手の名前を見落としていて、解説自体読んでなかったのだ。直後に本棚から桃色の背表紙の文春文庫を取り出して読んでみたことは言うまでもない。
十代の頃から愛読してきた二人の作家に意外な接点があることを知ったのは収穫だった。しばらくまた何冊か読み返してみようと思う。