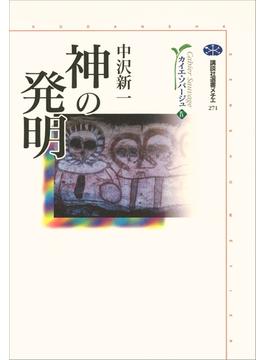神のマテリアリズムを探求する学術エンターテインメント
2003/06/28 20:10
4人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オリオン - この投稿者のレビュー一覧を見る
講義録「カイエ・ソバージュ」シリーズ──旧石器人類の思考から一神教の成り立ちまで、「超越的なもの」について、およそ人類の考え得たことの全領域を踏破することをめざした野放図な思考の散策──全五冊のハイライトとも言える本書で、中沢新一は「神のマテリアリズム(唯物論)」を試みた。
それは「神(ゴッド)の観念」の出現を、マルクス・エンゲルスの顰みに倣って「自然史の過程として」探求しようとするもので、中沢氏が議論の出発点に据えた「マテリアル」とは脳、それも認知考古学が想定する現生人類の脳──スイス・アーミー・ナイフのようなネアンデルタール人の「特化型」の脳ではなく、認知的流動性をもった「一般型」へと進化した現生人類の脳(スティーヴン・ミズン『心の先史時代』)──である。
ホモサピエンス・サピエンスの脳=心の内部の出来事としての超越、つまり「内在的超越」(スピノザ)という現生人類の心の基本構造をもとに、「超越性」の発生、つまり人間の心が神を発明する物質的=精神的プロセスを明らかにすること。具体的には、日本古語の「モノ」が含意する「タマ」や「カミ」、つまり精神的なものと物質的なものとの界面で立ち上がる「半‐物質」的な「スピリット」を「心の胎児・心の原素材」として、そのトポロジー変形を通じて「多神教宇宙」が、ついで「唯一神」が出現するプロセスを解明すること。
中沢氏一流のほとんど名人芸の域に達した軽やかでのびやかな語りが堪能できる本書は、唯一神の誕生という「スリリングな話題」に関する部分が「抑圧」の一語で片づけられていて、やや説明不足の感を拭えない点を除き、知的刺激と興奮に満ちた、新しい学──観念論と唯物論、心の科学と物質の科学がひとつにつながるレベルを示す「二十一世紀の思考」、あるいは一神教の成立、科学革命に続く第三次の「形而上学革命」をもたらすもの──の可能性を予感させる学術エンターテインメントである。
とりわけ興味深いのは、キリスト教の三位一体の教義のうちに「情報」(父と子の同質性)と「生命力」(聖霊の増殖する力)という二つの機構を抽出し、それらを「生命」と「経済」と「神」の三位一体的関係をめぐる議論へと敷衍した上で、生命力=増殖力としてのスピリット(精霊・聖霊)の未来を透視する終章だ(それは、「カイエ・ソバージュ」シリーズ最終巻のテーマを予言するものなのだろうか)。
《しかし、そんな人類に変わっていないものが、ひとつだけあることを忘れてはいけません。それは私たちの脳であり、心です。数万年の時間を耐えて、原初のみずみずしさをいまだに保ち続けている、現生人類の脳だけは、いまだに潜在的な可能性を失ってはいません。そこにはまだ、はじめて現生人類にスピリット世界が出現したときそっくりそのままの環境が、保たれ続けています。根本的に新しいものが出現する可能性をもった場所と言えば、そこにしかありません。私たちはそこに、来るべき未来のスピリットを出現させるしか、ほかには道などないでしょう。》
──ところで、本書の全編にわたって繰り広げられる人文知と科学知との比喩的重ね合わせ、たとえば、スピリット世界から多神教宇宙への精神力学的過程を物理学の「対称性の自発的破れ」の概念でもって説明したり、多神教的な神々の宇宙の基本構造「高神‐来訪神」を、ラカンの心のトポロジー論を援用して「トーラス型‐メビウス縫合型」と表現しているところなどは、それがほとんど本書の魅力と可能性の中心であるだけに、アラン・ソーカル(『「知」の欺瞞』)流の批判への無防備さが気になる。
しかし、よくよく考えてみると、本書の全編、というより「カイエ・ソバージュ」シリーズ全体が、まさにソーカル流の一見妥当な外観をもった批判に対する、よりスケールの大きな回答になっている。
3人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yuyuoyaji - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルから推測されるように、本書では神がどのような思考のプロセスをへて生まれてきたか、を考察する。ここでいう神とは、「超越者として世界を創造し、秩序を与えている」抽象的な神(ゴッド)と「森羅万象に住む」具体的なスピリットとしてのカミが前提とされる。本シリーズの他の巻でもそうであるように、キイワードは「流動的知性」と「対称性」である。
現世人類はニューロンの革命的進化によって思考自体について思考することができるようになった。その流動的知性が生み出した神には、常在神としての「高神型」—グレートスピリットや南島の御嶽の神など—と遠方から来訪する「来訪神型」がある。高神が生の領域のみを支配するのにたいして、来訪神—スピリット—は死と生、裏と表の領域を往き来できる対称性をもつ。高神は来訪神の対称性の原理と多神教宇宙のなかに共存しあっている。流動的知性が開く超越の領域と自分たちの外にひろがる自然のあいだをつなぐ通路をスピリットたちが飛び交っている。スピリットたちが活動する世界に「対称性の自発的破れ」がおこると、その切れ目を縫い合わせようとして神々のイメージが生まれる。さらに自分自身が全体性そのものになろうとする思考によって、多神教の宇宙が構想される。さらに、この世を秩序ある、知的にも理解可能なものにするためにことば的表現で満たそうとして「高神+来訪神=ゴッド」の世界がつくられた。しかし、現実はことばの象徴的秩序によってつくられるという考えそのものが「空虚な穴」を必然的に生み出してしまう。そこで一神教の神だけがこの空虚を満たすことができると考え、「完全な知性」としての神が発明された。キリスト教の唯一神のもたらした「あらゆるものを商品化し、管理する今日のグローバル文明」に代わって根本的にあたらしいものを生み出す流動的知性がもとめられている。「地球上のあらゆるものにたいして慎ましさの感覚をもつ」ことが必要である。それを実現するのは、「現生人類の脳」が誕生したときとおなじように、高次の対称性をもつスピリット世界を人類の心によみがえらせることによってのみ可能である。言い換えれば、スピリットは観念論と唯物論を統一し、野生の思考をとりもどす精神世界の救い主である。
ユダヤ教のヤハウェやアポリジニの神、日本の神社信仰などを示し、華麗な比喩を交えながら神の発生学が心の構造の表現としてときあかされている。かつて『雪片曲線論』で密教による心の解放を追求した著者が「全体性の思考」の必要性をアピールするいっぽう、著者自らが宗教全体を精神考古学として総括している。仏教との関連はもっとも深いと考えられるが、それは『カイエ・ソバージュ第5巻』で展開されると思われ本書ではほとんど触れられていない。また王と国家の発生と神の発生が具体的にどのように対応してきたのか、近い将来明らかにされることを望みたい。文化人類学や民俗学・民族学に関心をもつ者、あるいは宗教にひきつけられながらも組織の束縛や権力のもたらす腐敗、おぞましい暴力や絶対主義の独善性にためらい、現実の宗教活動にはふみだせない者にとって刺激的な書である。
投稿元:
レビューを見る
一神教の世界は真ん中の空いた浮き輪のようなもの(トーラス)をびっしりと「ことば」が覆いつくしているイメージで描かれている。「この世」の現実はことばの象徴秩序によってつくられているという考え方だ。しかし、真ん中にぽっかり空いた穴は埋めることはできない。それを満たすことができるのが唯一、神(ゴッド)であると考えられている。
かくして知性偏重、「知」と「権力」が一体であるような文明が生まれた。
しかし、当然のことながら、知性のみで全てのものごとを掌握することは難しい。例えば「生命」だって、形質についての情報を伝えるゲノムのみでは、生命体が「生きる」ことはできない。それが動き出すような着火剤の働きをする「生命力」のような存在が必要である。
キリスト教はそこで上手に「三位一体」のシステムの中に「スピリット」という項目を組み込んで、うまく「生命の原理」を取り入れることに成功した。そして「神は死んだ」とまで言われる時代になってもそのスピリットの持つ増殖・均質・多様といった性質は、貨幣や商品、コンピュータに受け継がれている。しかしそのスピリットは半ば亡霊と化している。あらゆる宗教のあとに出現するもの〜Religion After Religion〜が期待されている。それを生み出すのは原初から変わらない脳であり心でしかない、と筆者は強く訴える。
2006.08.15-31.
投稿元:
レビューを見る
またしてもなんとな〜く、ウスラボンヤリ思っていたことを理路整然と整理してもらって、スッキリ!!!しました。
もともとヒトとは、”超越したもの”の存在を自然と感じている生き物であって、それがアニミズム信仰になったり、発展して宗教になったり、しているらしい。
だいたいどの地域にも、高神と来訪神、という2つの相対するカミがいて、高神は太陽や山のように、常にそこにあって日々の生活を守ってくれるカミ、対して来訪神はいつもは不在なんだが決まった日にやってきて、この世と異界(死者の世界とか)をつなげたり、するというカミ。この2つが揃っているとバランスが良いようで。本州にはわかりやすい来訪神はいらっしゃらないようですが、沖縄のニライカナイ信仰とか、まさにこれ。目からウロコがぼろぼろ。
まったく違う世界観に基づいているように感じられる唯一神の宗教も、おおもとのカタチは、同じなんだそうです(唯一神しか居ない西洋世界にも、妖精やトロールというものが残っているのはその証拠。日本の妖怪も広い意味ではおんなじもの)。
投稿元:
レビューを見る
[ 内容 ]
内部視覚、瞑想、夢の時間…。
「宗教的思考」の根源はどこにあるのか?精霊が超越を生む。
高神から唯一神へ。
“精神の考古学” が、神々の基本構造をあざやかに解き明かす。
[ 目次 ]
スピリットが明かす神の秘密
脳の森の朝
はじめての「超越」
神にならなかったグレートスピリット
自然史としての神の出現
神々の基本構造(メビウス縫合型;トーラス型)
高神から唯一神へ
心の巨大爬虫類
未来のスピリット
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
投稿元:
レビューを見る
カイエ・ソバージュ第四弾。
「神の発明」では今までに比べてスピリチュアルな話が多かった。
以下気になったところをつらつらと。
第一章より
・「ヤヘ集会」という一般の人に開かれた集会ではシャーマンが調合して液体ジュースを飲んで、幻覚体験を行って、宇宙の力と生命の源泉である「銀河」へ出かける体験をしていた。
・幼い子供が立派な抽象画家であるのは「内部閃光」に基づいているため。昔の土器などの模様も内部視覚によるもの。つまり芸術は外の世界を見て書き始めたのではなく、自分の内側を見て書かれたのではないか。
第三章より
・アボリジニの間で知られている虹の蛇。これは創造を司るスピリット。それは雨期に雨を降らせ、大地を潤わせ、繁殖を促すため。一方虹の蛇は偉大な律法者でもあった。
第四章より
・現実とドリームタイムが同じ空間で生起しているのはメビウスの帯で表わせる。
・蛙は死の領域に近いところに生息している両義的な水中動物だとされている。月の表面にくっつき「月の隈」となっているのも蛙だといわれているし、水を吐いて大切な火を消すのも蛙。
・二つのゴッドは高神型と来訪神型にわけられる。
第五章より
・「訪れ神」は面をつけたり奇怪ないでたちで音楽性まで豊か。奄美の島の「ポシェ」という仮面の神はマラ棒という棒で女性たちを追い掛け回す。
・高神のイメージは無象性。来訪神は対極のイメージ。
・来訪神に与えられた特質のすべてが死と生命をひとつに繋ぎ、身体の内部と外部をひとつに繋ごうとする。たとえば母乳、涙、血、精液、唾液、排泄物など。人と外の境界に生えているのは植物だからそれを身にまとうことで中間的対象の性質をおびる。またグロテスクの美に近親性をもつ。
第六章より
・人間は自分の直感がとらえている世界の全体性を表現しようとして次々言葉を繰り出すが、常に自分の語りたいことを語り損ねる宿命を持っている。必ず空虚な中心が出現する。しゃべっていることはすべて比喩にすぎなく、言葉とモノを一致させることはできない。人間は真ん中に空虚な穴が開いたトーラスである。
第八章より
・空虚な穴を満たすことが出来るのは一神教の神だけである。神の知性だけが完全。私たちの非知をも包み込んでいる。
終章より
・一神教の想像力のもとでは(聖書のゴーレムや錬金術師によるホムンクルス創造は神の行為の真似のため)ロボットも人造人間も生命と非生命の対立をかかえたことで苦しみ続ける。
まとめとなる第五巻への序章である気がする。
その想像と幻想的な話の誕生の由縁の話のために別世界に迷い込みながら案内人で話を聴いている気分。
神”の”発明というタイトルも的を得ている。
神が私たちを創り、私たちが神を創ったのだ。
投稿元:
レビューを見る
「国家」「神orグレートスピリット」など、超越性をもったものがいかにして生まれたのか? 野生の覚書(カイエ・ソバージュ)は4冊目にして雲を突き抜けはじめる!
投稿元:
レビューを見る
本書は、文化人類学や宗教学をはじめとして様々な分野・領域の成果を利用しながら、「神」という存在が人類の心のなかにどのようにして成立したのかを論じる。
「神(God)」とは、本書ではキリスト教など唯一神を奉ずる宗教における神を指す。しかし原初的なアミニズムやグレート・スピリットなど、また多神教における神的存在やスピリット(精霊)といった存在をどう考えればよいか。人類が当初思い描いた数多くのスピリット集団を説明し、そのなかからグレート・スピリットといわれる特に重要な精霊が分化・発生し「来訪神」と呼ばれる存在になる段階を説く。そして、そこから人類の思考がさらに変化して「高神」と呼ばれる、いわゆる唯一神が発生する。このように本書では、精神考古学的な検討で人類の宗教的思考を原初から辿り、最終的には唯一神的神観念が成立する人類の心の様相の変化を、順序立てて論じる。
日本におけるカミ観念も交えながら、横断的に「超越」の思考を語る本書は、大学での講義録を元にしており、難解な説明に陥りやすい本書内容を理解しやすくしている。
投稿元:
レビューを見る
神を発明した、というタイトルがすばらしい。
人間の能力を超えた出来事やものを体験した場合、それは神様なのだと人間は感じるため、本当の無神論者にはなかなかなれないとのこと。たしかに。
あの世とこの世、一神教と多神教の対比が面白い。人間を知るには宗教なのだなと感じさせられた。
投稿元:
レビューを見る
カイエソバージュの4冊目。一神教の、それも原理主義が大統領選挙を動かす国で「多神教っていいな」と思いはじめて久しい。アイヌにもグレートスピリットに当たるものがあるのだろうか?中国の宗教って何なのか、などと思いながら読みました。
投稿元:
レビューを見る
神がどのように存在しているのかが、分かりやすいことばで書かれている本。シリーズ物だが、この一冊だけでも問題なく読める。
投稿元:
レビューを見る
「神の発明」という題名に惹かれて読みだした
人間を人間たらしめた創造力がもたらす
姿を持つ肉体と相対する見えない意識の世界を切り口に
歴史を紐解いていく内容も面白いけれど
即興に近い講義のノートを
本にしたという語り口調も軽くて読みやすい
資本主義や経済とスピリットや神が関わる道筋など
楽しい発想がイッパイだけれど
無限と有限の織り成すパラドックス観のところで
相対性時空間に関する思いがずれてか
しっくりこないものとでくわす
最初のタグは「純粋贈与の本質がはっきりと見えてくる」
二度目は「心の内部と外部の世界をつなぐドリームタイム」
3番目は「グレートスピリットの形態学」
4は「シュミット学説再考」の後半
5は「カーテンの向こう側へ」の後半
6は「南島へ」・・・
第六章のトーラス型になって膝を乗り出すも
少しずつ違和感も感じだす
言葉の行き違いだけのようにも思うし・・
何度か読み返す必要を感じる
最後に描かれている「未来のスピリット」で
私自身が馴染めない手塚治虫のアトムが出てきてしまう
どうやらこの世の要はスピリットなのかもしれない
投稿元:
レビューを見る
ようこそ!「精神考古学」の世界へ!!この講義に必要なのは、古代から変わらぬ、あなたの脳と心。
さぁ、ここにあるのはスピリット、あると信じてもらわねば話は始まりませんよ!!
スピリットを材料に、いかにして神が生まれたか、精神考古学で解き明かしていきましょう!!という内容です。
文章は講義の内容なので読みやすいです!!
ラスト、現代の宗教は無宗教の皮を被った経済主義。知識が権力となり、情報が、物質が最大に価値を持つようになっている、というところに大興奮。
投稿元:
レビューを見る
Mon, 15 Sep 2008
神といっても唯一神に焦点があたる.
スピリットとしての多神はどこの文化においても古来から見受けられる.
これに対して,ユダヤが生み出した唯一神はどのような相転移を元に生まれたのか?というところに焦点があたる.
中沢氏は読んでいると,純粋にレヴィ・ストロースの構造主義人類学の影響をうけていて,そこに深遠さ,
かっこよさがあるんだけど,その後の現代思想的な議論の飛躍を内包している.
本書の議論の中にで「トポロジー」「対称性の破れ」などという,数学的・
物理学的言語を使って多神教から一神教への流れを切っていくのだが,比喩以上のものがあるのかどうかは非常に怪しいように感じた.
純粋数学とフィールドの現象をマッチングさせるのは構造主義の特徴なので,よいのだが,
ブルバギとの交流で四元数を近親相姦禁止のルールの考察というフィールドに持ち込んだレヴィ・ストロースに比べると,
フィールドの現象と,上記数学的言語との間の対応が比喩の域を出ていない気がした.
ともあれ,一神教が科学的思考,そして現在の非共生型社会の根本に据えられていそうという考えは多くの人が了解するところ.
多神教と一神教の相容れぬ相の違い.この差異を考えることは非常に重要だ.
おもしろかった考察は,自然の中にスピリットが潜むという多神教から一神教へ移ったフェーズにおいて,神の位置が街・
村落の外部にある<自然>から都市の中心に位置する国王の上へと移り<自然>が対象化されたという考え方だ.
これは至極なっとくした.
まあ,一神教の信者の方には,国王・司教と神様の関係については御異論あるかと思いますが,その辺りは本書にて・・・・.
神様は森の中におらず,国王の上にいるんだから,森の動物や木々,氾濫する川の水は最早,神様の意思ではなく,
統御すべき<対象>にすぎない.その過程で自然に対する畏敬の念は消えたのかもしれない.
投稿元:
レビューを見る
「客観的な現実などというものはなく、お互いの会話を通じて共通の認識をつくることができる」という趣旨のことが書いてあり、まったくその通りだと思いました。