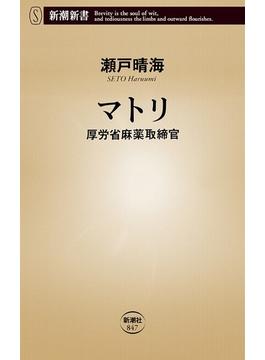紙の本
マトリの使命感が強く伝わりました
2020/01/30 20:13
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
マトリ(麻薬取締官)の皆さんの、世の中の人々を薬物から守る!という使命感が強く伝わる、情熱高い1冊です。思わず感動しました。
著者がこれまで携わった事件を多く取り上げ、詳細に著しています。ドキュメントさながらの文面です。著者、マトリの皆さんの正義感の高さに感心しました。
紙の本
知られざる仕事
2020/03/06 21:54
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ライディーン - この投稿者のレビュー一覧を見る
警察とは違って、小さな組織。
しかし、その仕事内容はキツく、なかなかスポットが当たらないが、無いといけない仕事。
職業として「マトリになろう」と言うのは少ないと思う。
日本は良いマーケットとあるが、そのとおりかも知れない。
自分の金儲けのためには一般人が犠牲になろうとも関係ない。
危険ドラッグの販売人が「自分たちは絶対に使わない」と言う発言には呆れた。
知らない薬物の歴史、マトリの仕事が少しわかったような気がします。
紙の本
リアル感
2020/08/06 20:47
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mic - この投稿者のレビュー一覧を見る
マトリという言葉は聞いたことがあっても、具体的な仕事の内容や範囲については事前知識がなかった。
取り締まりに関わる機関(警察、税関、海保、マトリ)の役割分担や、マトリに求められる適性、緻密な捜査など、最前線で指揮を執っていた著者ならではの話に迫力があり、面白く読んだ。
紙の本
アナログからデジタルまで、全てを駆使して闘ってます
2020/03/08 19:09
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ばぁ - この投稿者のレビュー一覧を見る
「俺たちは猟犬だ!」
力強いキャッチコピーが目に止まり、思わず買ってしまった。
気概がにじみ出ている。
40年間の元麻薬取締官(マトリ)の体験談。泥臭い捜査から最近のグローバルでサイバーな事例まで書かれている。
色んな手法を駆使してくる犯罪者に対し、目を光らせている姿はカッコイイ。
紙の本
興味深い
2020/03/13 20:02
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:飛行白秋男 - この投稿者のレビュー一覧を見る
第6章 ネット密売人の正体 では悲惨な状況が表現されています。
絶対に麻薬はだめです。
今後は芸能人が逮捕された場合、逮捕したのは「マトリ」か「警察」か「税関」それとも
「海保」か、興味をもって見ていきます。
また、逮捕までには大変なご苦労があることにも、思いをはせたいと思います。
止めろや、死ぬぞ!
投稿元:
レビューを見る
違法薬物の実態や歴史、流れがすごく理解できたし、市場規模に愕然とした。また、日本の市場規模や蔓延の実態にも驚愕した。
投稿元:
レビューを見る
薬物犯罪捜査と医療麻薬等のコントロールに特化した専門家的公務員であり、約300名の精鋭からなるおそらく世界最小の捜査機関である厚生労働省麻薬取締官、通称「マトリ」。本書は、その実質上の本部である関東信越厚生局麻薬取締部部長等を歴任した著者が、知られざるマトリの実像を紹介。日本の薬物犯罪を時系列で振り返りながら、それぞれの時代に麻薬取締官がどのような捜査を行ってきたのかを、著者の実体験からのエピソードを交えつつ解説している。
日本の薬物犯罪がどのように変遷してきたのかや、麻薬取締官はどのような捜査をしているのかなどについて、普段薬物犯罪があったときの新聞報道くらいでしか知らなかったので、とても理解が深まった。ドラマを見ているような臨場感のある描写が多く、読み物としても面白かった。
薬物犯罪は思っている以上に身近な存在であることに驚かされた。一方で、著者をはじめとする麻薬取締官の薬物犯罪捜査のプロとしての矜持を感じた。もぐら叩き的ではあるが、マトリの薬物犯罪撲滅に向けた尽力に敬意を表したい。
投稿元:
レビューを見る
ニュースではよく見る「覚醒剤」の事件をはじめとして、麻薬や危険ドラックを取り締まっている組織に長年勤めた方が、日本の麻薬取締の歴史と自分の活動を重ねて語る一冊。
ドヤ街の猟犬、とかイラン人組織との攻防のような、章ごとのタイトルを見るだけで只者ではないという感じがするのだが、書かれている内容もかなり壮絶だ。今では映画やドラマでしか見られないような足で情報を稼ぎ、実際の場に踏み込むという経験がこれでもかと詰め込まれている。
奥付の年代を見ると、自分が大人になってからもかなりの数の事件があったことがわかるのだが、正直にいうとそこまで麻薬や危険ドラッグなどを意識したことなどなかった。危険ドラッグとの戦いなど2010年代の話なのだが、そこまでニュースで取り上げられていたっけ・・という感じですらある。
一般の市民(といっていいかわからないが)が意識しない裏側で壮絶な戦いが行われているという意味において、まさに日本を裏で支えるという組織という感じがする。言い換えると、著者のような方がいるおかげで我々が意識せずに暮らすことができるのだろう。
・・・ただ、この著者、明らかに「狩ること」を楽しんでるよなぁ。
投稿元:
レビューを見る
「薬物禍」という言葉が耳目に触れる場面が時々在る。主に、何かの分野で著名な方が違法な薬物を所持、使用というようなことで逮捕されてしまうというような報道の場面であるが…そういう報に触れる都度、誰でも出来るというのでもないことを成して一定の名声も得た人が「何故?!」というように、誰でも出来そうなことさえうまく出来ない場合も多々在るような自身は思ってしまう。そして、違法薬物の所持、使用で逮捕というのは“著名人”であったが故に報じられているのであろうが、それは恐らくは「氷山の一角」であろうとも思う。こういうような問題は「どういうことになっている??」と時々考える。
本書は“マトリ”という通称で一部に知られる「厚労省麻薬取締官」の仕事を40年間近くに亘って務めていたという筆者が、「違法薬物を巡る問題がどういうことになっている?」ということが判るように、「日本の薬物犯罪の変遷」、「薬物犯罪に対峙する取締部署の仕事の経過」というようなことで、或る種の“歴史”として読むことが出来るように纏めたものである。最終盤の辺りは「危険なモノから人々を護る」という仕事に携わる後輩達への応援、そしてそういう仕事に全力で取り組む人達が在ることを少し広く知って欲しいという呼び掛けの意味も籠っていたように感じた。
筆者は1980年代初めに「駆け出しの取締官」として大阪での任務を振り出しに活動を続け、2010年代に東京で「取締部長」を務めて退官しているようだが、1980年代初めから2010年代の約40年間では世の中が色々と変わり、“犯罪”と“犯罪への対峙”の方法等も変わっている。そういう現場の様子も、律義に「今後の現場に差し支えが無いように」と断りながら、現場を視ている人だけが判るようなリアルな感じで語っているのが本書の魅力でもある。電話連絡用に“10円玉”を何枚もポケットに入れて街を走り回ったという1980年代から始まって、ネットを利用する密売への対峙と時代は移ろう。様々な組織が国際的な連携までして非常に大掛かりな違法薬物密輸を手掛けている事例や、追跡し悪いようにドンドン巧妙化する密売の集団、“脱法”という地点から起こった危険ドラッグの密造等、色々な事例が上っている。
「困難な現場で真摯に働き続けた人」だけが発することが出来るような言葉で綴られた一冊で、強く引き込まれるものが在り、大変に興味深く読了に至った。
投稿元:
レビューを見る
【目的】
「マトリ」とはどんな職業なのか
なぜ、薬物逮捕者が減らないのか
どのようにして薬物と接してしまうのか
【内容】
知らぬ間に「運び屋」にされたり動く「薬物コンビニ」が存在し、売る人も普通の人がほとんど
日本で麻薬を取り締まる組織としては、薬物取締りを任務とする「マトリ」、「警察」(警視庁等地方警察の薬物捜査専門部署)、「税関」(各税関の禁制品取締部門)、及び「海上保安庁」(各海上保安本部の密輸事犯取締本部署)の4機関があり、それぞれが専門性を生かした対策を講じている(p.19)
国連等国際機関の調査結果や各国の分析資料から、その取引総額は優に50兆円を超えていると推計できる(p.31)
世界の麻薬ビジネスの売上げは、既に国内の情報通信分野を超えている(p.31)
日本でも欧米諸国と同様に多くの薬物が出回っている。だが、実際に使用される薬物は覚醒剤が圧倒的に多い。日本では、犯罪組織が密輸・密売する薬物も覚醒剤が大半を占める(p.47)
【まとめ】
日本は最大の「覚醒剤市場」で、世界で毎年「243万人」も薬物使用者が急増中
マトリは、精鋭300名の薬物犯罪捜査専門組織で薬剤師、捜査官、行政官の顔をもつ
投稿元:
レビューを見る
名前は聞いていても、具体的に何をやってるかはなかなか分からない麻薬取締官。 その実情は凄まじい。
今後の捜査を考慮し細かく書けないとしつつ、ここに書かれた内容だけでも非常に濃密。冒頭の話から、まるでドラマを観てるかのように感じた。
薬物乱用防止はポスターなどで啓蒙されてるが、ある程度以上の方はこの本も読むと、やってみようという気が起きなくなるのでは…と思う。
投稿元:
レビューを見る
40年勤めあげた専門家なればこそ、「木鶏子夜に鳴く」の精神を大事にしてほしかった。誰か諌める人いなかったのかな。文体のせいで安っぽく見える。
映画化したらいいんじゃないかな。
投稿元:
レビューを見る
「俺たちは、猟犬だ!」激増する薬物犯罪に敢然と立ち向かうのが厚生労働省の麻薬取締官、通称「マトリ」だ。麻薬、覚醒剤など人間を地獄に陥れる違法薬物の摘発、密輸組織との熾烈な攻防、「運び屋」にされた女性の裏事情、親から相談された薬物依存の子供の救済、ネット密売人の正体の猛追、危険ドラッグ店の壊滅…約四十年間も第一線で戦ってきた元麻薬取締部部長が薬物事犯と捜査のすべてを明かす。
投稿元:
レビューを見る
厚労省麻薬取締官を40年にわたり続けてこられた方のノンフィクション。下手な刑事モノより迫力、怖さがあったし、ご苦労とかもつぶさに伝わった。
投稿元:
レビューを見る
非常に面白い本です。
そもそもマトリ=麻薬取締官が厚生労働省に
属していることを、どれだけの人が知っている
のでしょうか。
警察ではないのです。
戦後間も無くのヒロポンから、最近の危険ドラ
ッグまで、いわゆる薬物に関わる事例が全て
網羅されています。
こういう本を読むと、今までは新聞やニュース
で何となくスルーしていた情報に対しても、
「おっ、彼らマトリはまた大きな事案の検挙を
成し遂げたのだな」と、関心を持つようになり
ます。
社会に対する目が広がります。
もう一つ彼らの仕事に対する姿勢には感動しま
した。
昨今の麻薬取引はIT化されていることは想像に
難くないと思います。ネット経由での取引は
とても増えているらしいとか。
それらに対して、マトリの方々はIT知識を得よ
うと必死に勉強するのです。何歳になっても
です。
「俺には無理」と言うことなく、幾つになって
も新しい知識を仕入れようとするその姿勢には
学ぶことが多い一冊です。