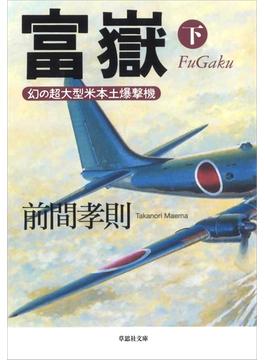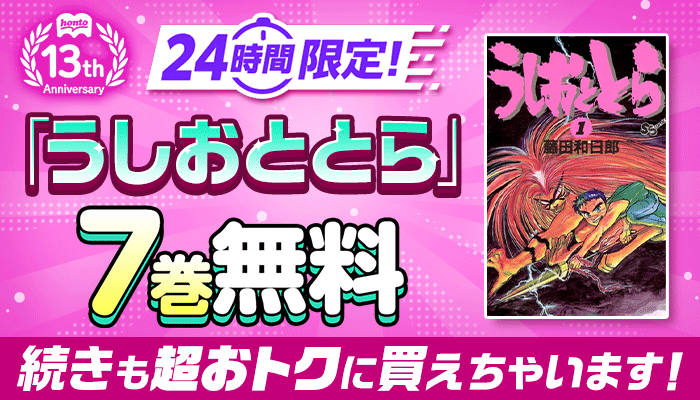富嶽(下):幻の超大型米本土爆撃機
著者 著者:前間 孝則
山積する難題、枯渇する資材、そして悪化する一方の戦局にあって、どうにか昭和20年の初飛行への計画が立てられた。だがそれを待たず開発中止命令が下される。そして敗戦。関係書類...
富嶽(下):幻の超大型米本土爆撃機
商品説明
山積する難題、枯渇する資材、そして悪化する一方の戦局にあって、どうにか昭和20年の初飛行への計画が立てられた。
だがそれを待たず開発中止命令が下される。
そして敗戦。
関係書類はすべて焼却され、中島飛行機は終焉を迎えた。
――幻に終わった「富嶽」計画とは何だったのか。
その開発にあたった技術者たちはどんな思いを抱いていたのだろうか。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
日本で軍事技術を考える事へのアレルギーを再考させられる貴重な提言
2021/06/14 07:26
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:YK - この投稿者のレビュー一覧を見る
太平洋戦争で劣勢になった日本軍が、戦局の打開を狙って開発しようとした大型爆撃機「富嶽」の開発を巡るノンフィクションの下巻。
下巻ではアメリカにおけるB29の開発状況、戦局の進展に伴い次第に実現の可能性が消えてゆく「富嶽」開発計画の推移を、終戦の時点まで追っていきます。実用化され戦局に多大な影響を与えたB29と、計画だけに終わった「富嶽」の違いを生んだのは、日本とアメリカとの航空機産業の裾野の大きさ、積み重ねてきた経験の質と量の差であることが多くの証言と共に解説されています。
本書は1991年に単行本として出版され、1995年に講談社文庫で発刊、そして2020年に3度目となる草思社文庫からの発刊となります。太平洋戦争期の航空機技術を辿る大作ですが、発刊された時代背景によってその位置づけは大きく異なります。本書には3度の発刊にあたっての”あとがき”が3回分収録されており、実はこれが一番の読みどころではないかと感じました。
太平洋戦争で劣勢であった日本軍が戦局の打開を狙ってアメリカの主要都市の爆撃を企図したのは、現代のアメリカに対して劣勢となっていた武装組織が起死回生を狙った2001年の同時多発テロと構図が同じなのではないか、という著者の分析には説得力があります。
また生活を豊かにする身の周りの技術の源流が軍事技術であるケースが多かったのに対し、現在は軍事と民生の境界が曖昧で、”軍事技術に繋がるから”という一点だけに拘って科学技術に対する思考を避けていると、世界の技術開発の潮流から孤立してしまうという問題点も鋭く指摘されています。
軍事=一部の軍事オタクもの、軍事=忌避すべきもの、といった思い込みが結構多い日本で、腰を据えてその技術や時代背景を描く著者の姿勢に、改めて共感できたノンフィクションでした。
戦時中の「富嶽」計画を綿密な取材で明らかにした傑作です。
2021/05/02 12:11
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、『マン・マシンの昭和伝説』をはじめ、『弾丸列車』、『新幹線を航空機に変えた男たち』、『日本の名機をつくったサムライたち』などの作品で知られるノンフィクション作家の前間孝則氏による名著です。草思社文庫からは上下2巻シリーズで刊行されており、同書はその下巻にあたります。第二次世界大戦の中、山積する難題、枯渇する資材という現状を抱え、悪化する一方の戦局下、軍部は「富嶽」の開発中止を命じます。そして敗戦となり、関係書類はすべて焼却され、中島飛行機はその終焉を迎えます。幻に終わった「富嶽」計画ですが、その開発技術者たちはどのような思いを抱いていたのでしょうか。関係者への取材と資料検証を通じてその実相に迫った前間氏の傑作です。
日本で軍事技術を考える事へのアレルギーを再考させられる貴重な提言
2024/12/18 19:57
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:YK - この投稿者のレビュー一覧を見る
太平洋戦争で劣勢になった日本軍が、戦局の打開を狙って開発しようとした大型爆撃機「富嶽」の開発を巡るノンフィクションの下巻。
下巻ではアメリカにおけるB29の開発状況、戦局の進展に伴い次第に実現の可能性が消えてゆく「富嶽」開発計画の推移を、終戦の時点まで追っていきます。実用化され戦局に多大な影響を与えたB29と、計画だけに終わった「富嶽」の違いを生んだのは、日本とアメリカとの航空機産業の裾野の大きさ、積み重ねてきた経験の質と量の差であることが多くの証言と共に解説されています。
本書は1991年に単行本として出版され、1995年に講談社文庫で発刊、そして2020年に3度目となる草思社文庫からの発刊となります。太平洋戦争期の航空機技術を辿る大作ですが、発刊された時代背景によってその位置づけは大きく異なります。本書には3度の発刊にあたっての”あとがき”が3回分収録されており、実はこれが一番の読みどころではないかと感じました。
太平洋戦争で劣勢であった日本軍が戦局の打開を狙ってアメリカの主要都市の爆撃を企図したのは、現代のアメリカに対して劣勢となっていた武装組織が起死回生を狙った2001年の同時多発テロと構図が同じなのではないか、という著者の分析には説得力があります。
また生活を豊かにする身の周りの技術の源流が軍事技術であるケースが多かったのに対し、現在は軍事と民生の境界が曖昧で、”軍事技術に繋がるから”という一点だけに拘って科学技術に対する思考を避けていると、世界の技術開発の潮流から孤立してしまうという問題点も鋭く指摘されています。
軍事=一部の軍事オタクもの、軍事=忌避すべきもの、といった思い込みが結構多い日本で、腰を据えてその技術や時代背景を描く著者の姿勢に、改めて共感できたノンフィクションでした。