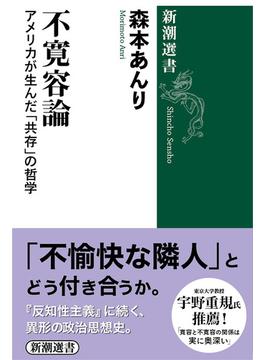2020年を象徴するかのような1冊
2021/06/27 12:41
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:第一楽章 - この投稿者のレビュー一覧を見る
未知のウィルス、政治の選択などでさまざまな分断、軋轢が表に出た2020年をある意味で象徴するようなタイトルですね。
そもそも寛容さを示す対象はキライなもの(好きなものには寛容になり得ない(なる必要もない))というところからしてなるほどと思わされたのですが、ピューリタンが国を作り上げるというアメリカの建国の過程で顕在化した不寛容さに争った(あらがった)ロジャー・ウィリアムズという、現代から見れば極めて先見的な、当時から見れば異端の、一人の人物の悪戦苦闘から、「不愉快な隣人」と共存するための哲学を読み解く1冊です。
同氏の『反知性主義』も愛読しているのですが、歴史、特にあまり焦点の当たらない(”歴史がない”とまで言われてしまう)アメリカ史から、現代にも通ずる多くのヒントを汲み取れるのはとても興味深いです。
アメリカが生んだ共存の哲学
2023/10/08 07:59
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:いずみ - この投稿者のレビュー一覧を見る
主人公であるロジャー・ウィリアムズの思想・経験だけでなく中世の寛容論、クエーカーの歴史、ピルグリム父祖のこと、次々に興味深い内容が出て来て、付箋をつけながら読みました。
エピローグより、「多くの日本人は、寛容は美徳だと思っているだろうし、自分のことをどちらかと言えば寛容な人間だと思っているだろう。だがそれは、あくまでも一般論であり、問題が他人事の時だけであり、寛容の問いが自分自身に及び、深刻な利害が身の回りにひた寄せてくると、ようやくその不愉快さに思い至るようになる」否定的な感情を内にもちながらも、何とか相手と一緒にやってゆこうとしている人が寛容のお手本、「寛容はちっとも美徳ではない」
投稿元:
レビューを見る
通販生活の表紙に「私はあなたの意見には反対だけど、あなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」というヴォルテールの言葉が掲げられていた。確かに、美しい言葉かもしれないけど、この通りにするのは、かなり無理をして、頑張らないといけない感じする。
この本によると、中世の「寛容」は、大きな悪が実現しないように小さな悪をそのままにしておくという、かなり消極的な、相対的な考え方だったというのです。金貸しも、娼婦も、それ自体は悪には違いないけど、それが無くなったら、社会全体はもっと悪くなるので、まぁ、放っておくか。そんな考え方だと。
なるほど。
この現実主義が、カトリック教会をさまざまな極論から守り、大いなる中庸を維持させてきたんだろうと思う。
それに比べて、上記の近代啓蒙主義の寛容論は、多様性を守ることを「絶対視」するような「非」寛容が見え隠れする。人間はそうあるべき。啓かれた近代人は、そういう考え方をするべき。そんな生堅な人間観が見えてくる。
ここ数日のオリンピック組織委員会の森会長の「女性蔑視発言」を巡るゴタゴタも、「多様性」を「絶対善」として、それが否定されると、その相手を全否定するような潔癖感が現れていて、ちょっと危ない感じがする。
そんな時代に、この本は、もっと現実的な「寛容論」を提示してくれる。悪は悪なんだけど、そんなに大きな悪ではないので、とりあえずは放っておくか的な(現教皇の同性婚に対する「寛容」も、この線にあるのではないだろうか)。
またまた、今年のベスト3候補の1冊。
投稿元:
レビューを見る
近代や現代の寛容論ではなく、その源流とも言える中世の寛容論を下敷きに、米国建設前(植民地時代)の人物でもあるロジャーウィリアムズに焦点をあて、彼にとって寛容が如何なるものだったのかを中心に論じている。
彼が重んじた「礼節」について、「マナー」に通じるところがあると感じつつも、「マナー」よりもより深層にあるような、所作や心情の向け方まで表したものであるように感じた。
ウィリアムズみたいなちょっとおかしな(褒め言葉のつもり)人達が社会から少しずつはみ出ることで、漸進的に社会が変わってきたのだと感じる。もちろん、そういうおかしな人たちを下支えしてきた他者や社会があってのことだけれど。
投稿元:
レビューを見る
ちょっとだけ感動した。特に、平和と真理の対立の横にいるのが、言葉を発しない忍耐であることに。
不寛容論、というのは、異文化理解や多様性がキーワードとなった我々の目の前にある「寛容」の矛盾に向き合うにあたり、まず「不寛容」から考えてみようではないか、という取り組みを表す。不寛容の代表例はプロテスタント(ピューリタン)へのカトリックの弾圧である。特に宗教と政治が繋がった時代において、宗教の違いがそのまま村八分と弾圧による死につながる問題であった。その根拠は、異端の存在が、コミュニティの平穏を揺るがす問題であるとの認識にあった。不寛容にもそれなりの根拠はあるわけである。それなりの根拠を持つ不寛容に対して何ができるだろう、というのをアメリカ史をたどりながらこの本ではみていく。
なお、寛容は日本では簡単に扱われがちだが、難民の数万規模で訪れる欧州では、イスラム教徒が増えていることを恐れる向きもあるし、日本でも外国人が増えて治安が悪くなるという恐れの声は聞こえており、簡単なものではない。冒頭(本ではエピローグ)の、平和と真理と忍耐の話は、理想論がぶつかり合う時、間には忍耐がいなくては、相互の関係は不可逆的に壊れてしまう、ということを表していると考えている。寛容とは、忍耐や礼節に近いものであって、必ずしも心から歓迎することではないのではないか。
寛容は、言葉の前提として、すでにその「寛容」の対象となる物事に否定的な姿勢がある。そして、その上でなお、存在を認めてあげる、というやや上から目線の姿勢である。しかもそれは、認めるのが正しいからではなく、面倒ごとになるよりはましだから、攻撃しないというのが、その原義である。これは中世カトリックが他宗教に対して持っていた考え方と共通する。
現代では寛容は、あくまでそれ自体が望ましく正しいことだから、多様性を歓迎するもののように扱われる。しかし、自分の文化と全く相入れない人が目の前に来た時、自分の生活が脅かされるかもしれないと感じる時、簡単に歓迎できるものとは言えなくなる。
さて、森本の紹介するロジャーウィリアムズは狂信的なクリスチャンであるからこそ、他の人の信仰もまた認めるべきであり、彼の異端的信仰は他の人によって侵害されるべきでないし、特に信仰の問題で街を追い出したりするべきでない、という寛容の論理を主張した。彼を弾圧したジョンコトンもまた、単なる頭ごなしの弾圧者ではなく、教派が異なっていて、心では信じていなかったとしても礼拝に出ていれば街から追い出さないという一定の寛容は見せていた。ここで彼らの差は、当然考え方の道筋にもあるが、結局のところ、どこまでがその人の許容範囲なのか、ということである。というのも、ロジャーウィリアムズは当初は弾圧される側、権利を主張する側だったわけだが、その後街を追い出されて自分でコミュニティを作る為政者となってから、そのコミュニティ内の異端分子に手を焼き、彼は彼でクエーカー教徒の信仰を痛烈に批判することになる。
ウィリアムズのこの転向に対しては批判もあるが、一貫して礼節を重視していたことは変わりない。ウィ��アムズは礼節を重視したがクエーカーはそうではなく攻撃してきたから、批判したようである。森本は完全な答えを示しはしなかったが、このように信仰について正しい正しくないの結論をつけることはせずに、とにかく市民的な分野では礼節を保とう、ウィリアムズの立場を一つの人権史上の重大事件と捉え、これこそ今必要な寛容だという。
わかる。宗教的真理の統一、政治的平和の達成、そしてその双方の合一、全て、現実的には解決しきれない課題が山積みであり、それを見て見ぬ振りしながら、忍耐をして行くしかない現実がある、という話か。べき論とである論は分けて、どちらも必要であるが、どちらかだけになってはいけないし、どちらの方が重要とも言えない、というように思う。
投稿元:
レビューを見る
私には難しそうで最後まで読み切れるかと心配したが、易しい言葉で、興味がずっと保たれたまま読み続けられた。
歴史から学ぶこと、遠い昔の他国の人や出来事から得たことを今現在を生きるに当たって知恵としてそのまま具体的に取り入れられること、しみじみと実感できた。
投稿元:
レビューを見る
入国審査書面の契約ひとつとっても、何故そのような項目が設けられているのかという歴史的背景を知ると納得が出来る。他者と暮らすとは何かを考えるきっかけとなる。
投稿元:
レビューを見る
「反知性主義」を面白く読みました。「不寛容論」も分析すべき現代アメリカの問題を論じてるのかと思い、書店にあったのを何度も見かけ、迷った末買ってみました。
けれど、「線」の思考、アースダイバー神社編、、と同じく。。いまこれを読む時間を割けるかというと、なかなか。。。ということで、途中でパラパラ読みになってしまいました。。。
ただ、ピューリタンがパブティストなどを不寛容な態度を取っていた。契約結んで作られたコミュニティは、そのルールを承認してない人を入れる必要はない。。てことになる=不寛容=排斥。。って考えを学べました。
投稿元:
レビューを見る
「寛容」の如何を問うとするよりは、むしろそれを通した初期アメリカ社会から連なる歴史と人々のあり方を知る端緒となった。
それが現在の、そして我々日本の基部の上でどう受容されうるか。
投稿元:
レビューを見る
寛容と無関心
”万人が万人に対して寛容であることは、そもそも不可能である。では、寛容と不寛容の線引きはどこでなされるべきなのか。”
”人は、未知のものには不寛容に、既知のものには寛容になりやすい。特にこれは、宗教や性の問題に関する態度決定で顕著である。”
https://kangaeruhito.jp/trial/40146
https://note.com/ogatahisato/n/nac180c11df6a
投稿元:
レビューを見る
不寛容なしに寛容はない と最初の方に出てくるが、「寛容」はこれに尽きる感じだ.アメリカへイギリスから移住したピューリタンが原住民と交渉しながら植民地を建設する過程で、「寛容」をどう取り扱うかを議論しているが、宗教の問題が基盤にあることは日本人には理解が難しいと思った.ロジャー・ウイリアムズに焦点を当てて「寛容」の問題を解説しているが、彼の頑なさはある程度理解できると感じた.契約を結ぶこと、宣誓をすることなど、現代社会にも通用することが17世紀のニューイングランドでなされていたことに驚いた.
投稿元:
レビューを見る
不寛容なしに寛容はあり得ない。
自分が嫌悪する、許容できないものに対してどうするのか、という問いこそが寛容論。
わかりあうことはできないが、わからないままに受け入れることはできる。
ウィリアムズを切り口に寛容論について述べられた本。この内容でこの読みやすさはとてもよかった。
内容としても、筆者が述べている通り、まさに今求められる考え方なのではないだろうか。
投稿元:
レビューを見る
BIBLIOTHECAで紹介された本。読み応えがあった。「悪を最小限に抑えるために寛容になる」というフレーズが印象的だった。
投稿元:
レビューを見る
なぜ今まで宗教学に興味をもってこなかったのかと後悔してしまうほどすばらしい内容。人間が考えたものである以上、政治思想や哲学や歴史や人々の価値観にはいつも宗教の下地があることが理解できる。もっと学びたい。
価値観が異なっても許容し共存するという意味での寛容は、「トルコから世界を見る ――ちがう国の人と生きるには? (ちくまQブックス)」に書かれていた「ものさしは複数ある」という認識に近いし、子どもの学級内での過ごし方としてよく言われる、「みんな仲良くは難しいが平和的に共存しよう」という考え方とも通じる。
皆が「礼節をもって、暴力に訴えず、会話を遮断せずに続けるだけの開放性を維持する」ことができれば平和になるので、さほど難しくはないように思えるが、その境地に至るのが困難だから諸々の問題が生じるのではと思う。まず自らの信念によほど強い確信がなければ、他者の異なる意見に接することで自分の内部に揺らぎが生じ、不安になる。自分を不安にするものは排除しなければならない、となる。相手の態度があまりに確信に満ちていると、自らの不安定を指摘されているようで、あたかも自分が攻撃を受けたかのように感じる。攻撃を受けたら自らを守るため反撃しなければならない、となる。これらの問題をどのように乗り越えるかが、私たちが考えなければならない課題だと思う。
投稿元:
レビューを見る
分断が進むアメリカにおいて、「寛容」とは何かを論じる一冊。トランプ以後、顕在化した分断を前に、現代アメリカについて語られるのかと思うと、豈図らんや、アメリカ入植史と、当時活躍されたロジャー・ウィリアムズ氏についての本になっている。
アメリカのピューリタンの対極に位置する中世カトリックの寛容さについて触れたあと、政教分離と内心の自由を認めるウィリアムズについて語られ続ける。あとがきでも述べているが、森本先生、ウィリアムズ大好きでしょ。
端的に言えば、「ムカつくけど排除しないし礼節を持って接してやる」のが寛容だと論じられている。ユダヤ人の弁護士がネオナチを「テメーの意見はムカつくけど、テメーの言論の自由は守ってやる」という民主主義の根幹をなすところと同じである。逆に昨今よく言われる、多様性を認めない多様性の押し付けも非難の対象となっている。上記の心がけでいるのはなかなか大変だが、これからの時代、皆がその心持でいればいいのにね。